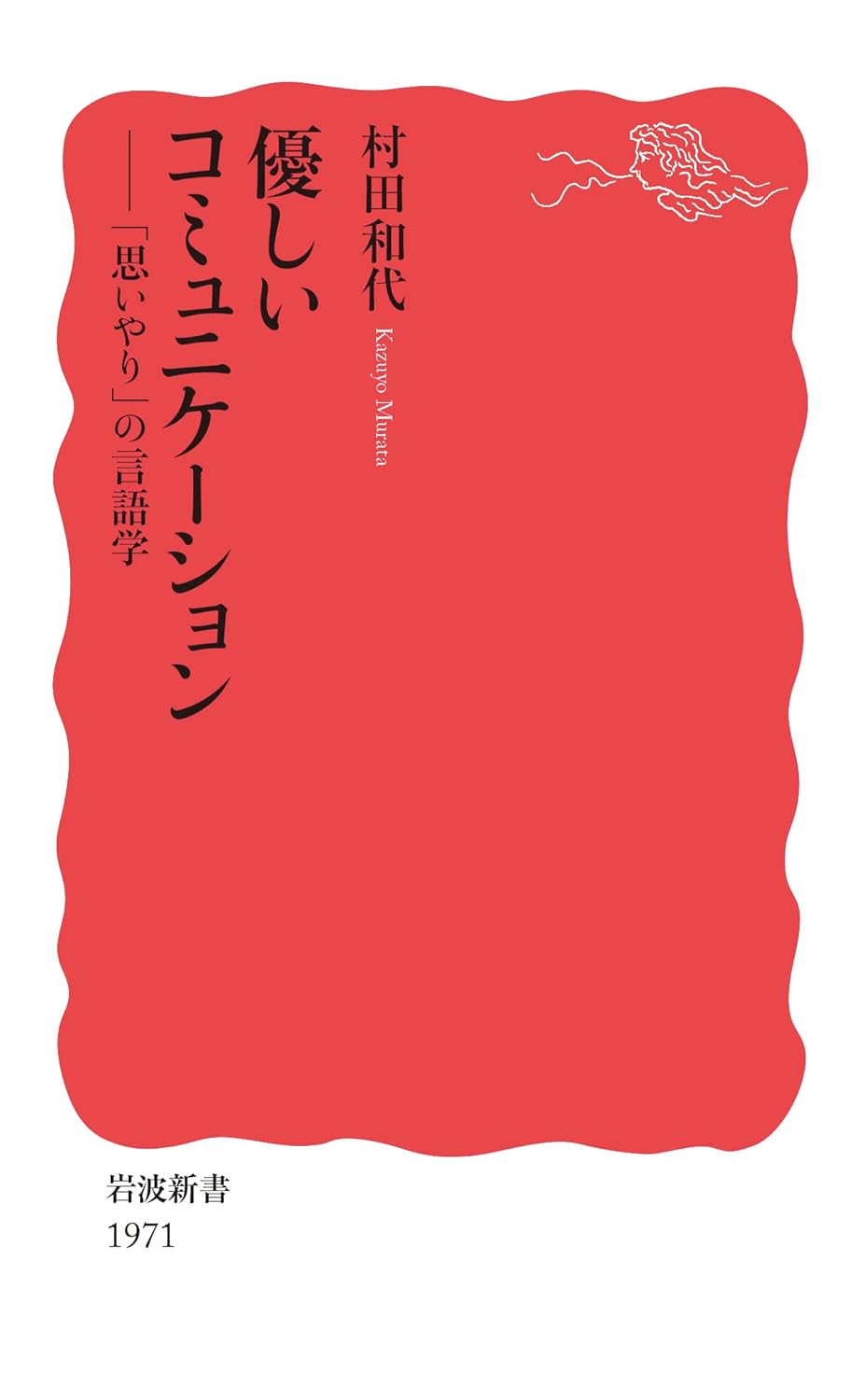
著者について
奈良県橿原市生まれ.ニュージーランド国立ヴィクトリア大学大学院言語学科Ph.D. (言語学).現在,龍谷大学政策学部教授・学部長.専門は社会言語学(コミュニケーション研究).主な編著に,『シリーズ話し合い学をつくる 全3巻』『聞き手行動のコミュニケーション学』(ひつじ書房),『包摂的発展という選択――これからの社会の「かたち」を考える』『「対話」を通したレジリエントな地域社会のデザイン』(日本評論社,共編)など.
言葉の大切さが分かります
伝える際の言葉選びを
分かりやすく事例に応じて解いてくださってます
会社や組織で上司にあたる方には
是非読んで欲しい本です
そうですね
コミュニケーションの方法を論じています。
「優しい」コミュニケーションとは何かを捉えることができます。
最終章では、雑談・聞くこと・双方向がキーワードなっているようです。。
そのことを、この最終章に至るまで、例を出しながら論じています。
納得ですね。
最近、私の職場で、あることについて、仕事の同僚と話していた時のことを思い出しました。
我々より自分が偉い(?)と思っている方が、断りも無く
突然、私と話をしている同僚に話しかけてきました。
その方は、コミュニケーションの仕方をわかっていない方だと思いました。
(困った人ですね。たぶん、このような方にコミュニケーションの仕方を言っても無駄であると思います。)
私は蚊帳の外となり、話は中断して、その場を去りました。
とにかく、
「優しい」コミュニケーションを考えるために読んでも良い本でしょう。
優しいコミュニケーションの実現へ向けた社会言語学の貢献
社会言語学者である著者による、①社会言語学の魅力や面白さを伝える、②優しいコミュニケーションのエッセンを考える、③言語・コミュニケーション研究の社会への貢献方法を提示する、という三つのメッセージが込められた書である。
本書は6つの章から構成されるが、まず1章で概念や理論が紹介される。
この後も、学術的な知見に裏打ちされた記述が基本となるが、特に1章はその性格が強い。続く2章からは、より具体的な話が中心となり、「雑談」の効用が説かれる。さらに、3章は「聞くこと」の重要性が説かれる。
4章は、具体事例から、優しさを表すことが難しい場面でのコミュニケーションについて、コロナ禍初動期のリーダーのコミュニケーションにつき安倍首相・小池都東京都知事・吉村大阪府知事のコミュニケーションのあり方が分析される。オンラインでのコミュニケーションについても事例分析も行われる。
5章では、社会貢献に関する著者自身も関わる実践例を示す。終章は、優しいコミュニケーションについて整理した短めの章となる。
新書200ページ程というコンパクトな分量に、研究と実践がバランス良く盛り込まれ、著者が言うところの「優しいコミュニケーションとは」ということを読者に伝え、さらに考えさせてくれる好著である。
本当は怖い優しすぎる社会
果たしてデス・マス体を使えば優しいコミュニケーションなのかについては疑念が残る。しかしそれは措いておくとして、本書p.3にこんな記述がある。
[引用開始]
たとえば、廊下で学生とぶつかってしまった時に「ごめんなさい、痛くなかったですか?」と言ったら、「いや、全然大丈夫っす! 先生こそ、痛くなかったっすか?」と返事が返ってきたとしましょう。
規範主義的なアプローチをとれば、「その日本語は間違っていますよ」と答えるべきでしょう。すなわち「全然は否定形と呼応するので、「全然痛くなかったです」といったように後ろに否定形をもってくる必要があります。それから、「大丈夫っす」は正しい文末表現ではありません。「大丈夫です、痛くなかったですか」と言うべきです」というのがその解説です。
一方、社会言語学的(記述文法的)アプローチは、言語使用は時代と共に変化すると考え、「全然+肯定形」を新しい表現(使い方)としてとらえます。加えて、「っす」については、主として若い男性が使用し相手への親しい丁寧さを表す(社会的な意味)という研究結果があります。[引用おわり]
この箇所を読んだだけで、ダメだこりゃと思った。四角括弧や丸括弧が煩雑過ぎて何やら訳が分からない。
しかしもっと本質的な誤謬を指摘したい。「言語使用は時代と共に変化する」のは事実だが、「その日本語は間違っていますよ」の規範主義そのものが誤りだ。これはどういうことかと言うと、「全然+肯定形」は全然新しい表現ではなく、明治大正期の文学作品に度々出てくる、ごく当たり前の表現なのだ。新しいというより先祖返り現象と言って良い。こうした歴史も踏まえずに、こんな無知な状態で「優しいコミュニケーション」もへったくれも無い。
「全然+肯定形」が廃れ、「全然+否定形」の一辺倒になるのは昭和に入ってからだが、そこに昭和軍国主義が絡んでいるのか否かは不明だ。一部の識者は、英語の授業で習う not ・・・ at all =「全然・・・ない」と、昔のドイツ語の授業でエリートの卵たちが習った gar nicht ・・・ =「全然・・・ない」という訳語に影響され、いつの間にか「全然」は肯定形に使ってはならないという誤った規範意識が芽生えたという説を提唱している。
これが平成に入ると主に若者の間で「全然+肯定形」が復活した。そして明治大正期の文学作品を読んだこともない無知な大人(教員に多い)が、「その日本語は間違っていますよ」と余計な事を言ったものだ。
まぁとにかく物を知らずに本を書くことの恐ろしさを教えてくれた点だけは評価できよう。
「優しい」とは?
著者の言う「優しいコミュニケーション」と言うのが一体何なのか最後までわからなかった。
これからの時代に求められる「コミュ力」を身に付ける本
多様性を重んじる時代、何をもって「正しい」言葉遣い、「正しい」コミュニケーションとするかが一概に言えなくなり、学校や会社といった組織レベルから、家族や友人といった身近な人間関係レベルまで、異なるバックグラウンドを持つ人同士でぎくしゃくする場面が増えている。
これは〇〇ハラにあたるのか、これは炎上するのか、誰もが手探りで言葉を探している。
そんなコミュニケーションの過渡期とも言えるこの時代に、本書は相手を思いやるコミュニケーション方法に立ち返り、様々な事例とともに、どうすればその時々のオーディエンスにとって「やさしい」交流が出来るか追究している。
世代や性別、価値観や文化等が自分と異なる相手に対してのコミュニケーションに悩む、あらゆる読者が、明日からのコミュ力を劇的に変えられる一冊となっている。
『コミュニケーション』を立体的に...
「コミュニケーションとは双方向である」...あたりまえのこととわかっていても、
ふり返ってみると、一方的に話すことばかりしている...そんなことはないでしょうか。
一対一のコミュニケーションから、集団で意見をまとめる会合のファシリテーション
まで、コミュニケーションを立体的に考えさせてくれます。
コミュニケーションについ
ての考え方を整理することができました。
理解を進めるための具体的なやり取りを示してくれていますが、紙幅のために限られ
てしまっています。この本を入門として、続編ではそれぞれの場面でどのような意図で、
どのようなやり取りをしているかを教えていただきたいと思います。
雑談は、優しいコミュニケーションにとって非常に重要
私は製薬企業のMRとして長年、営業活動に携わってきたが、現役時代の私は雑談が苦手で、「○○先生、本日、私がお話ししたい事項は3つでございます。第1は・・・」と、単刀直入に用件を切り出したものです。
このたび、『優しいコミュニケーション――「思いやり」の言語学』(村田和代著、岩波新書)を読んで、雑談の重要性に気づいたが、時、既に遅しですね。
「雑談はユーモアと並び、職場談話の典型的な、人と人との関係を紡ぐ言語実践です。このような機能を担う言語的ふるまいは、相手のフェイス(対人関係上の基本的な欲求)への配慮として働くと同時に、業務遂行にとってもプラスに働く点が指摘されています」。
「雑談の主要な目的として、沈黙を解消することがあげられます」。
「話し合いの基礎作り・場作りを担うのは、本題に関わる情報伝達を行う談話ではなく雑談なのです。とりわけ、価値観もバックグランドも異なる者同士で行われる話し合いにおいて、雑談は非常に重要な役割を担います。話し合いが活発に進み、参加メンバーが忌憚なく意見を出し合える活発で建設的な話し合いを行うためにも、雑談は必要不可欠なのです」。
「雑談は、『雑』でもなく『small』でもなく、優しいコミュニケーションにとって非常に重要です。皆さんは一日の中で、誰と、どれくらい、どんな話題で雑談していますか?」。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます