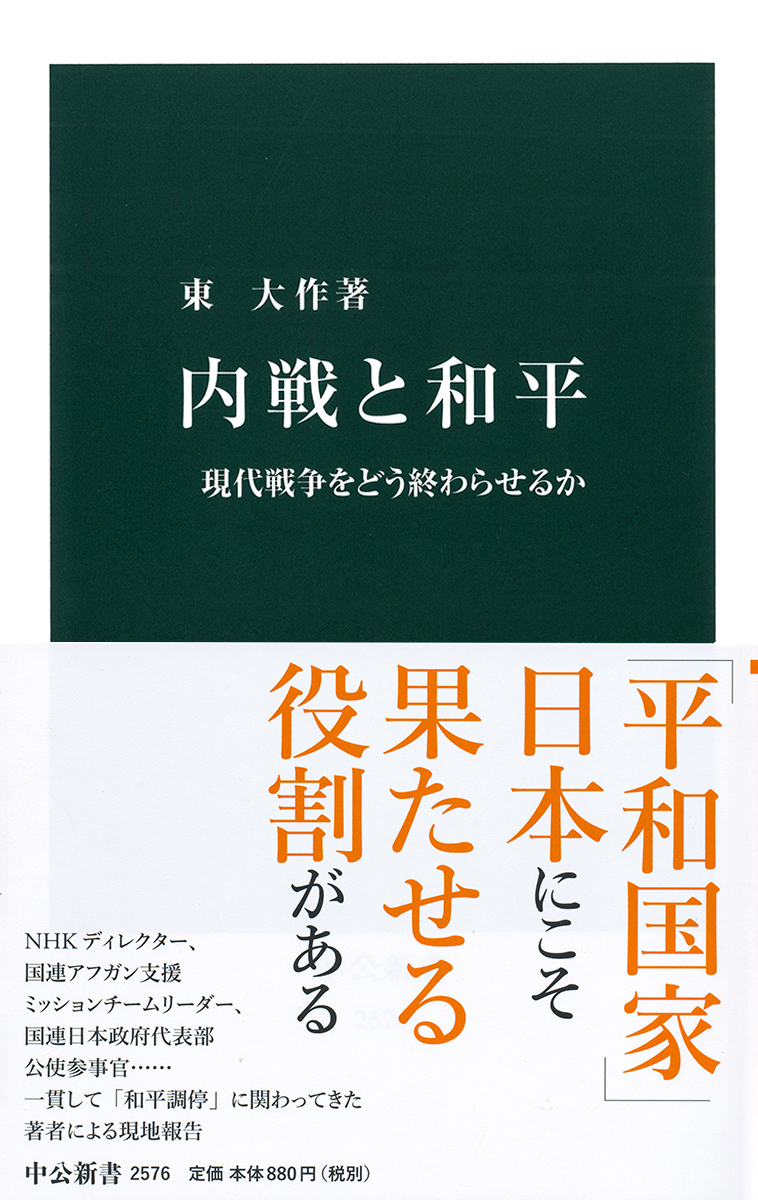
東大作 著
人類の不治の病と言われる戦争。そのほとんどが国家間の紛争ではなく凄惨な内戦である。本書ではシリア、イラク、アフガニスタン、南スーダンなど二十一世紀以降の内戦を例に、発生から拡大、国連や周辺国の介入の失敗、苦難の末に結ばれたはずの和平合意の破綻といった過程を分析。テレビ局の報道ディレクター、国連日本政府代表部公使参事官、そして研究者として一貫して和平調停に関わる著者が、戦争克服の処方箋を探る。
東大作
1969年(昭和44年)、東京都に生まれる。NHKディレクターとしてNHKスペシャル『我々はなぜ戦争をしたのか ベトナム戦争・敵との対話』(放送文化基金賞)、『イラク復興 国連の苦闘』(世界国連記者協会銀賞)などを企画制作。退職後、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学でPh.D.取得(国際関係論)。
国連アフガニスタン支援ミッション和解再統合チームリーダー、東京大学准教授、国連日本政府代表 部公使参事官などを経て、現在、上智大学グローバル教育センター教授。著書に『我々はなぜ戦争をしたのか』『犯罪被害者の声が聞こえますか』『平和構築』、Challenges of Constructing Legitimacy in Peacebuilding、『人間の安全保障と平和構築』(編著)など。
アフガン、イラク、南スーダン、シリア、紛争渦中の内戦の現場で50人以上の指導者と議論を重ねまとめあげた調査報告。我々は今、「内戦」という名の戦争の世紀に生きている、しかもその「内戦」の背後に周辺国、大国の利己が複雑に絡まり合っていることを政府軍、反体制派それぞれのインタビューで暴き、その上で「ファシリテーター」としての日本の役割について確かな展望を得ようとする著者の悪戦苦闘する様が伝わってくる。
この本を手にする直前、イラク・バグダッドでイラン革命防衛軍のソレイマニ司令官が米軍に殺害されるというニュースが世界に衝撃を与えた。そのイラン・アメリカの対立の構図を理解する上でも、この本はその根源を探る必読書になると思う。
現在の紛争、戦争を理解する上で現場のフィールドワークに基づいて説得力があるが、特に現在のアメリカとイランの対立を知る上では、その背景が極めてよくわかった。平和に慣れすぎた(?)、”平和ボケ”の日本人は今、この本を読んだ方が良い。この本でも書かれているが、先ごろ亡くなった緒方貞子さんの精神、そして中村哲さんに本を読みながら、思いを馳せてしまった!!
現代の戦争の95%以上が「内戦」であり、どれもが「和平交渉」で終わらせることが困難だという。そんな現実の中、どう交渉相手を巻き込むかという「包摂性」にこだわり、徹底的に解決の糸口を探った書。筆者は、NHKの報道現場が原点であり、どこまでも現場の当事者にこだわる。南スーダンやイラク、アフガニスタンというただでさえ入国が困難な国で、難しい高官インタビューを重ね、かつ庶民の様子や現場の空気も大切にする。報道、国連、大学という異なる分野を渡り歩き、「ファクト」「現実的な戦略と実行性」「崇高な理想と理論」の各分野の重要な要素をバランスよく盛り込んだ良書だ。膨大な時間をかけて取材、理論構築しており、説得力にもあふれている。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます