利根輪太郎は、改めて自身の不徹底さに腹を立てたのだ。
自宅を出た時、さらに取手駅から競輪行きのバスに乗った時には、口惜しさをバネにと決意していたのだ。
だが、その口惜しさをバネには出来なかったのだ。
手元には、5-7からの2-3-4の各500円の負け車券があった。
これは、高知競輪最終日(12月27日)の12レースに勝負した車券だった。
今日は、何がなんでも、5-7-2 5-7-3 5-7-4を買うのだと意気込む。
さらに昨日の12レースのおさえは、5-1と5-2 2-5 2-3 2-4であった。
だが、肝心な5の頭を軽視する結果となる。
非常に、悔やまれた。
GP 静岡競輪 KEIRINグランプリ2024
12月28日
6レース
並び予想 5-1-8 6(単騎)2-7-9 3(単騎)4(単騎)
レース評
捲りカマシ強烈な松本を目標に松岡が確かな差し脚を発揮。転倒の支障無ければ新村−簗田が脅威だし伊藤も一発
2-7 7-2 1-7 7-1Ⅰ-5の3連単で勝負してしまう。
1番人気 7-2(3・2倍)
5番の頭が意識から遠のくのだ。
今日は、5-7の3連単は何が何でも買うと思っていたのに、オッズや競馬専門紙の青競を見てしまったことが禍する。
しかも、X◎○のボックス車券も頭になかった。
大きな魚を釣り損ねた気分となる。
「口惜しさをバネに」が利根輪太郎の競輪人間学 であったのに・・・・
| 予 想 |
着 順 |
車 番 |
選手名 | 着差 | 上り | 決ま り手 |
S / B |
勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 5 | 新村 穣 | 11.8 | 捲 | B | 鐘3半捲り | |
| ◎ | 2 | 7 | 松岡 貴久 | 2車身 | 11.6 | 差 | 振上げ差し | |
| ○ | 3 | 2 | 松本 秀之介 | 1/4車輪 | 11.8 | 叩き赤板逃 | ||
| 注 | 4 | 9 | 小酒 大勇 | 2車身 | 11.6 | 熊本勢続き | ||
| 5 | 8 | 田中 孝彦 | 1車身1/2 | 11.7 | 前阻れ切替 | |||
| ▲ | 6 | 3 | 伊藤 信 | 1/2車身 | 11.6 | 機を逸して | ||
| 7 | 4 | 栗山 俊介 | 3/4車身 | 11.5 | 追走のまま | |||
| 8 | 6 | 尾崎 剛 | 3車身 | 11.8 | 切替も後方 | |||
| △ | 9 | 1 | 簗田 一輝 | 2車身 | 12.3 | S | 新村追振れ |
| 2 枠 連 |
複 |
|
2 車 連 |
複 |
|
3 連 勝 |
複 |
|
ワ イ ド |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 |
|
単 |
|
単 |
|
戦い終わって
打鐘の周回で後ろ攻めの松本秀之介-松岡貴久が叩くと、そこに単騎勢が次々と切り替え、下げた新村穣は7番手に。最終ホームから新村が一気に前団を巻き返し、1着ゴール。新村マークの簗田一輝を飛ばした松岡が2着に入線。
1着の新村は「2分戦なので(初手は)前か後ろのどちらかしかない。松本君はそんな徹底先行というタイプでないし、一回引いても巻き返して行けるかなと。今回は怪我もあり欠場後、自分が7番手からどれだけ踏めるかでしたが、静岡の風もあって恵まれた。これだけ動ければ戦えると思うが、上位で大きなレースをするなら、それなりの力が要る。今回はメンバーが良いし、持てる力を出し切れる様に」。
2着の松岡は「捲りに併せて仕事をする準備をしていたら、もうそこに(新村が)来てましたね。気づくのが遅かった。あれで1着を取ろうと思えば、そこから切り替えて捲るしかないが、それをやるのは鬼かなと(苦笑)。完璧ではないけど、そこそこ動けているし大丈夫」。











 </picture>
</picture>

 </picture>
</picture> </picture>
</picture>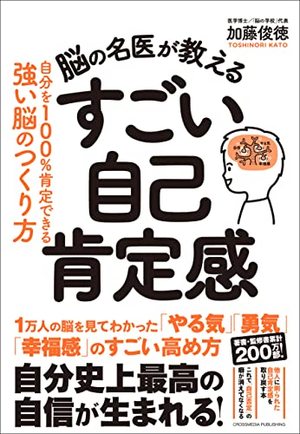



 </picture>
</picture> </picture>
</picture>