先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人 第二回
陽明学入門(二) 苦難の人生体験の中で摑んだ「致良知」の確信
学問の悪弊を正す為に主張された知行合一
自己の心を深めていく事で真理に到達出来ると確信した王陽明(おうようめい)は、知識の多寡(たか)を重視する学問風潮に異議(いぎ)を唱(とな)えた。「知行(ちこう)合一(ごういつ)」の提唱(ていしょう)である。当時の学問の主流だった朱子学(しゅしがく)は、物事の道理(どうり)を究明する事に主眼(しゅがん)を置き、「先知後(せんちこう)行(こう)」(先ず知って後に行う)を当然視していた。その結果、実行を伴わない知識の悪弊(あくへい)が蔓延(まんえん)していた。現代で言えば、知識欲だけは旺盛(おうせい)で、日々知識を追い求めて満足し、他人から実際の行動を求められても、「まだ知識が不充分で確信を持てないから、もっと勉強して行動します。」という「言(い)い訳(わけ)人間」の類(たぐい)である。王陽明は、次の様に断言した。
●「真知(しんち)は即(すなわ)ち行(こう)たる所以(ゆえん)なり。行(おこな)はざれば、これを知(ち)といふに足(た)りず。未(いま)だ知(し)りて行(おこな)はざるものあらず。知(し)りて行(おこな)はざるは、只(た)だ是(こ)れ未(いま)だ知(し)らざるなり。」
(真に知っている事には必ず行動が伴(ともな)う。何も行(おこな)わないのでは、その知識は本物と言えない。未だかつて知っていながらそれを実際行動に移さなかった者は居ない。知っていると言いながら何も行わないのは、実は本当には知らないのである。)
本来「知(ち)」と「行(こう)」は不可分(ふかぶん)で一つのものであり、その静的側面を「知」、動的側面を「行」と称しているに過ぎない。
日本人の心に適合した「存天理去人欲(てんりをそんしてじんよくをさる)」
王陽明は、書斎(しょさい)の人ではなかった。僻遠(へきえん)の地から戻された陽明は、南京(なんきん)や江西省(こうせいしょう)の官職(かんしょく)に任じられ、民政(みんせい)に携(たずさ)わると共に、山賊の平定など治安確保(ちあんかくほ)の為に各地を転戦(てんせん)している。諸族(しょぞく)討伐(とうばつ)の途中、門人宛(もんじんあて)の手紙に陽明は「山中(さんちゅう)の賊を破るは易(やす)く、心中(しんちゅう)の賊を破るは難(かた)し」(山の中に居る山賊を破る事は容易(たやす)い事ですが、自分の心の中に巣食(すく)う欲の賊を破る事は非常に難しい事です。)と書いて送った。自分の心を磨(みが)いて行く学問に終わりはなかった。陽明は門人達に対し「天理(てんり)を存(そん)して人(じん)欲(よく)を去(さ)る」工夫(くふう)を行う様に勧めた。
●「学(がく)とは、これ人欲(じんよく)を去(さ)り天理(てんり)を存(そん)するを学(まな)ぶなり。必(かなら)ず此(こ)の心(こころ)の天理(てんり)に純(じゅん)にして、一毫(いちごう)も人欲(じんよく)の私(わたくし)なからんことを欲(ほっ)す。これ聖(せい)と作(な)るの功(こう)なり。」
(学問とは、心の中に湧(わ)き起こって来る欲望(よくぼう)を取り去って、宇宙の真理とも言うべき「天理(てんり)」と一体の境地(きょうち)まで自分の心を磨き上げて行く事を学ぶ事なのだ。心の中が天理で満たされ、ほんのわずかな人欲(じんよく)の私(わたくし)に執着(しゅうちゃく)する事が無くなる事を求めるべきである。その事こそが、聖人(せいじん)の心境に近づいて行く実践(じっせん)なのだ。)
●「我輩(わがはい)の功(こう)を用(もち)ふる、只(た)だ日(ひ)に減(げん)ずることを求(もと)めて、日(ひ)に増(ま)すことを求(もと)めず。一分(いちぶん)の人(じん)欲(よく)を減(げん)じ得(う)れば、便(すなわ)ち是(こ)れ一分(いちぶん)の天理(てんり)を復(ふく)し得(う)るなり。何等(なんら)の軽快脱洒(けいかいしゃだつ)ぞ、何等(なんら)の簡易(かんい)ぞ。」
(私の言う実践(じっせん)の方法は、ただ、毎日毎日〈人欲(じんよく)に捉(とら)われる自分の愚(おろ)かさを〉減(へ)らして行く事を言うのであって、決して〈知識などを〉増やして行く事を求めない。「日減(にちげん)の学(がく)」である。ほんの少しでも人欲を減らす事が出来れば、その分の天理が心の内に顕(あら)われて来ている事となる。何と快(こころよ)く嬉(うれ)しい事ではないか。何と簡単(かんたん)な事ではないか。)
ここで、「人(じん)欲(よく)を去る」については補足が必要であろう。「人欲」を去れと言う王陽明の言葉は、全く無欲(むよく)の人間になれと言って居るかに誤解されがちだが、人間に肉体がある以上、人欲を消滅(しょうめつ)する事は出来ない。七情(しちじょう)と称せられる喜怒哀楽愛悪欲(きどあいらくあいおよく)の感情は決して無くなる事は無い。問題なのは、その感情に溺(おぼ)れ・執着(しゅうちゃく)する事によって、心が乱れ「人(じん)欲(よく)」の虜(とりこ)になっていく事なのである。人欲が湧(わ)き起こって来てもそれに執着する事の無い心を養う事が出来るならば、感情も天理に合致(がっち)した状態で収(おさ)まり、安らかな境地(きょうち)を維持(いじ)出来る。正に人欲の「適正化(てきせいか)」が述べられているのだ。
●「その数頃(すうけい)の源(みなもと)なきの塘(とう)水(すい)とならんよりは、数尺(すうしゃく)の源(みなもと)あるの井水(いど)の生意(せいい)窮(きわ)まらざるものとならんには若(し)かず。」
(湧(わ)き来(く)る水が無くいつも淀(よど)んでいる広大(こうだい)なため池になるよりも、例(たと)え狭(せま)くともいつも水が渾渾(こんこん)と湧(わ)き立(た)っているような、生命感(せいめいかん)溢(あふ)れる井戸水の様な心境(しんきょう)でありたいものだ。)
王陽明の心には天理と繋(つな)がる無限(むげん)の水源(すいげん)を見出(みいだ)していた。陽明学(ようめいがく)は「有源(ゆうげん)の学(がく)」なのである。
又、王陽明は、天理を存する人間の在(あ)り方を「純金(じゅんきん)」に例えた。人間は皆、光り輝く様な純金を持っている。その純金の量は人間によって違う。吾々はともすると、純金を磨(みが)き出すのではなく、その分量を増す為に鉄や鉛(なまり)などの夾雑物(きょうざつぶつ)を一杯溜(た)め込(こ)まんとする。分量の多寡(たか)を問題にするのでは無く、自らに備わった丈(たけ)の純金を美しく輝き出す事こそが大切なのであると。
この陽明学の考え方は、日本人が求めてきた「清明(せいめい)心(しん)」の伝統に適合(てきごう)するものだった。日本人は、人間は「神(かみ)の子(こ)」として光り輝く生命(いのち)を元来持っているが、罪(つみ)や穢(けが)れによってそれは眩(くら)まされており、不断(ふだん)に禊(みそぎ)祓(はら)いを行(おこな)う事によって、心は清く明るく本来の輝きを取り戻していくという考え方を有(ゆう)して来た。陽明学に連なる日本人が多数出たのは、根本的な人間観に於て一致するものがあったからだと思う。
如何に心を磨きだして行くのか
王陽明の周(まわ)りには、旧来(きゅうらい)の学問に満足出来ない純粋な魂の青年達が次々と集まって来る様になる。彼らに対して王陽明は自己を磨き出す実践(じっせん)の工夫(くふう)を説いた。それが四個(しこ)箇条(かじょう)「立志(りっし)・勤学(きんがく)・改過(かいか)・責(せき)善(ぜん)」である。
●「志(こころざし)、立(た)たざれば、舵(かじ)なきの舟(ふね)のごとく、銜(くつわ)なきの馬(うま)のごとく、漂蕩奔逸(ひょうとうほんいっ)して、つひにまた何(なん)の底(いた)るところかあらん。」
(志が立たなければ、舵(かじ)の無い舟やくつわの無い馬の様に、暴(あば)れ狂ってどこへ行くか解りはしない。それでは、決して目的地に至る事は出来ない。)
先(ま)ずは「聖人(せいじん)と為(な)らん」との志(こころざし)を立てる「立志」から全(すべ)て始まる。現代流に言えば「立派な人間になろう」との強い志を抱き続けるという事である。その志を「立志(りっし)・励(れい)志(し)・持(じ)志(し)」即ち、立て・励(はげ)まし・持ち続ける事が重要なのである。志は何百回、何千回と立て続けねばならない。
次は「勤学(きんがく)」、先哲(せんてつ)の言葉や先人(せんじん)の生き方に日々学び、自らの人生の在(あ)り方を省(かえり)みて行く学問に親しみ勤(いそ)しむ事である。その上で、日常生活での実践(じっせん)を積み重ねていく必要がある。
「改過(かいか)」過(あやま)ちを即座(そくざ)に改(あらた)める事である。人間は過(あやま)ちを犯(おか)しやすい、だが、過ちに気付(きづ)く力も持っている。それ故、過ちを飾(かざ)り弁解(べんかい)して取り繕(つくろ)うのではなく、過ちを素直(すなお)に認めて即座(そくざ)に改める事が出来るか否かに、人間の勇気や誠実(せいじつ)さが現(あらわ)れるのである。「改過(かいか)」こそが自分の驕(おご)りや高ぶりを克服する方法である。
更には「責(せき)善(ぜん)」人間には「善(ぜん)」を識別(しきべつ)できる能力が備わっている。それ故、「善」なるものを即座(そくざ)に行い、「悪」なるものは即座に拒否する事を習慣化(しゅうかんか)するだけで、人間本来の輝きが発揮(はっき)されて行くのである。
王陽明は、ともすれば本来(ほんらい)の心を失(うしな)いがちな門人に対して、かつての竜場(りゅうじょう)での修行(しゅぎょう)を振り返り、静坐(せいざ)の効用(こうよう)を説(と)いた。多忙を極(きわ)める現代人にとっても、じっくりと自分自身を見つめる時間を持つ事は極めて重要である。
だが、弟子達の中には、静坐の時は自己を摑(つか)んだ気がするが、普通の生活に戻ると心が乱れるという、静坐好(せいざごの)みの弊害(へいがい)が生れて来た。そこで王陽明は「事上磨錬(じじょうまれん)」の必要を強調した。
●「人(ひと)はすべからく事上(じじょう)に在(あ)りて磨錬(まれん)し、功夫(くふう)を做(な)すべし。すなはち益(えき)あらん。もし只(た)だ静(せい)を好(この)まば、事(こと)に遇(あ)ひてすなはち乱(みだ)れ、ついに長進(ちょうしん)なく、静時(せいじ)の工夫(くふう)もまた差(たが)はん。」
(人間は実(じっ)生活(せいかつ)を生きている。それ故、実際の物事に当りながら心を磨(みが)き練(ね)り上げて行く工夫(くふう)こそが大切なのだ。そうすれば、必ず身についていくであろう。もし、静坐(せいざ)にばかり頼(たよ)っていたら、物事に遭遇(そうぐう)した時には、心が乱れて、それ迄の功夫(くふう)は全く役に立たなくなってしまう。)
日常生活の有(あ)らゆる事柄(ことがら)において、本来の自分を実現して行くことによってのみ人間は生長(せいちょう)して行くのである。
「致良知(ちりょうち)」こそ陽明学の心髄(しんずい)
王陽明は四十八歳の時、江西省(こうせいしょう)南昌(なんしょう)に拠(よ)って叛乱(はんらん)を起した王族の寧王(ねいおう)宸(しん)濠(ごう)を討伐(とうばつ)しわずか二週間で平定(へいてい)する。その手際(てぎわ)の見事(みごと)さは逆に朝廷(ちょうてい)に嫉妬(しっと)を生み、王陽明の学問の隆盛(りゅうせい)は旧来(きゅうらい)の学者達の総攻撃を生む。誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)渦巻(うずま)く中にあって、陽明哲学の心髄(しんずい)ともいう「致良知(ちりょうち)」説に到達する。
●「其(そ)れ良知(りょうち)は、即(すなわ)ちいはゆる是非(ぜひ)の心(こころ)、人(ひと)みなこれあり。学(まな)ぶを待(ま)たずして有(あ)り、慮(おもんばか)るを待(ま)たずして得(う)る者(もの)なり。人(ひと)たれかこの良知(りょうち)なからんや。独(ひと)りこれを致(いた)すことあたはざるあるのみ。」
(良知(りょうち)というのは、物事(ものごと)の是非(ぜひ)を弁別(べんべつ)出来る自己(じこ)本来(ほんらい)の心で、全(すべ)ての人が持っている。それは、学ぶ以前から備(そな)わっており、思い運(めぐ)らさ無くても元々身についているものなのだ。人間であれば全ての人が良知を持っている。しかし、普通の人は、この良知(りょうち)を致(いた)す事、良知に基づいて生きる事が出来ないでいるだけなのである。)
「良知」は『孟子(もうし)』尽心章句上(じんしんしょうくじょう)に出て来る「慮(おもんばか)らずして知覚(ちかく)する、人間本来の『知(ち)』」という意味で、王陽明はこの言葉に着眼(ちゃくがん)して、良知を「致(いた)す」事、即ち良知の発する叫びのままに生き行動することが「聖人」に至る道であり、「良知」のみに従って生きれば良いと、これ迄求め続けて来た自らの学問の究極(きゅうきょく)を「致良知(ちりょうち)」の三語で表現した。
若い時に落馬(らくば)して胸を強打していた王陽明は、歳を重ねるにつれて体調(たいちょう)不良(ふりょう)を覚(おぼ)え、官職(かんしょく)を退(しりぞ)く事を願い出た。だが許されず、五十六歳にして江西省(こうせいしょう)思恩(しおん)・田州(でんしゅう)の匪賊(ひぞく)平定(へいてい)を命じられる。陽明は見事に匪賊(ひぞく)を討伐恭順(とうばつきょうじゅん)させると共に、賊(ぞく)の生れる原因を根絶(こんぜつ)すべく、民生(みんせい)と教化(きょうか)に力を注(そそ)いだ。翌年、病状が悪化し、故郷への帰路(きろ)、十月二十九日に南安(なんあん)の青竜舗(せいりゅうほ)(江西(こうせい)省)にて逝去(せいきょ)した。五十七歳だった。
●「この心(こころ)、光明(こうみょう)なり。はたまた何(なに)をか言(い)はん。」(自分の心の中では良知が光り明るく輝いている。これ以上何を望もうか。何を言おうか。)
王陽明の生涯には、様々な苦難が襲(おそ)った。その中で見出された「致良知(ちりょうち)」の訓(おし)えには、実践(じっせん)に裏打ちされた万鈞(ばんきん)の重みがある。それ故にこそ幕末維新(ばくまついしん)の志士達(ししたち)を始め多くの日本人を惹(ひ)きつけ魅了(みりょう)する言葉を歴史に残したのである。
陽明学入門(二) 苦難の人生体験の中で摑んだ「致良知」の確信
学問の悪弊を正す為に主張された知行合一
自己の心を深めていく事で真理に到達出来ると確信した王陽明(おうようめい)は、知識の多寡(たか)を重視する学問風潮に異議(いぎ)を唱(とな)えた。「知行(ちこう)合一(ごういつ)」の提唱(ていしょう)である。当時の学問の主流だった朱子学(しゅしがく)は、物事の道理(どうり)を究明する事に主眼(しゅがん)を置き、「先知後(せんちこう)行(こう)」(先ず知って後に行う)を当然視していた。その結果、実行を伴わない知識の悪弊(あくへい)が蔓延(まんえん)していた。現代で言えば、知識欲だけは旺盛(おうせい)で、日々知識を追い求めて満足し、他人から実際の行動を求められても、「まだ知識が不充分で確信を持てないから、もっと勉強して行動します。」という「言(い)い訳(わけ)人間」の類(たぐい)である。王陽明は、次の様に断言した。
●「真知(しんち)は即(すなわ)ち行(こう)たる所以(ゆえん)なり。行(おこな)はざれば、これを知(ち)といふに足(た)りず。未(いま)だ知(し)りて行(おこな)はざるものあらず。知(し)りて行(おこな)はざるは、只(た)だ是(こ)れ未(いま)だ知(し)らざるなり。」
(真に知っている事には必ず行動が伴(ともな)う。何も行(おこな)わないのでは、その知識は本物と言えない。未だかつて知っていながらそれを実際行動に移さなかった者は居ない。知っていると言いながら何も行わないのは、実は本当には知らないのである。)
本来「知(ち)」と「行(こう)」は不可分(ふかぶん)で一つのものであり、その静的側面を「知」、動的側面を「行」と称しているに過ぎない。
日本人の心に適合した「存天理去人欲(てんりをそんしてじんよくをさる)」
王陽明は、書斎(しょさい)の人ではなかった。僻遠(へきえん)の地から戻された陽明は、南京(なんきん)や江西省(こうせいしょう)の官職(かんしょく)に任じられ、民政(みんせい)に携(たずさ)わると共に、山賊の平定など治安確保(ちあんかくほ)の為に各地を転戦(てんせん)している。諸族(しょぞく)討伐(とうばつ)の途中、門人宛(もんじんあて)の手紙に陽明は「山中(さんちゅう)の賊を破るは易(やす)く、心中(しんちゅう)の賊を破るは難(かた)し」(山の中に居る山賊を破る事は容易(たやす)い事ですが、自分の心の中に巣食(すく)う欲の賊を破る事は非常に難しい事です。)と書いて送った。自分の心を磨(みが)いて行く学問に終わりはなかった。陽明は門人達に対し「天理(てんり)を存(そん)して人(じん)欲(よく)を去(さ)る」工夫(くふう)を行う様に勧めた。
●「学(がく)とは、これ人欲(じんよく)を去(さ)り天理(てんり)を存(そん)するを学(まな)ぶなり。必(かなら)ず此(こ)の心(こころ)の天理(てんり)に純(じゅん)にして、一毫(いちごう)も人欲(じんよく)の私(わたくし)なからんことを欲(ほっ)す。これ聖(せい)と作(な)るの功(こう)なり。」
(学問とは、心の中に湧(わ)き起こって来る欲望(よくぼう)を取り去って、宇宙の真理とも言うべき「天理(てんり)」と一体の境地(きょうち)まで自分の心を磨き上げて行く事を学ぶ事なのだ。心の中が天理で満たされ、ほんのわずかな人欲(じんよく)の私(わたくし)に執着(しゅうちゃく)する事が無くなる事を求めるべきである。その事こそが、聖人(せいじん)の心境に近づいて行く実践(じっせん)なのだ。)
●「我輩(わがはい)の功(こう)を用(もち)ふる、只(た)だ日(ひ)に減(げん)ずることを求(もと)めて、日(ひ)に増(ま)すことを求(もと)めず。一分(いちぶん)の人(じん)欲(よく)を減(げん)じ得(う)れば、便(すなわ)ち是(こ)れ一分(いちぶん)の天理(てんり)を復(ふく)し得(う)るなり。何等(なんら)の軽快脱洒(けいかいしゃだつ)ぞ、何等(なんら)の簡易(かんい)ぞ。」
(私の言う実践(じっせん)の方法は、ただ、毎日毎日〈人欲(じんよく)に捉(とら)われる自分の愚(おろ)かさを〉減(へ)らして行く事を言うのであって、決して〈知識などを〉増やして行く事を求めない。「日減(にちげん)の学(がく)」である。ほんの少しでも人欲を減らす事が出来れば、その分の天理が心の内に顕(あら)われて来ている事となる。何と快(こころよ)く嬉(うれ)しい事ではないか。何と簡単(かんたん)な事ではないか。)
ここで、「人(じん)欲(よく)を去る」については補足が必要であろう。「人欲」を去れと言う王陽明の言葉は、全く無欲(むよく)の人間になれと言って居るかに誤解されがちだが、人間に肉体がある以上、人欲を消滅(しょうめつ)する事は出来ない。七情(しちじょう)と称せられる喜怒哀楽愛悪欲(きどあいらくあいおよく)の感情は決して無くなる事は無い。問題なのは、その感情に溺(おぼ)れ・執着(しゅうちゃく)する事によって、心が乱れ「人(じん)欲(よく)」の虜(とりこ)になっていく事なのである。人欲が湧(わ)き起こって来てもそれに執着する事の無い心を養う事が出来るならば、感情も天理に合致(がっち)した状態で収(おさ)まり、安らかな境地(きょうち)を維持(いじ)出来る。正に人欲の「適正化(てきせいか)」が述べられているのだ。
●「その数頃(すうけい)の源(みなもと)なきの塘(とう)水(すい)とならんよりは、数尺(すうしゃく)の源(みなもと)あるの井水(いど)の生意(せいい)窮(きわ)まらざるものとならんには若(し)かず。」
(湧(わ)き来(く)る水が無くいつも淀(よど)んでいる広大(こうだい)なため池になるよりも、例(たと)え狭(せま)くともいつも水が渾渾(こんこん)と湧(わ)き立(た)っているような、生命感(せいめいかん)溢(あふ)れる井戸水の様な心境(しんきょう)でありたいものだ。)
王陽明の心には天理と繋(つな)がる無限(むげん)の水源(すいげん)を見出(みいだ)していた。陽明学(ようめいがく)は「有源(ゆうげん)の学(がく)」なのである。
又、王陽明は、天理を存する人間の在(あ)り方を「純金(じゅんきん)」に例えた。人間は皆、光り輝く様な純金を持っている。その純金の量は人間によって違う。吾々はともすると、純金を磨(みが)き出すのではなく、その分量を増す為に鉄や鉛(なまり)などの夾雑物(きょうざつぶつ)を一杯溜(た)め込(こ)まんとする。分量の多寡(たか)を問題にするのでは無く、自らに備わった丈(たけ)の純金を美しく輝き出す事こそが大切なのであると。
この陽明学の考え方は、日本人が求めてきた「清明(せいめい)心(しん)」の伝統に適合(てきごう)するものだった。日本人は、人間は「神(かみ)の子(こ)」として光り輝く生命(いのち)を元来持っているが、罪(つみ)や穢(けが)れによってそれは眩(くら)まされており、不断(ふだん)に禊(みそぎ)祓(はら)いを行(おこな)う事によって、心は清く明るく本来の輝きを取り戻していくという考え方を有(ゆう)して来た。陽明学に連なる日本人が多数出たのは、根本的な人間観に於て一致するものがあったからだと思う。
如何に心を磨きだして行くのか
王陽明の周(まわ)りには、旧来(きゅうらい)の学問に満足出来ない純粋な魂の青年達が次々と集まって来る様になる。彼らに対して王陽明は自己を磨き出す実践(じっせん)の工夫(くふう)を説いた。それが四個(しこ)箇条(かじょう)「立志(りっし)・勤学(きんがく)・改過(かいか)・責(せき)善(ぜん)」である。
●「志(こころざし)、立(た)たざれば、舵(かじ)なきの舟(ふね)のごとく、銜(くつわ)なきの馬(うま)のごとく、漂蕩奔逸(ひょうとうほんいっ)して、つひにまた何(なん)の底(いた)るところかあらん。」
(志が立たなければ、舵(かじ)の無い舟やくつわの無い馬の様に、暴(あば)れ狂ってどこへ行くか解りはしない。それでは、決して目的地に至る事は出来ない。)
先(ま)ずは「聖人(せいじん)と為(な)らん」との志(こころざし)を立てる「立志」から全(すべ)て始まる。現代流に言えば「立派な人間になろう」との強い志を抱き続けるという事である。その志を「立志(りっし)・励(れい)志(し)・持(じ)志(し)」即ち、立て・励(はげ)まし・持ち続ける事が重要なのである。志は何百回、何千回と立て続けねばならない。
次は「勤学(きんがく)」、先哲(せんてつ)の言葉や先人(せんじん)の生き方に日々学び、自らの人生の在(あ)り方を省(かえり)みて行く学問に親しみ勤(いそ)しむ事である。その上で、日常生活での実践(じっせん)を積み重ねていく必要がある。
「改過(かいか)」過(あやま)ちを即座(そくざ)に改(あらた)める事である。人間は過(あやま)ちを犯(おか)しやすい、だが、過ちに気付(きづ)く力も持っている。それ故、過ちを飾(かざ)り弁解(べんかい)して取り繕(つくろ)うのではなく、過ちを素直(すなお)に認めて即座(そくざ)に改める事が出来るか否かに、人間の勇気や誠実(せいじつ)さが現(あらわ)れるのである。「改過(かいか)」こそが自分の驕(おご)りや高ぶりを克服する方法である。
更には「責(せき)善(ぜん)」人間には「善(ぜん)」を識別(しきべつ)できる能力が備わっている。それ故、「善」なるものを即座(そくざ)に行い、「悪」なるものは即座に拒否する事を習慣化(しゅうかんか)するだけで、人間本来の輝きが発揮(はっき)されて行くのである。
王陽明は、ともすれば本来(ほんらい)の心を失(うしな)いがちな門人に対して、かつての竜場(りゅうじょう)での修行(しゅぎょう)を振り返り、静坐(せいざ)の効用(こうよう)を説(と)いた。多忙を極(きわ)める現代人にとっても、じっくりと自分自身を見つめる時間を持つ事は極めて重要である。
だが、弟子達の中には、静坐の時は自己を摑(つか)んだ気がするが、普通の生活に戻ると心が乱れるという、静坐好(せいざごの)みの弊害(へいがい)が生れて来た。そこで王陽明は「事上磨錬(じじょうまれん)」の必要を強調した。
●「人(ひと)はすべからく事上(じじょう)に在(あ)りて磨錬(まれん)し、功夫(くふう)を做(な)すべし。すなはち益(えき)あらん。もし只(た)だ静(せい)を好(この)まば、事(こと)に遇(あ)ひてすなはち乱(みだ)れ、ついに長進(ちょうしん)なく、静時(せいじ)の工夫(くふう)もまた差(たが)はん。」
(人間は実(じっ)生活(せいかつ)を生きている。それ故、実際の物事に当りながら心を磨(みが)き練(ね)り上げて行く工夫(くふう)こそが大切なのだ。そうすれば、必ず身についていくであろう。もし、静坐(せいざ)にばかり頼(たよ)っていたら、物事に遭遇(そうぐう)した時には、心が乱れて、それ迄の功夫(くふう)は全く役に立たなくなってしまう。)
日常生活の有(あ)らゆる事柄(ことがら)において、本来の自分を実現して行くことによってのみ人間は生長(せいちょう)して行くのである。
「致良知(ちりょうち)」こそ陽明学の心髄(しんずい)
王陽明は四十八歳の時、江西省(こうせいしょう)南昌(なんしょう)に拠(よ)って叛乱(はんらん)を起した王族の寧王(ねいおう)宸(しん)濠(ごう)を討伐(とうばつ)しわずか二週間で平定(へいてい)する。その手際(てぎわ)の見事(みごと)さは逆に朝廷(ちょうてい)に嫉妬(しっと)を生み、王陽明の学問の隆盛(りゅうせい)は旧来(きゅうらい)の学者達の総攻撃を生む。誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)渦巻(うずま)く中にあって、陽明哲学の心髄(しんずい)ともいう「致良知(ちりょうち)」説に到達する。
●「其(そ)れ良知(りょうち)は、即(すなわ)ちいはゆる是非(ぜひ)の心(こころ)、人(ひと)みなこれあり。学(まな)ぶを待(ま)たずして有(あ)り、慮(おもんばか)るを待(ま)たずして得(う)る者(もの)なり。人(ひと)たれかこの良知(りょうち)なからんや。独(ひと)りこれを致(いた)すことあたはざるあるのみ。」
(良知(りょうち)というのは、物事(ものごと)の是非(ぜひ)を弁別(べんべつ)出来る自己(じこ)本来(ほんらい)の心で、全(すべ)ての人が持っている。それは、学ぶ以前から備(そな)わっており、思い運(めぐ)らさ無くても元々身についているものなのだ。人間であれば全ての人が良知を持っている。しかし、普通の人は、この良知(りょうち)を致(いた)す事、良知に基づいて生きる事が出来ないでいるだけなのである。)
「良知」は『孟子(もうし)』尽心章句上(じんしんしょうくじょう)に出て来る「慮(おもんばか)らずして知覚(ちかく)する、人間本来の『知(ち)』」という意味で、王陽明はこの言葉に着眼(ちゃくがん)して、良知を「致(いた)す」事、即ち良知の発する叫びのままに生き行動することが「聖人」に至る道であり、「良知」のみに従って生きれば良いと、これ迄求め続けて来た自らの学問の究極(きゅうきょく)を「致良知(ちりょうち)」の三語で表現した。
若い時に落馬(らくば)して胸を強打していた王陽明は、歳を重ねるにつれて体調(たいちょう)不良(ふりょう)を覚(おぼ)え、官職(かんしょく)を退(しりぞ)く事を願い出た。だが許されず、五十六歳にして江西省(こうせいしょう)思恩(しおん)・田州(でんしゅう)の匪賊(ひぞく)平定(へいてい)を命じられる。陽明は見事に匪賊(ひぞく)を討伐恭順(とうばつきょうじゅん)させると共に、賊(ぞく)の生れる原因を根絶(こんぜつ)すべく、民生(みんせい)と教化(きょうか)に力を注(そそ)いだ。翌年、病状が悪化し、故郷への帰路(きろ)、十月二十九日に南安(なんあん)の青竜舗(せいりゅうほ)(江西(こうせい)省)にて逝去(せいきょ)した。五十七歳だった。
●「この心(こころ)、光明(こうみょう)なり。はたまた何(なに)をか言(い)はん。」(自分の心の中では良知が光り明るく輝いている。これ以上何を望もうか。何を言おうか。)
王陽明の生涯には、様々な苦難が襲(おそ)った。その中で見出された「致良知(ちりょうち)」の訓(おし)えには、実践(じっせん)に裏打ちされた万鈞(ばんきん)の重みがある。それ故にこそ幕末維新(ばくまついしん)の志士達(ししたち)を始め多くの日本人を惹(ひ)きつけ魅了(みりょう)する言葉を歴史に残したのである。
















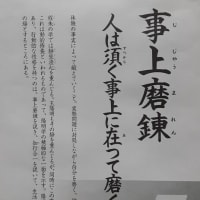









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます