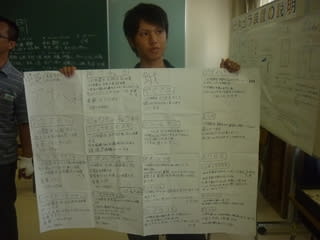10月7日(金)
今日、デンドロビウム・ファレノプシス、いわゆる「デンファレ」といわれるランが咲きました。
枯れかけていたものを何年もかけて育て上げました。
職員室でずっと管理していましたが、ようやく花がたくさん咲きそうなので紹介します。

これがデンファレです。
デンファレはニューギニアや北オーストラリア原産の洋ランの一種です。
比較的育てやすいランです。
しかし、名古屋の夏の暑さには弱いようです。

デンファレの花です。
バルブと言われる茎から花芽を長く伸ばすのが特徴です。

花のアップです。
花の後ろにもう一本、花芽が出ているのがわかります。

つぼみです。
もうそろそろ花が咲きます。

後1週間ほどで花が咲く茎です。
1ヶ月後には、花が一杯になる予定です。
この鉢は、学園本部に飾ってもらうことにしました。
一生懸命育てた花が喜んでもらえるのも、理科部として嬉しいことです。
今後も、いろんな植物を育てていきたいと思います。
今日、デンドロビウム・ファレノプシス、いわゆる「デンファレ」といわれるランが咲きました。
枯れかけていたものを何年もかけて育て上げました。
職員室でずっと管理していましたが、ようやく花がたくさん咲きそうなので紹介します。

これがデンファレです。
デンファレはニューギニアや北オーストラリア原産の洋ランの一種です。
比較的育てやすいランです。
しかし、名古屋の夏の暑さには弱いようです。

デンファレの花です。
バルブと言われる茎から花芽を長く伸ばすのが特徴です。

花のアップです。
花の後ろにもう一本、花芽が出ているのがわかります。

つぼみです。
もうそろそろ花が咲きます。

後1週間ほどで花が咲く茎です。
1ヶ月後には、花が一杯になる予定です。
この鉢は、学園本部に飾ってもらうことにしました。
一生懸命育てた花が喜んでもらえるのも、理科部として嬉しいことです。
今後も、いろんな植物を育てていきたいと思います。