「今日、ホタルを見に行くんだ。」
小1の娘が先生に話したという。普段引込み思案な彼女は積極的に先生に話しかけることはしない。「先生にも言っちゃった。」こうも表現していた。
朝なかなか準備しない娘が、今日は夜3人でホタルを見に行こうというと、目の奥が静かに輝いた。そこにぐずり、だらだらするいつもの彼女はいなくて、6/17はホタルの日になっていた。一日の学校がホタルを見るための過程になり、そこに辿り着くには学校をやり過ごしかないことを彼女は理解していた。
登校班の集合場所に向かう時「ホタルはね、ホントはね、お尻がヒカルんじゃないんだよ。ちょうどベルトの上、この辺がヒカルんだよ。」そして自分のお腹をさすってみせた。
想像以上の反応に戸惑う自分。「飛んでなかったらどうしよう・・」
最近娘とちゃんと遊べていなかった。土日と旗日がお休みの彼女と平日休みがほとんどの自分はすれ違いが増えていた。そしてその休みの日も家の事情でゆっくり休めないことがつづいていた。その日の午前中も義理の父とそのことで打ち合わせをしていた。仕事も不器用な自分であることも影響しているが残業がつづき娘との時間は幼稚園時代と格段に少なくなっていた。
ホタルが神奈川県横浜市旭区のこども自然公園(大池公園)で飛んでいることは3年前から知っていた。職場の同僚が公園近くの二俣川周辺に住んでいてホタルのことを教えてくれていた。その間行けなかったのは、6月10日前後から同月末までがホタルの飛んでいる時期で期間がタイトに限定されていること、そしてコロナがあったから。
夜のお出かけは翌日の小学校がお休みでないとなかなかできないということで、今週が今年のラストチャンスと思い誘ってみた。雨だといけなくなるので、この日が動くには丁度よかった。
観に行くことは決まったが、2つのことが気になった。一つはホタルは出てくるのかということ。そしてもう一つはホタルを見て喜ぶかということ。
これがディズニーランドのエレクトリカルパレードならば、出てくる時間もわかるし、娘が喜ぶことも自信が持てる。今回はホタルだ。出現に関しても自然頼み、喜ぶかどうかも娘の感性・ご機嫌次第。お金はかからないが他力に委ねる、流れに任せるのが今回の試みだった。
初めて行くということと失敗したくないという思いもあり、その大池公園に下見に行った。ホタルが出るくらいなので水が奇麗で自然が豊かな緑地がある公園。どうやら間違って裏の駐車場に着いたらしく、現場までは舗装されていない林道を歩くことになった。時間帯も夕方に差し掛かる時間で誰も歩いていない。一人緑の小路を歩く。木々に囲まれているので気温は2℃ぐらい涼しくひんやりとし、それでいて葉々の隙間を太陽の光が細かくそして優しく差し込み木漏れ日が美しかった。木の臭い、土の香につつまれアスファルトとは違う不規則な感触が足の裏に広がった。足の10本の指それぞれが思い出したかのようにその感覚を懐かしがった。見えない空気が身体に入る時、その清々しい違和感に戸惑いを感じていた。異質の場所にいると感じていたのは身体だけではなかった。深緑の気の循環で、魂にこびりついていた重たい憑物が剥がれ落ちた。心が“5kg”軽くなった。
二俣川に行ったのはもう一つ理由があった。免許の更新だった。電車代がもったいなくて車で向かうも着いてみたら受付時間を1時間過ぎていた。係りの方が長い列を整理するポールを片付けていた。駐車場代に1000円かかり電車よりも倍の金額を支払い目的は果たせず虚しく空ぶった。その凡ミスに自分を責め、自己嫌悪の徒労の中で、日常の疲弊とイライラは増幅していた。緑地の下見はそのすぐ後のことだった。“5kg”というのは大袈裟ではなく、実感を伴う感覚だった。それだけ軽くなった。
しばらく歩くと、ホタルが出てくると言われている場所に辿り着いた。夕暮れ時とはいえ夏日の太陽はまだ黄色くまだその気配は一切なかった。
「本当に現れてくれるのか・・・・」後は夜行ってみてだ。
夕飯を三人でとり、日も落ちいよいよ出かける。娘は夜のお出かけを楽しみにしていた。Colemanのピンクのリュックに大人からすればいらないものを詰め込んでいた。注意書きに、虫よけをするとホタルが寄ってこないとあり、薄手の長袖とロングパンツで出かけた。子どものドキドキと親のドキドキは少し違う。ホタルが出るかどうかは同じだが、それを見て喜んでくれるのかが気になるドキドキなのだ。
下見したことで今度は間違えず表の駐車場に止めることができた。多数の車数でたくさんの人たちが自然のホタルを見に来ているのがすぐにわかった。幸い天気にも恵まれ、あとは現場に向かうのみ。
3人で手を繋いでホタルを見に行く。
懐中電灯で足元を照らす。
歩きながらみんなでホタルの気配を探す。
5ミリぐらいの微かな光がスーッと目の前を舞った。
「ホタルだぁー!」言葉は強いが息を抑えながら娘が言った。
しばらく歩くとところどころにホタルたちは5匹から6匹の単位で木々の中を、小川の上を舞っては消えを繰り返していた。その小さな小さな光は、サイズとは反比例して優しい存在感を放っていた。
肩車をすると娘はホタルの目線でその不規則な小さな光を瞳で追った。その瞳の奥のどこかに儚くも美しいあの光が残ってほしいと祈った。
自分の中に、何百年もの間、繰り返しこの感覚を積み重ねてきた累積を感じた。相続されゆくデジャヴ(既視感)。明らかに初見ではなく遺伝子の中に佇む夏の日常の経験を自分という【代】で追体験した。そして娘も。
帰りにドラッグストアーでアイスを買って帰ろうとなり立ち寄る。ちょうど21:00、閉店10分前。がさごそアイスを3人で探していると店内に流れてくるホタルの光の調べ。
ホタルの光 窓の雪
書(ふみ)読む月日 重ねつつ
いつしか年も 過ぎのとを
明けてぞ 今朝は別れ行く
「ホタルの光 窓の雪・・・」って雪なら冬じゃん!と?はてなが浮かんだ。
だからという訳ではないけれど、雪見だいふくを選んで店を出た。
ホタル見て、ホタルの光が流れてくるなんて粋なエンディングだなんて思いつつ、どうして窓の雪なのかがなぜか気になった。雪見だいふくは口の中ですーっと甘く溶けて消えた。
ホタルの光のように。
昔々あるところに貧しい家族がありました。一人の少年はお父さん、お母さんを助けようと、たくさんの人を幸せにする仕事ができるようになるためにたくさん勉強しました。ところが夜になると暗くて勉強ができません。少年は夏はホタルをたくさんつかまえて、それを灯り代わりにしました。冬は雪の白さを灯り代わりにして勉強をしました。
こんな話から、ホタルの光の詩は生まれた。蛍雪時代という受験雑誌もここに由来があるとのこと。
由来といえばこの曲はスコットランド民謡が原曲の【Auld Lang Syneーオールド・ラング・ザインー】。大晦日にかかる曲。それこそ30数年前、17歳のころUCLAの学生にこの曲を教えてくれとお願いした。LAから日本に英語を教えに来たアダムはそれを喜んだ。二人で日本語と英語で歌い合った。意味はわからなくともメロディーで二人は繋がれた。国を越え、民族を越え、世代を越えて。それは17歳の自分にはとても刺激的で濃厚で美しい体験だった。今思えばアダムにしても初めて来た日本で20歳そこそこの青年が異国の少年とホタルの光を歌い合うのは相当ディープな体験だっただろう。
アダムのルーツはわからないが、白人でその名前からアングロ・サクソン系であることは想像できた。【Auld Lang Syne】は英語の古語で歌われている。彼にしてもまた、彼の地スコットランド、母語の原点に還っている瞬間でもあったろう。
国を越えるもの、時代・世代を越えるもの。その普遍性の中に引き継がれていくものの尊さを想う。魂の根っこに滋養する。
ホタルの寿命は1~2週間、人の一生は長くて80数年そこら。宇宙の時間軸で見ればそんなに変りはしない。その放たれた光に意味はないかもしれない。でも、そのどこかの光が命の記憶に宿ることで残っていくものもある。
濾過して、濾過して残り引き継がれていくもの。この全存在をもって、時の媒体となります。たとえそれが小さくとも。三人で見たホタルの光を刻み籠めよう、今ここに。
小1の娘が先生に話したという。普段引込み思案な彼女は積極的に先生に話しかけることはしない。「先生にも言っちゃった。」こうも表現していた。
朝なかなか準備しない娘が、今日は夜3人でホタルを見に行こうというと、目の奥が静かに輝いた。そこにぐずり、だらだらするいつもの彼女はいなくて、6/17はホタルの日になっていた。一日の学校がホタルを見るための過程になり、そこに辿り着くには学校をやり過ごしかないことを彼女は理解していた。
登校班の集合場所に向かう時「ホタルはね、ホントはね、お尻がヒカルんじゃないんだよ。ちょうどベルトの上、この辺がヒカルんだよ。」そして自分のお腹をさすってみせた。
想像以上の反応に戸惑う自分。「飛んでなかったらどうしよう・・」
最近娘とちゃんと遊べていなかった。土日と旗日がお休みの彼女と平日休みがほとんどの自分はすれ違いが増えていた。そしてその休みの日も家の事情でゆっくり休めないことがつづいていた。その日の午前中も義理の父とそのことで打ち合わせをしていた。仕事も不器用な自分であることも影響しているが残業がつづき娘との時間は幼稚園時代と格段に少なくなっていた。
ホタルが神奈川県横浜市旭区のこども自然公園(大池公園)で飛んでいることは3年前から知っていた。職場の同僚が公園近くの二俣川周辺に住んでいてホタルのことを教えてくれていた。その間行けなかったのは、6月10日前後から同月末までがホタルの飛んでいる時期で期間がタイトに限定されていること、そしてコロナがあったから。
夜のお出かけは翌日の小学校がお休みでないとなかなかできないということで、今週が今年のラストチャンスと思い誘ってみた。雨だといけなくなるので、この日が動くには丁度よかった。
観に行くことは決まったが、2つのことが気になった。一つはホタルは出てくるのかということ。そしてもう一つはホタルを見て喜ぶかということ。
これがディズニーランドのエレクトリカルパレードならば、出てくる時間もわかるし、娘が喜ぶことも自信が持てる。今回はホタルだ。出現に関しても自然頼み、喜ぶかどうかも娘の感性・ご機嫌次第。お金はかからないが他力に委ねる、流れに任せるのが今回の試みだった。
初めて行くということと失敗したくないという思いもあり、その大池公園に下見に行った。ホタルが出るくらいなので水が奇麗で自然が豊かな緑地がある公園。どうやら間違って裏の駐車場に着いたらしく、現場までは舗装されていない林道を歩くことになった。時間帯も夕方に差し掛かる時間で誰も歩いていない。一人緑の小路を歩く。木々に囲まれているので気温は2℃ぐらい涼しくひんやりとし、それでいて葉々の隙間を太陽の光が細かくそして優しく差し込み木漏れ日が美しかった。木の臭い、土の香につつまれアスファルトとは違う不規則な感触が足の裏に広がった。足の10本の指それぞれが思い出したかのようにその感覚を懐かしがった。見えない空気が身体に入る時、その清々しい違和感に戸惑いを感じていた。異質の場所にいると感じていたのは身体だけではなかった。深緑の気の循環で、魂にこびりついていた重たい憑物が剥がれ落ちた。心が“5kg”軽くなった。
二俣川に行ったのはもう一つ理由があった。免許の更新だった。電車代がもったいなくて車で向かうも着いてみたら受付時間を1時間過ぎていた。係りの方が長い列を整理するポールを片付けていた。駐車場代に1000円かかり電車よりも倍の金額を支払い目的は果たせず虚しく空ぶった。その凡ミスに自分を責め、自己嫌悪の徒労の中で、日常の疲弊とイライラは増幅していた。緑地の下見はそのすぐ後のことだった。“5kg”というのは大袈裟ではなく、実感を伴う感覚だった。それだけ軽くなった。
しばらく歩くと、ホタルが出てくると言われている場所に辿り着いた。夕暮れ時とはいえ夏日の太陽はまだ黄色くまだその気配は一切なかった。
「本当に現れてくれるのか・・・・」後は夜行ってみてだ。
夕飯を三人でとり、日も落ちいよいよ出かける。娘は夜のお出かけを楽しみにしていた。Colemanのピンクのリュックに大人からすればいらないものを詰め込んでいた。注意書きに、虫よけをするとホタルが寄ってこないとあり、薄手の長袖とロングパンツで出かけた。子どものドキドキと親のドキドキは少し違う。ホタルが出るかどうかは同じだが、それを見て喜んでくれるのかが気になるドキドキなのだ。
下見したことで今度は間違えず表の駐車場に止めることができた。多数の車数でたくさんの人たちが自然のホタルを見に来ているのがすぐにわかった。幸い天気にも恵まれ、あとは現場に向かうのみ。
3人で手を繋いでホタルを見に行く。
懐中電灯で足元を照らす。
歩きながらみんなでホタルの気配を探す。
5ミリぐらいの微かな光がスーッと目の前を舞った。
「ホタルだぁー!」言葉は強いが息を抑えながら娘が言った。
しばらく歩くとところどころにホタルたちは5匹から6匹の単位で木々の中を、小川の上を舞っては消えを繰り返していた。その小さな小さな光は、サイズとは反比例して優しい存在感を放っていた。
肩車をすると娘はホタルの目線でその不規則な小さな光を瞳で追った。その瞳の奥のどこかに儚くも美しいあの光が残ってほしいと祈った。
自分の中に、何百年もの間、繰り返しこの感覚を積み重ねてきた累積を感じた。相続されゆくデジャヴ(既視感)。明らかに初見ではなく遺伝子の中に佇む夏の日常の経験を自分という【代】で追体験した。そして娘も。
帰りにドラッグストアーでアイスを買って帰ろうとなり立ち寄る。ちょうど21:00、閉店10分前。がさごそアイスを3人で探していると店内に流れてくるホタルの光の調べ。
ホタルの光 窓の雪
書(ふみ)読む月日 重ねつつ
いつしか年も 過ぎのとを
明けてぞ 今朝は別れ行く
「ホタルの光 窓の雪・・・」って雪なら冬じゃん!と?はてなが浮かんだ。
だからという訳ではないけれど、雪見だいふくを選んで店を出た。
ホタル見て、ホタルの光が流れてくるなんて粋なエンディングだなんて思いつつ、どうして窓の雪なのかがなぜか気になった。雪見だいふくは口の中ですーっと甘く溶けて消えた。
ホタルの光のように。
昔々あるところに貧しい家族がありました。一人の少年はお父さん、お母さんを助けようと、たくさんの人を幸せにする仕事ができるようになるためにたくさん勉強しました。ところが夜になると暗くて勉強ができません。少年は夏はホタルをたくさんつかまえて、それを灯り代わりにしました。冬は雪の白さを灯り代わりにして勉強をしました。
こんな話から、ホタルの光の詩は生まれた。蛍雪時代という受験雑誌もここに由来があるとのこと。
由来といえばこの曲はスコットランド民謡が原曲の【Auld Lang Syneーオールド・ラング・ザインー】。大晦日にかかる曲。それこそ30数年前、17歳のころUCLAの学生にこの曲を教えてくれとお願いした。LAから日本に英語を教えに来たアダムはそれを喜んだ。二人で日本語と英語で歌い合った。意味はわからなくともメロディーで二人は繋がれた。国を越え、民族を越え、世代を越えて。それは17歳の自分にはとても刺激的で濃厚で美しい体験だった。今思えばアダムにしても初めて来た日本で20歳そこそこの青年が異国の少年とホタルの光を歌い合うのは相当ディープな体験だっただろう。
アダムのルーツはわからないが、白人でその名前からアングロ・サクソン系であることは想像できた。【Auld Lang Syne】は英語の古語で歌われている。彼にしてもまた、彼の地スコットランド、母語の原点に還っている瞬間でもあったろう。
国を越えるもの、時代・世代を越えるもの。その普遍性の中に引き継がれていくものの尊さを想う。魂の根っこに滋養する。
ホタルの寿命は1~2週間、人の一生は長くて80数年そこら。宇宙の時間軸で見ればそんなに変りはしない。その放たれた光に意味はないかもしれない。でも、そのどこかの光が命の記憶に宿ることで残っていくものもある。
濾過して、濾過して残り引き継がれていくもの。この全存在をもって、時の媒体となります。たとえそれが小さくとも。三人で見たホタルの光を刻み籠めよう、今ここに。













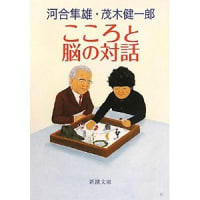






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます