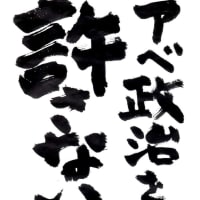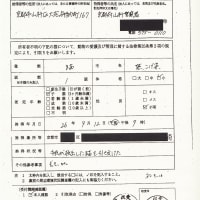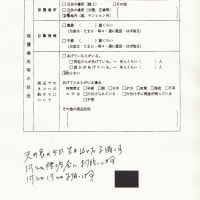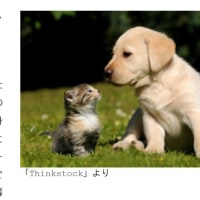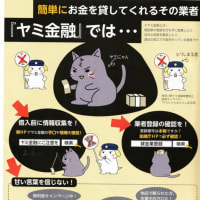2013年8月11日、auのニュースサイト EZニュースフラッシュ増刊号
「潜入! ウワサの現場」で記事
「『半沢直樹』も勝てない!? 『ミタ』の視聴率が40%を超えた理由」
を企画、取材、執筆しました。
現在放送中のドラマ『あまちゃん』(NHK)や『半沢直樹』(TBS系列)の人気が話題になっているが、それでも視聴率は20%台。それに比べて、最終回で「40%」もの視聴率を叩きだした『家政婦のミタ』の人気ぶりは際立っていた。なぜ『家政婦のミタ』は、ここまで多くの人々の心を掴んだのか。
その理由を探求する「人気ドラマに託されたもの『家政婦のミタ』視聴率40%の背景」と題する講演会が7月20日、東京都八王子市内であった。主催は八王子市。講演したのは、中央大学教授の宇佐美毅氏。同氏はテレビドラマを研究をする学者である。空前の人気ドラマの背景にあるものを知るため、現地へ向かった。
会場は60代の男女を中心に約50人が参加。そのうち約半数は『家政婦のミタ』の視聴者だった。
『家政婦のミタ』は11年10月~12月日まで日本テレビ系列で放送された水曜ドラマ(全11話)。脚本は遊川和彦。出演は松嶋菜々子、長谷川博己など。
主人公は、母親を自殺で失った家族で働き始めた家政婦の三田灯(あかり)。灯は無表情で機械のようにそつなく無機質に作業し、掃除箇所などを依頼されると「承知しました」と繰り返し、「私を殺して」といわれても「承知しました」と言ってのけ、何を尋ねられても必要最小限しか話さない。そんな灯には実は秘密があった、というストーリー。
『家政婦のミタ』は平均視聴率25.2%。通常のドラマは初回視聴率が高く、その後、継続して見る人とやめる人に分かれるので、徐々に落ちて行くのが相場だが、『家政婦のミタ』の場合は、1~4話は20%弱、5~7話が20%前半、そして8話29.6%、9話27.6%、10話28.6%と跳ね上がり、SNSなどネット上で結末への期待が高まり、最終話は40.0%と今世紀ドラマ最高視聴率を叩き出した。
なぜ、高視聴率になったのか? 宇佐美氏はこう分析する。
まず、脚本家・遊川和彦氏の知名度と期待度。遊川氏は『ADブギ』(91年、TBS)でダウンタウンの浜田雅功を主演に抜擢したり、近年では天海祐希主演の『女王の教室』(05年、日本テレビ)などを手がけた人物。
「遊川和彦という脚本家を普段、あまり意識されないとしても、作品名を見れば、『ああ、あれを書いていた人か』と思う人も多いのではないでしょうか。ちなみに、フツーのドラマといいますか、一般的なドラマは書かない。衝撃的な作品、変わった作品を書く人、といってもいいかもしれません。『純と愛』(NHK、12~13年、遊川氏が脚本)は記憶に新しいですけど、NHKの朝ドラの中で、あれほどヒロインが嫌われたドラマはない、と言われました。視聴率はいいんですけど、『あの主人公がとにかく不愉快だ』とか『独善的だ』とか『朝からイライラする』といった投書や書き込みがされました。NHKの朝ドラは大体、けな気で明るくて前向きな女の子が定番なんですが、みんなから嫌われる人物をもってくる。これは遊川和彦さんならではいえるかもしれません」(宇佐美氏)
キレイごとだけではない、醜さも含めた人間の本質に迫ろうとする遊川氏の才能。それ以外に、タイトルのネーミングにも特徴があるという。
かつて『家政婦は見た!』というドラマがあった。83年~08年にテレビ朝日系列で放送された番組で、市原悦子が演じる家政婦が、派遣された先の家庭でさまざな出来事を見聞きするというドラマ。視聴者のなかは、この作品を連想して、『家政婦のミタ』に興味を持つケースもあった。
もう一つの要因は、「ドラマ冒頭の衝撃」と宇佐美氏は語り、『家政婦のミタ』の冒頭シーンをスクリーンに流した。出だしは、早朝のカラスのいる住宅街を、一人の女性が無表情で闊歩し、一つの家の前に辿り着き、玄関の「阿須田」という名札をジッと見て立っている。場面は変わり、散らかった家の中を、菓子パンを食べたりする阿須田家の四人の子どもと、トイレにこもった若い父親の映像が流れる。そして場面は戻って、冒頭の女性がチャイムを鳴らし、父親がドアを開けると、「家政婦の三田です。晴海家政婦紹介所から参りました」という出だし。
「普通、ドラマの冒頭は、主人公を説明するんですが、このドラマは謎に包まれた人物として出てる。何を狙っているのかわからせないという衝撃があります」(宇佐美氏)
次に、『家政婦のミタ』の背後にあるものについて、宇佐美氏は語った。
ドラマは回が進むにつれて、三田灯の謎が徐々に明かされていく。実は灯には、暗い過去があった。幼少期には、川で溺れた自分を助けようとした父親が溺死。それ以来、実の母に疎まれるようになった。さらに、結婚後は、夫の弟がストーカー行為のはてに家に火を点けたため、最愛の夫と長男を失ってしまう。しかもそのことを、灯のせいだと夫の母に責められ、「二度と笑うな」と罵倒された。
灯はその過去を、阿須田家にだけ打ち明けた。それはなぜか。
「阿須田は、妻を自殺で失った家庭で、そのことで子どもたちが苦悩していた。つまり、『家政婦のミタ』は、身近な家族に死なれてしまった者同士の物語であり、同じ境遇たからこそ、共有する苦悩と回復があった。特に三田灯の方は、自分のせいで夫と長男を死なせてしまった、という罪の意識から、一生笑わないことを決めて生きている。阿須田家の方は、三田灯ほどの罪の意識ではないかもしれないが、『自分がいけないから妻を死なせてしまったのかもしれない』という夫と、自殺による心の傷を抱えている四人の子どもたちです。同じように大事な家族を失ってしまった者同士だからこそ、苦悩を共有し、そしてそこから回復していくことができる。そういう物語になっている」と宇佐美氏は指摘する。
さらに、「『家政婦のミタ』は『サバイバーズ・ギルド』をめぐる物語ではないか」と氏は語る。
「サバイバーズ・ギルド」とは、事故や災害などで命を失った人の家族や友人、知人など生き残った周囲の人が「自分だけ助かってよかったのか」と、自責の念にさいなまれる“トラウマ現象”である。
そして、『家政婦のミタ』は、その「死」というトラウマを乗り越える人々の物語である、と宇佐美氏はいう。古今東西、「死を乗り越える人々」をテーマにした小説、映画、ドラマなどのフィクション作品は多いが、『家政婦のミタ』の場合は、「生き残ってしまった申し訳ない」というサイバーズ・ギルドとしての「死」を乗り越えるストーリーになっている。
さらに時代背景にも言及した。「近代は、安全性が保たれて、それ以前に比べて、『死』が身近ではない社会といわれます。また、昔は大家族が中心で、祖父、祖母などの死が身近にあったが、現代は核家族化して、人の死が身近でなくなった社会です。そのなかで突然身近な人を失う衝撃は、死が身近でない社会なだけに、衝撃を受ける度合いが高い。もう一つは、自殺者が多い社会であるという点です。昨年は下回りましたが、それまでここ十数年、日本の自殺者は毎年3万人を超えていました。これは諸外国と比べても高い数字です。自殺によって身近な人を失うということは、他の原因以上に、自殺された側の心の傷になることが多い。『なぜ自分に話してくれなかったのか』『自分が声をかけていれば自殺は防げたんじゃないか』『自分がもうちょっと親身になってあげたら、自殺せずに済んだのではないか』、そういった気持ちになりやすい。このように現代社会は、人の死が心の傷になりやすい社会であるといえます。ですから、サバイバーズ・ギルドは現代にとって、大きな課題だと思います」
このように『家政婦のミタ』の背景に現代社会の抱える課題が存在する点を指摘した上で、最後に宇佐美氏はこう語った。
「『家政婦のミタ』が多くの人の心に届いたことと、東日本大震災と同じ年に放送されたことは、偶然ではないと思います。東日本大震災のあとの日本人の心の傷が、作品に共鳴したのではないか。こういった人気のテレビドラマの深層には、その背景となる社会の気持ち、願いが込められているものです」
このように、視聴率40%にはそれ相応の理由があった。社会現象となっているテレビドラマを分析することで、今がどういう時代なのかを浮き彫りにしていく。テレビドラマを観る際、ここまでつき詰めることができれば、一層楽しめるのではないか。(佐々木奎一)
写真は、中央大学教授の宇佐美毅氏。