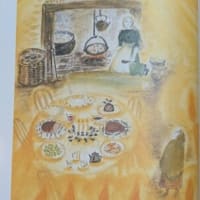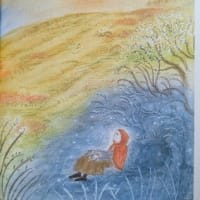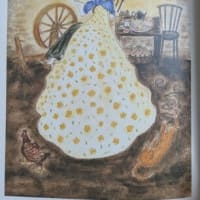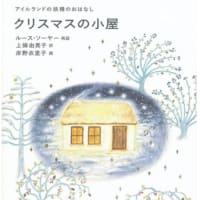■『危機に立つアンコール遺跡』(朝日新聞社)
初版1990年 2600円
※2001.8~のノートよりメモを抜粋しました。
※「読書感想メモリスト2」カテゴリーに追加しました。
(著者名などメモになかったけど、リンク先のこちらだと思われ
▼あらすじ(ネタバレ注意
 歴史
歴史
カンボジア(クメール民族)文化は、大河メコンのほとりで
9~14C(クメール王国・アンコール王朝)時が最隆
15C シャム(タイ)侵攻
1860 フランス学者の再発見により植民地化
シェムレアプ市に「アンコール遺跡保存事務所」設立
1920~修復開始
1970 第二次インドシナ戦争に巻き込まれ“赤色クメール(カンプチア共産党)”により修復中止
1975 終戦 ポルポト政権の「集産主義」による大量虐殺
1980~外国人訪問を許可 日本も含め保全事業が始まるが、インドの安価修復等の問題も多い
(ダイオキシンによる洗浄
 荒廃
荒廃
雨季と乾季の繰り返しによる砂岩の鱗剥、砂泥化、コケの枯死後に大発生したカビ、
酸性雨 、コウモリの排泄物等による「とろけ」、落雷
、コウモリの排泄物等による「とろけ」、落雷 、大竜巻
、大竜巻 などの天災、
などの天災、
緑 の生育による倒壊、人為的破壊、タイ、西欧への盗難、密輸は日本にも及ぶ!
の生育による倒壊、人為的破壊、タイ、西欧への盗難、密輸は日本にも及ぶ!
「人と遺跡の運命は一体」だから遺跡修復も人間再生と一体でなくてはならない
文化=人の生の様式
文化遺産=過去の生の様式を現在に、未来に伝えることにより、歴史の連続性を保証する生きた実体
*
2016.9.20
アンコールワットは一度行ってみたい場所の1つだった
親が行った時の感想を聞くと、まず遠いこと、暑いことが難儀だよね
「浮き彫りがセクシーだった」と母の感想(そっちかい
星野道夫さんの著書には、少数民族のある考えでは、滅びゆくものは、自然に任せるほうがいいって書いてあって、それも納得
人的破壊はともかく、ひとつの文化が“崩れる”のではなく“自然に還る”姿は美しいという見方もできる
初版1990年 2600円
※2001.8~のノートよりメモを抜粋しました。
※「読書感想メモリスト2」カテゴリーに追加しました。
(著者名などメモになかったけど、リンク先のこちらだと思われ
▼あらすじ(ネタバレ注意
 歴史
歴史カンボジア(クメール民族)文化は、大河メコンのほとりで
9~14C(クメール王国・アンコール王朝)時が最隆
15C シャム(タイ)侵攻
1860 フランス学者の再発見により植民地化
シェムレアプ市に「アンコール遺跡保存事務所」設立
1920~修復開始
1970 第二次インドシナ戦争に巻き込まれ“赤色クメール(カンプチア共産党)”により修復中止
1975 終戦 ポルポト政権の「集産主義」による大量虐殺
1980~外国人訪問を許可 日本も含め保全事業が始まるが、インドの安価修復等の問題も多い
(ダイオキシンによる洗浄
 荒廃
荒廃雨季と乾季の繰り返しによる砂岩の鱗剥、砂泥化、コケの枯死後に大発生したカビ、
酸性雨
 、コウモリの排泄物等による「とろけ」、落雷
、コウモリの排泄物等による「とろけ」、落雷 、大竜巻
、大竜巻 などの天災、
などの天災、緑
 の生育による倒壊、人為的破壊、タイ、西欧への盗難、密輸は日本にも及ぶ!
の生育による倒壊、人為的破壊、タイ、西欧への盗難、密輸は日本にも及ぶ!「人と遺跡の運命は一体」だから遺跡修復も人間再生と一体でなくてはならない
文化=人の生の様式
文化遺産=過去の生の様式を現在に、未来に伝えることにより、歴史の連続性を保証する生きた実体
*
2016.9.20
アンコールワットは一度行ってみたい場所の1つだった
親が行った時の感想を聞くと、まず遠いこと、暑いことが難儀だよね

「浮き彫りがセクシーだった」と母の感想(そっちかい
星野道夫さんの著書には、少数民族のある考えでは、滅びゆくものは、自然に任せるほうがいいって書いてあって、それも納得
人的破壊はともかく、ひとつの文化が“崩れる”のではなく“自然に還る”姿は美しいという見方もできる