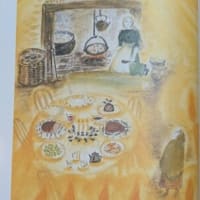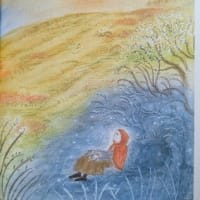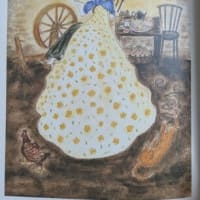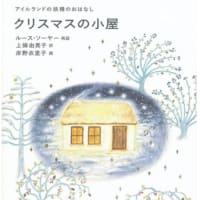■本人が語る認知症@あさイチ
専門家ゲスト:福田人志さん(認知症当事者)、松本一生さん(認知症専門医)
ゲスト:ミッツ・マングローブさん、柴田理恵さん
リポーター:雨宮萌香アナウンサー
“2025年には高齢者の5人に1人がなるといわれる認知症。
「なんとなく怖いもの」として不安を抱いている人が多いかもしれません。
番組では、認知症のご本人をスタジオに招き、世間のイメージと現実とのギャップを本音で語ってもらいました。
キーワードは認知症の人の「語り」です。まず大切なのは、認知症の本人どうしでの語り合い。
家族にも言えない悩みや、日々の困りごとを解消する知恵を共有することで、
症状が悪化せずに済んでいるという人たちをご紹介しました。
また、認知症の症状が進んで話すことができなくなったとしても、
周囲にいる「語れる認知症の人」がその人の気持ちを代弁することで、よりよい介護につながった現場も取材。
さらに、本人の行動をとことん見つめることで、その背景にある本音を探り当てる自治体の取り組みについても紹介しました。
本人の声によって大きく変わりつつある、認知症の今についてお伝えしました。”
【ブログ内関連記事】
 認知症×人気カフェ@あさイチ
認知症×人気カフェ@あさイチ
 「認知症介護 家族交流会で“介護離職”を防ぐ」@ビッグイシュー
「認知症介護 家族交流会で“介護離職”を防ぐ」@ビッグイシュー
●ゲスト:福田人志さん(認知症当事者)
51歳で発症した時は、半年間落ち込み、外へも出なかった
本人同士がコミュニケーションできる場をもってから明るくなった
ヤナギー:こうして見ると、認知症にはまったく見えないがどんな症状がある?
(ハキハキ喋って、明るくて、認知症のイメージがまったく変わった/驚
福田さん:
私は調理師をやっていたが、味覚が分からなくなってしまった
ショックで病院に行ったら認知症と診断された
医師:味覚は認知症判断のポイントの1つ
福田さん:
今でも約束したことを忘れたり、家に来た封筒とかもやらなきゃと思っていても忘れる
どこかにしまってしまうと、そのままたまってしまう
柴田理恵さん:でも、そういうことって私たちでもありますよね
福田さん:
家族に迷惑をかけたくないから、本音が言えない
当事者同士だと分かり合えて、元気になれる
以前の職場の友人とかも疎遠になっていたが、訪ねてきてくれる機会ができた
●認知症の進行の分かれ目の1つは「本人同士のコミュニケーション」

専門家:
「認知症になったら終わり」ではなく、そこからが勝負
医者にも言えないことがたくさんある
当事者同士のコミュニケーションは、気持ちの共有は悪化を防ぐし、支える家族も勇気づけられる
イノ:
このグラフだと悪化されている方もいらっしゃる
すでに悪化してしまっても、当事者同士のコミュニケーションは効果ある?
専門家:
経過や効果は人それぞれです
悪化してからでもコミュニケーションで良い傾向が見られる方もいれば
コミュニケーションに参加していても悪化する人もいる
●家族にも言えない思いを本人どうしで語り合う
“長崎県佐世保市では月に一度、認知症の本人同士が語る会が開かれています。
主催するのは認知症の本人である福田人志さん。
目的は、本人どうしでないと共感が得られにくい困りごとを共有したり、
家族には遠慮して言えない本音を素直に吐き出したりすることです。
実はこの「本人どうしの語り合い」は今、認知症と診断された直後、気持ちの落ち込みなどによって
引き起こされる状態の低下を防ぐ鍵として注目されています。
こうした本人どうしの語り合いの場は、「本人ミーティング」という名称で2017年度から全国各地で開かれています。
会で出た意見は、行政の施策に反映されるなど、本人の声を生かす取り組みが広がっています。”
「峠の茶屋」(長野に同じ名前の釜飯の美味しい飲食店があるな


認知症の患者を支える家族のグループと、認知症本人中心のグループが集まって
普段話しづらいことも話して共有することでココロが軽くなったり
ちょっとした工夫で乗り越えられるアイデアをもらったりする
認知症の男性:忘れることは何も怖くない ストレスがたまるのが怖い
認知症の女性:なんでここに立っているのかな?という時がたまにある
認知症の男性:「何するか分からんぞ」と家族に言っている
認知症の女性:「発病時はこんなことあったよね」と言ったら「うん、そうそう」って通じ合えるものがある
認知症の女性:
私は引っ込み思案で、もともと外に出たくない
できたら家で本を読んだり、ラジオを聞いて1日を過ごしていたい
でも、もしこれ以上症状が進んだら、娘や孫に迷惑がかかるかなとかと思うと
そうもしていられない、出かけなきゃと思うんです
福田さん:
「峠の茶屋」を最初にした頃は、私もお話出来なかった
なかなか人との会話が難しくて プライドみたいなのもあったんでしょうね
でも、気持ちを吐き出したいと思いはじめた
誰とも喋らなかった時期があった
言葉が出ない、字も出てこない、さっきしたことも忘れてる
言われたことも忘れて、言わなきゃいけないことも忘れて
意思の疎通が出来ずに、気持ちがどんどん暗くなっていた
奥さん:モノがパーンと飛んできたりしてた
●メモに気持ちを吐き出すようにした


福田さん:
我慢している喜怒哀楽、不完全な部分を書いていた 字を書くリハビリも兼ねて
「こうありたい」といういろんなものを書いていた
それを知人が清書し、「認知症の歌」展示会で発表したところ反響が大きかった



福田さん:
認知症当事者が来られて、お話をするようになったけれども
「また一緒に会う場所がないよね 集う場所をなんとかしてみようか」ということになって「峠の茶屋」を始めた
僕らなりのストレスの話も出来るし、忘れ物があって、自分も相当落ち込むけど
自分が落ち込むと家族も悲しむから落ち込まないようにしようとする
でも、1人になったら泣いてしまうという、本人同士だとそういう話もできる
別に涙も流していいし、怒ってもいい そういう場所がないと絶対ダメ 本音でね
<福田さんの工夫>

福田さん:
時刻表を見てもバスの発車まで「あと何分」かが分からない 足し算しなきゃならないから
これを見れば、「針がこの辺かな」と分かる
他の認知症の方:これいいですね 分かりやすい
●各地でのイベント
兵庫県:認知症の語り合いを100人ほどの人が聞く

国立市:認知症本人同士の話をフセンに書いて貼り出した


福田さん:私も500円玉と100円玉を勘違いすることがあります
●症状が進み「介護」が必要になった場合
長崎県佐世保市 デイサービス施設

“認知症の本人・福田さんは、週に一回、近所のデイサービスにボランティアで通っています。
目的は、自分では語ることのできなくなった認知症の人の思いを代弁すること。
利用者の中に、季節を問わず厚着をしている男性がいました。
行動の背後にある本人の気持ちに気がつき、介護観が変わったと言います。
このように、一見「困った行動」には何かしら理由が存在する。
「なぜそうするのか」という視点を持って接することが大切であると、認知症の専門医も指摘していました。”
福田さんが今一番気にかけている松田さん ほとんど言葉を発しない

介護スタッフもコミュニケーションが出来ず、とくに季節に問わず「厚着」をしていることが気がかり
介護の常識では「季節感が分からない」「皮膚感覚が鈍い」と考えていた
大汗をかいていて、脱がせようとしても絶対脱がせない
福田さん:
自分もそうだったが、厚着をするのは寒いからではなく、不安だから
温まったほうが不安な気持ちがなくなるような気がする
スタッフはムリに脱がせるのをやめたら、自然と重ね着をやめた
介護スタッフ:教科書どおりではない 寄り添う気持ちを学ばせていただいています
<福田さんが実際に聞いたその他の悩み>

口の位置の検討がつかない場合は、スプーンを短くしたり、
おにぎりを小さく握って、両手で口までもっていける工夫をする
専門的な道具も売っている
松本:
脳のダメージを受けるのが「認知症」 位置関係が分からなくなる
失敗が続いたりすると自信がなくなる 本人が安心できると進行も遅らせることができる
Q:本人に「認知症」だといつ・どう伝えたほうがいいか
松本:
人それぞれだけれども、医師的には早いほうがいいが
許容力がある人とそうでない人がいる 人柄を見てタイミングをはかる
家族と相談してから伝えるようにもしている
告知がショックで進行が心配になるケースもある
●本人の行動パターンを知り 生活の質に結びつける
“一方、自分で思いを語ることもなく、福田さんのような代弁者も近くにいない場合は、どんなアプローチの方法があるのか。
和歌山県御坊市では、日々市民や事業所から寄せられる介護の悩みに対して、福祉課の職員が訪問して共に解決策を探っています。
たとえば、家族からの「認知症が疑われる80代の夫の運転をやめさせたい」という相談。
職員が男性についていくと、かつての仕事場でひとり、夕方まで座って過ごしていました。
元大工であった男性のために「役割」を作ろうと、職員は、デイサービスでいすや看板を作る仕事を依頼。
その結果、生き生きとデイサービスに通い、ひとりで運転して仕事場に向かうことはなくなりました。
専門家はこのケースに関して「本人の行動パターンを知ることが大事」と話し、
家族が、認知症本人の行動の理由に思いをはせて容認し、
ある程度のところからは医師や介護福祉士などプロの手に任せることが、
本人らしい生活を維持することにつながると話していました。”
介護福祉課には、認知症の介護する家族、ケアマネージャー、介護事務所の方から質問のメールが届く
<副主任・谷口さんに寄せられた相談の例>
元大工であった男性が毎朝仕事に行くと言ってクルマに乗ろうとするのをどう止めたらいいか

谷口さんは一緒についていったら、かつて男性が仕事で使っていた倉庫
ここでイスに座って木材を触っているだけだったので、、何か役割ができないかと思った

まず、男性にデイサービスに通うことをすすめた
それまでの仕事を生かして、自分の倉庫でイスと看板作りをお願いしたことで
一人で運転して倉庫に行くことはなくなった
男性の顔がイキイキとして、よく喋り、全然違う/驚

ヤ:どうしたら本人の本音を聞きだせる?
松本:介護する家族もピリピリしているが、力を抜くと、本人も言いやすくなる
●『本人にとってのよりよい暮らしガイド』を全国に配布予定



認知症と診断された直後の方向け 認知症の先輩たちのアドバイスも書かれている
福田さんも製作に関わった
市町村の役場に問い合わせるともらえる
<FAX>
Q:母がアルツハイマーになり、いろいろ忘れてしまうことについて悔しそうなのをどうしてあげたらいいか?
松本:自分を取り戻したいという思いがある アルバムなどを見て、記憶を取り戻す努力から始めてみてはどうか

松本:専門医と会うことで安心できる ネットで検索したり、地域包括支援センターに問い合わせるのもよい

福田:
よく高齢者にされるような大きな声は出さずに、ゆっくり話して欲しい
叱らないで、本人のやりたいことをさせて、手伝ってあげる
イノ:クルマの運転が一番心配では?
松本:
免許に関しては、積極的、勇気ある退却、説得が大切
火や入浴なども支援が必要
周囲にも認知症であることを告げて、町全体で支える

専門家ゲスト:福田人志さん(認知症当事者)、松本一生さん(認知症専門医)
ゲスト:ミッツ・マングローブさん、柴田理恵さん
リポーター:雨宮萌香アナウンサー
“2025年には高齢者の5人に1人がなるといわれる認知症。
「なんとなく怖いもの」として不安を抱いている人が多いかもしれません。
番組では、認知症のご本人をスタジオに招き、世間のイメージと現実とのギャップを本音で語ってもらいました。
キーワードは認知症の人の「語り」です。まず大切なのは、認知症の本人どうしでの語り合い。
家族にも言えない悩みや、日々の困りごとを解消する知恵を共有することで、
症状が悪化せずに済んでいるという人たちをご紹介しました。
また、認知症の症状が進んで話すことができなくなったとしても、
周囲にいる「語れる認知症の人」がその人の気持ちを代弁することで、よりよい介護につながった現場も取材。
さらに、本人の行動をとことん見つめることで、その背景にある本音を探り当てる自治体の取り組みについても紹介しました。
本人の声によって大きく変わりつつある、認知症の今についてお伝えしました。”
【ブログ内関連記事】
 認知症×人気カフェ@あさイチ
認知症×人気カフェ@あさイチ 「認知症介護 家族交流会で“介護離職”を防ぐ」@ビッグイシュー
「認知症介護 家族交流会で“介護離職”を防ぐ」@ビッグイシュー●ゲスト:福田人志さん(認知症当事者)
51歳で発症した時は、半年間落ち込み、外へも出なかった
本人同士がコミュニケーションできる場をもってから明るくなった
ヤナギー:こうして見ると、認知症にはまったく見えないがどんな症状がある?
(ハキハキ喋って、明るくて、認知症のイメージがまったく変わった/驚
福田さん:
私は調理師をやっていたが、味覚が分からなくなってしまった
ショックで病院に行ったら認知症と診断された
医師:味覚は認知症判断のポイントの1つ
福田さん:
今でも約束したことを忘れたり、家に来た封筒とかもやらなきゃと思っていても忘れる
どこかにしまってしまうと、そのままたまってしまう
柴田理恵さん:でも、そういうことって私たちでもありますよね
福田さん:
家族に迷惑をかけたくないから、本音が言えない
当事者同士だと分かり合えて、元気になれる
以前の職場の友人とかも疎遠になっていたが、訪ねてきてくれる機会ができた
●認知症の進行の分かれ目の1つは「本人同士のコミュニケーション」

専門家:
「認知症になったら終わり」ではなく、そこからが勝負
医者にも言えないことがたくさんある
当事者同士のコミュニケーションは、気持ちの共有は悪化を防ぐし、支える家族も勇気づけられる
イノ:
このグラフだと悪化されている方もいらっしゃる
すでに悪化してしまっても、当事者同士のコミュニケーションは効果ある?
専門家:
経過や効果は人それぞれです
悪化してからでもコミュニケーションで良い傾向が見られる方もいれば
コミュニケーションに参加していても悪化する人もいる
●家族にも言えない思いを本人どうしで語り合う
“長崎県佐世保市では月に一度、認知症の本人同士が語る会が開かれています。
主催するのは認知症の本人である福田人志さん。
目的は、本人どうしでないと共感が得られにくい困りごとを共有したり、
家族には遠慮して言えない本音を素直に吐き出したりすることです。
実はこの「本人どうしの語り合い」は今、認知症と診断された直後、気持ちの落ち込みなどによって
引き起こされる状態の低下を防ぐ鍵として注目されています。
こうした本人どうしの語り合いの場は、「本人ミーティング」という名称で2017年度から全国各地で開かれています。
会で出た意見は、行政の施策に反映されるなど、本人の声を生かす取り組みが広がっています。”
「峠の茶屋」(長野に同じ名前の釜飯の美味しい飲食店があるな


認知症の患者を支える家族のグループと、認知症本人中心のグループが集まって
普段話しづらいことも話して共有することでココロが軽くなったり
ちょっとした工夫で乗り越えられるアイデアをもらったりする
認知症の男性:忘れることは何も怖くない ストレスがたまるのが怖い
認知症の女性:なんでここに立っているのかな?という時がたまにある
認知症の男性:「何するか分からんぞ」と家族に言っている
認知症の女性:「発病時はこんなことあったよね」と言ったら「うん、そうそう」って通じ合えるものがある
認知症の女性:
私は引っ込み思案で、もともと外に出たくない
できたら家で本を読んだり、ラジオを聞いて1日を過ごしていたい
でも、もしこれ以上症状が進んだら、娘や孫に迷惑がかかるかなとかと思うと
そうもしていられない、出かけなきゃと思うんです
福田さん:
「峠の茶屋」を最初にした頃は、私もお話出来なかった
なかなか人との会話が難しくて プライドみたいなのもあったんでしょうね
でも、気持ちを吐き出したいと思いはじめた
誰とも喋らなかった時期があった
言葉が出ない、字も出てこない、さっきしたことも忘れてる
言われたことも忘れて、言わなきゃいけないことも忘れて
意思の疎通が出来ずに、気持ちがどんどん暗くなっていた
奥さん:モノがパーンと飛んできたりしてた
●メモに気持ちを吐き出すようにした


福田さん:
我慢している喜怒哀楽、不完全な部分を書いていた 字を書くリハビリも兼ねて
「こうありたい」といういろんなものを書いていた
それを知人が清書し、「認知症の歌」展示会で発表したところ反響が大きかった



福田さん:
認知症当事者が来られて、お話をするようになったけれども
「また一緒に会う場所がないよね 集う場所をなんとかしてみようか」ということになって「峠の茶屋」を始めた
僕らなりのストレスの話も出来るし、忘れ物があって、自分も相当落ち込むけど
自分が落ち込むと家族も悲しむから落ち込まないようにしようとする
でも、1人になったら泣いてしまうという、本人同士だとそういう話もできる
別に涙も流していいし、怒ってもいい そういう場所がないと絶対ダメ 本音でね
<福田さんの工夫>

福田さん:
時刻表を見てもバスの発車まで「あと何分」かが分からない 足し算しなきゃならないから
これを見れば、「針がこの辺かな」と分かる
他の認知症の方:これいいですね 分かりやすい
●各地でのイベント
兵庫県:認知症の語り合いを100人ほどの人が聞く

国立市:認知症本人同士の話をフセンに書いて貼り出した


福田さん:私も500円玉と100円玉を勘違いすることがあります
●症状が進み「介護」が必要になった場合
長崎県佐世保市 デイサービス施設

“認知症の本人・福田さんは、週に一回、近所のデイサービスにボランティアで通っています。
目的は、自分では語ることのできなくなった認知症の人の思いを代弁すること。
利用者の中に、季節を問わず厚着をしている男性がいました。
行動の背後にある本人の気持ちに気がつき、介護観が変わったと言います。
このように、一見「困った行動」には何かしら理由が存在する。
「なぜそうするのか」という視点を持って接することが大切であると、認知症の専門医も指摘していました。”
福田さんが今一番気にかけている松田さん ほとんど言葉を発しない

介護スタッフもコミュニケーションが出来ず、とくに季節に問わず「厚着」をしていることが気がかり
介護の常識では「季節感が分からない」「皮膚感覚が鈍い」と考えていた
大汗をかいていて、脱がせようとしても絶対脱がせない
福田さん:
自分もそうだったが、厚着をするのは寒いからではなく、不安だから
温まったほうが不安な気持ちがなくなるような気がする
スタッフはムリに脱がせるのをやめたら、自然と重ね着をやめた
介護スタッフ:教科書どおりではない 寄り添う気持ちを学ばせていただいています
<福田さんが実際に聞いたその他の悩み>

口の位置の検討がつかない場合は、スプーンを短くしたり、
おにぎりを小さく握って、両手で口までもっていける工夫をする
専門的な道具も売っている
松本:
脳のダメージを受けるのが「認知症」 位置関係が分からなくなる
失敗が続いたりすると自信がなくなる 本人が安心できると進行も遅らせることができる
Q:本人に「認知症」だといつ・どう伝えたほうがいいか
松本:
人それぞれだけれども、医師的には早いほうがいいが
許容力がある人とそうでない人がいる 人柄を見てタイミングをはかる
家族と相談してから伝えるようにもしている
告知がショックで進行が心配になるケースもある
●本人の行動パターンを知り 生活の質に結びつける
“一方、自分で思いを語ることもなく、福田さんのような代弁者も近くにいない場合は、どんなアプローチの方法があるのか。
和歌山県御坊市では、日々市民や事業所から寄せられる介護の悩みに対して、福祉課の職員が訪問して共に解決策を探っています。
たとえば、家族からの「認知症が疑われる80代の夫の運転をやめさせたい」という相談。
職員が男性についていくと、かつての仕事場でひとり、夕方まで座って過ごしていました。
元大工であった男性のために「役割」を作ろうと、職員は、デイサービスでいすや看板を作る仕事を依頼。
その結果、生き生きとデイサービスに通い、ひとりで運転して仕事場に向かうことはなくなりました。
専門家はこのケースに関して「本人の行動パターンを知ることが大事」と話し、
家族が、認知症本人の行動の理由に思いをはせて容認し、
ある程度のところからは医師や介護福祉士などプロの手に任せることが、
本人らしい生活を維持することにつながると話していました。”
介護福祉課には、認知症の介護する家族、ケアマネージャー、介護事務所の方から質問のメールが届く
<副主任・谷口さんに寄せられた相談の例>
元大工であった男性が毎朝仕事に行くと言ってクルマに乗ろうとするのをどう止めたらいいか

谷口さんは一緒についていったら、かつて男性が仕事で使っていた倉庫
ここでイスに座って木材を触っているだけだったので、、何か役割ができないかと思った

まず、男性にデイサービスに通うことをすすめた
それまでの仕事を生かして、自分の倉庫でイスと看板作りをお願いしたことで
一人で運転して倉庫に行くことはなくなった
男性の顔がイキイキとして、よく喋り、全然違う/驚

ヤ:どうしたら本人の本音を聞きだせる?
松本:介護する家族もピリピリしているが、力を抜くと、本人も言いやすくなる
●『本人にとってのよりよい暮らしガイド』を全国に配布予定



認知症と診断された直後の方向け 認知症の先輩たちのアドバイスも書かれている
福田さんも製作に関わった
市町村の役場に問い合わせるともらえる
<FAX>
Q:母がアルツハイマーになり、いろいろ忘れてしまうことについて悔しそうなのをどうしてあげたらいいか?
松本:自分を取り戻したいという思いがある アルバムなどを見て、記憶を取り戻す努力から始めてみてはどうか

松本:専門医と会うことで安心できる ネットで検索したり、地域包括支援センターに問い合わせるのもよい

福田:
よく高齢者にされるような大きな声は出さずに、ゆっくり話して欲しい
叱らないで、本人のやりたいことをさせて、手伝ってあげる
イノ:クルマの運転が一番心配では?
松本:
免許に関しては、積極的、勇気ある退却、説得が大切
火や入浴なども支援が必要
周囲にも認知症であることを告げて、町全体で支える