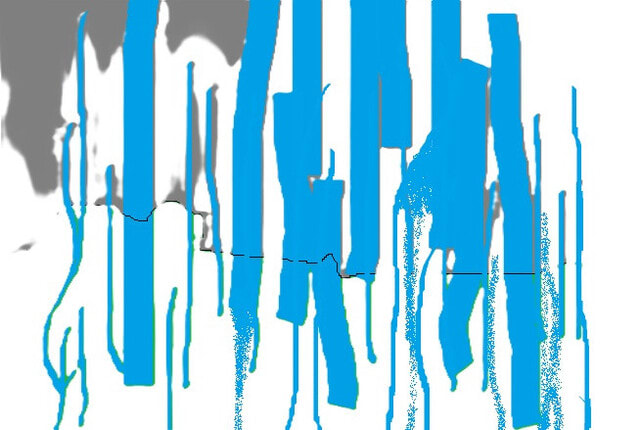一枚の白い紙を掬い上げるように
向うの鏡の中に
美しい女は現われては来ない
漂流する飛行機の上で
故障した無電機から
かすかな鋸の音を聞いているような
不安な影が
――上林猷夫「機械と女」
もはや、松本零士の四畳半の世界であるようだが、いまだって、このような美女と機械の組み合わせは、大きく観れば非常に非常に多く追及されている。それはそれで面白いのであろうが、わたくしは、そういうことをやりたがる人間とは何かという問いしか頭に浮かべることができない。
どちらかといえば、わたくしには、フェミニストが問題にしていたような修辞的介入の有効性みたいなものが引っかかり続けているのだ。
昨日も、「ものすごい猫好きは、ケネディにも猫を感じるらしい。ネが入っているのとケとかデとかイが猫が寝転んでいる姿に似ているらしいのだ。世の中ほとんどが猫では。」などと妄想し独りごちでいたわけであるが、果たしてこういう修辞に意味はあるのか?またわたくしは、ドジャースで試合前にマグロの解体をやったという記事をみつけて、「コロッセオで猛獣殺すかわりにマグロの解体かよとも思うが、こういうのがないから授業とかが眠くなるんだろうな、わしも授業前にマグロの解体ショーでもしようかな。むかしPerfumeもどさ回りでマグロの解体ショーやったって言ってたし。」とか妄想した。わたくしにとって、こういう行為さえ、修辞的介入ではあるのだ。しかし、こういうのは果たして、世界の修羅場をくぐった人間たちの怖ろしい権力に勝てるのか?東浩紀が言うように、むろん勝てるはずがない。勝つことは政治的な問題である。そういう局面になると、文学も「修辞的介入」とか言っている場合ではなく、ラスコーリニコフの次元にうつってゆくしかない。
春すぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山
最近は、「春すぎて」が一番うるっときてしまう私は、実に平和ボケしている。
あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む
そもそもあまり勤勉でなかったむかし、鴨がひとりで眠そうにしているのかと思っていたぐらいなのだ。
我々の文化風土は、生と死の次元にすぐ政治的な問題が移ってしまう。いままで数々の屍体を葬ってきたからではなかろうか。死をもたらした大きな人為的事件には生を生み出す何かがあり、私の世代なんかは自分が連合赤軍事件の山岳ベースで生まれたのかもとか妄想するやつもいたであろう(私が実際そうだった)。このまえ、桐野夏生が似たような発想で小説書いていた。オウム事件に関してもそういう人いるにちがいない。むろん、こういう妄想に政治的な力はない。桐野の小説に、連合赤軍の行為にフェミニズム的な希望への反転をみる文学的願望があったとしても、あれでは、内戦事件をある意味弔ったことにしかなっていないではないか?
よって、我々は現実に無力な教師たちを笑えない。子どものとき、学校世界で仲間はずれと友だちになったことのないやつが「寄り添いたいです」とか言って教員になっても、そのさきどうなるかは明瞭だ。しかし、放置された武士たちの死体を埋めて弔うことしかできなかった農民たちの行為と、その無責任さは何処が違うのだ。多様性を実際に擁護したことのないやつが一番多様性が素晴らしいとか言うのは、自分を擁護し、仲間はずれをつくるためだ。かくして、仲良く出来そうな(コミュ力ありそうな)やつばかりを身の回りに配置し、結果、群れ上手な奴だけしかいないディストピアのなかに生きる。創造性は無論ないが、時々やってくるマレビトや怒りのあまり磔になるやつを利用して少し学ぶ。そもそも大学はいる年齢のときに自分の将来を宣言できる人間に可能性なんかあるわけないが、そもそも可能性を抑圧するとこに我々の生き方があったのだ。この様態は、まるである種のブリコラージュ、文学のつくりなのである。
先ほど、森祐香里氏の野間宏論を手掛かりに野間宏のいくつかを読み直したが、確かに彼は可能性を見出そうともがいていたことは確かだと思った。