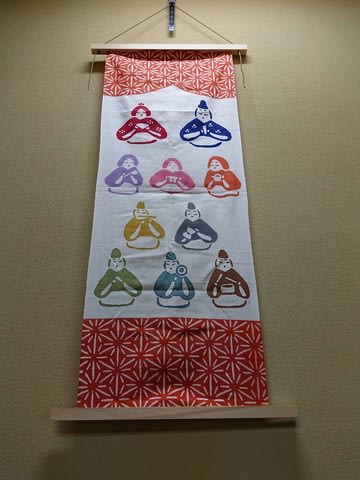大阪府の緊急事態宣言が昨日から20日まで延長され、
17日に予定されていたお稽古も中止になりました。
私などは仕事などの関係で、最後のお稽古が3月14日。
3ヶ月もお稽古なしになりました。(みなさん、ご無沙汰しています)
という間に、『茶道雑誌』から、
大徳寺の門前に店を構える畳屋さんの記事を書いてほしいというご依頼があり、
このたび6月号に1回目の原稿が掲載されました。

もともとは、この畳屋さんからの
お茶室の畳は、さまざまな作法のもとになっている大切なものなのに
今日、いい加減に扱われているので、「お茶室の畳とは」について語りたい
というご提案が発端になっています。
京都に伺って(取材は緊急事態宣言前でした)
おいしいお菓子もいただいて、
いろいろ伺ってみれば、知らないことばかり。
(ン十年もお茶を習っているのに、お恥ずかしい)
印刷直前に、畳屋さんからのお願いにより、記事が2回に分けられることになり、
急遽、テーマを2つに設定してまとめ直しています。
6月号の1回目は「京間」で、
8月号の2回目は「畳の目」です。

ご関心のある方はご一読ください。
すみません、宣伝ぽい記事になりまして。(近況報告がてら)
緊急事態宣言のおかげで下関への出張がなくなって
がっかりしているS・Kでした。
(おいしい魚を食べて帰ってこようと目論んでいたのに)