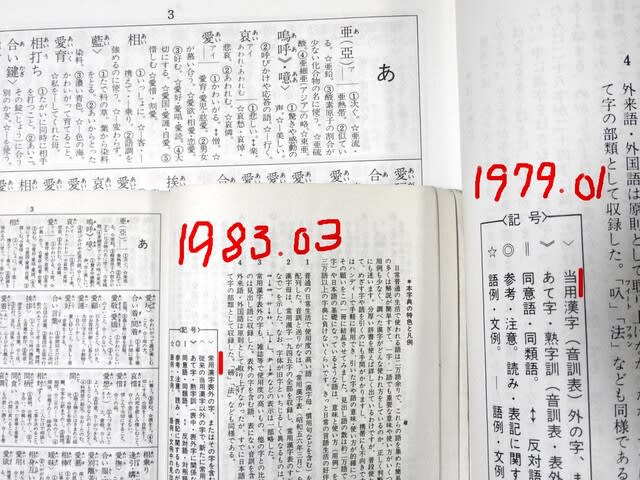・1冊目のときも2冊めのときもそうですが、あまりこう、達成感とか、高揚感とか、ましてや幸福感とかはないんですね。思った以上に淡々としている。やっと形になったか、という感覚はさすがにあるんですが、感情の起伏としてはとても小さい。学生諸君とのあいだでふと交わされたやりとりで、互いの意志疎通ができたことの方がよっぽど起伏は大きいですね(意思疎通できないときは言うもさらなり?)。 ・手がかかったなあ、という感覚もあまりない。いや、もちろん、手はかかっているんですよ。だだそれは、本にする過程での手間が一番つらいといいますか、労力がかかった感が大きい。場合によっては苦痛ですらあります。だったら出さなければいいのに。その通りです。
・なにが辛いんだろうな。頭のなかでは分かっていることを、今一度、文章にしなければならないこと(労力かかる~)。文章にするからには、ちゃんとした日本語じゃないといけない。できればより分かりやすい文章で。そのためには自分の文章を見つめなおす必要がある。ここが一番つらいかもしれません。ほんと、文章書くの下手ですからね。で、それをみずから見なおさなきゃならない。日々、自己嫌悪との戦いです。超克するには見つめなおすしかないんですから。ちょっと以上に憂鬱です。これが一番応えるか。
・校正手入れ。原稿を渡すまえに散々見直すんですが、それでも、上がってきた校正刷りに目を通すと、誤字・脱字があちこちにあります。これでヨシとして出したものに欠陥が多々ある。これも応える。で、初校・二校・三校とあるわけですが、そのたびに同じ苦しみをするわけです。うんざりちゃんです。しかも、それだけ見ているので、よりよい考えとかが浮かんだりする。で、手を加えられれはいいんですが、限度があります。
・400ページくらいのものになりますから、全体的な統一をとる必要も出てくるんですが、これがなかなか。たとえば用語など。これが結構あって、原稿段階でも気づいた分は直すのだけれど、校正で出てくる出てくる。分かりやすいのだと「本を(出版/刊行/発行)する」でどれをとるか。一語に統一してしまってよいか、意味差やニュアンスで書き分けるかどうか。書き分けるとするならどう書き分けるか、とか。
・用字の問題もあります。印刷の「摺る/刷る/擦る」。どれを使ってもほぼよい。なのでバラバラ。「摺る」が多いかなと思っていたら「刷る」もありました。たしかに、現代的な感覚だと「刷る」でしょうが、板木の原版に墨を載せて紙にこすりとるという技法が頭のなかのイメージとしてあるから、何となく「摺る」を使いたくなる。こう、実際に手を動かしているイメージからでしょうかね。手偏の字がいいような気がする。だから、職人さんも「刷(り)師」ではなく「摺(り)師」を使いたくなる。それをどちらかに寄せることになります。・・・・・ね、疲れるでしょ?
・ちょっと失敗だったかなと思うのが、書名。「諸問題」というのは、こう、場当たり的に研究してきたんだろうな、あてどもなくね、ふふふ・・・と思われそうなニュアンスがありますよね。もちろん、はじめに決めた折には、これでドンピシャリ、と思っているわけです。さすがに。
・最初の案としてはいくつかあって、「節用集史詳説」とかいうのもありました。たしかにそうなんですが、バランスというか、統一感というか、そうした点が少々弱いのですね。この点は、前著『近世節用集史の研究』の方がよかった(第一部で序説、第二部が集約的な本論、第三部は自由演技な事例研究、第四部は将来計画)。今回の3冊目は、ほぼ自由演技が主体になってますそれが、室町期から幕末近くまで。視点も多様です。「多様」といえば聞こえはいいですが、ばらばらというに近い。そんなことを考えると「諸問題」の方がよいかなと思った次第です。もちろん、「節用集史の」と前に付くので、ばらける範囲は限定的ではあります。
・私の、これは癖といいますか、研究者としての限界というべきか、少々飽きっぽいところがあります。同じテーマのもと、室町時代から明治~昭和初期まで通せればいいんですが、そういう研究スタイルが性に合わない感じです。いや、もう少し言うといろんなことをしてみたいんですね。で、一つのケーススタディができたなら、それはもそれでよい。手法の可能性は示せたのだから、それでよいだろうと考えがちです。さらに別の観点ではどう見えるか、また、いかに見せることができるか、そうしたことをやり続けていきたい、そんな風に思っていますね。手法の発見・開発に興味があるタイプといってもよいでしょう。
・そういうスタンスで臨むことで、節用集という辞書類に、どのような光の当てかたかありうるかを調べ尽くしてみたいという野望(笑)があるようです。いや、あるんだな。だんだん言葉が見つかってきた。そう、節用集研究の可能性を示したい、のだな。それはそのまま、現状での研究の限界を見極めたいということでもあるのだな。ここまでは出来ましたよ、これから先は無理ですよ、こうした条件が揃えば一歩進めるかもしれませんねぇ・・・ そう、そういうことをしたいのだ。だから、今回の『節用集史の諸問題」は、自分が関心のあること、やりたかったことだけで出来ている、と言ってもよさそうです。最後の、早引節用集の諸本を扱ったところだけは、やや苦痛。6類ある早引節用集のうちの2類4変種を同じ方法で検討しなければならなかったから。