
皆さんこんにちは!
風邪がまだ続いてるので今回も簡単に。
今回は「顰に倣う(ひそみにならう)」。
意味は「無暗に人の真似をして失敗すること」、「他人の言動をまねる時に、それを謙遜して使うこと」の二つで、
「顰」というのは眉間にしわを寄せて顔をしかめていることを指します。
中国の春秋時代、越の国に西施(せいし)という美女がいました。
彼女は胸に病気を持っており、たえかねて顔をしかめることがあったのですが、その様子が魅力的で、村の男たちの評判になっていたそうです。
それを知った醜女(しこめ。いわゆる不細工な女性)が、同じように顔をしかめれば美しく見えるだろうと思って、
西施と同じように顔をしかめたのですが、あまりの醜さに気味悪がり、門を閉ざして外に出なくなったり、
村から逃げ出してしまったそうです。
この話から、良し悪しを考えずに人の真似をすることや、他人と同じ行動をするとき、見習う気持ちを表す謙遜の言葉として、
西施の「顰に倣う」と言うようになったそうです。
それにしてもこの言葉の由来を調べてて、男共が女性の苦しんでる顔に見とれてた(←言い方が悪い)、というのを見て、
「村の男どもは見とれてないで助けろや!」
と思ったのですが、もしかしたら見とれながらも助けてはいたんでしょうかね。
綺麗な女性はどんな表情でも美しく見える、ということでしょう(笑)
それでは今回はここまで!ではでは!











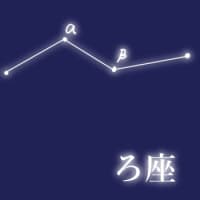




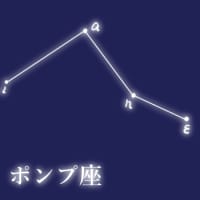



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます