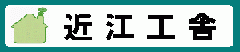滋賀県に生息する両生類の紹介、今日の1匹はニホンイモリ。山間部にある神社の排水路でニホンイモリを捕まえました。排水路は三面コンクリート張りで、水路底に細かい砂が堆積し、水深が0.3m程度、日影で水温がとても冷たい環境でした。水路の落差下の水量が多いところにタモ網でを入れると、枯葉と一緒に黒い物体。山椒魚の子供?とか思いましたが、裏返すと腹が赤い為、アカハラ(ニホンイモリ)だと判明。久し振りに見ると背面は、大分黒かったんだなと改めて思いました。ちなみに、惚れ薬の必要も空き水槽も無い為、その場で放流してあげました。
<データ>
名前:アカハライモリまたはニホンイモリ
分布:滋賀県の山側
体長:100mm程度の個体まで採取経験あり
生息:水田・池・沼・小川・渓流付近の水溜りなどの止水域

特徴:
漢字で「赤腹井守、日本井守」と書く日本固有種の両生類です。体型はトカゲ型と申しましょうか、そんな形をしています。尻尾は泳ぎ易いように平たく、短い足にやや長い指を持ちますね。体色はザラザラの背面が黒褐色、腹面は赤と黒の斑模様という姿をしている(だからアカハライモリ)。繁殖期は春から夏でして、卵から孵った幼生はオタマジャクシ風。成体は皮膚から有毒の液を分泌するらしいのでので、触った後は手を洗う(生物全般に言えますが)。毒とを持つらしいので食べないように!
参考・引用文献
私見:
骨まで再生する再生能力はモンスター級ですね~
採取:
山間部の水路のやや水位がある所をタモ網で掬う。枯葉などの下に居る場合もあるので枯葉ごと掬う
飼育:
①容器:30cm成体飼育数は2、3匹
②底床:粗めで角の無い砂利
③濾過:どれでも可
④設備:ヒーター△、エアーポンプ×、ファンorクラー△
⑤水草:アナカリスやマツモ
⑥餌 :人工配合飼料
⑦混泳:お互いが口に入らないサイズの魚
⑧置物:流木などの隠れ家
⑨繁殖:難しい
水槽は直射日光が当らず、水温が上昇しない場所に設置する(高水温に弱い)。水草や隠れ家(植木蜂、流木など)をレイアウトする。濾過器をつけて水を清潔に保つ(水槽が小さい場合、水換えも頻繁にしてあげる。)冬眠させる場合は、陸を作り水苔をレイアウト。冬眠させない場合は、熱帯魚用のヒーター(水温設定ができ、カバーの付いたもの)を入れる。脱走する可能性が有りますので、水槽に蓋をつける。餌は、ミミズや鶏ササミを食べますが、慣れれば人工飼料も食べる様です。過密飼育を行うと共食いの恐れも有ります。
※それから陸地を作る(浮き島で良い)必要があります。陸地が無いと溺れてしまうのと、体温調整ができずに死んでしまうことがあります。水槽飼育する場合、隙間を全て塞がないと脱走します。上部濾過装置にも侵入します。
(情報提供者 きつねさん)
動画:
画像:


08.10.29追加画像。
よろしければこちらにもお越し下さい。
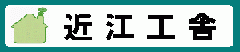
<データ>
名前:アカハライモリまたはニホンイモリ
分布:滋賀県の山側
体長:100mm程度の個体まで採取経験あり
生息:水田・池・沼・小川・渓流付近の水溜りなどの止水域

特徴:
漢字で「赤腹井守、日本井守」と書く日本固有種の両生類です。体型はトカゲ型と申しましょうか、そんな形をしています。尻尾は泳ぎ易いように平たく、短い足にやや長い指を持ちますね。体色はザラザラの背面が黒褐色、腹面は赤と黒の斑模様という姿をしている(だからアカハライモリ)。繁殖期は春から夏でして、卵から孵った幼生はオタマジャクシ風。成体は皮膚から有毒の液を分泌するらしいのでので、触った後は手を洗う(生物全般に言えますが)。毒とを持つらしいので食べないように!
参考・引用文献
私見:
骨まで再生する再生能力はモンスター級ですね~
採取:
山間部の水路のやや水位がある所をタモ網で掬う。枯葉などの下に居る場合もあるので枯葉ごと掬う
飼育:
①容器:30cm成体飼育数は2、3匹
②底床:粗めで角の無い砂利
③濾過:どれでも可
④設備:ヒーター△、エアーポンプ×、ファンorクラー△
⑤水草:アナカリスやマツモ
⑥餌 :人工配合飼料
⑦混泳:お互いが口に入らないサイズの魚
⑧置物:流木などの隠れ家
⑨繁殖:難しい
水槽は直射日光が当らず、水温が上昇しない場所に設置する(高水温に弱い)。水草や隠れ家(植木蜂、流木など)をレイアウトする。濾過器をつけて水を清潔に保つ(水槽が小さい場合、水換えも頻繁にしてあげる。)冬眠させる場合は、陸を作り水苔をレイアウト。冬眠させない場合は、熱帯魚用のヒーター(水温設定ができ、カバーの付いたもの)を入れる。脱走する可能性が有りますので、水槽に蓋をつける。餌は、ミミズや鶏ササミを食べますが、慣れれば人工飼料も食べる様です。過密飼育を行うと共食いの恐れも有ります。
※それから陸地を作る(浮き島で良い)必要があります。陸地が無いと溺れてしまうのと、体温調整ができずに死んでしまうことがあります。水槽飼育する場合、隙間を全て塞がないと脱走します。上部濾過装置にも侵入します。
(情報提供者 きつねさん)
動画:
画像:


08.10.29追加画像。
よろしければこちらにもお越し下さい。