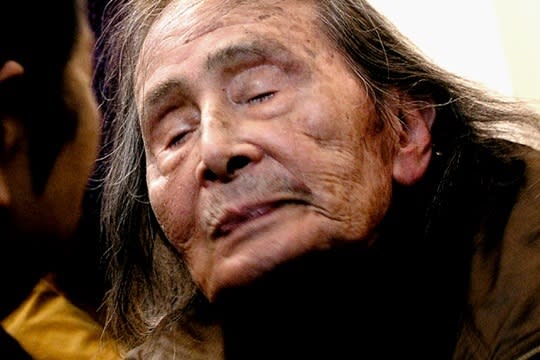『
オペラ座の怪人』を観ました。
このミュージカル映画はイギリスの代表的ミュージカル脚本家であり作曲家の、
ウェバー(アンドリュー・ロイド)の手による、本人曰く最高傑作のミュージカルを映画化したものです。
全編に流れる印象的な曲は、ウェバーが当時熱愛中だったサラ・ブライトマンのために書いたもの。
勿論サラが出演するオリジナル版は観てませんが、公演をそのまま録音したCDは、発売されています。
それを聞く限り、クリスティーヌの歌声は今回の映画版のエミー・ロッサムの方がいい感じだと思います。
それはさておき、舞台となるオペラ座の廃墟から始まるこの映画は、
怪人の住む洞窟状の部屋など、充分廃墟心を満たしてくれる作品でした。
この舞台設定があるからこそ、怪人のかなわない思いもいっそう強調されていると。
ところでイギリスのミュージカルと言えば『ロッキー・ホラー・ショー』を忘れられません。
ジェンダーの宇宙人フランケン・フルターが自分好みのマッスル人造人間を作っては大暴れする、
イギリスのみならず世界でも屈指のB級ミュージカル。
映画版は、アカデミー賞常連女優のスーザン・サランドンの初主演映画でもありますが、
この作品も廃墟(古城)が舞台です。
この古城の廃墟は実在する建物がモデルになっていて、今では
オークリーコートというホテルになっています。
もう20年位前、ロッキー・ホラー・ショーにはまってこの古城を観に行ったことがありますが、
確かに映画に出くるまさにそれと同じ外観でした。
この映画の配給はアメリカで、舞台もアメリカという設定にはなっていますが、
原作者のオブライエン(リチャード)は生粋のイギリス人です。
イギリスのミュージカルに漂う独特な廃墟感が好きです。
■blog search■
ノース・ヨークシャーにお住まいの方の美しい廃墟の写真
・
ウィットビー修道院跡|
スカーバラ城|
ボルトン小修道院跡