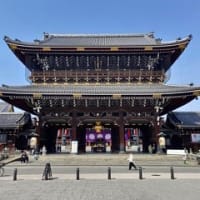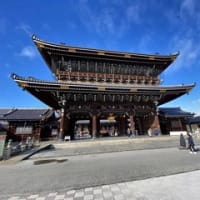松江城
2度目の登城ですが、前回は重文のときで国宝になっては初登城
内部展示は

後藤又兵衛具足

大橋茂右衛門所用具足
兜は蜻蛉形

松平直政・綱隆父子筆 自詠和歌集
ここからは大名茶人松平不昧ゆかりの茶室

明々庵
家老有澤家の本邸に不昧好みで建てられた茶室。不昧自身も度々訪れたとされます。

内部は二畳台目。床の「明々庵」は不昧筆

次ぎは普門院にある

観月庵
三斎流の茶室。不昧も城中より堀川を舟で下り茶事を催したとされます。

一間の深い庇を付けた内路地は不昧が賞賛した所。
お次は現在松江歴史館内にある

伝利休茶室
江戸時代には松江藩家老大橋家に在った茶室。不昧も何度も訪れ「悦んだ」そうです。
この茶室は「伝利休」の名の通り利休が関わったとされ2つの系譜が伝わる。
1つ目は福嶋正則が利休に頼んで茶室を造ってもらい、その後家臣であった大橋茂右衛門に渡ったとする説。
2つ目は利休の持っていた茶室を堀尾吉晴が譲り受け、従兄弟の堀尾但馬に渡った後に大橋家に入ったとする説がある。

この茶室の特色は茶室と内路地がひとつの屋根に納まっている事。この内路地から縁に上がり、さらに縁から躙口を入るのも珍しい。
また刀掛の側面の壁には丸窓が開いており、これは長刀を帯びていた加藤清正の刀を架けるようにする為と伝わっています。
利休と不昧2人の茶人を繋ぐ不思議な茶室でした。