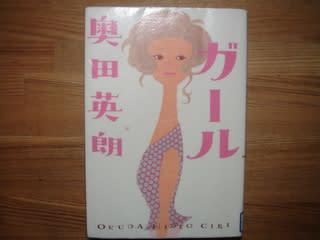「掛川ライススタイルデザインカレッジに細川護煕氏を呼ぼう!」と声が上がり、細川氏の著作を読むうちに、別の人物にも興味を持つようになった。
白洲次郎である。
久しぶりに書店に行ったら「白洲次郎~日本で一番カッコイイ男」(KAWADE夢ムック)が目に止まった。奥付を見れば、2002年初版で現在12刷。ムックとしては異例のことである。
そもそも白洲次郎のことは、「目利きと言われた白洲正子の夫であり、吉田茂の側近だった」くらいしか知らなかった。しかし、このムックを読み進めるうちにこんなにカッコいい人がいたのか、とある意味ものすごく驚いた。「白洲次郎とは誰か」という対談が組まれていたように、「いったいこの人は誰なのか」と深く深く考えたくなるような、まったく枠にはまらない、別の言い方をすればカテゴリーに分けられない人に思えるのだ。
まず、白洲次郎とは。
旧白州邸武相荘HPによれば、以下のように紹介されている。
http://www.buaiso.com/
兵庫生まれ。若くしてイギリスに留学、ケンブリッジに学ぶ。
第二次世界大戦にあたっては、参戦当初より日本の敗戦を見抜き鶴川に移住、農業に従事する。戦後、吉田茂首相に請われてGHQとの折衝にあたるが、GHQ側の印象は「従順ならざる唯一の日本人」。高官にケンブリッジ仕込みの英語をほめられると、返す刀で「あなたの英語も、もう少し勉強なされば一流になれますよ」とやりこめた。その人となりを神戸一中の同級・今日出海は「野人」と評している。日本国憲法の成立に深くかかわり、政界入りを求める声も強かったが、生涯在野を貫き、いくつもの会社の経営に携わる。
晩年までポルシェを乗り回し、軽井沢ゴルフ倶楽部理事長を務めた。「自分の信じた『原則(プリンシプル)』には忠実」で「まことにプリンシプル、プリンシプルと毎日うるさいことであった」と正子夫人。遺言は「葬式無用、戒名不用」。まさに自分の信条(プリンシプル)を貫いた83年だった。
「白洲次郎~日本で一番カッコイイ男」のインタビュー記事より。
――あなたのモットーは?
死んだらクサルということだ。ボクは生まれつき、座右の銘とかモットーとかをどうこういうほど人間が高尚でもなければ、ヒマでもない。
――なぜ百姓仕事が好きなのか?
少しキザな言い方だが、百姓をやっていると、人間というものがいかにチッチャな、グウタラなもんかということがよくわかるから。
――なぜ、吉田首相の側近になっているのか?
結局、吉田に個人的に愛情を持っているだけの話だ。ほかに、何もありゃせん。
――あなたのものの考え方には、古風な所があると思うが?
ボクは人からアカデミックな、プリミティブ(素朴)な正義感を振り回されるのは困る、とよく言われる。しかしボクにはそれが貴いものだと思っている。他の人には幼稚なものかもしれんが、これだけは死ぬまで捨てない。ボクの幼稚な正義感にさわるものは、みんなフッとばしてしまう。
辻井喬のエッセイ「反骨ではなかった白洲次郎」から。
彼は反権力という意味で反骨の人なのではない。ただ卑しい人間が嫌いなだけなのである。ただ長く権力の座にいると人間は次第に卑しくなっていく。(中略)自分の判断の間違いを謝らない点では、マスメディアは戦前から一貫していたが、白須次郎はそうした卑しい人達とのつきあいを無視し続けたのであった。だから世間の堕落に反比例して彼は反骨の人、無愛想な人になっていった。
白洲正子のエッセイ「いまなぜ『白洲次郎』なの」から。
最近は政治家でも何でも、すぐに「命を懸けて」なんて安っぽいことを言ったり、窮地に陥ると平気で涙を見せるじゃないですか。美意識が高く、苦労は人に見せず、常にかっこつけ続ける、ということなんか、いまやないでしょう。だからこそ、次郎さんのような人間がまた興味を持たれているのかもしれませんね。
私の中で「もっと知りたい人」が増えた。惚れました。
今後も、白洲次郎に関する書籍を読んでいきます。