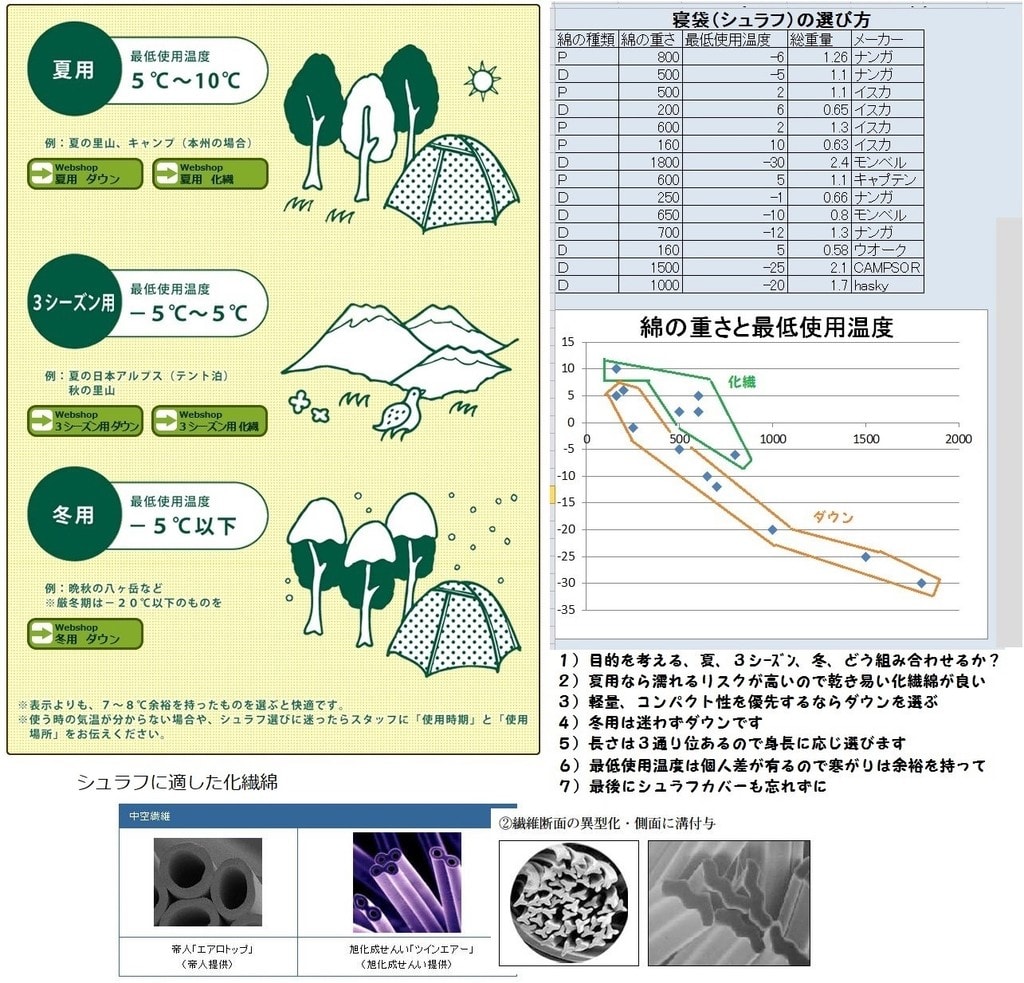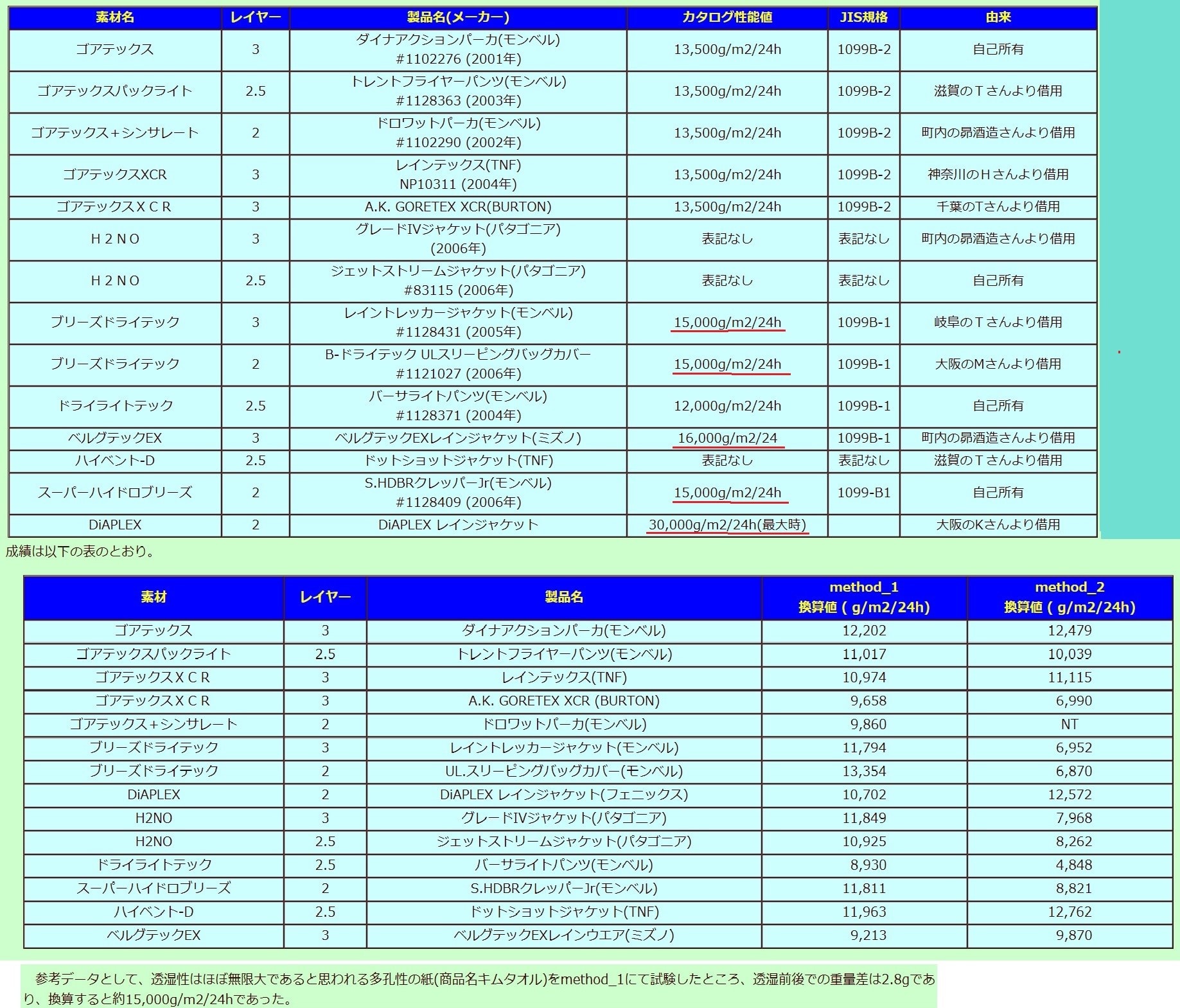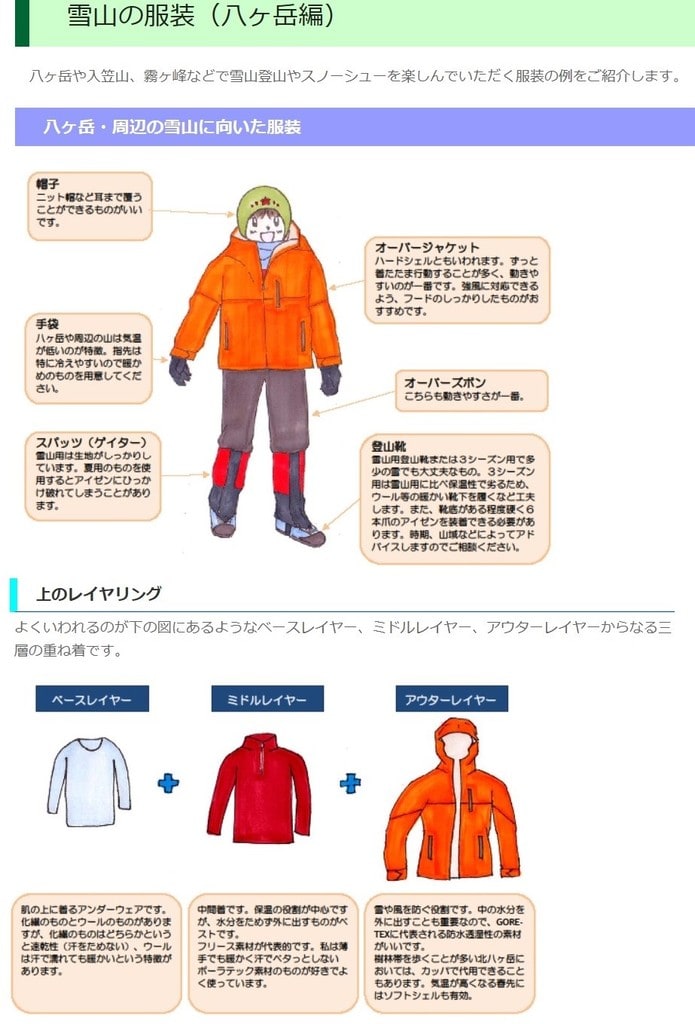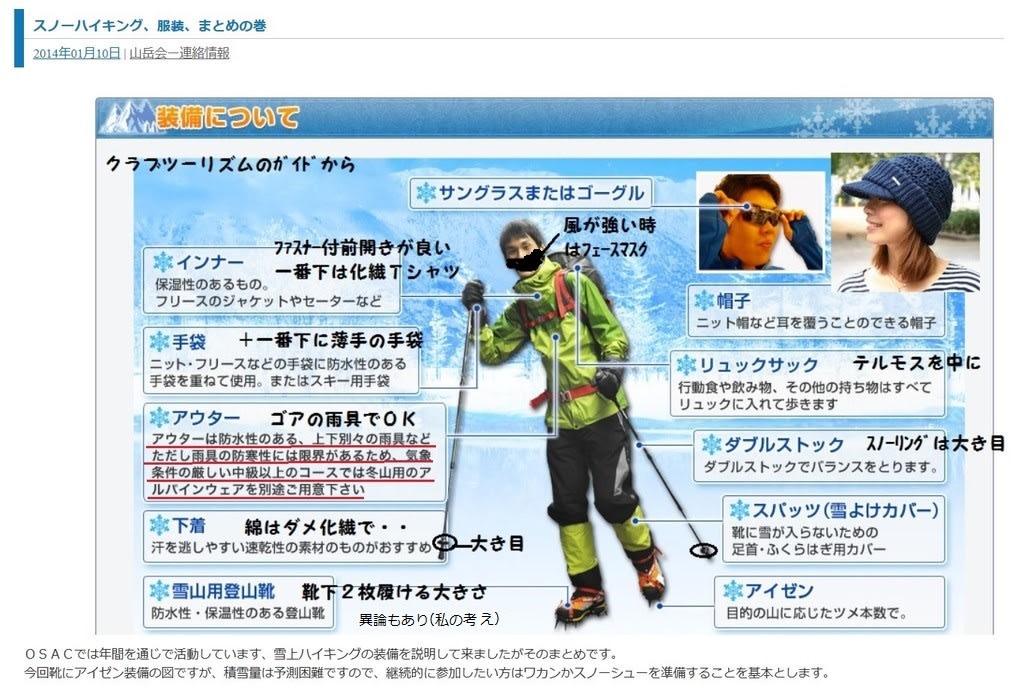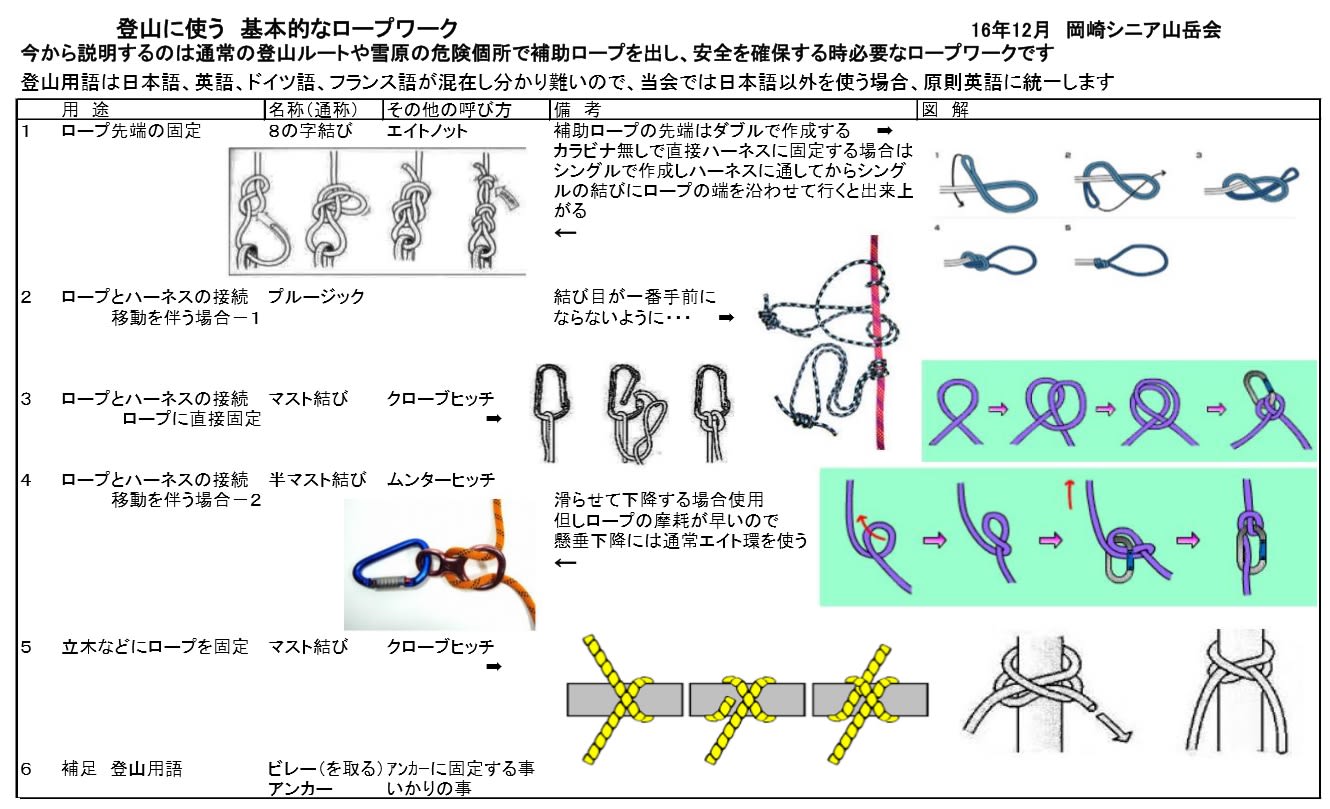先日開催したロープワーク講習会でY代表から紹介されたチエーンノットを解説します。
大事な事はハーネスにスリングやヌンチャクをぶら下げる時、整然とぶら下げることが重要です。
自分ではスリング右、ヌンチャクは左とか場所を決めて置き、とっさの時迷わないようにしましょう。
私は今まで捻じり式を採用していましたが、比較的長いスリング場合の捩れ易く使い難い欠点が有りました。
チェーン式は少しセットに時間が掛ますが、短縮率が大きく見た目綺麗で使い易いと思います。
チェーンノットは図では分かり難いので、youtubeを参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=YJVZMLCgPF8
大事な事はハーネスにスリングやヌンチャクをぶら下げる時、整然とぶら下げることが重要です。
自分ではスリング右、ヌンチャクは左とか場所を決めて置き、とっさの時迷わないようにしましょう。
私は今まで捻じり式を採用していましたが、比較的長いスリング場合の捩れ易く使い難い欠点が有りました。
チェーン式は少しセットに時間が掛ますが、短縮率が大きく見た目綺麗で使い易いと思います。
チェーンノットは図では分かり難いので、youtubeを参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=YJVZMLCgPF8