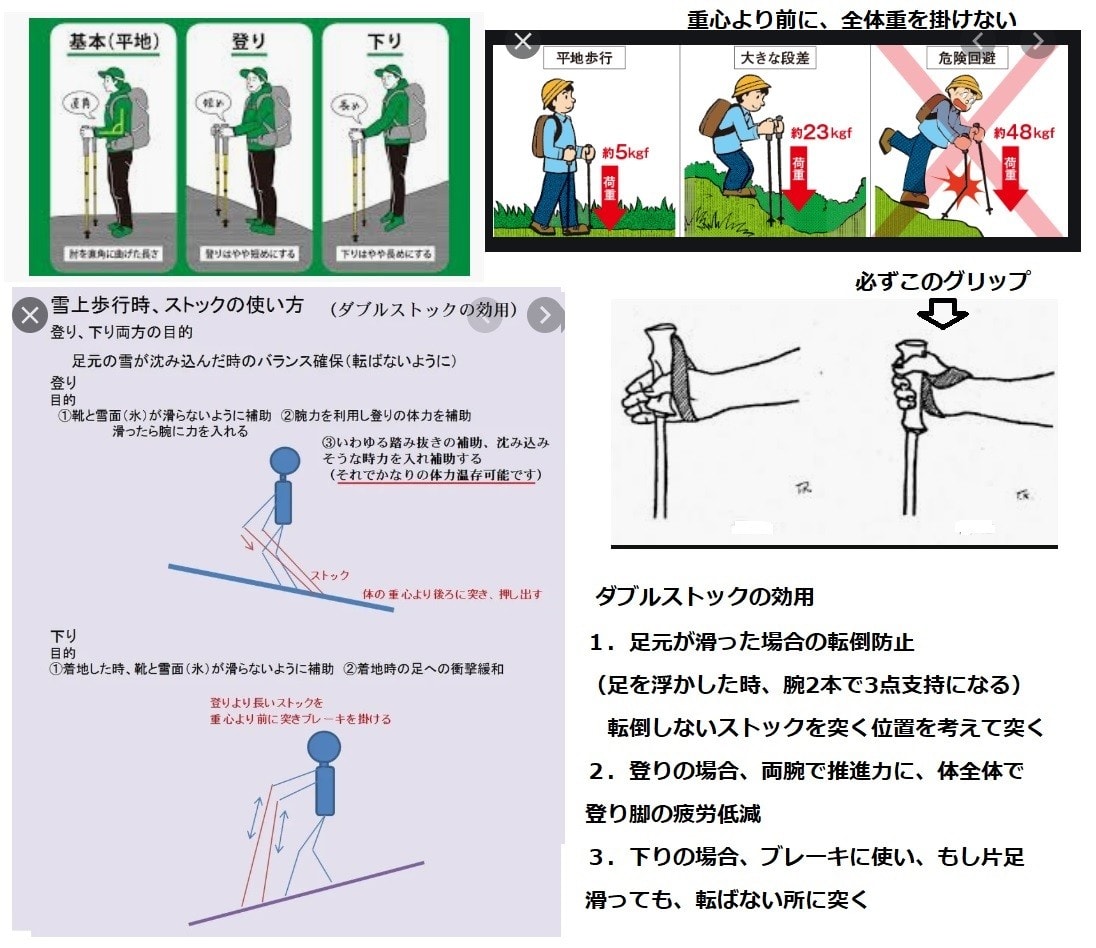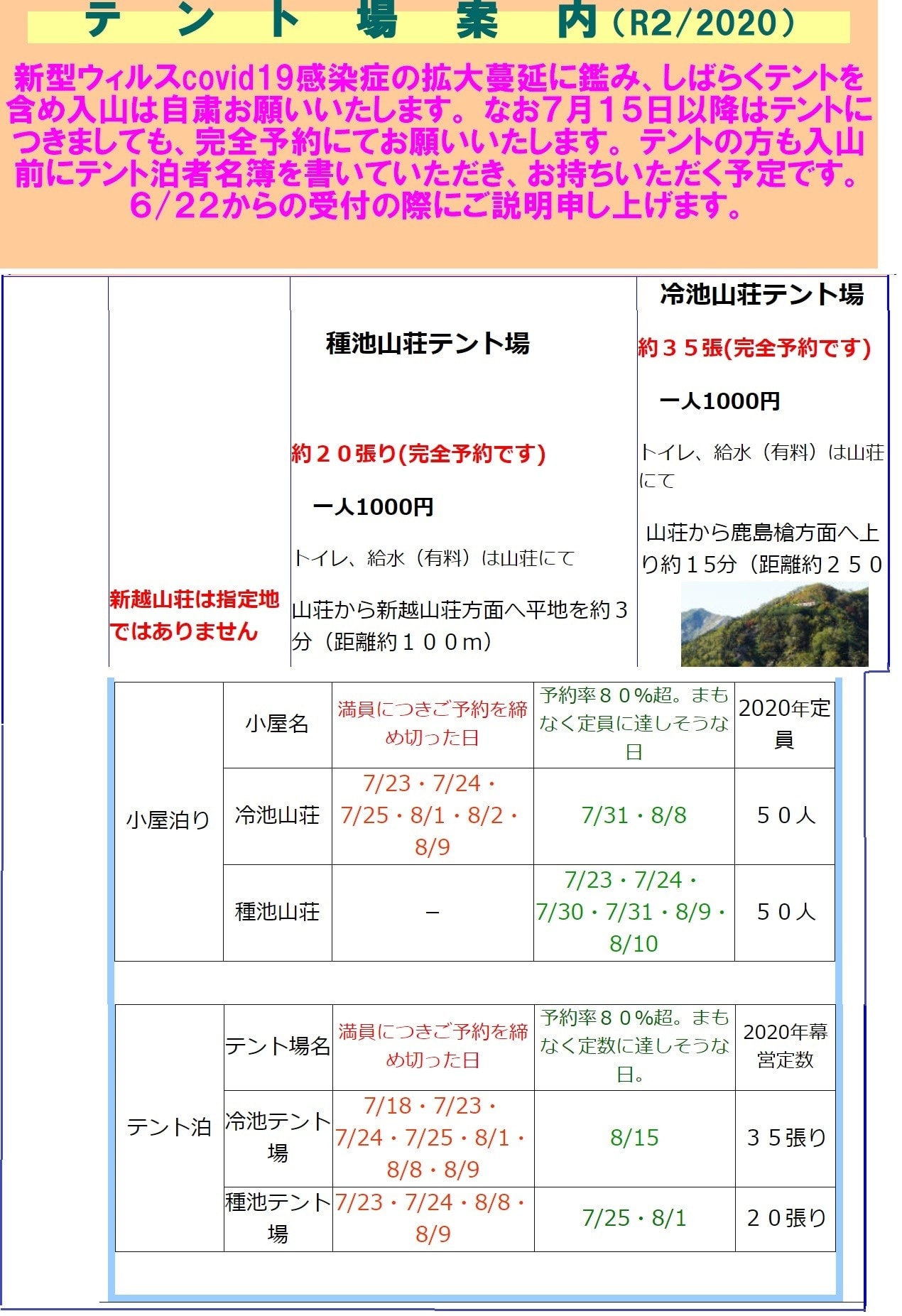ロッククライミングではなくバリエーションルートにおける岩場で、CLがロープを下し初心者がそのロープに対しプルージックで確保して登ることが有ります。
そこでプルージックに変わり便利な道具が有りますが、色々あり、どれを選ぶか迷います。
プルージックに代わり使う道具をアッセンダー(図の下 大型の物はユマールとも言う)と言い、登攀時登山者が操作せずに勝手に付いてくるので、登攀に集中でき大変便利で、安全です。
私は小型のユマールを持っていますが、右上の「roc’teryx」(ロックテリクス)を購入予定です。
上記はAmazonで粗悪なコピー品も販売しているので注意が必要です。