9月後半の三連休、友人と一緒に山陰へ出かけてきました。
まずは特急「やくも」で島根県へ。
以前、社会人になってすぐに一度乗りましたが、
相変わらず、揺れる揺れる!
揺れる「やくも」を安来で降りて、足立美術館へ向かいます。

足立美術館って、海外での評価高いんですってね。
確かにきれいです。ものすごくつくりこまれている。
だけどね……ごめんなさい、好みではありませんでした。
つくった感がすごすぎて、撮影用セットとかテーマパークの中を
歩いているみたい。
まあでも、これだけのものを文字通り「造って」「維持」している、
それはすごいと思います。
初日は、まっすぐお宿へ。
お宿は宍道湖沿い。
夜散歩した時と翌朝との写真です。宍道湖って本当に大きいですよね。


お隣には「しじみ館」。しじみの研究展示とお土産を置いています。
「乗って遊んで」のしじみ船にはちょっと笑いました。

2日目の午前中は、出雲大社へ。
一畑電車で出雲大社前へ向かいます。
電車の中には「しまねっこ」。
まあ、頭に出雲大社の屋根被ってるしね。

そして、平坦地を走るのにスイッチバックあるのね、この路線。
一畑口駅。珍しい~。
駅に目玉の親父さんがいてそれも不思議だったんだけど、
「目のお薬師様」と言われる一畑薬師の最寄り駅だからだそうです。
(後で調べました。笑)

そして川跡の駅で派手なラッピング電車に乗り換えとなり、
出雲大社前に到着。
ラッピング電車にももちろん「しまねっこ」が乗っています。
そして、ステンドグラスのはまった不思議な駅に到着。
裏手には、「デハニ50形」という古いタイプの車両が保存されています。




さて、いよいよ出雲大社へ。
勢溜の大鳥居(二の鳥居)は改修中のようでしたが、
平成の大遷宮より前、しかもすごい雨の日に一度行ったきりなので、
全然違う場所のよう(笑)

まずは、祓社へ。
祓戸四柱の神・瀬織津比咩神(せおりつひめのかみ)、速開都比咩神
(はやあきつひめのかみ)、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)、
速佐須良比咩神(はやさすらひめのかみ)が祀られます。

続く松の参道は、松の保護のため通れませんとのこと。
そういう理由?(笑)
で、脇の道を通ったわけですが……神苑の中、兎だらけ!
ああ、うん、大国主だし、因幡の白兎ね、とは思ったものの……
ちょっと場所違うような(笑) 可愛いけどさ。

そして拝殿へ。
その前にある銅鳥居(四の鳥居)は、もともと毛利輝元が寄進したものを、
孫の毛利綱広が造り直したもので、銅製の鳥居としては日本最古だそう。

総檜造りの拝殿。うん、出雲大社のイメージです。
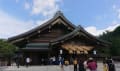
そして大社造りの御本殿を眺めます。
前にある八足門が、まず見事。
御本殿の、千木を置いた屋根の形と檜皮葺が美しい~!
なお、千木の小口は、男神は垂直(外削ぎ)、女神は水平(内削ぎ)に
切る事が多いと言いますが、あくまでも“多い”だけのようで。
鰹木の数も、女神は偶数本、男神は奇数本が多いそうですが、
これまた“多い”だけみたいです。
ともかくも、美しいです、寺社建築。良いわ~!



御本殿の奥には、素戔嗚尊を祀る素鵞社(そがのやしろ)があります。
なんか、勢溜の大鳥居の所にいたおじさんが、
「ここへ行くと空気が変わる」とか「御利益」とかおっしゃってましたが、
まあ、うん。うふふ(爆)
あ、お社は素敵だし、必見ですよ。もちろん。


ほかにも文庫とか彰古館とか、全国から八百万の神が集まる東西の十九社とか、
出雲大社は見どころが多いですね。
大きい注連縄がある神楽殿も有名です。


広い神社をぐるりと一回りして、出雲そばを食べて。
参道の「八雲」というお店の出雲そば。
つゆがけっこう甘いんですね。意外でした。

と、いうわけで。
お次は松江です。
まずは特急「やくも」で島根県へ。
以前、社会人になってすぐに一度乗りましたが、
相変わらず、揺れる揺れる!
揺れる「やくも」を安来で降りて、足立美術館へ向かいます。

足立美術館って、海外での評価高いんですってね。
確かにきれいです。ものすごくつくりこまれている。
だけどね……ごめんなさい、好みではありませんでした。
つくった感がすごすぎて、撮影用セットとかテーマパークの中を
歩いているみたい。
まあでも、これだけのものを文字通り「造って」「維持」している、
それはすごいと思います。
初日は、まっすぐお宿へ。
お宿は宍道湖沿い。
夜散歩した時と翌朝との写真です。宍道湖って本当に大きいですよね。


お隣には「しじみ館」。しじみの研究展示とお土産を置いています。
「乗って遊んで」のしじみ船にはちょっと笑いました。

2日目の午前中は、出雲大社へ。
一畑電車で出雲大社前へ向かいます。
電車の中には「しまねっこ」。
まあ、頭に出雲大社の屋根被ってるしね。

そして、平坦地を走るのにスイッチバックあるのね、この路線。
一畑口駅。珍しい~。
駅に目玉の親父さんがいてそれも不思議だったんだけど、
「目のお薬師様」と言われる一畑薬師の最寄り駅だからだそうです。
(後で調べました。笑)

そして川跡の駅で派手なラッピング電車に乗り換えとなり、
出雲大社前に到着。
ラッピング電車にももちろん「しまねっこ」が乗っています。
そして、ステンドグラスのはまった不思議な駅に到着。
裏手には、「デハニ50形」という古いタイプの車両が保存されています。




さて、いよいよ出雲大社へ。
勢溜の大鳥居(二の鳥居)は改修中のようでしたが、
平成の大遷宮より前、しかもすごい雨の日に一度行ったきりなので、
全然違う場所のよう(笑)

まずは、祓社へ。
祓戸四柱の神・瀬織津比咩神(せおりつひめのかみ)、速開都比咩神
(はやあきつひめのかみ)、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)、
速佐須良比咩神(はやさすらひめのかみ)が祀られます。

続く松の参道は、松の保護のため通れませんとのこと。
そういう理由?(笑)
で、脇の道を通ったわけですが……神苑の中、兎だらけ!
ああ、うん、大国主だし、因幡の白兎ね、とは思ったものの……
ちょっと場所違うような(笑) 可愛いけどさ。

そして拝殿へ。
その前にある銅鳥居(四の鳥居)は、もともと毛利輝元が寄進したものを、
孫の毛利綱広が造り直したもので、銅製の鳥居としては日本最古だそう。

総檜造りの拝殿。うん、出雲大社のイメージです。
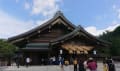
そして大社造りの御本殿を眺めます。
前にある八足門が、まず見事。
御本殿の、千木を置いた屋根の形と檜皮葺が美しい~!
なお、千木の小口は、男神は垂直(外削ぎ)、女神は水平(内削ぎ)に
切る事が多いと言いますが、あくまでも“多い”だけのようで。
鰹木の数も、女神は偶数本、男神は奇数本が多いそうですが、
これまた“多い”だけみたいです。
ともかくも、美しいです、寺社建築。良いわ~!



御本殿の奥には、素戔嗚尊を祀る素鵞社(そがのやしろ)があります。
なんか、勢溜の大鳥居の所にいたおじさんが、
「ここへ行くと空気が変わる」とか「御利益」とかおっしゃってましたが、
まあ、うん。うふふ(爆)
あ、お社は素敵だし、必見ですよ。もちろん。


ほかにも文庫とか彰古館とか、全国から八百万の神が集まる東西の十九社とか、
出雲大社は見どころが多いですね。
大きい注連縄がある神楽殿も有名です。


広い神社をぐるりと一回りして、出雲そばを食べて。
参道の「八雲」というお店の出雲そば。
つゆがけっこう甘いんですね。意外でした。

と、いうわけで。
お次は松江です。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます