昨日(3月8日)は、夕方から深夜まで本堂にこもりきり。勿論、掃除。仏具が運ばれ、設置されたまでは良かったのですが、設置作業に伴うホコリ・ゴミ等が散乱状態。これはいけません。という事で、大掃除となりました。
お寺を預かる僧侶とは、法話・読経も大切ですが、お預かりしているお寺の掃除が一番大切。結局、本堂を掃除するという事は、自分のこころの雑草を掃除しているようなものです。「本堂・境内が、綺麗になれば自分の心も雑念なし。」こんな境地に至りたいものです。これが、「阿弥陀様に対する御恩報謝」であると思います。でも、この言葉は私の言葉ではありません。亡き父親の言葉。その入口付近には、自分も至りたいものです。
1年有余に渡った本堂工事も、明日(3月10日)で工事事務所も解体されます。思う事があります。本当に、境内が綺麗になったのです。それは、金剛組の社訓かも判りませんが、徹底した清掃の賜物。「飛ぶ鳥 あとを濁さず」。この言葉の持つ重さを今かみ締めています。だからこそ、飛鳥時代から今に続く宮大工集団として存続しているのだと思います。写真は、3月9日撮影

1年間、本堂修復工事を担当していただき「飛ぶ鳥 あとを濁さず」を実践された監督の小澤さん。3月9日撮影

お寺を預かる僧侶とは、法話・読経も大切ですが、お預かりしているお寺の掃除が一番大切。結局、本堂を掃除するという事は、自分のこころの雑草を掃除しているようなものです。「本堂・境内が、綺麗になれば自分の心も雑念なし。」こんな境地に至りたいものです。これが、「阿弥陀様に対する御恩報謝」であると思います。でも、この言葉は私の言葉ではありません。亡き父親の言葉。その入口付近には、自分も至りたいものです。
1年有余に渡った本堂工事も、明日(3月10日)で工事事務所も解体されます。思う事があります。本当に、境内が綺麗になったのです。それは、金剛組の社訓かも判りませんが、徹底した清掃の賜物。「飛ぶ鳥 あとを濁さず」。この言葉の持つ重さを今かみ締めています。だからこそ、飛鳥時代から今に続く宮大工集団として存続しているのだと思います。写真は、3月9日撮影

1年間、本堂修復工事を担当していただき「飛ぶ鳥 あとを濁さず」を実践された監督の小澤さん。3月9日撮影













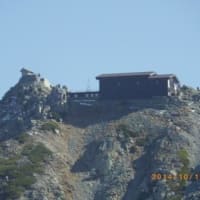







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます