「行く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」とは、高校時代古典の時間に習った『方丈記(ほうじょうき)』の有名な一節。鎌倉時代初期の鴨長明(かものちょうめい)の作品。写真は、自坊の前を流れる用水路。水量豊かに流れている。昭和30年代後半まで、生活の全てで使用されていた。勿論、飲料水でもあった。源は藤原岳に発する名水である。今は、農業用水としてのみ使用されている。

上記の『方丈記(ほうじょうき)』の一節は、仏教的思想を背景に、河の流れを人生になぞらえて書かれている。河の流れは、いつも同じように流れていますが、よくよく考えれば流れている水は全部はじめての水の筈。日本は、水には恵まれた国。だから、水道の蛇口を捻(ひね)ればいつでもあるように思っている。昔の人は、同じ用水路の水でも使用ルールが決められており、大変貴重なものとして扱った。米粒一粒も流すことは無かったと聞いている。それが、現代はやりたい放題。断水となり、始めて水の貴重さ、大切さが判るというお粗末な話。それで、河の水を見てもなかなか鴨長明(かものちょうめい)のようセンチメンタルな気持ちにはなれない。でも、河の流れは人生そのもの。

人生は、誕生し、育ち、学び、働き、恋をし、失恋し、結婚し、成功し、失敗し、悩み、苦しみ、喜び、病気となり、老いて、死んでいく。まさに、人生は河の流れである。しかも、河の流れは水滴の集まり。一滴一滴の水滴は、集まり流れ下る。水滴そのものは、始めて流れくだっている。私は、今年で59歳。来年の2月10日で60歳となる。私にとっては、59歳と一口に言っても、はじめての59歳の日々をおくっている事になる。しかも、自分の河の流れがどこまで流れていくかも不明である。ここのところを『方丈記(ほうじょうき)』は、次のように述べている。「よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、ひさしくとどまりたるためしなし」とあり、人の一生を、水面に浮かぶ泡にたとえている。泡は、つかの間に消えるものである。そういえば、バブル経済も見事に弾けた。ここまでくると、私達は蓮如上人の「白骨のお文」の一節が頭に浮かぶ。「されば、朝(あした)には、紅顔(こうがん)ありて、夕(ゆうべ)には白骨となれる身なり」である。
鴨長明(かものちょうめい)は、『方丈記(ほうじょうき)』の中で無常感を切々とつづるのである。はかない命を散らす、桜吹雪が大好きな日本人の好みにはピッタリの表現である。しかし、仏教でいう無常は、違うのである。無常観という。読み方は同じでも、感と観はおおよそ違う。感は、感傷的な感。観は、しっかりと見る観なのである。何をしっかり観るのか?水面に浮かぶバブルは、一瞬で消えうせても、その一瞬を見事に生ききっているバブルを観るのである。だからこそ、釈尊(お釈迦様)は法句経(ほっくきょう)にて、「やがて死すべきこのいのち、今いのちあるはありがたし」と述べられた。「ありがたし」を漢字で書けば「有難し」となる。あることが難しいこの一瞬を、生きさせていただいている事に感謝し、必死で生きよという事に他ならない。蓮如上人も、「白骨のお文」の結語には、「たれの人もはやく後生の一大事をこころにかけて」とお示しである。
最後に下の写真。

二本の水路から、水が合流して一本の水となっている。しかも、何のわだかまりもなく最初から一本の水であったかのように流れる。これを見ていると、縁により恋仲となった二人が、苦しみもがきながらも一身同体のごとくになる様を考えてしまうのだが・・・・

上記の『方丈記(ほうじょうき)』の一節は、仏教的思想を背景に、河の流れを人生になぞらえて書かれている。河の流れは、いつも同じように流れていますが、よくよく考えれば流れている水は全部はじめての水の筈。日本は、水には恵まれた国。だから、水道の蛇口を捻(ひね)ればいつでもあるように思っている。昔の人は、同じ用水路の水でも使用ルールが決められており、大変貴重なものとして扱った。米粒一粒も流すことは無かったと聞いている。それが、現代はやりたい放題。断水となり、始めて水の貴重さ、大切さが判るというお粗末な話。それで、河の水を見てもなかなか鴨長明(かものちょうめい)のようセンチメンタルな気持ちにはなれない。でも、河の流れは人生そのもの。

人生は、誕生し、育ち、学び、働き、恋をし、失恋し、結婚し、成功し、失敗し、悩み、苦しみ、喜び、病気となり、老いて、死んでいく。まさに、人生は河の流れである。しかも、河の流れは水滴の集まり。一滴一滴の水滴は、集まり流れ下る。水滴そのものは、始めて流れくだっている。私は、今年で59歳。来年の2月10日で60歳となる。私にとっては、59歳と一口に言っても、はじめての59歳の日々をおくっている事になる。しかも、自分の河の流れがどこまで流れていくかも不明である。ここのところを『方丈記(ほうじょうき)』は、次のように述べている。「よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、ひさしくとどまりたるためしなし」とあり、人の一生を、水面に浮かぶ泡にたとえている。泡は、つかの間に消えるものである。そういえば、バブル経済も見事に弾けた。ここまでくると、私達は蓮如上人の「白骨のお文」の一節が頭に浮かぶ。「されば、朝(あした)には、紅顔(こうがん)ありて、夕(ゆうべ)には白骨となれる身なり」である。
鴨長明(かものちょうめい)は、『方丈記(ほうじょうき)』の中で無常感を切々とつづるのである。はかない命を散らす、桜吹雪が大好きな日本人の好みにはピッタリの表現である。しかし、仏教でいう無常は、違うのである。無常観という。読み方は同じでも、感と観はおおよそ違う。感は、感傷的な感。観は、しっかりと見る観なのである。何をしっかり観るのか?水面に浮かぶバブルは、一瞬で消えうせても、その一瞬を見事に生ききっているバブルを観るのである。だからこそ、釈尊(お釈迦様)は法句経(ほっくきょう)にて、「やがて死すべきこのいのち、今いのちあるはありがたし」と述べられた。「ありがたし」を漢字で書けば「有難し」となる。あることが難しいこの一瞬を、生きさせていただいている事に感謝し、必死で生きよという事に他ならない。蓮如上人も、「白骨のお文」の結語には、「たれの人もはやく後生の一大事をこころにかけて」とお示しである。
最後に下の写真。

二本の水路から、水が合流して一本の水となっている。しかも、何のわだかまりもなく最初から一本の水であったかのように流れる。これを見ていると、縁により恋仲となった二人が、苦しみもがきながらも一身同体のごとくになる様を考えてしまうのだが・・・・












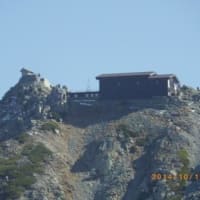







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます