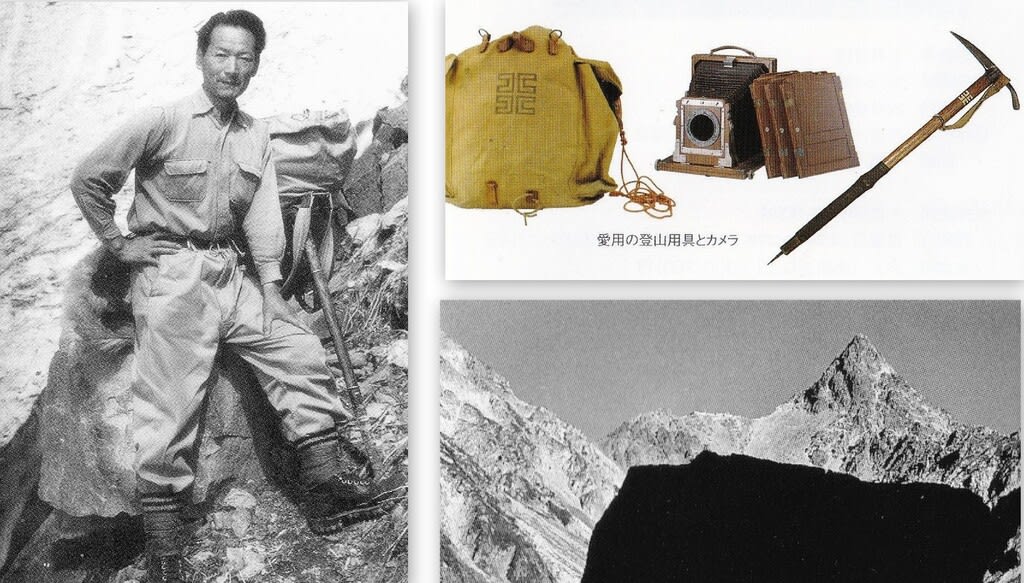信州上田の・・・六文銭の写真帳
2月中旬、厳冬の北信濃・・・大町へ・・・神仏集合そのまんま残存する若一王神社を尋ねてのドライブ・・・
若一王子神社(にゃくいちおうじじんじゃ)・・・長野県大町市大町2097、JR大糸線北大町駅徒歩10分、国道148号線。県道31号線(糸魚川街道、千国街道)からすぐ。
若一王子権現(若一王寺)の三重塔・・・
★江戸時代中期に木食三居上人の勧進によって1711年建立、方三間三層、杮葺き屋根。高さ20.21m。明治初年の1868年、神仏分離令により廃仏毀釈の運動が起こったが若一王子神社と名前を変え三重塔は物見塔であると言い張り難を逃れたという。



※撮影日は2月9日。
★日本の近世以前の三重塔は102(うち国宝が13)。信州には10(うち国宝が2、重要文化財が3)あります。1月から上田市塩田平の安楽寺八角三重塔、前山寺三重塔、青木村の大法寺三重塔、上田市国分の国分寺三重塔、御代田町の真楽寺三重塔、佐久市田口の新海三社神社の三重塔、佐久市前山の貞祥寺三重塔、大町の若一王子神社の三重塔を尋ね、過去に小川町高山寺の三重塔を尋ねていますから計9塔を尋ねています。残るは駒ケ根市の光前寺の三重塔だけに。★神仏分離令は明治初年に太政官布告で出された法令。廃仏毀釈は最初は藩主が主導、そのご民間の運動に。比叡山延暦寺への攻撃からはじまり奈良興福寺への襲撃、鹿児島では藩領の1066寺のすべてが廃寺。説明すると平田国学、神道国教化、明治の蛮行とか長くなるので割愛。
★松本藩での廃仏毀釈は藩主の戸田氏の主導のもとに始まり領内180寺のうち140寺が廃寺、打ち毀しなどは78%に及んだという。松本藩領大町の若一王子権現は若一王子神社に、三宝荒神は竈神社に名を変え難を逃れた。
※コメント欄オープンにしています。
・URL無記入のコメントは削除します。
・URL無記入のコメントは削除します。