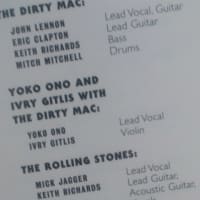《2012年秋のGⅠノ日に更新していく競馬小説》
(13)
日曜日。早くから目覚めていたにもかかわらず、なかなか布団から起き上がってこなかった亮一だが、それでも昼過ぎには支度を終えて家を出た。
まんじりともしないでいると、考えばかりが先走ってよくないことになってしまうのだ、と亮一は分かってはいるのだが、何故かそうなってしまう。
考えすぎは無駄。いや、それどころか悪いことですらある。なにしろ亮一は昨夜のなまめかしい記憶も手伝い、あの金全てが自分のものになったら、などということまで頭の中に浮かべていたのだから。
それは、積極的という意味にではない。ただ単に、今日自分がこのまま動かなければあの金は……、という消極的な考えからだった。しかしそんな思いが30分、1時間と頭の中に居座ると、次に、自分ならそれはありえるぞ、と考えるようになる。そしてそれが時間の経つうちに、より現実味を帯びてくる。
あの金があれば山浦への借金も返せるし、いつもより豪華な正月も過ごせる。そんな危険な考えが膨らんできては亮一を揺さぶる。どの道あのせがれはこの金のことなど知らないのだから……、だから……、だから……。
しかし気の弱さ、臆病さも長所となりうる時がある。そんな危険な考えを打ち消してくれるような突拍子もない反対意見を組み立ててしまうからだ。
――もし、万が一あのせがれがこの金のことを知っていたら。あるいは知ったら……。
山浦のとき以上のものが待ち受けていることは、想像に難しくない。あの額のキズ、乾いた目、先の尖った靴。
もしもクーさんが、自分亡き後せがれが素性の分からない輩にからまないよう、いかにもおとなしくからまれ続けていってくれそうな俺のことを生け贄に考えていたら、どうだろう。その因縁をつけさせるために金を渡したのでは、と被害妄想そのものの想像まで働かせた末の、昼過ぎの出発なのだった。
今日のジャンパーは、1年前のあのクーさんと初めて飲みに行った日と同じ、分厚くて重いものだ。そしてその内ポケットに突っ込んだものが、より重さを増している。
駅に着いたところで病院に電話をかけてみる。声音を思い切り低くし、クーさんの縁者だと言い、容態を尋ねた。
「残念ながら昨晩遅く。で、失礼ですがどちら…」
そうですか、と失意を含め、一方的に電話を切った。病院は遺体の処理に困っているのかも知れない。内ポケットの中でずしりと膨らんだものは、相続人にとって遺産となってしまった。
布団の中で考えたことが頭の中に甦ってくる。彼はタバコを取り出し、1本分、その場に佇んだ。動けば胸や肩に内ポケットの重いものが響き渡ってしまう。
どうしよう、このまま家に戻ってしまおうか、しかし、と気持ちは揺れ動いていたが、駅のアナウンスに誘われるように電車に乗り込んだ。
駅から場外に向う途中、なるべく見ないようにしていたのだが、目線はついついあのせがれにいってしまう。せがれはそんな亮一の視線に気付くこともなく、競馬新聞の束を前に、仲間や客と軽口をたたき合っている。
父親が死んだというのに、知ってか知らずか路地で笑いあっている男。あんな男に声を掛け、クーさんの趣旨を説明し、ぬか喜びになるかも知れない遺産を手渡す……。自分にはそんなことできっこない、とくるりと踵を返したかった。場外のいつもの場所だけは避けなければならない。数少ない顔見知りに、万が一にもクーさんのことでも尋ねられたら、冷静に対応できるはずがない。亮一は大幅に場所を変え、そこでひたすら単勝のオッズだけを見つめていた。
発走1時間前の、1番人気馬の単勝オッズは2・4倍。現在2番人気馬が倍以上の5・7倍だから、もう人気がひっくり返ることはない。
40分前、準メインのレース。30分前、パドック。15分前、本馬場入場。1分、また1分と、時間が過ぎてゆく。
単勝1点170万円分。一体どれくらいの時間がかかるのだろう。つっ立っている時間はないはずなのだが。
以前、たしか百万円以上の高額購入は窓口の後ろからお偉いさんが出てくると聞いたことがある。今は機械だからどうなのだろう。
「あと約5分で第10競争の発走を締め切ります。あと約5分で……」
いつも聞き慣れたお決まりの放送が、今日は体の芯に突き刺さる。
もう買い始めなければ手遅れだ。しかし足が動かない。締め切り時間が1分単位で迫ってくる。
――シシャノイサンヲノムナ。
頭の中で危険信号が鳴っている。一度大失敗してるじゃないか。ノむのはまずい!
あと1分。売り場窓口には数人ずつ並んでいて、今後ろについても間に合うかどうか。
クーさん、和生、1番人気、黒の札入れ。様々なものが頭の中を駆け巡る。山浦、昨日の女、クーさんの家、俺の部屋。気付かないうちに息が荒くなっている。吊るし上げ、カードの借金、単勝オッズ……。思い浮かぶものの間に警報が鳴り響く。ノムナ、ノムナ。警報が耳に、ひときわ大きく鳴り響いた。それは締め切りのベルだった。
ノムナ、ノムナ……。
もう遅い。震える足をかばうようにトイレに行き、顔を洗った。
ファンファーレが鳴り、出走馬が次々とゲートに入ってゆく。あぁやってしまったと虚脱状態の亮一だったが、それでものろのろとモニターの前に進み出る。
――来なけりゃいいんだ、1番人気が。そうなりゃなにも問題がない。
亮一は1番人気馬が1着にならないことだけを願って、テレビモニターを見つめた。
スタート。フロアがワッと歓声につつまれる。有馬記念は、毎年中山の2千5百メートル。およそ2分半。
――長すぎる、早く終わってくれ。
まだ各馬の位置取りすら定まっていないというのに、亮一はそればかり考えていた。
強烈な末脚で現在の地位を築いた1番人気の馬は手綱をがっちり抑え、今回も後方待機の策を採った。
――ペースよ遅くなれ…。
レースのペースが遅ければ、前半楽をした逃げ馬や先行馬がバテず、後方から差してくる馬が届かない。ましてや中山は直線が短く、ただでさえ先行有利だ。千メートル通過が60秒をゆうに超えている。間違いなくスローペースだ。
よし、と亮一が思ったのも束の間、スローペースを見越した1番人気馬が3コーナーから上がり始め、フロア全体が再びどよめく。
馬の反応はすこぶるよい。次々に他馬を追い抜いていく。亮一はまるで心臓を鷲づかみにされたような感覚で、それを見つめている。
「やっぱ強えぜ」
横の男がふてくされたように声を出した。
4コーナーで先頭集団に並びかけ、軽くかわして行こうとしたその時、
「――!」
ものすごいざわめきがフロアを包み、それと重なるようにいくつかの怒声が響き渡った。
1頭の先行馬が急に外に膨れ、まともに横からぶつけられた1番人気馬は大きく外へとはじかれた。完全に勢いを殺されたその馬は今まで経験したことのない着順でゴール板を過ぎて行った。
この瞬間1番人気馬の単勝馬券は、もし買っていれば外れとなった。
今のレースが審議であることを告げる放送が流れると、フロアの怒声が一段と激しくなった。
亮一はフワフワとした足取りで下りエスカレーターに向かって行った。たとえぶつかった馬が失格となったとしても、五着までの掲示板にすら馬番が載っていない一番人気馬が繰り上がるわけではない。単勝馬券を買っていたら紙クズになっていたという事実に変わりはないのだ。それよりもあの角の新聞売場を覗いてみる方が先決だ。当たろうが外れようが、ノんでしまったことには変わりがない。万が一にも奴が父親の計画を知っていたら、単に金を渡すだけで済むかどうか。
しかしそんな心配も杞憂に終った。和生は客や仲間連中となにやら騒がしく喋り合っていた。自動販売機でジュースを買うふりをして聞き耳を立てたが、どうやら仲間の一人が当てたようで、そいつのおごりで飲みに行こうと話し合っていた。
亮一は大きく安堵の溜息を吐いた。和生が自分にあてた遺産があるなどと夢にも思わない振る舞いだったからだ。
亮一はその場を離れていった。足がまだ震えている。とても最終レースなどする気になれない。とりあえず、からからになった喉の渇きを癒したかった。
亮一はふらふらと歩いた。
とにかく、疲れていた。疲れて、無性に喉が渇いていた。
路地に入り、近くに人のいないのを確かめ、クーさんの札入れを開く。ずっしりと、170万程の札束が収まっている。あとは数枚のカード類。再び震えが走り、汗が噴き出す。やってしまったなぁ、とかすれた声で小さく呟いた。
カードの中に、以前クーさんと通った店のボトルキープのものがあった。彼は急に懐かしさを感じ、その店に向かうべく路地を進んで行った。
まだやってないかもしれないと、覗き込むような感じで階段を降りていった。しかし不景気のご時勢、競馬帰りの客をいち早く取りこみたいのか、すでに店は開いていた。
それでもさすがに店は閑散としていた。まだ他に客もなかったことで、ホールに女はたったの2人だったがその2人にはさまれるように亮一は席に着いた。クーさんの札入れに入っていたボトルのカードを出すときに、知った店に来るのはまずかったかと不安が一瞬よぎった。
水割りを作る女の子の手元を見つめながら。亮一は、クーさんは、本当は馬券が外れることを願っていたんじゃないかと、ぼんやり思った。
もし自分が言い付け通りにしていたら、今頃あのせがれは、外れ馬券とこの店のボトルのカードが入った財布を父親の死と引き換えに持つことになっていた。
それを想像すると可笑しくなり、彼は笑いをかみ殺した。
水割りを受け取り、渇きを潤すように一気に飲み干す。
あいつは根こそぎおれから持って行く、とクーさんは口癖のように何度も嘆いていた。だとするとあのせがれは、クーさんの最後の遺産となったここのボトルさえも飲み干してしまったんだろうなぁ、と考え、亮一は抑え切れずに一人笑いを浮かべた。
しかし笑い顔は上手く作れず、亮一は代わりにしかめ面を浮かべることになった。酒の味がとんでもなく苦かったからだ。
焼け付くような感覚が喉から体中に広まる間に、亮一は全てを了解した。クーさんがこの最後のゲームで、せがれにどうしたかったかを……。
指先の震えは全身に伝わり、亮一は椅子から崩れ落ちた。悲鳴の上がる店の中で、亮一は目を異常に開きながら横たわっていた。そして、自分の体中を駆け巡っているのはきっと単純な毒物なのだろうと思った。なにしろ検出されたって、毒を盛った者が捕まることは絶対にないのだから。
─―そうか、ボトルに。なるほどいいアイデアだ、クーさん。だけどノまれるとは、さすがにそこまでは……。
亮一は散り散りに薄れていく意識の中で、ぼんやり考えていた。
(おわり)
・有馬記念 10番 ダークシャドウ単勝複勝
(13)
日曜日。早くから目覚めていたにもかかわらず、なかなか布団から起き上がってこなかった亮一だが、それでも昼過ぎには支度を終えて家を出た。
まんじりともしないでいると、考えばかりが先走ってよくないことになってしまうのだ、と亮一は分かってはいるのだが、何故かそうなってしまう。
考えすぎは無駄。いや、それどころか悪いことですらある。なにしろ亮一は昨夜のなまめかしい記憶も手伝い、あの金全てが自分のものになったら、などということまで頭の中に浮かべていたのだから。
それは、積極的という意味にではない。ただ単に、今日自分がこのまま動かなければあの金は……、という消極的な考えからだった。しかしそんな思いが30分、1時間と頭の中に居座ると、次に、自分ならそれはありえるぞ、と考えるようになる。そしてそれが時間の経つうちに、より現実味を帯びてくる。
あの金があれば山浦への借金も返せるし、いつもより豪華な正月も過ごせる。そんな危険な考えが膨らんできては亮一を揺さぶる。どの道あのせがれはこの金のことなど知らないのだから……、だから……、だから……。
しかし気の弱さ、臆病さも長所となりうる時がある。そんな危険な考えを打ち消してくれるような突拍子もない反対意見を組み立ててしまうからだ。
――もし、万が一あのせがれがこの金のことを知っていたら。あるいは知ったら……。
山浦のとき以上のものが待ち受けていることは、想像に難しくない。あの額のキズ、乾いた目、先の尖った靴。
もしもクーさんが、自分亡き後せがれが素性の分からない輩にからまないよう、いかにもおとなしくからまれ続けていってくれそうな俺のことを生け贄に考えていたら、どうだろう。その因縁をつけさせるために金を渡したのでは、と被害妄想そのものの想像まで働かせた末の、昼過ぎの出発なのだった。
今日のジャンパーは、1年前のあのクーさんと初めて飲みに行った日と同じ、分厚くて重いものだ。そしてその内ポケットに突っ込んだものが、より重さを増している。
駅に着いたところで病院に電話をかけてみる。声音を思い切り低くし、クーさんの縁者だと言い、容態を尋ねた。
「残念ながら昨晩遅く。で、失礼ですがどちら…」
そうですか、と失意を含め、一方的に電話を切った。病院は遺体の処理に困っているのかも知れない。内ポケットの中でずしりと膨らんだものは、相続人にとって遺産となってしまった。
布団の中で考えたことが頭の中に甦ってくる。彼はタバコを取り出し、1本分、その場に佇んだ。動けば胸や肩に内ポケットの重いものが響き渡ってしまう。
どうしよう、このまま家に戻ってしまおうか、しかし、と気持ちは揺れ動いていたが、駅のアナウンスに誘われるように電車に乗り込んだ。
駅から場外に向う途中、なるべく見ないようにしていたのだが、目線はついついあのせがれにいってしまう。せがれはそんな亮一の視線に気付くこともなく、競馬新聞の束を前に、仲間や客と軽口をたたき合っている。
父親が死んだというのに、知ってか知らずか路地で笑いあっている男。あんな男に声を掛け、クーさんの趣旨を説明し、ぬか喜びになるかも知れない遺産を手渡す……。自分にはそんなことできっこない、とくるりと踵を返したかった。場外のいつもの場所だけは避けなければならない。数少ない顔見知りに、万が一にもクーさんのことでも尋ねられたら、冷静に対応できるはずがない。亮一は大幅に場所を変え、そこでひたすら単勝のオッズだけを見つめていた。
発走1時間前の、1番人気馬の単勝オッズは2・4倍。現在2番人気馬が倍以上の5・7倍だから、もう人気がひっくり返ることはない。
40分前、準メインのレース。30分前、パドック。15分前、本馬場入場。1分、また1分と、時間が過ぎてゆく。
単勝1点170万円分。一体どれくらいの時間がかかるのだろう。つっ立っている時間はないはずなのだが。
以前、たしか百万円以上の高額購入は窓口の後ろからお偉いさんが出てくると聞いたことがある。今は機械だからどうなのだろう。
「あと約5分で第10競争の発走を締め切ります。あと約5分で……」
いつも聞き慣れたお決まりの放送が、今日は体の芯に突き刺さる。
もう買い始めなければ手遅れだ。しかし足が動かない。締め切り時間が1分単位で迫ってくる。
――シシャノイサンヲノムナ。
頭の中で危険信号が鳴っている。一度大失敗してるじゃないか。ノむのはまずい!
あと1分。売り場窓口には数人ずつ並んでいて、今後ろについても間に合うかどうか。
クーさん、和生、1番人気、黒の札入れ。様々なものが頭の中を駆け巡る。山浦、昨日の女、クーさんの家、俺の部屋。気付かないうちに息が荒くなっている。吊るし上げ、カードの借金、単勝オッズ……。思い浮かぶものの間に警報が鳴り響く。ノムナ、ノムナ。警報が耳に、ひときわ大きく鳴り響いた。それは締め切りのベルだった。
ノムナ、ノムナ……。
もう遅い。震える足をかばうようにトイレに行き、顔を洗った。
ファンファーレが鳴り、出走馬が次々とゲートに入ってゆく。あぁやってしまったと虚脱状態の亮一だったが、それでものろのろとモニターの前に進み出る。
――来なけりゃいいんだ、1番人気が。そうなりゃなにも問題がない。
亮一は1番人気馬が1着にならないことだけを願って、テレビモニターを見つめた。
スタート。フロアがワッと歓声につつまれる。有馬記念は、毎年中山の2千5百メートル。およそ2分半。
――長すぎる、早く終わってくれ。
まだ各馬の位置取りすら定まっていないというのに、亮一はそればかり考えていた。
強烈な末脚で現在の地位を築いた1番人気の馬は手綱をがっちり抑え、今回も後方待機の策を採った。
――ペースよ遅くなれ…。
レースのペースが遅ければ、前半楽をした逃げ馬や先行馬がバテず、後方から差してくる馬が届かない。ましてや中山は直線が短く、ただでさえ先行有利だ。千メートル通過が60秒をゆうに超えている。間違いなくスローペースだ。
よし、と亮一が思ったのも束の間、スローペースを見越した1番人気馬が3コーナーから上がり始め、フロア全体が再びどよめく。
馬の反応はすこぶるよい。次々に他馬を追い抜いていく。亮一はまるで心臓を鷲づかみにされたような感覚で、それを見つめている。
「やっぱ強えぜ」
横の男がふてくされたように声を出した。
4コーナーで先頭集団に並びかけ、軽くかわして行こうとしたその時、
「――!」
ものすごいざわめきがフロアを包み、それと重なるようにいくつかの怒声が響き渡った。
1頭の先行馬が急に外に膨れ、まともに横からぶつけられた1番人気馬は大きく外へとはじかれた。完全に勢いを殺されたその馬は今まで経験したことのない着順でゴール板を過ぎて行った。
この瞬間1番人気馬の単勝馬券は、もし買っていれば外れとなった。
今のレースが審議であることを告げる放送が流れると、フロアの怒声が一段と激しくなった。
亮一はフワフワとした足取りで下りエスカレーターに向かって行った。たとえぶつかった馬が失格となったとしても、五着までの掲示板にすら馬番が載っていない一番人気馬が繰り上がるわけではない。単勝馬券を買っていたら紙クズになっていたという事実に変わりはないのだ。それよりもあの角の新聞売場を覗いてみる方が先決だ。当たろうが外れようが、ノんでしまったことには変わりがない。万が一にも奴が父親の計画を知っていたら、単に金を渡すだけで済むかどうか。
しかしそんな心配も杞憂に終った。和生は客や仲間連中となにやら騒がしく喋り合っていた。自動販売機でジュースを買うふりをして聞き耳を立てたが、どうやら仲間の一人が当てたようで、そいつのおごりで飲みに行こうと話し合っていた。
亮一は大きく安堵の溜息を吐いた。和生が自分にあてた遺産があるなどと夢にも思わない振る舞いだったからだ。
亮一はその場を離れていった。足がまだ震えている。とても最終レースなどする気になれない。とりあえず、からからになった喉の渇きを癒したかった。
亮一はふらふらと歩いた。
とにかく、疲れていた。疲れて、無性に喉が渇いていた。
路地に入り、近くに人のいないのを確かめ、クーさんの札入れを開く。ずっしりと、170万程の札束が収まっている。あとは数枚のカード類。再び震えが走り、汗が噴き出す。やってしまったなぁ、とかすれた声で小さく呟いた。
カードの中に、以前クーさんと通った店のボトルキープのものがあった。彼は急に懐かしさを感じ、その店に向かうべく路地を進んで行った。
まだやってないかもしれないと、覗き込むような感じで階段を降りていった。しかし不景気のご時勢、競馬帰りの客をいち早く取りこみたいのか、すでに店は開いていた。
それでもさすがに店は閑散としていた。まだ他に客もなかったことで、ホールに女はたったの2人だったがその2人にはさまれるように亮一は席に着いた。クーさんの札入れに入っていたボトルのカードを出すときに、知った店に来るのはまずかったかと不安が一瞬よぎった。
水割りを作る女の子の手元を見つめながら。亮一は、クーさんは、本当は馬券が外れることを願っていたんじゃないかと、ぼんやり思った。
もし自分が言い付け通りにしていたら、今頃あのせがれは、外れ馬券とこの店のボトルのカードが入った財布を父親の死と引き換えに持つことになっていた。
それを想像すると可笑しくなり、彼は笑いをかみ殺した。
水割りを受け取り、渇きを潤すように一気に飲み干す。
あいつは根こそぎおれから持って行く、とクーさんは口癖のように何度も嘆いていた。だとするとあのせがれは、クーさんの最後の遺産となったここのボトルさえも飲み干してしまったんだろうなぁ、と考え、亮一は抑え切れずに一人笑いを浮かべた。
しかし笑い顔は上手く作れず、亮一は代わりにしかめ面を浮かべることになった。酒の味がとんでもなく苦かったからだ。
焼け付くような感覚が喉から体中に広まる間に、亮一は全てを了解した。クーさんがこの最後のゲームで、せがれにどうしたかったかを……。
指先の震えは全身に伝わり、亮一は椅子から崩れ落ちた。悲鳴の上がる店の中で、亮一は目を異常に開きながら横たわっていた。そして、自分の体中を駆け巡っているのはきっと単純な毒物なのだろうと思った。なにしろ検出されたって、毒を盛った者が捕まることは絶対にないのだから。
─―そうか、ボトルに。なるほどいいアイデアだ、クーさん。だけどノまれるとは、さすがにそこまでは……。
亮一は散り散りに薄れていく意識の中で、ぼんやり考えていた。
(おわり)
・有馬記念 10番 ダークシャドウ単勝複勝