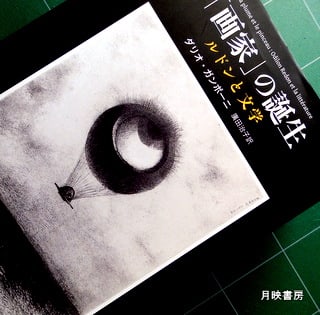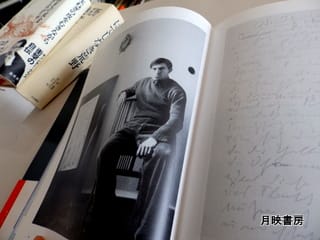ギリシャ生まれの美しい声の持主『ナナ・ムスクーリ』

『ナナ・ムスクーリ』、ギリシャ生まれの美しい声の持主、フランスでシャンソンを歌って知られるようになりました。ここに、フランスの『民謡』をナナ・ムスクーリが歌っているアルバムがあります。長く歌い継がれてきたせいか、洗練されたメロヂィーと繰り返しの多い歌詞、その場の空気が驚くほど澄み渡ります。日本の『民謡』と同様の魅力、その地域の風土と人々の生活や気質が伝わってきます。わたしは、レコードで聴いていますが、CDでもPCでダゥンロードしてぜひ聴いてみてください。