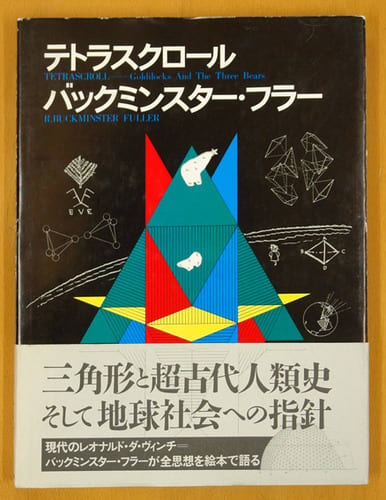これでいいのか『九谷焼』
ウルトラマンや怪獣の「九谷焼」に、はたして意味や未来があるのだろうか。はやりの「B級グルメ」の伝統工芸版なのか、それにしても、このような貧しい発想には呆れてしまいます。

美術品としての「九谷焼」は、作家たちの創作力が支えています。九谷焼独自の絵付け職人は、個々の技術により繊細な彩色美を創り出しています。作家であれ職人であれ、手業が伴う商品には、それ相応の価値があります。買う側の思いも加わり、伝統産業としての『九谷焼』は発展してきました。
ウルトラマンや怪獣に絵付けをすることの意味がわからない、壺や皿に絵付けをするのと変わらないと答える人がいるとすれば、教えていただきたい。これらをどのような人が、どのような気持ちで買うのか・・・。これらはもはや、子どもの玩具ではありません、ウルトラマンや怪獣の姿をした『焼き物(飾り)』です。これらの制作に関わった「絵付け職人」に、はたして「未来(可能性)」はあるのか・・・。
作家や職人の美意識が高揚している地域にのみ、優れた伝統産業が維持され発展するのです。このような「B級グルメ」のような発想に縋っては、ほんらいの『九谷焼』の美しい姿は早晩消えてしまいます。