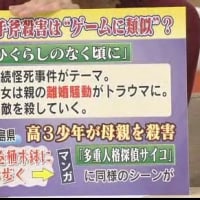婚外子も相続平等 自民が民法改正案了承し今国会成立へ(産経新聞) - goo ニュース
自民党法務部会(大塚拓部会長)は5日、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案を了承した。党内の保守派議員から慎重論が出たが、最高裁が9月の決定で非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法条文を「違憲」と判断したことを踏まえた。
政府は近く民法改正案を提出するが、公明党がすでに改正案を了承しているほか、野党も同様の法改正を求めており、今国会での成立が確実になった。
部会では政府が提示した改正案について、「最高裁の判断をそのまま受け入れるのか」「家族制度を守る法整備と合わせて来年の通常国会で改正すべきだ」などの反発が相次いだ。このため、大塚氏が自民党内に特命委員会を設置し、1年をめどに家族制度を守るための諸施策をとりまとめることを提案し、ようやく了承された。具体的には、配偶者の相続割合拡大などを法務省とともに検討する。
ただ、出生届に嫡出子か否かを記載する規定を削除する戸籍法改正については、「最高裁判決はそこまで求めていない」と異論が相次ぎ、了承は見送られた。これに先立ち、民主党とみんなの党、社民党は5日、民法の婚外子規定を削除する同様の民法改正案を参院に共同提出した。
私は戦前の「家制度」に賛同する者ではないですが、最高裁の非嫡出子相続分違憲判決には正直失望しました。確かに、私は以前に「非嫡出子法定相続分規定は憲法違反」と主張しました。しかし、かかる主張は今では間違いだと考えています。その理由は以下の通りです。
まず、民法の家族制度に対する基本スタンス(考え方)です。民法は家族制度について法律婚を定め、法律婚を保護するという立場を採っています。「保護する」ということは、法律婚と類似する他の関係(内縁等)よりも、法律婚を優先的に、すなわち類似する他の関係に差を設けて優遇するということです。そして、その一つが民法900条4号であると考えます。
したがって、嫡出子と非嫡出子の相続分に差を設けるというのは、法律婚を優先的に保護する以上、許されるべき帰結であるといえます。
次に、実際上の非嫡出子の相続分についてです。確かに民法900条4号は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と規定しますが、かかる規定は強行規定(=当事者の意思によって法律上の規定を覆すことができない規定のこと、たとえば殺人を委任する契約を禁じる民法90条。)ではないので、たとえば被相続人が遺言によって非嫡出子と嫡出子の相続分を平等にすることも、逆に非嫡出子の相続分のほうを多くすることも自由です。
このように、900条4号は非嫡出子の相続分は2分の1で「なければならない」と規定しているものではなく、相続分は被相続人が自由に決めることができるので、一概に憲法14条に反すると言えないのではないかと考えます。
3点目として、民法はどのような者であっても法律婚を行えるとしているのに、敢えて事実婚=内縁を選択した以上、内縁関係を選択した者はそこから生じる不利益も甘受すべきです。このようなことを言うと、内縁関係から生まれた子供に罪はないとの批判を受けると思います。しかし、子供に不憫な思いをさせたくないなら上で述べたように遺言で非嫡出子の相続分を同額にすればよいし、内縁から生まれた子供に罪がないからこそ、民法は900条4号において非嫡出子であっても一定程度の相続権を認めているとも考えることができます。それが2分の1である理由は最初に述べた通りです。
このように考えると、民法900条4号は憲法14条に反するような類の条文ではなく、法律婚の保護を図り、他方で法律婚以外で生まれた子の保護との調和を取り、しかも遺言によって相続分を平等にすることも否定しない、極めて合理的な規定であるといえます。
したがって、民法900条4号は合憲の規定であると理解しますが、最高裁によって違憲判決が(遺憾ながら)出てしまった以上、しばしば指摘されるように配偶者の相続分を手厚くするなど、法律婚の保護という理念を貫徹した法改正が望まれます。
自民党法務部会(大塚拓部会長)は5日、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案を了承した。党内の保守派議員から慎重論が出たが、最高裁が9月の決定で非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法条文を「違憲」と判断したことを踏まえた。
政府は近く民法改正案を提出するが、公明党がすでに改正案を了承しているほか、野党も同様の法改正を求めており、今国会での成立が確実になった。
部会では政府が提示した改正案について、「最高裁の判断をそのまま受け入れるのか」「家族制度を守る法整備と合わせて来年の通常国会で改正すべきだ」などの反発が相次いだ。このため、大塚氏が自民党内に特命委員会を設置し、1年をめどに家族制度を守るための諸施策をとりまとめることを提案し、ようやく了承された。具体的には、配偶者の相続割合拡大などを法務省とともに検討する。
ただ、出生届に嫡出子か否かを記載する規定を削除する戸籍法改正については、「最高裁判決はそこまで求めていない」と異論が相次ぎ、了承は見送られた。これに先立ち、民主党とみんなの党、社民党は5日、民法の婚外子規定を削除する同様の民法改正案を参院に共同提出した。
私は戦前の「家制度」に賛同する者ではないですが、最高裁の非嫡出子相続分違憲判決には正直失望しました。確かに、私は以前に「非嫡出子法定相続分規定は憲法違反」と主張しました。しかし、かかる主張は今では間違いだと考えています。その理由は以下の通りです。
まず、民法の家族制度に対する基本スタンス(考え方)です。民法は家族制度について法律婚を定め、法律婚を保護するという立場を採っています。「保護する」ということは、法律婚と類似する他の関係(内縁等)よりも、法律婚を優先的に、すなわち類似する他の関係に差を設けて優遇するということです。そして、その一つが民法900条4号であると考えます。
したがって、嫡出子と非嫡出子の相続分に差を設けるというのは、法律婚を優先的に保護する以上、許されるべき帰結であるといえます。
次に、実際上の非嫡出子の相続分についてです。確かに民法900条4号は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と規定しますが、かかる規定は強行規定(=当事者の意思によって法律上の規定を覆すことができない規定のこと、たとえば殺人を委任する契約を禁じる民法90条。)ではないので、たとえば被相続人が遺言によって非嫡出子と嫡出子の相続分を平等にすることも、逆に非嫡出子の相続分のほうを多くすることも自由です。
このように、900条4号は非嫡出子の相続分は2分の1で「なければならない」と規定しているものではなく、相続分は被相続人が自由に決めることができるので、一概に憲法14条に反すると言えないのではないかと考えます。
3点目として、民法はどのような者であっても法律婚を行えるとしているのに、敢えて事実婚=内縁を選択した以上、内縁関係を選択した者はそこから生じる不利益も甘受すべきです。このようなことを言うと、内縁関係から生まれた子供に罪はないとの批判を受けると思います。しかし、子供に不憫な思いをさせたくないなら上で述べたように遺言で非嫡出子の相続分を同額にすればよいし、内縁から生まれた子供に罪がないからこそ、民法は900条4号において非嫡出子であっても一定程度の相続権を認めているとも考えることができます。それが2分の1である理由は最初に述べた通りです。
このように考えると、民法900条4号は憲法14条に反するような類の条文ではなく、法律婚の保護を図り、他方で法律婚以外で生まれた子の保護との調和を取り、しかも遺言によって相続分を平等にすることも否定しない、極めて合理的な規定であるといえます。
したがって、民法900条4号は合憲の規定であると理解しますが、最高裁によって違憲判決が(遺憾ながら)出てしまった以上、しばしば指摘されるように配偶者の相続分を手厚くするなど、法律婚の保護という理念を貫徹した法改正が望まれます。