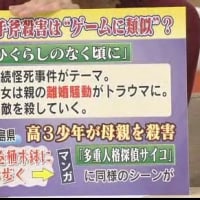【裁判員裁判】性犯罪初公判 求刑通り懲役15年(産経新聞) - goo ニュース
検察側の求刑通りとなった4日の青森地裁判決。主任弁護人の竹本真紀弁護士は「裁判員は、法律家以上に強姦(ごうかん)の結果を重く見たのではないか」と感想を漏らした。被告よりも被害者に感情が傾きがちな“素人感覚”が厳罰化を招くともいわれる裁判員裁判では、被告なりの事情を訴え、情状面を強調せざるをえない弁護活動は困難を強いられそうだ。3日間の審理は、“求刑の8ガケ”とされてきたいわゆる「量刑相場」に一石を投じるものとなった。
懲役15年とする判決には意義ない。ただし当然のことながら、ただ罰を与えればそれでよいのではなく、その罰が今後の被告にとってプラスになるのか(社会復帰的側面)、そして凶悪な犯罪にはそれ相応の制裁をして欲しいという面(被害者の視点からの側面)のバランスをきちんと取っている必要がある。
ちなみに、今回の事件は強姦のみのものではなく、強盗強姦事件なので、刑法177条の強姦罪ではなく、刑法241条の強盗強姦罪が問題となる事件である。強盗強姦罪の法定刑は、無期または7年以上の懲役である。
強盗強姦罪とは、強盗を目的とした者が女子を強姦した場合を定める規定で、強姦を目的とした者が強盗を働いた場合には強姦罪+強盗罪の刑で裁かれることになる。
今回、一番注目されている「量刑の相場」に関しては、これまでの強盗強姦事件においては、同類の他の犯罪(強盗、強姦等)が1~2件の場合には、懲役5~10年、単一の強盗強姦事件の場合は、おおよそ懲役3年6カ月、懲役4~5年といったところであるという。
これら「相場」に照らして今回の事件を考えてみると、弁護側は「懲役5年が妥当」としていたのだから、弁護側の判断はこれまでの「相場」に倣ったものだと言える。したがって、弁護側が不当に軽い判決を求めたわけではない。
しかしながら、これまでの「相場」による判断が、一体どれだけ被告の贖罪と、被害者の被害の回復に貢献してきたかについては、疑問がないでもない。そもそも、ここが一番重要なポイントであろう。
刑が軽すぎれば被告の更生も不十分に終わるだろうし、被害者の無念も晴れないだろう。かといって、刑が重すぎれば刑務所のキャパシティに問題が出てくることはもとより、刑法の基本的考えである「刑は人を裁くのではなく、その者が犯した罪を裁くものである」という原則を覆しかねず、そうなると魔女裁判のように、刑が先に挙げたバランスを失い、ただの制裁に傾いてしまう危険性もある。
したがって、やはり最初に指摘したように、刑を科すというのは、両者のバランスを考慮するという、実は極めて難しい作業であると言える。
ところで、私も使用した言葉だが、刑を判断するにあたって使用される「相場」という言葉の使用は控えたほうがいいかも知れない。なぜならば、「相場」という言葉からは、被害者をいたずらに軽視し、事件を裁く裁判に機械的で人間の血が通っていない印象を与えるからだ。
「相場」という言葉からは、事件それぞれで被害者も、そして加害者も違っていることを忘れさせ、事件によって被害者は甚大な苦痛を被り、精神的にも肉体的にも傷ついているのに、そうした「生身の人間の声」に耳を傾けず、ただ、これまでの「判断」にしたがい、機械的に「事件を処理している」という印象を、私は持つ。
こうした印象をもし多くの人が共有しているとしたら、これまでの「相場」に捕われず、求刑通りの懲役を下した今回の裁判に賛同する人は当然増えるだろう。それが「国民の判断(感覚)」を反映させるという、裁判員裁判の制度趣旨にも適うというものだ。
余談だが、先述したように、裁判員裁判は裁判に国民の判断(感覚)を反映させるための制度として始まったが、これは裏から見れば、これまでの裁判(裁判官、弁護士、検察官の法曹三者によってなされる裁判)が国民の感覚から離れたものであるということを証明していることである。
法的判断が一部の者だけがなしえる特権であるという時代は、もう終わったものだと思う。
検察側の求刑通りとなった4日の青森地裁判決。主任弁護人の竹本真紀弁護士は「裁判員は、法律家以上に強姦(ごうかん)の結果を重く見たのではないか」と感想を漏らした。被告よりも被害者に感情が傾きがちな“素人感覚”が厳罰化を招くともいわれる裁判員裁判では、被告なりの事情を訴え、情状面を強調せざるをえない弁護活動は困難を強いられそうだ。3日間の審理は、“求刑の8ガケ”とされてきたいわゆる「量刑相場」に一石を投じるものとなった。
懲役15年とする判決には意義ない。ただし当然のことながら、ただ罰を与えればそれでよいのではなく、その罰が今後の被告にとってプラスになるのか(社会復帰的側面)、そして凶悪な犯罪にはそれ相応の制裁をして欲しいという面(被害者の視点からの側面)のバランスをきちんと取っている必要がある。
ちなみに、今回の事件は強姦のみのものではなく、強盗強姦事件なので、刑法177条の強姦罪ではなく、刑法241条の強盗強姦罪が問題となる事件である。強盗強姦罪の法定刑は、無期または7年以上の懲役である。
強盗強姦罪とは、強盗を目的とした者が女子を強姦した場合を定める規定で、強姦を目的とした者が強盗を働いた場合には強姦罪+強盗罪の刑で裁かれることになる。
今回、一番注目されている「量刑の相場」に関しては、これまでの強盗強姦事件においては、同類の他の犯罪(強盗、強姦等)が1~2件の場合には、懲役5~10年、単一の強盗強姦事件の場合は、おおよそ懲役3年6カ月、懲役4~5年といったところであるという。
これら「相場」に照らして今回の事件を考えてみると、弁護側は「懲役5年が妥当」としていたのだから、弁護側の判断はこれまでの「相場」に倣ったものだと言える。したがって、弁護側が不当に軽い判決を求めたわけではない。
しかしながら、これまでの「相場」による判断が、一体どれだけ被告の贖罪と、被害者の被害の回復に貢献してきたかについては、疑問がないでもない。そもそも、ここが一番重要なポイントであろう。
刑が軽すぎれば被告の更生も不十分に終わるだろうし、被害者の無念も晴れないだろう。かといって、刑が重すぎれば刑務所のキャパシティに問題が出てくることはもとより、刑法の基本的考えである「刑は人を裁くのではなく、その者が犯した罪を裁くものである」という原則を覆しかねず、そうなると魔女裁判のように、刑が先に挙げたバランスを失い、ただの制裁に傾いてしまう危険性もある。
したがって、やはり最初に指摘したように、刑を科すというのは、両者のバランスを考慮するという、実は極めて難しい作業であると言える。
ところで、私も使用した言葉だが、刑を判断するにあたって使用される「相場」という言葉の使用は控えたほうがいいかも知れない。なぜならば、「相場」という言葉からは、被害者をいたずらに軽視し、事件を裁く裁判に機械的で人間の血が通っていない印象を与えるからだ。
「相場」という言葉からは、事件それぞれで被害者も、そして加害者も違っていることを忘れさせ、事件によって被害者は甚大な苦痛を被り、精神的にも肉体的にも傷ついているのに、そうした「生身の人間の声」に耳を傾けず、ただ、これまでの「判断」にしたがい、機械的に「事件を処理している」という印象を、私は持つ。
こうした印象をもし多くの人が共有しているとしたら、これまでの「相場」に捕われず、求刑通りの懲役を下した今回の裁判に賛同する人は当然増えるだろう。それが「国民の判断(感覚)」を反映させるという、裁判員裁判の制度趣旨にも適うというものだ。
余談だが、先述したように、裁判員裁判は裁判に国民の判断(感覚)を反映させるための制度として始まったが、これは裏から見れば、これまでの裁判(裁判官、弁護士、検察官の法曹三者によってなされる裁判)が国民の感覚から離れたものであるということを証明していることである。
法的判断が一部の者だけがなしえる特権であるという時代は、もう終わったものだと思う。