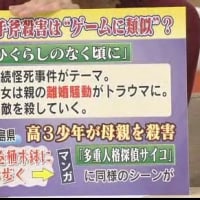後方支援の基準厳格化 政府 グレーゾーンは運用改善(産経新聞) - goo ニュース
政府は5日、多国籍軍などに対する自衛隊の後方支援活動を拡大するため「安全保障法制整備に関する与党協議会」に提示していた4つの新たな判断基準を見直し、厳格化する方針を固めた。自衛隊の活動範囲や任務の大幅な拡大を懸念する公明党に配慮した。6日の与党協議に提案する。一方、有事に至らない「グレーゾーン事態」への対応強化では、現行法内での運用改善で与党合意する見通しとなった。
政府は3日の与党協議会で、後方支援の新基準として(1)支援先が現に戦闘を行っている他国部隊(2)戦闘行為に直接用いられる物品や役務を提供(3)支援する他国部隊が現に戦闘を行う現場で提供(4)支援が他国部隊の個々の戦闘行為と密接に関係-の4条件を提示。全ての条件を満たすときに限って憲法が禁じる「武力行使との一体化」とみなし、後方支援を認めないとした。
物品輸送など後方支援の一部が「戦闘地域」でも可能になるため、公明党は「戦闘地域での戦闘行為以外は何でもできるようになる」と反発していた。このため、政府は4条件を一旦撤回し、後方支援できる対象を厳格化する方針だ。
政府内では「現に戦闘行為が行われている現場に行っている他国部隊に支援する」場合について「武力行使との一体化」とみなす案が浮上している。条件を減らし、簡略化することで「武力行使との一体化」の範囲を広げ、後方支援が可能になる範囲を狭める。
一方、離島警備などグレーゾーン事態への対処では、自民党は「自衛隊の武器の使用基準を見直すべきだ」として自衛隊法の改正などを主張してきたが、新たな法整備を「今後の研究課題」とし、公明党が主張している自衛隊の海上警備行動の発令手続きの簡略化など運用改善で対応する。
私は集団的自衛権行使を容認すべきとの立場ですが、近時の集団的自衛権に関する議論、とりわけ反対派ないしは慎重派の議論には非常な違和感を覚えています。以下、その違和感について考えてみたいと思います。
まず、安倍内閣が集団的自衛権行使の一例として提示したもの(米艦船の護衛等)に対し、個別的自衛権の範囲で対処できるとする見解もあるといって、集団的自衛権行使の必要はないとして批判します。しかし、私はこうした考え方は危険であると考えます。
というのは、有事の際に、「○○でも可能と理解されている」という解釈では現場を混乱させるだけでしょうし、また人権の保護のためにも、きちっと厳格に「やっていいこととやってはならないこと」の線引きがなされる必要がありますが、○○でも可能というのでは、厳格な自衛隊の運用を阻害し、かえって自衛権の範囲をいたずらに拡大させかねません。
そもそも、個別的自衛権の範囲を、集団的自衛権反対のために茫漠と拡大することこそ、平和主義と相いれない考え方でしょう。したがって、ここで求められているのは、現行憲法9条の縛りの中で自衛権とは何かを考え、それから個別的自衛権で何ができるか、そして集団的自衛権を行使しないとできないことは何かを考えることでしょう。
ところで、集団的自衛権反対派の中には、日本が今まで全く集団的自衛権を行使してこなかったかのように主張する者もいます。しかし、これは間違いです。実は、日本は既に集団的自衛権を行使しているのです。
日米安全保障条約6条で、同条約は「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」とし、そのために日本国内に米軍に基地を提供していますが、これは集団的自衛権のあらわれであり、集団的自衛権によらなければ、本来説明できないものなのです。
もっとも解せないのが、集団的自衛権を容認すると、「日本は戦争のできる国になる」といって、まるで日本が平和国家ではなくなるかのように喧伝している者たちです。
そもそも、戦争が「できる」ということは、それが直ちに戦争勃発と結びつくのでしょうか。「できる」という言葉には、「(できるけど)やらない」という意味も当然に包摂されています。たとえば、私は人を殺すことが「できる」。これは紛れもない事実です。しかし、私はそれを「しない」。なぜでしょうか。
理由は簡単です。その意味も必要性もないからです。ただしこれは「現在のところ」必要がないのであって、たとえば私が暴漢に襲われたとき、その場を凌ぐために、この手や足を使って暴漢に攻撃を加えることもありえます。最悪、その暴漢を殺してしまうかも知れないでしょう。しかし、もし暴漢が私を殺す気でかかってくれば、私のした行為は必ずしも「平和」に反した行為とはいえません。国家の行う戦争もこれと同じことではないでしょうか。
つまり、戦争をできる状態にしておくことで、自国の安全と生存を守るための最終手段を担保しておく必要があるのです。したがって、戦争を「できない」状態にする憲法9条は早々に改正されねばならないことになります。よって、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまでも憲法改正までの弥縫策であって、その先の憲法改正も見据えて議論する必要があるでしょう。
それにしても護憲派というものは、どうして常に「戦争」というと、日本がふっかけるのを前提としてしか考えられないのでしょう。改憲派は憲法9条を改正して日本の防衛力を確固たるものにして、常に「いざという時」に備えろと言っているにすぎません。しかし、護憲派の想定する「戦争」とは、常に日本側がふっかけるものと理解しているから、ここに改憲派の主張を正しく理解できないことの一因があるのではないでしょうか。
しかし、集団的自衛権行使容認を目指す安倍内閣にも問題はあります。確かに今まで最低でも50年余り日本の自衛権の解釈は問題にされてきたのに、議論が整理されていないなどという自民党内リベラル派や公明党は論外ですが、せっかく安保法制懇から報告書が提出されたのだから、次の国会ぐらいまでは議論してもいいと思います。
また、政府も日米同盟のために「も」集団的自衛権の行使を可能にするというのなら、せめて米軍駐留費(いわゆる「思いやり予算」)の軽減ぐらいアメリカに申し出すべきではないでしょうか。アメリカの要請もあって集団的自衛権の行使容認を議論しているのですから、これぐらいのことはバーターとして取引できないものかと思います。
政府は5日、多国籍軍などに対する自衛隊の後方支援活動を拡大するため「安全保障法制整備に関する与党協議会」に提示していた4つの新たな判断基準を見直し、厳格化する方針を固めた。自衛隊の活動範囲や任務の大幅な拡大を懸念する公明党に配慮した。6日の与党協議に提案する。一方、有事に至らない「グレーゾーン事態」への対応強化では、現行法内での運用改善で与党合意する見通しとなった。
政府は3日の与党協議会で、後方支援の新基準として(1)支援先が現に戦闘を行っている他国部隊(2)戦闘行為に直接用いられる物品や役務を提供(3)支援する他国部隊が現に戦闘を行う現場で提供(4)支援が他国部隊の個々の戦闘行為と密接に関係-の4条件を提示。全ての条件を満たすときに限って憲法が禁じる「武力行使との一体化」とみなし、後方支援を認めないとした。
物品輸送など後方支援の一部が「戦闘地域」でも可能になるため、公明党は「戦闘地域での戦闘行為以外は何でもできるようになる」と反発していた。このため、政府は4条件を一旦撤回し、後方支援できる対象を厳格化する方針だ。
政府内では「現に戦闘行為が行われている現場に行っている他国部隊に支援する」場合について「武力行使との一体化」とみなす案が浮上している。条件を減らし、簡略化することで「武力行使との一体化」の範囲を広げ、後方支援が可能になる範囲を狭める。
一方、離島警備などグレーゾーン事態への対処では、自民党は「自衛隊の武器の使用基準を見直すべきだ」として自衛隊法の改正などを主張してきたが、新たな法整備を「今後の研究課題」とし、公明党が主張している自衛隊の海上警備行動の発令手続きの簡略化など運用改善で対応する。
私は集団的自衛権行使を容認すべきとの立場ですが、近時の集団的自衛権に関する議論、とりわけ反対派ないしは慎重派の議論には非常な違和感を覚えています。以下、その違和感について考えてみたいと思います。
まず、安倍内閣が集団的自衛権行使の一例として提示したもの(米艦船の護衛等)に対し、個別的自衛権の範囲で対処できるとする見解もあるといって、集団的自衛権行使の必要はないとして批判します。しかし、私はこうした考え方は危険であると考えます。
というのは、有事の際に、「○○でも可能と理解されている」という解釈では現場を混乱させるだけでしょうし、また人権の保護のためにも、きちっと厳格に「やっていいこととやってはならないこと」の線引きがなされる必要がありますが、○○でも可能というのでは、厳格な自衛隊の運用を阻害し、かえって自衛権の範囲をいたずらに拡大させかねません。
そもそも、個別的自衛権の範囲を、集団的自衛権反対のために茫漠と拡大することこそ、平和主義と相いれない考え方でしょう。したがって、ここで求められているのは、現行憲法9条の縛りの中で自衛権とは何かを考え、それから個別的自衛権で何ができるか、そして集団的自衛権を行使しないとできないことは何かを考えることでしょう。
ところで、集団的自衛権反対派の中には、日本が今まで全く集団的自衛権を行使してこなかったかのように主張する者もいます。しかし、これは間違いです。実は、日本は既に集団的自衛権を行使しているのです。
日米安全保障条約6条で、同条約は「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」とし、そのために日本国内に米軍に基地を提供していますが、これは集団的自衛権のあらわれであり、集団的自衛権によらなければ、本来説明できないものなのです。
もっとも解せないのが、集団的自衛権を容認すると、「日本は戦争のできる国になる」といって、まるで日本が平和国家ではなくなるかのように喧伝している者たちです。
そもそも、戦争が「できる」ということは、それが直ちに戦争勃発と結びつくのでしょうか。「できる」という言葉には、「(できるけど)やらない」という意味も当然に包摂されています。たとえば、私は人を殺すことが「できる」。これは紛れもない事実です。しかし、私はそれを「しない」。なぜでしょうか。
理由は簡単です。その意味も必要性もないからです。ただしこれは「現在のところ」必要がないのであって、たとえば私が暴漢に襲われたとき、その場を凌ぐために、この手や足を使って暴漢に攻撃を加えることもありえます。最悪、その暴漢を殺してしまうかも知れないでしょう。しかし、もし暴漢が私を殺す気でかかってくれば、私のした行為は必ずしも「平和」に反した行為とはいえません。国家の行う戦争もこれと同じことではないでしょうか。
つまり、戦争をできる状態にしておくことで、自国の安全と生存を守るための最終手段を担保しておく必要があるのです。したがって、戦争を「できない」状態にする憲法9条は早々に改正されねばならないことになります。よって、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまでも憲法改正までの弥縫策であって、その先の憲法改正も見据えて議論する必要があるでしょう。
それにしても護憲派というものは、どうして常に「戦争」というと、日本がふっかけるのを前提としてしか考えられないのでしょう。改憲派は憲法9条を改正して日本の防衛力を確固たるものにして、常に「いざという時」に備えろと言っているにすぎません。しかし、護憲派の想定する「戦争」とは、常に日本側がふっかけるものと理解しているから、ここに改憲派の主張を正しく理解できないことの一因があるのではないでしょうか。
しかし、集団的自衛権行使容認を目指す安倍内閣にも問題はあります。確かに今まで最低でも50年余り日本の自衛権の解釈は問題にされてきたのに、議論が整理されていないなどという自民党内リベラル派や公明党は論外ですが、せっかく安保法制懇から報告書が提出されたのだから、次の国会ぐらいまでは議論してもいいと思います。
また、政府も日米同盟のために「も」集団的自衛権の行使を可能にするというのなら、せめて米軍駐留費(いわゆる「思いやり予算」)の軽減ぐらいアメリカに申し出すべきではないでしょうか。アメリカの要請もあって集団的自衛権の行使容認を議論しているのですから、これぐらいのことはバーターとして取引できないものかと思います。