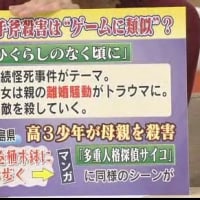足利事件:菅家さん「被告と呼ばせぬ」 21日に再審公判(毎日新聞)
菅家さんは6月4日に無期懲役の刑が執行停止され、再審開始決定を待たずに釈放された。異例のケースだが、再審で無罪判決が出るまで「被告」の立場が続く。
「今は自由ですよ。でも半分被告、半分自由。(刑務所から)出てますから、被告人と言われてもピンとこない。裁判では『菅家さん』と言ってもらいたい。『菅家氏』でもいい」と話す。弁護団も提出した上申書の中で「(被告と呼ぶのは)起訴状朗読の際以外には認めない。事件の呼び上げなどの際にもくれぐれも注意されたい」と求めている。
10月に入り、足利事件に関する供述が含まれる取り調べ録音テープを聞いた。検事に君は人間性がないと迫られ、泣きながら「自白」した。菅家さんは「反省して泣いたんじゃない。悔しかったんです。いくら『やってない』と言っても分かってくれなかった。どうして自分を犯人と決めつけたんだ。自分の立場と検事の立場を逆にすれば絶対、苦しみが分かる」と強い口調で話した。
菅谷氏は被告ではなく、被告「人」なのである。したがって、彼が「被告」と呼ばれることは、マスコミを除き、これまでも、そしてこれからもないはずなのだが。
それでは、「被告」と「被告人」の違いは具体的に何なのかということであるが、簡単に言うと、前者は民事事件または行政事件において訴えられた者の呼称で、後者は刑事事件において訴えられた者の呼称である。
上記の定義にしたがえば、菅谷氏は殺人罪で起訴され、刑事訴訟事件において争ってきたのだから、彼は被告ではなく被告「人」ということになる。だから冒頭で彼が「被告」と呼ばれたことは、これまでもそしてこれからもないはずだと述べたわけである。
刑事事件についてもう少し詳しく申し上げれば、捜査段階では「被疑者」であり、公訴提起(検察官による訴えのこと。)がなされると、訴えの対象という意味で「被告人」と呼称されることになる。
とはいうものの、この両者の間に名称以外の本質的な違いはないとされる。ちなみに、公訴提起されたが、裁判が確定していない者を被告人と呼ぶ。
なので余談だが、この記事には、「弁護団も提出した上申書の中で『(被告と呼ぶのは)起訴状朗読の際以外には認めない。事件の呼び上げなどの際にもくれぐれも注意されたい』と求めている。」とあるが、裁判官が菅谷氏を「被告」などと呼ぶはずもなく、記事中の()の部分は完全に読者をミスリードさせる誤報である。
ところで、これはマスコミのせいだとも思われるが、一般的に、「被告」という呼び方は、もうそのように呼ばれる者は「クロ」であり、「犯罪者確定」という印象を持っている人が多いように思われる。
しかし、刑の確定は、検察官による立証と弁護人による反証を経て、判決がなされ、14日間の控訴提起期間を経過し(刑事訴訟法373条)、出された判決により有罪が確定することによって、はじめて「クロ」になるのである。
菅谷氏は再審請求事件の対象となっている以上、最新のDNA鑑定等によって「シロ」という結果が出されてはいるものの、再審公判によって無罪の言い渡しを受けていない以上、法的には未だに「被告人」なのである。
つまり本来ならば、彼は未だ「シロ」ではなく、「クロ」として扱われなければならないのである。換言すれば、たとえ再審の結果が明らかであったとしても、菅谷氏は「限りなくシロに近いクロ」ということである。
裁判員制度も始まり、司法が身近になった現在、マスコミには正確な法律用語の使用による報道が求められているはずだ。
菅家さんは6月4日に無期懲役の刑が執行停止され、再審開始決定を待たずに釈放された。異例のケースだが、再審で無罪判決が出るまで「被告」の立場が続く。
「今は自由ですよ。でも半分被告、半分自由。(刑務所から)出てますから、被告人と言われてもピンとこない。裁判では『菅家さん』と言ってもらいたい。『菅家氏』でもいい」と話す。弁護団も提出した上申書の中で「(被告と呼ぶのは)起訴状朗読の際以外には認めない。事件の呼び上げなどの際にもくれぐれも注意されたい」と求めている。
10月に入り、足利事件に関する供述が含まれる取り調べ録音テープを聞いた。検事に君は人間性がないと迫られ、泣きながら「自白」した。菅家さんは「反省して泣いたんじゃない。悔しかったんです。いくら『やってない』と言っても分かってくれなかった。どうして自分を犯人と決めつけたんだ。自分の立場と検事の立場を逆にすれば絶対、苦しみが分かる」と強い口調で話した。
菅谷氏は被告ではなく、被告「人」なのである。したがって、彼が「被告」と呼ばれることは、マスコミを除き、これまでも、そしてこれからもないはずなのだが。
それでは、「被告」と「被告人」の違いは具体的に何なのかということであるが、簡単に言うと、前者は民事事件または行政事件において訴えられた者の呼称で、後者は刑事事件において訴えられた者の呼称である。
上記の定義にしたがえば、菅谷氏は殺人罪で起訴され、刑事訴訟事件において争ってきたのだから、彼は被告ではなく被告「人」ということになる。だから冒頭で彼が「被告」と呼ばれたことは、これまでもそしてこれからもないはずだと述べたわけである。
刑事事件についてもう少し詳しく申し上げれば、捜査段階では「被疑者」であり、公訴提起(検察官による訴えのこと。)がなされると、訴えの対象という意味で「被告人」と呼称されることになる。
とはいうものの、この両者の間に名称以外の本質的な違いはないとされる。ちなみに、公訴提起されたが、裁判が確定していない者を被告人と呼ぶ。
なので余談だが、この記事には、「弁護団も提出した上申書の中で『(被告と呼ぶのは)起訴状朗読の際以外には認めない。事件の呼び上げなどの際にもくれぐれも注意されたい』と求めている。」とあるが、裁判官が菅谷氏を「被告」などと呼ぶはずもなく、記事中の()の部分は完全に読者をミスリードさせる誤報である。
ところで、これはマスコミのせいだとも思われるが、一般的に、「被告」という呼び方は、もうそのように呼ばれる者は「クロ」であり、「犯罪者確定」という印象を持っている人が多いように思われる。
しかし、刑の確定は、検察官による立証と弁護人による反証を経て、判決がなされ、14日間の控訴提起期間を経過し(刑事訴訟法373条)、出された判決により有罪が確定することによって、はじめて「クロ」になるのである。
菅谷氏は再審請求事件の対象となっている以上、最新のDNA鑑定等によって「シロ」という結果が出されてはいるものの、再審公判によって無罪の言い渡しを受けていない以上、法的には未だに「被告人」なのである。
つまり本来ならば、彼は未だ「シロ」ではなく、「クロ」として扱われなければならないのである。換言すれば、たとえ再審の結果が明らかであったとしても、菅谷氏は「限りなくシロに近いクロ」ということである。
裁判員制度も始まり、司法が身近になった現在、マスコミには正確な法律用語の使用による報道が求められているはずだ。