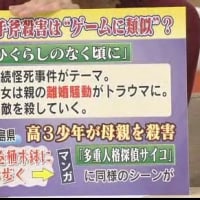児童ポルノ禁止法改正案、今国会成立へ…与党と民主党一致(読売新聞) - goo ニュース
与党と民主党は2日、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の修正協議を行い、修正したうえで今国会で成立させることで一致した。
9日の次回協議にそれぞれが修正案を持ち寄る。与党と民主党はそれぞれ独自の改正案を提出しており、児童ポルノの「単純所持」を禁じる与党案に対し、民主党は買ったり何度も入手したりする行為を処罰する「取得罪」を新設すべきだと主張している。
今回も前回に引き続き、この世紀の悪法とも言っていい改正児童ポルノ法(以下単に「児ポ法」と言う。)について、徹底批判を加えていくことにする。
まず、しばしば規制推進派は「国際社会の動向」をその理由に挙げているが、国連における「子供の売買、子供売買春および子供ポルノグラフィーに関する子供の権利条約の選択議定書」および「サイバー犯罪条約」いずれにおいても、児童ポルノの単純所持の罰則化を義務付けていない。
そして、社民党の保坂展人氏のブログによれば、児童ポルノサイトの国別利用者数は
【2004年】
①アメリカ 32.71%
②ドイツ 5.72%
③ロシア 3.93%
④日本3.59%
⑤フランス 2.52%
⑥イタリア 2.25%
⑦オランダ 1.94%
⑧スイス 1.57%
⑨ポーランド 1.55%
⑩イギリス 1.54%
【2007年】
①アメリカ 22.82%
②ドイツ 14.57%
③ロシア 8.39%
④イギリス 7.02%
⑤イタリア 6.14%
⑥フランス 3.56%⑦カナダ 3.16%
⑧スウェーデン 2.94%⑨スペイン 2.05%
⑩日本 1.74%
であり、3年間で日本の利用者数が半減していることが分かる。しかも興味深いことに、児童ポルノの単純所持を規制しているドイツとイギリスの利用者数が倍増している。つまり、その国で児童ポルノの単純所持を禁止したところでその国での児童ポルノの散布はなくなったとしても、児童ポルノの被写体になったりするといった被害自体は無くなっていないことが分かる。
そして、自民の葉梨議員は全く理解できていない(理解しようともしていない、と言ったほうが正確か?)が、「児童ポルノ」という、定義が極めて曖昧なものを、麻薬や覚醒剤等と同じく、単純所持で犯罪とすることの弊害は図り知れないものがある。
麻薬や覚醒剤であれば、それが客観的にみて何であるのかは分かるものだが、児童ポルノをこれらと同じく単純所持で処罰しようとする場合、それの定義は非常に主観的な要素が入ってしまうため、警察による恣意的な捜査、摘発を可能にする。そもそも法というものは、権力の乱用や暴走を防ぐための道具であるにもかかわらず、これでは法が法としての役目を全く果たせていないどころか、法が権力の暴走の手助けをしてしまっていることになる。
人間の生活における自由を非常に重んじたF.A.ハイエクは著書『隷属への道』の中で、法の支配とは権力の制限にこそあり、そして法の支配とは立法権の範囲を制限することを意味すると言う。
そして法の支配は、「立法を形式法として知られる種類の一般的なルールに限定するものであり、特定の人々を直接の目標とした立法や、そういう差別のために誰かに国家の強制権力を使用できるようにさせるのではなく、むしろ逆に、国家の強制権力は、法によって事前に明らかにされている場合のみ使用可能とされる」のである。
つまり、法の支配とは、そこで暮らす人々が、自分がどのような行為をすればそれが法に抵触するのか明確にされていなければならない。すなわち法は、他者(ここでは国家権力)がどのような行動をするのか正確に予測させるものでなければならない。
したがって、非常に主観的で曖昧な定義しかできない「児童ポルノ」を、単純所持で処罰するということは、公権力に無制限の権力を付与することに等しく、国家権力の濫用であることは明確であり、決して許されない。よって葉梨議員の「顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される 」などという妄言は全くもって論外であり、彼は一から法学を勉強し直したほうがいい。
次に、規制推進派は現行の児ポ法では規制が弱いと言うが、果たしてその主張は本当なのか、検討してみたい。
マンガのわいせつ性について争われた「松文館事件」で主任弁護士を担当した山口貴士氏によれば、現行の児ポ法では、物理的な手段、電気通信回線を通じた「提供」、「提供を目的とする所持、保管等」はすべて刑事罰の対象となっており、ここで言う「提供」とは、「相手方において利用し得べき状態に置く一切の行為」を意味するという。
そして、児童ポルノの販売、譲渡、インターネット上への児童ポルノのデータのアップロード、メール等で児童ポルノのデータを送信すること等は全て処罰の対象になる。提供を目的とする所持、保管も処罰の対象となる以上、第三者に譲渡または送信する目的、あるいは、アップデートする目的で児童ポルノまたは児童ポルノのデータを収めた媒体を所持すること、インターネット上のサーバー等に児童ポルノのデータを保管することも全て処罰の対象になっている(文藝春秋『日本の論点2009』448頁)。
続いて、葉梨議員やアグネス・チャンの日本ユニセフ協会が主張するような、「顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される 」と言う、この無茶苦茶な主張を論駁しておく。
児ポ法に言う「児童」とは18歳未満の者を言うが、もし彼らの言うようなことがまかり通るならば、たとえば21歳の女優が高校を舞台としたドラマで制服を着て登場する場合、もしその女優の見た目が幼く(童顔であって)、18歳未満に「見えた」ならば、児ポ法の対象となって摘発されてしまうが、年齢相応の顔つきであれば摘発されないというのは、不可解を通り越して、法の支配を根底から覆す事態が生じかねない。
しかし、これは容姿による差別であることは言うまでもない。更に、「見た目による年齢確認」という判断は、主観という人によって異なる基準を法解釈に入れることになり、先にも指摘した警察権力による恣意的な捜査を許し、国家権力の暴走を許すことになるので断じて許されない。そもそも、このような法律は憲法違反である。
最後に、これは前回の上田知事の件でも触れたが、内心の自由は絶対に保障されなければならない。こんなことを言うのは、規制推進派はまるで、内心において児童に対する性的な欲望までも否定するような物言いが目立つからである(特にアグネス)。
人は、内心においては自由は絶対に保障される。これは法治国家における大前提となる原則である。たとえば、職場の憎い上司を包丁でメッタ刺しにして殺すことを「内心において」考えても、それは行為に移されない限り、決して処罰してはならない(処罰「できない」のではなく、「してはならない」ということに注意)。
同じく、児童に対して性的な願望を抱いたとしても、それだけでは犯罪になってはならない。内心における自由が絶対に保障されなければ、国家によるそれこそ無制限な国民生活への介入を許してしまうことになるからだ。したがって、そのような願望が「道徳的」には非難に値するとしても、「法的」には処罰の対象にはならない(道徳と法の区別)。
いずれにせよ、政府・与党案の改正児ポ法は表現の自由を侵害するだけでなく、ひろく国民生活そのものにも危害をもたらすものであるという認識を、われわれはもっと共有するべきではないか。
与党と民主党は2日、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の修正協議を行い、修正したうえで今国会で成立させることで一致した。
9日の次回協議にそれぞれが修正案を持ち寄る。与党と民主党はそれぞれ独自の改正案を提出しており、児童ポルノの「単純所持」を禁じる与党案に対し、民主党は買ったり何度も入手したりする行為を処罰する「取得罪」を新設すべきだと主張している。
今回も前回に引き続き、この世紀の悪法とも言っていい改正児童ポルノ法(以下単に「児ポ法」と言う。)について、徹底批判を加えていくことにする。
まず、しばしば規制推進派は「国際社会の動向」をその理由に挙げているが、国連における「子供の売買、子供売買春および子供ポルノグラフィーに関する子供の権利条約の選択議定書」および「サイバー犯罪条約」いずれにおいても、児童ポルノの単純所持の罰則化を義務付けていない。
そして、社民党の保坂展人氏のブログによれば、児童ポルノサイトの国別利用者数は
【2004年】
①アメリカ 32.71%
②ドイツ 5.72%
③ロシア 3.93%
④日本3.59%
⑤フランス 2.52%
⑥イタリア 2.25%
⑦オランダ 1.94%
⑧スイス 1.57%
⑨ポーランド 1.55%
⑩イギリス 1.54%
【2007年】
①アメリカ 22.82%
②ドイツ 14.57%
③ロシア 8.39%
④イギリス 7.02%
⑤イタリア 6.14%
⑥フランス 3.56%⑦カナダ 3.16%
⑧スウェーデン 2.94%⑨スペイン 2.05%
⑩日本 1.74%
であり、3年間で日本の利用者数が半減していることが分かる。しかも興味深いことに、児童ポルノの単純所持を規制しているドイツとイギリスの利用者数が倍増している。つまり、その国で児童ポルノの単純所持を禁止したところでその国での児童ポルノの散布はなくなったとしても、児童ポルノの被写体になったりするといった被害自体は無くなっていないことが分かる。
そして、自民の葉梨議員は全く理解できていない(理解しようともしていない、と言ったほうが正確か?)が、「児童ポルノ」という、定義が極めて曖昧なものを、麻薬や覚醒剤等と同じく、単純所持で犯罪とすることの弊害は図り知れないものがある。
麻薬や覚醒剤であれば、それが客観的にみて何であるのかは分かるものだが、児童ポルノをこれらと同じく単純所持で処罰しようとする場合、それの定義は非常に主観的な要素が入ってしまうため、警察による恣意的な捜査、摘発を可能にする。そもそも法というものは、権力の乱用や暴走を防ぐための道具であるにもかかわらず、これでは法が法としての役目を全く果たせていないどころか、法が権力の暴走の手助けをしてしまっていることになる。
人間の生活における自由を非常に重んじたF.A.ハイエクは著書『隷属への道』の中で、法の支配とは権力の制限にこそあり、そして法の支配とは立法権の範囲を制限することを意味すると言う。
そして法の支配は、「立法を形式法として知られる種類の一般的なルールに限定するものであり、特定の人々を直接の目標とした立法や、そういう差別のために誰かに国家の強制権力を使用できるようにさせるのではなく、むしろ逆に、国家の強制権力は、法によって事前に明らかにされている場合のみ使用可能とされる」のである。
つまり、法の支配とは、そこで暮らす人々が、自分がどのような行為をすればそれが法に抵触するのか明確にされていなければならない。すなわち法は、他者(ここでは国家権力)がどのような行動をするのか正確に予測させるものでなければならない。
したがって、非常に主観的で曖昧な定義しかできない「児童ポルノ」を、単純所持で処罰するということは、公権力に無制限の権力を付与することに等しく、国家権力の濫用であることは明確であり、決して許されない。よって葉梨議員の「顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される 」などという妄言は全くもって論外であり、彼は一から法学を勉強し直したほうがいい。
次に、規制推進派は現行の児ポ法では規制が弱いと言うが、果たしてその主張は本当なのか、検討してみたい。
マンガのわいせつ性について争われた「松文館事件」で主任弁護士を担当した山口貴士氏によれば、現行の児ポ法では、物理的な手段、電気通信回線を通じた「提供」、「提供を目的とする所持、保管等」はすべて刑事罰の対象となっており、ここで言う「提供」とは、「相手方において利用し得べき状態に置く一切の行為」を意味するという。
そして、児童ポルノの販売、譲渡、インターネット上への児童ポルノのデータのアップロード、メール等で児童ポルノのデータを送信すること等は全て処罰の対象になる。提供を目的とする所持、保管も処罰の対象となる以上、第三者に譲渡または送信する目的、あるいは、アップデートする目的で児童ポルノまたは児童ポルノのデータを収めた媒体を所持すること、インターネット上のサーバー等に児童ポルノのデータを保管することも全て処罰の対象になっている(文藝春秋『日本の論点2009』448頁)。
続いて、葉梨議員やアグネス・チャンの日本ユニセフ協会が主張するような、「顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される 」と言う、この無茶苦茶な主張を論駁しておく。
児ポ法に言う「児童」とは18歳未満の者を言うが、もし彼らの言うようなことがまかり通るならば、たとえば21歳の女優が高校を舞台としたドラマで制服を着て登場する場合、もしその女優の見た目が幼く(童顔であって)、18歳未満に「見えた」ならば、児ポ法の対象となって摘発されてしまうが、年齢相応の顔つきであれば摘発されないというのは、不可解を通り越して、法の支配を根底から覆す事態が生じかねない。
しかし、これは容姿による差別であることは言うまでもない。更に、「見た目による年齢確認」という判断は、主観という人によって異なる基準を法解釈に入れることになり、先にも指摘した警察権力による恣意的な捜査を許し、国家権力の暴走を許すことになるので断じて許されない。そもそも、このような法律は憲法違反である。
最後に、これは前回の上田知事の件でも触れたが、内心の自由は絶対に保障されなければならない。こんなことを言うのは、規制推進派はまるで、内心において児童に対する性的な欲望までも否定するような物言いが目立つからである(特にアグネス)。
人は、内心においては自由は絶対に保障される。これは法治国家における大前提となる原則である。たとえば、職場の憎い上司を包丁でメッタ刺しにして殺すことを「内心において」考えても、それは行為に移されない限り、決して処罰してはならない(処罰「できない」のではなく、「してはならない」ということに注意)。
同じく、児童に対して性的な願望を抱いたとしても、それだけでは犯罪になってはならない。内心における自由が絶対に保障されなければ、国家によるそれこそ無制限な国民生活への介入を許してしまうことになるからだ。したがって、そのような願望が「道徳的」には非難に値するとしても、「法的」には処罰の対象にはならない(道徳と法の区別)。
いずれにせよ、政府・与党案の改正児ポ法は表現の自由を侵害するだけでなく、ひろく国民生活そのものにも危害をもたらすものであるという認識を、われわれはもっと共有するべきではないか。