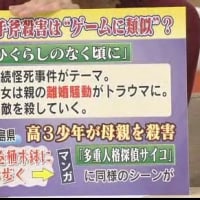都の性描写規制案、総務委で可決 15日成立へ(共同通信) - goo ニュース
過激な性行為を描いた漫画やアニメの販売などを規制する東京都の青少年健全育成条例の改正案について、都議会総務委員会が13日午後、開かれた。民主、共産など3会派が意見を述べた後に、賛成多数で可決した。改正案は15日の本会議で採決され、成立する。出版業界は「作者が萎縮、創作活動に悪影響がある」「表現の自由の侵害」と強く反対している。
一見すると妥当なように見えるこの条例だが、看過できない問題点を孕んでいる。その問題点について徹底批判を試みることにする。
まず、その問題点は都条例の文言に現れている。すなわち、「刑罰法規に触れる性交等」を「不当に賛美・誇張するよう描写した漫画」というものを、客観的に定義できるのか。そしてそもそも、それを一体誰が判断するのか(できるのか)ということである。
何をもって「刑罰法規に触れる」のか。これはおそらく「チャタレイ夫人の恋人事件」判決の言う、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」のことを指しているのだろうが、これも少し考えてみると、非常に曖昧な定義である。
(なお、9日の総務委員会において、共産党の吉田信夫都議が創作物の中で「刑罰法規に反する」か否かをどのように判断するのかをただしても、都側は明確に答えられなかったという。)
この「刑罰法規に触れる」という基準も、「その具体的判断には、時代による変遷がある」(松宮孝明『刑法各論講義』)。したがって、何をもって「刑罰法規に触れる」のかを判断するのは、「一応の基準」は立てられたとしても、非常に困難なのである。しかしながら、そうした一応の基準をもって処罰ができるというのは、後述するように、表現の自由を考慮すれば危険極まりないことは言うまでもない。
したがって、「不当に賛美・誇張するよう描写」したなどという定義は論外である。一体、何を基準に、誰が、どのように、それを判断するのか?石原か?(笑)
ちなみに、いかなる漫画なりアニメが「青少年にとって有害か」つまり悪書なのかという基準も、昔と今とでは全く異なっている。今では考えられないだろうが、あの手塚治虫の「鉄腕アトム」も、当時は悪書として攻撃されていたのだ。
これも余談だが、そもそも創作物には、それがテレビドラマにせよ映画にせよ、そして漫画やアニメにせよ、加害者も加害者も実在していない以上、こうしたものを何故規制する必要があるのか、私には全く分からない。
よく言われる、「そうしたものに触発されて犯罪を犯す者が出る危険性がある」との指摘があるが、その因果関係、つまり、そうしたものを見たことによって犯罪に走る、というこの原因と結果の関係について、客観的かつ科学的な立証はできるのか。
この点について河合幹雄教授によれば、「刺激的な出版物や映像が、性犯罪を増やすという効果は検証できていないどころか、減少させるのではという研究結果さえある」(「世界」1月号)のだという。
このように考えていくと、それではいかなる規制が望ましいのか、という議論につながっていく。もっと言えば、「法の支配」とはどのようなことを言うのか、ということになる。ここで参考になるのが、F.A.ハイエクの考え方である。
ハイエクは著書『隷属への道』の中で、「法の支配」について述べている。それによると、「法の支配」とは、「しかじかの状況において政府当局がどのような形で強制権力を発動するか、ということがはっきりと予測でき、個人はそれをもとにそれぞれの活動を計画できるようなルールが存在している」ということである。
つまり、「法の支配」とはゲームのルールのようなもので、事前にゲームに参加する者は、何をしたら反則(刑罰)になるのか予測できる状態で、そのルールの範囲内ならば、「個人は自由にその目的や欲望を追求することができ、政府権力(ここでは「行政」と置き換えたほうがしっくりくるだろうか。)が意図的にその活動を妨げるようなことはない、と確信できる」(ハイエク)ものでなればならない。
よって、国家の活動は、確固としたルールによってなされなければならない。そして、国家が自分の価値を人々に押し付けるとき、すなわち、「法律を制定する時点で特定の結果がすでにわかっているような場合、法律はただちに人々に使用される道具であることをやめ、立法者が人々に彼の目的を押しつける道具になってしまう」(ハイエク)のである。
以上のハイエクの見解に立つならば、今回の改正案は上記の「法の支配」の要件を全くもって満たしていないのであるから、当然論外である。こうしたハイエクの理解にしたがえば、改正案によって「表現活動が委縮してしまう」と漫画家らが強く反対している理由も理解できるだろう。
なぜならば、ルール(条例)が曖昧で恣意的に運用される危険性を除去できていない以上、漫画家=ゲームのプレイヤーからすれば、「何を書いたらルール(条例)に反するのか分からない」のだから、明らかにルールに反しないような表現へとシフトしていき、それは結局は表現の自由を委縮させ、侵害しているに等しい結果を招くからだ(それに、作家としては作品が売れないと生活できないのだから、こうならざるを得ない)。
こうした規制がまかり通れば、社会は規制だらけで自由を謳歌できなくなってしまう。「法の支配」に反するかかる条例は速やかに廃案にされなければならない。
過激な性行為を描いた漫画やアニメの販売などを規制する東京都の青少年健全育成条例の改正案について、都議会総務委員会が13日午後、開かれた。民主、共産など3会派が意見を述べた後に、賛成多数で可決した。改正案は15日の本会議で採決され、成立する。出版業界は「作者が萎縮、創作活動に悪影響がある」「表現の自由の侵害」と強く反対している。
一見すると妥当なように見えるこの条例だが、看過できない問題点を孕んでいる。その問題点について徹底批判を試みることにする。
まず、その問題点は都条例の文言に現れている。すなわち、「刑罰法規に触れる性交等」を「不当に賛美・誇張するよう描写した漫画」というものを、客観的に定義できるのか。そしてそもそも、それを一体誰が判断するのか(できるのか)ということである。
何をもって「刑罰法規に触れる」のか。これはおそらく「チャタレイ夫人の恋人事件」判決の言う、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」のことを指しているのだろうが、これも少し考えてみると、非常に曖昧な定義である。
(なお、9日の総務委員会において、共産党の吉田信夫都議が創作物の中で「刑罰法規に反する」か否かをどのように判断するのかをただしても、都側は明確に答えられなかったという。)
この「刑罰法規に触れる」という基準も、「その具体的判断には、時代による変遷がある」(松宮孝明『刑法各論講義』)。したがって、何をもって「刑罰法規に触れる」のかを判断するのは、「一応の基準」は立てられたとしても、非常に困難なのである。しかしながら、そうした一応の基準をもって処罰ができるというのは、後述するように、表現の自由を考慮すれば危険極まりないことは言うまでもない。
したがって、「不当に賛美・誇張するよう描写」したなどという定義は論外である。一体、何を基準に、誰が、どのように、それを判断するのか?石原か?(笑)
ちなみに、いかなる漫画なりアニメが「青少年にとって有害か」つまり悪書なのかという基準も、昔と今とでは全く異なっている。今では考えられないだろうが、あの手塚治虫の「鉄腕アトム」も、当時は悪書として攻撃されていたのだ。
これも余談だが、そもそも創作物には、それがテレビドラマにせよ映画にせよ、そして漫画やアニメにせよ、加害者も加害者も実在していない以上、こうしたものを何故規制する必要があるのか、私には全く分からない。
よく言われる、「そうしたものに触発されて犯罪を犯す者が出る危険性がある」との指摘があるが、その因果関係、つまり、そうしたものを見たことによって犯罪に走る、というこの原因と結果の関係について、客観的かつ科学的な立証はできるのか。
この点について河合幹雄教授によれば、「刺激的な出版物や映像が、性犯罪を増やすという効果は検証できていないどころか、減少させるのではという研究結果さえある」(「世界」1月号)のだという。
このように考えていくと、それではいかなる規制が望ましいのか、という議論につながっていく。もっと言えば、「法の支配」とはどのようなことを言うのか、ということになる。ここで参考になるのが、F.A.ハイエクの考え方である。
ハイエクは著書『隷属への道』の中で、「法の支配」について述べている。それによると、「法の支配」とは、「しかじかの状況において政府当局がどのような形で強制権力を発動するか、ということがはっきりと予測でき、個人はそれをもとにそれぞれの活動を計画できるようなルールが存在している」ということである。
つまり、「法の支配」とはゲームのルールのようなもので、事前にゲームに参加する者は、何をしたら反則(刑罰)になるのか予測できる状態で、そのルールの範囲内ならば、「個人は自由にその目的や欲望を追求することができ、政府権力(ここでは「行政」と置き換えたほうがしっくりくるだろうか。)が意図的にその活動を妨げるようなことはない、と確信できる」(ハイエク)ものでなればならない。
よって、国家の活動は、確固としたルールによってなされなければならない。そして、国家が自分の価値を人々に押し付けるとき、すなわち、「法律を制定する時点で特定の結果がすでにわかっているような場合、法律はただちに人々に使用される道具であることをやめ、立法者が人々に彼の目的を押しつける道具になってしまう」(ハイエク)のである。
以上のハイエクの見解に立つならば、今回の改正案は上記の「法の支配」の要件を全くもって満たしていないのであるから、当然論外である。こうしたハイエクの理解にしたがえば、改正案によって「表現活動が委縮してしまう」と漫画家らが強く反対している理由も理解できるだろう。
なぜならば、ルール(条例)が曖昧で恣意的に運用される危険性を除去できていない以上、漫画家=ゲームのプレイヤーからすれば、「何を書いたらルール(条例)に反するのか分からない」のだから、明らかにルールに反しないような表現へとシフトしていき、それは結局は表現の自由を委縮させ、侵害しているに等しい結果を招くからだ(それに、作家としては作品が売れないと生活できないのだから、こうならざるを得ない)。
こうした規制がまかり通れば、社会は規制だらけで自由を謳歌できなくなってしまう。「法の支配」に反するかかる条例は速やかに廃案にされなければならない。