鎖国政策により、キリスト教を禁止した江戸時代。徳川幕府は、キリスト教を危険思想と決め、根絶やしにしようと血眼だった。
隠れキリシタンの詮議は厳しく、信仰を捨てない者たちへの残忍な拷問は絶えなかった。
日本に残っていた神父たちもことごとく極刑に憂き目にあった。
それをキリスト教にとっての受難とみる視点は間違いではないし、現代においてはなおさら、他人によって信仰の妨げを受けることはあってはならない。
しかし当時。幕府の立場で思い返せば、それは当然だった。
このときでさえすでに昔ばなしになろうとしている戦国時代に、石山本願寺をはじめとした宗教勢力の、信仰心をバックボーンに命を懸けた抵抗力はすさまじかった過去を、幕府は忘れてはいない。
ようやく戦のない世の中になったと思っていたところに、それを思い出させる出来事がちかくの天草で起きてもいた。
その鎮圧にどれほどの労力をかけねばいけなかったか、あらためて肝を冷やした幕府なのだ。
なれば、厳格な身分制度の根幹を揺らがせかねない思想を放置するほど、生ぬるい施政者なわけがなかったのだ。
僕にとっては江戸初期の宗教事情をこう考えるように、この話、世間が非情の物語ととらえる視点とは、僕の見方は少々違っていた。
いや、違うというよりは、視線が真逆だといってもいい。
さて本筋。ほとんどのポルトガル人宣教師が処刑か、転ぶ(棄教)かした頃。
かつての師・フェレイラの安否を確かめに、日本に潜入した二人のパードレ(神父)、ロドリゴとガルペ。
彼等はその生死の確認よりも、フェレイラが転んだと伝わる噂の真相の確認こそが、行動の動機であったように思える。
あれほど厳格であった宗教者が、よもや転ぶことなどあるまい、と。
言い換えれば、そんな事実があったとすれば、それはまるで自己存在の否定にもとれたのであろう。
しかし、日本潜入の企ては、どうみても無謀でしかなかった。いずれ捕まるのは眼に見えていた。
そして、自分たちが潜伏することがもたらす災いを知らはずはなかった。
二人の行動は所詮、すでに十分火の廻ってしまった建物に、まだ残っている一人を助けに突入する消防士のようだった。
高潔な志のようでいて、かえって二次災害がもたらす面倒を顧みないお節介とでも言える。
ロドリゴを捕らえた奉行・井上筑後守が、ロドリゴにたいして、<醜女の深情け>だという。強制的な情愛の押し売りだと。
うまく言い当てたものだと思った。良かれと思う行動も、相手にとって無駄に波風を立てる話でしかない。
まるで、「最低でも県外」と沖縄県人に向かって放言した馬鹿と同じだ。おかげで、彼らは叶えられない希望を持たされた。
やはり教会は、キリスト教が禁教となった時点で先を見据え静かに身を引くべきだった。
しかし、そう簡単にはいとはいえないあちらの事情もあった。
小説には描かれていないが、実際の布教活動は純粋な宗教活動なのではなくて、貿易の利権、優位性をオランダや他国に出し抜かれたくない裏事情があったのだから。
そう考えればロドリゴたちは、純心な信心を組織に利用された善人ともいえよう。
そう、左の連中にうまく踊らされて戦争法案反対なんて間違ったデモの先頭に立った石田純一と同じだ。有害極まりない、「無能な善人」なのだ。
じゃあ、トモギ村の百姓たちがあれだけ酷い目に遭っているのをみすみす見逃すのか、と憤る人もいるが、それは論点が違っている。
中世ヨーロッパにおいても、現状は似たり寄ったりだ。
むしろ、結果として260年も平安を保った軍事政権徳川幕府は世界に類を見ず、それだけ幕府のテクノクラートたちの政策が的確であった証拠だ。
現在の平等の世の中は、こうした差別の時代を何世代も何世代も経てようやく人間が行きついたわけで、この時代はその過程なのだ。
所詮ロドリゴは、はじめから百姓たちを見くびり、どこか汚らしいものと蔑んでいたのだ。
なのに結局、自分が助けてやろうと下にみていた百姓の方が、人間として強く潔かったわけ。
そんな、じつは弱かった自分を恥じ、辟易し、嫌悪しながらも、言い訳のように「フェレイラよりはましだわ」と旧師を蔑む。
だけどその師にこそ、自分の姿が映しだされているようで、さらなる嫉妬と憎悪の対象でしかない。
そこで人間とはそもそも弱いものなのだと達観できれば気も楽なのだろうが、師を憎むことで自分を少しでもましな立場に置こうと自己弁護をしている。
狡猾でユダのようだと毛嫌いしていたキチジローを見ていても、自分の分身のような幻像がはがれないでいたわけだ。
その後、江戸に送られ、日本名岡田三右衛門と名を変えたロドリゴの死は延宝9年。おそらく70歳近くも生きた人生だった。
どれだけ抜け殻になった残りの人生だったことだろう。意外にも、あれだけ嫌っていたキチジローとも暮らしていた。
まるで彼自身が神に問い続けたように、沈黙し続けた残りの人生だった。
日本という国に、抵抗なく凌辱される乙女のような、自分の意志を捨てた人生だった。
案外さっぱりとした読後感、6★★★★★★
 |
沈黙 (新潮文庫) |
| 遠藤 周作 | |
| 新潮社 |
さて、映画『沈黙‐サイレンス‐』。
スコセッシ監督があるインタビューで言った。
「私が育った場所には、犯罪者が多くいました。その一方で、非常に高潔な宗教者もいたのです。ですからいつも疑問に思っていました。『人間は本来、善なのか、悪なのか。その両方なのか?』と。」
そう、その両方こそがまさに人の世だ。
ロドリゴ役の心の葛藤がよかった。フェレイラに対する態度も、じつにその時々の感情が出ていた。
贅沢なほど日本人俳優を端役で使う豪華さ。映像もよし。二時間半をを越す長さも感じなかった。
だけど、やはりどこか物足りない。
一つには、たとえ井上が元キリシタンであったとしても、あそこまでよその国の言葉をしゃべれるものか?(しかも、米映画という都合上、ポルトガル語じゃなくて英語なのが余計悩ませる)
また、武士はあんなに笑ったりしないということ。特に井上は、原作でも表情がないとなっているくらい、読めないはずなのだ。
(にこやかでいいのは通辞くらいのはずで、それがあとで叱責のシーンで活きるのだが)
ロドリゴの最期も、「心から棄教はしなかった」と言いたいのだろうが、それは「匂わすもの」で、十字架を見せて観客にネタバレしてはいけないと思うのだがどうか。
そここそ監督は”沈黙”し(せめて何かを握っているような拳であるとか)、観客自身をロドリゴの悩んだ自問と同じような心理に誘うほうが、効果的だったのでは。
良作であるも期待ほどでは・・。6★★★★★★
映画『沈黙-サイレンス-』本予告
なお、かつて篠田正浩が監督をつとめた同作『沈黙』もあるが、作品としては、スコセッシ作品の方がよし。










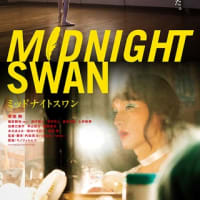

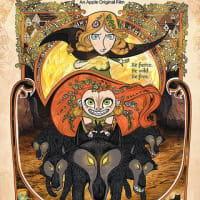





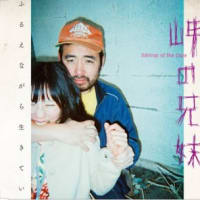
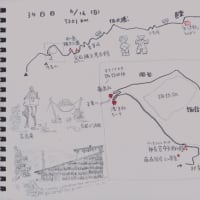
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます