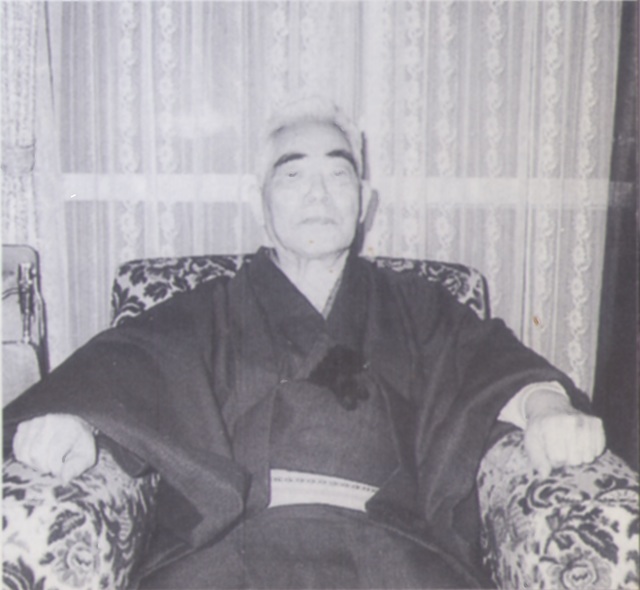トランプ政権が問題視した「消費税還付金が貿易障壁である」との主張は、同政権在任中からすでに繰り返し述べられていた。したがって、昨年の大統領選挙の結果が出た時点で、アメリカが高関税措置を取る可能性は十分に予想できたはずである。それを怠った日本政府は、経済の混乱を招いた責任を負うべきである。
マクロ経済学的に見れば、急激に貿易が落ち込んだ場合、減税によって消費を喚起し、加えて国民への一時金支給などの政府支出によって需要を下支えする以外に有効な手段はない。
さて、消費税が10%であることは広く常識とされているが、現在の消費税法では次のように規定されている。
『……
第二十九条 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
……』
すなわち、法律上「10%」という記述はなく、税率は国税部分として7.8%(軽減対象は6.24%)と定められ、地方消費税を加えて10%(軽減税率は8%)とされている。これは、消費税法単体ではなく、地方消費税法と合わせて成立する仕組みである。
税率の実際の構成は以下の通りである:
区分 | 国税率 | 地方税率(28.2%) | 合計 |
通常税率対象 | 7.8% | 7.8% × 0.282 = 2.2% | 10.0% |
軽減税率対象 | 6.24% | 6.24% × 0.282 = 1.76% | 8.0% |
では、7.8%という国税部分の税率はどのように決まったのか。
それは、平成28年3月29日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)」の附則」によって、平成31年(令和元年)10月1日から、消費税法第29条の税率を次のように引き上げる旨が定められたからである。
『……
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第29条
消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
第29条
消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
……』
このように、消費税率は条文に明記されてはいるものの、税率の引き上げ・引き下げを附則で変更可能とする立法技術が採られており、本則を頻繁に改正する必要がない構造となっている。
この方法は両刃の剣である。税率を引き上げる際には便利である反面、引き下げる場合にも同様に対応が可能であり、附則を改正するだけで済む。要するに、附則部分の審議だけで済む制度であるとも言える。
ところがこれまで、自由民主党税制調査会の宮沢洋一氏や、立憲民主党の野田佳彦氏などが、消費税の減税は技術的に困難であると繰り返し述べてきた。しかし、実際には消費税法附則を改正することで対応可能であり、国会において所定の議決を経ればすぐにでも実施できる。本当にやる気があるなら、減税は不可能ではなく、むしろ制度的にはすぐにでも可能な施策なのである。
以上(寄稿:近藤雄三)
【参考】
・(2025年02月16日)『トランプ大統領の相互関税。日本の場合は「消費税還付金」が問題となる。 自動車課税25%の可能性も!?』
・(2024年11月08日)『もしトラ⇒確トラ⇒新大統領へ(2024年2月15日、7月19に続き3度目の再録)』
・(2023年10月21日)『多額の消費税還元を受けているにもかかわらず、さらに、増額を求める経団連の狂気』
・(2023年10月15日)『消費税という名前の亡国政策、34年前に導入し順調に嵩上げして19%にまで持っていきたい反日亡国奴がいる不思議!』
・(2023年10月14日)『防衛三文書による防衛予算と消費増税のカラクリ -日本経済が活力を失ったわけ-』