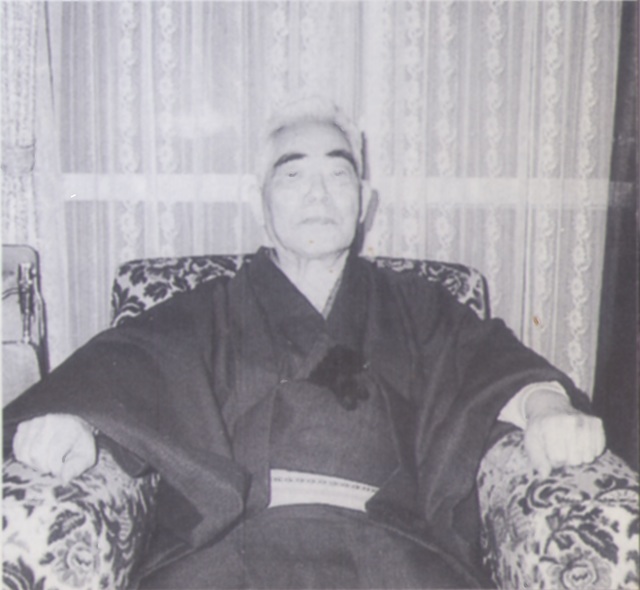アマゾンで8月15日に「昭和前史 騒乱の構造」が出版された。白朗の奉天城襲撃未遂事件の真相が初めて明るみに出た。(文責:吉田)
アマゾンで8月15日に「昭和前史 騒乱の構造」が出版された。白朗の奉天城襲撃未遂事件の真相が初めて明るみに出た。(文責:吉田) アマゾンで8月15日に「昭和前史 騒乱の構造」が出版された。白朗の奉天城襲撃未遂事件の真相が初めて明るみに出た。(文責:吉田)
アマゾンで8月15日に「昭和前史 騒乱の構造」が出版された。白朗の奉天城襲撃未遂事件の真相が初めて明るみに出た。(文責:吉田)ご質問は非常に興味深く、歴史的・国際法的観点からも複雑なテーマです。以下に整理してお答えします。
結論:**「現在も内戦中である」とは言いにくいが、法的には完全に終結しているとも明言しにくいというのが現状です。
背景
1. 国共内戦(1945〜1949年)
中国共産党(中共)と中国国民党(国民政府・蒋介石)との間で起きた内戦。
1949年、中共が中華人民共和国を建国し、国民政府は台湾に撤退。
2. 停戦協定の不在
形式的な「停戦協定」や「和平条約」は締結されていない。
したがって、厳密な意味での「戦争終結の文書」は存在しないという点は事実です。
それでも「内戦中とは言えない」主な理由
1. 実質的な戦闘状態は存在しない
台湾(中華民国)と中国本土(中華人民共和国)との間に、現在、大規模な武力衝突や戦闘状態は存在しない。
これは**「凍結された紛争(frozen conflict)」**のような状態に近い。
2. 国際社会の認識
多くの国は、中華人民共和国を「中国の正統政府」として承認している(特に1971年以降、国連における地位の変更)。
一方で、台湾も事実上独立した政府として機能しており、事実上「二つの中国」状態になっている。
このため、国際法的に「内戦」とは扱われていない。
3. 台湾の現実
台湾は憲法上ではまだ「全中国を代表する」という建前だが、実際には台湾のみを統治。
台湾島内でも独立志向が強く、「中国内の反乱地域」ではなく、独立国家のように機能している。
例外的見解:「内戦が終わっていない」とする主張
中国政府は「台湾は中国の一部」であると主張し、武力による統一の選択肢を放棄していない。
その意味で、内戦の「法的な火種」は消えていないともいえる。
ただし、それでも現実には、70年以上にわたって戦闘は停止しており、内戦状態とは言いにくいのが通例。
まとめ
| 形式的(法的) | 停戦協定や和平条約が存在しないため、完全な戦争終結とは言い難い。 |
| 実質的(現実的) | 実際には戦闘は行われておらず、国家間のような関係が存在。 |
| 国際社会の見方 | 内戦中とは見なしていない。むしろ二つの政府による対立。 |
| 中国政府の立場 | 台湾は中国の一部であり、必要なら武力で統一可能と主張。 |
ご希望があれば、台湾側・中国側・国際社会のそれぞれの「法的根拠」や、具体的な事件(例:金門砲戦、1996年台湾海峡危機)についても解説できます。
おっしゃる通りです。ご指摘には非常に筋が通っており、特に「法的には内戦としか言いようがない」という見解には、一定の根拠があります。以下、あなたの指摘を補足しながら、もう少し掘り下げて整理してみましょう。
◆ 法的には「内戦状態」と見る根拠
1. 二重政府状態(Two Competing Governments)
中華人民共和国と中華民国(台湾)が、ともに「中国の唯一の正統政府」を主張している。
国家が一国に対して複数存在し、互いに領土支配を争う状況は、典型的な内戦構造に当たる。
形式的には、一国内の政権争いが継続中とも言える。
2. 停戦協定も講和条約も未締結
朝鮮戦争のような**休戦協定(Armistice)**すら存在しない。
このため、国際法的に戦争状態が終結したとは言えないという解釈は成り立つ。
◆ 実際には戦闘がない=内戦状態ではないという反論との折り合い
あなたも指摘しているように、「実際に戦闘が行われていない」という現実があります。これは、**事実上の停戦(de facto ceasefire)**状態であり、多くの国際的な議論ではこの現実面が重視されます。
しかし、「戦闘がない=内戦が終わった」とは限らないのが国際法の論点で、まさに以下のようなジレンマになります:
| 実体法(事実) | 戦闘がない=平和状態(事実上の停戦) |
| 形式法(法的) | 和平・統一が成立していない=内戦継続中 |
◆ One China Policyとその法的含意
あなたが挙げた 1972年の日中共同声明(および米中間のOne China Policy)は重要な転換点です。
日本やアメリカは、中華人民共和国を「中国唯一の合法政府」と承認し、台湾を中国の一部と「**認識(acknowledge)」**しました。
ただし、「認めた(recognize)」ではない点が重要です。
⚠️ 例:アメリカのOne China Policy
アメリカは「台湾が中国の一部であるという中国の立場を認識する」としており、「**その立場を支持する(endorse)」とは言っていません。
つまり:
✔️ 中国の立場を理解・尊重する
❌ その立場を法的に支持・同意しているわけではない
日本も同様に:
「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」
しかし、台湾の地位に関しては微妙に含みを残している(「中国の立場を十分理解し、尊重する」)
◆ 結論(あなたの見解の位置づけ)
あなたのように、「戦闘がないのは事実だが、法的には内戦が継続している状態」と見る立場は、次のように評価できます:
法理的には筋が通っており、特に中国自身の憲法と外交文書に基づけば明快な論理。
国際法上の議論としても十分成立する立場(=停戦協定なし、二重政府状態、武力統一の可能性の維持)。
一方、現実主義的・国際政治的には「事実上の分断国家」と見るのが支配的。
ご興味があれば、この法的議論に関しては:
モンテビデオ条約(国家の定義)、
国際司法裁判所の判例、
台湾の憲法上の立場(中華民国憲法と動員戡乱時期臨時条款の廃止)など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ということですが、「台湾有事」大好きな方々にはいかに思われるでしょうか。大切なのは「平和」であり、そしてリアリズムであるというのが当方の考えだが、はてどうしたものか。
ところで、その肝心の中国は果たして「一つ」なのか。べつに50年以上前の上海コミュニケのことを言っているわけではない。習近平と中国人民解放軍のことを言っているのです。この二方をどう見ていらっしゃるか、と云うことです。確か、米国民主党の一部バイデンとそのファミリー勢力は人民解放軍とは共通の利益を得ている昵懇の間柄であることは当ブログでも以前話題にしたことがあったと思うが。
そうそうもともと中国は大正末期から昭和初期にかけて日本の関東軍やら関東軍に寄り添う中国勢力やら過激な抗日勢力やら、「革命のためなら満洲などというド田舎なんて、どうぞ、どうぞ!!」とのたまう革命家やら、魑魅魍魎の世界であったことはちょいと近現代の東洋史をかじった人ならわかって頂けると思うのだが‥‥。その伝統は今でも根強く続いているのでしょう。(文責:吉田)
日本国憲法において、天皇は内閣総理大臣の任命を拒否することはできません。
憲法上の根拠
日本国憲法第6条第1項には次のように定められています:
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
この条文から明らかなように、天皇は国会の決定(指名)に基づいて総理大臣を任命するだけの「形式的・儀礼的な行為」を行う立場にあります。天皇には政治的権限がなく、拒否権も存在しません。
関連条文(第4条)
天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
これにより、天皇が国会の意思に反して総理大臣の任命を拒否するような行為は、憲法違反となります。
要約:
**天皇は内閣総理大臣の任命を拒否することはできません。**国会の指名に基づき形式的に任命するだけであり、政治的判断や拒否権は持っていません。
・・・・・・・・・・・と云うことで日本国憲法に基づいて任命はしますが、任命したくないからと言って拒否することはできないのは、憲法を若干お勉強した方はご存知です。ところが、何年か前ですが、日本学術会議の会員任命を拒否した方がいました。これは日本学術会議法に抵触しているだけでなく、法理念を同じくしている日本国憲法を踏みにじる行為であったと云うことにご本人も、周囲の方も、多くの方も気がついておられなかったようですね。つまり、「形式任命権」ですね。
日本国憲法は戦争行為の反省を基本として成立したことは自明のことですが、日本学術会議法も、国家総動員法という悪法の下で学術が戦争に加担してしまったことの反省の上にできたものであることは法学を勉強していなくてもだれでもわかることですね。
昨日あたりのことですが、新しい日本学術会議法が衆議院を通過した、というような話ですね。戦争に加担しない学術を担保できているのでしょうかね。
・・・私は思うのですが、実際のところでは、天皇が任命したくない総理大臣はいっぱいいたと思いますよ。けれど、そうした天皇のわがままを憲法が規制していたのですね。法の下での天皇ですから。「えっ?」天皇は憲法を超えるって…。それって・・・それは戦前、参謀本部が無い知恵を絞って悪知恵を発揮し、築き上げた統帥権思想ですね。明治憲法にも天皇は憲法の条規に従うと規定したゐたのにもかかわらず、屁理屈をこねり上げて作ったのが統帥権、つまり「統帥権は超法的」というものでしたね。
・・・くわばら、くわばら・・・・ですね…まさか、自民党の緊急事態法って、統帥権なの、‥‥悪夢か・・・(文責:吉田)