連日、都内に行くことが重なり忙しくなってきた。今日もまた出掛けるつもりである。皆様も連日ご多忙中にも関わらず、このブログをお読みいただき言葉には言い表わせなれない喜びと同時に、感激の極みでもあります。なんとお礼を言っていいのか、お礼の言葉も浮かびません。浮かびませんので書きません。けれども、このブログをいつもパソコン画面で見ていただいている皆様お一人おひとりのために、書き込んでいるガチョウとアヒルの力であります。
たいへん失礼をいたしました。本当にいつもありがとうございます。お読みいただき感謝申しあげます。少しでも有意義に読んでいただければ幸いです。
さて、昨日はある大きな連絡会に行ってきました。
厚生労働省老健局振興課の遠藤征也課長補佐(介護支援専門官)の90分の講演のためである。19ページにも及ぶ資料もいただけ、制度改正の方向性や介護支援専門員に求められるものが内容である。この時期、内容的には一般的であろう。しかし、厚生労働省の考えや個人的見解も聞くことが出来たので満足している。また少しモチベーションも上がったかもしれない。
講演前半は、今までの振り返りや数値分析や推移などを話されていた。やはり平成18年4月の改正がたくさんのデータに異変をもたらしていることが理解できるし、冬の時代の突入も感じさせる。私も平成14年頃から冬の風を感じていた。やはり都道府県レベルの実地指導である。適切に行われている指導もたくさんあるが、不適切指導も目に付くようになった。保険者においても同じであるが、権限強化や委譲によってその差は激しいものがある。適切なものも多数あるけれども、不適切なものも保険者・事業者双方に目立つから極まりない。
厚生労働省として、都道府県の実地指導や保険者の判断に不満を持たれているようであった。「馬鹿な保険者が多くて困っている。」 「馬鹿な保険者も利用していかないと、制度がいい方向に進まない。「保険者にいろいろ教えてあげて欲しい、提案して欲しい」と。
当然、これらを額面通りに受け取れない。なんせ、この国は中央銀行総裁がいない国である。日銀総裁も村上ファンドに出資しても、同義的責任も取らない。福田高齢者も何でもかんでも他人事である。福井高齢者も「歴史的にも異例で残念」と述べたが、それこそ責任も取らず、辞任しない中央銀行総裁は、歴史的にも異例で残念である。福田高齢者も地方分権も分からず、痴呆ぶんけんである。福田高齢者の本当の余命はいつまでか?
話がそれてしまったが、課長補佐の保険者に呆れている発言から、会場内の雰囲気も変わった。
半値八掛け二割引のリップサービスとしても、本音が込められていた。
厚生労働省としても、ローカルルールについては好意的ではないようだ。それもスタンダードから良くすることはOKであるが、悪くするルールの方である。平成19年12月20日の厚生労働省老健局振興課の事務連絡も引き合いに出していた。
給付判断においても、介護支援専門員が専門的見地から行われるようにしたいらしく、
川崎市のケアプラン点検マニュアルを推奨していた。褒めていたように受けとめた。
これは、適切に課題分析をして、それに基づいて導かれたニーズや利用者の希望を両極的に捉えたケアプランであることは言うまでも無い。(私は課題分析力の是非は無しとする)そうは言っても資質の低くて法令を知らない介護支援専門員もいることは事実である。
このような場合、わたし個人的には地域のケアマネ連絡会や地域包括支援センターで助言したり、モニターすることが必要であるかもしれない。
また「都道府県のくだらない指導が行われている」「保険者の馬鹿な判断がある」ということも知っており、「全国会長会議でも再三指導しており、局の指導力不足で現場が混乱している」とも。更には「馬鹿な指導が行われると、短時間に伝播してしまう怖さがある」とも。結構、少しのため息交じりで、真剣に話されていて、とにかく画一的・形式的に判断することを嫌っていた。感動的に思えた発言では、「政省令や運営基準や法をそのまま解釈することではない」ということ。そこから判断して、画一的・形式的・事務的に判断して返還させる指導を望んでいないというところであった。事案も例示して、デイサービスのミニハイクなど、利用者にとっていいことがあるじゃないかと。いまだに、これを認めない保険者もあると嘆いていた。あえて理解として、極端であるが文章1枚で判断して欲しくないということ。制度の大極的見地というかマクロのソーシャルケースワークなんだろう。当然、最低限のというか普通の基準を満たしていることが前提であって、介護支援専門員には、これを進める上で本当に多大な責任を負うことになる。これを忘れてはならない。
また、その他であるが、今後の生活援助の在り方(時間概念無し・内容制限・身体介護のプラスアルファ)や特殊寝台の付属品の購入への移行、居宅介護支援業務の(線引きガイドライン・混合報酬・加算減算の見直し・精神的独立中立性)、自己負担割合(2割3割)や消費税問題の話も聞くことが出来ました。
とにかく有意義な話を聞くことが出来たと思っているし、地域の活動方法を教えていただいた気がする。手前味噌ではあるが、私に出来ることもたくさんあるかも知れないので、連携を密にして、特区じゃないけれど、なんちゃって特区みたいな高福祉活動を展開できるかもしれない。
ちなみに講演の演題が、平成20年2月23日に北海道介護支援専門員協会主催の北海道ケアマネージャー研究交流会と一字一句一緒でしたので、この時期はこの内容でどこでも話されていると思われる。全国で蔓延している不適切な指導が改善されることを切に願うところである。皆さんも是非とも地域のケアマネ連絡会などで改善に向けての活躍をしていただければ、私にとっても書き込み甲斐があるところです。
課長補佐と年齢的にもさほど変わりない。介護支援専門官と介護支援専門員とでは一文字しか変わらないのに、講演を聞いていて仕事のスケールの違い、国民に対しての責任の大きさ、日本の高齢者を思う気持ちが、やはり、とっても優れていると思いました。私の方が。・・・・・・・・・・笑笑笑
たいへん失礼をいたしました。本当にいつもありがとうございます。お読みいただき感謝申しあげます。少しでも有意義に読んでいただければ幸いです。
さて、昨日はある大きな連絡会に行ってきました。
厚生労働省老健局振興課の遠藤征也課長補佐(介護支援専門官)の90分の講演のためである。19ページにも及ぶ資料もいただけ、制度改正の方向性や介護支援専門員に求められるものが内容である。この時期、内容的には一般的であろう。しかし、厚生労働省の考えや個人的見解も聞くことが出来たので満足している。また少しモチベーションも上がったかもしれない。
講演前半は、今までの振り返りや数値分析や推移などを話されていた。やはり平成18年4月の改正がたくさんのデータに異変をもたらしていることが理解できるし、冬の時代の突入も感じさせる。私も平成14年頃から冬の風を感じていた。やはり都道府県レベルの実地指導である。適切に行われている指導もたくさんあるが、不適切指導も目に付くようになった。保険者においても同じであるが、権限強化や委譲によってその差は激しいものがある。適切なものも多数あるけれども、不適切なものも保険者・事業者双方に目立つから極まりない。
厚生労働省として、都道府県の実地指導や保険者の判断に不満を持たれているようであった。「馬鹿な保険者が多くて困っている。」 「馬鹿な保険者も利用していかないと、制度がいい方向に進まない。「保険者にいろいろ教えてあげて欲しい、提案して欲しい」と。
当然、これらを額面通りに受け取れない。なんせ、この国は中央銀行総裁がいない国である。日銀総裁も村上ファンドに出資しても、同義的責任も取らない。福田高齢者も何でもかんでも他人事である。福井高齢者も「歴史的にも異例で残念」と述べたが、それこそ責任も取らず、辞任しない中央銀行総裁は、歴史的にも異例で残念である。福田高齢者も地方分権も分からず、痴呆ぶんけんである。福田高齢者の本当の余命はいつまでか?
話がそれてしまったが、課長補佐の保険者に呆れている発言から、会場内の雰囲気も変わった。
半値八掛け二割引のリップサービスとしても、本音が込められていた。
厚生労働省としても、ローカルルールについては好意的ではないようだ。それもスタンダードから良くすることはOKであるが、悪くするルールの方である。平成19年12月20日の厚生労働省老健局振興課の事務連絡も引き合いに出していた。
給付判断においても、介護支援専門員が専門的見地から行われるようにしたいらしく、
川崎市のケアプラン点検マニュアルを推奨していた。褒めていたように受けとめた。
これは、適切に課題分析をして、それに基づいて導かれたニーズや利用者の希望を両極的に捉えたケアプランであることは言うまでも無い。(私は課題分析力の是非は無しとする)そうは言っても資質の低くて法令を知らない介護支援専門員もいることは事実である。
このような場合、わたし個人的には地域のケアマネ連絡会や地域包括支援センターで助言したり、モニターすることが必要であるかもしれない。
また「都道府県のくだらない指導が行われている」「保険者の馬鹿な判断がある」ということも知っており、「全国会長会議でも再三指導しており、局の指導力不足で現場が混乱している」とも。更には「馬鹿な指導が行われると、短時間に伝播してしまう怖さがある」とも。結構、少しのため息交じりで、真剣に話されていて、とにかく画一的・形式的に判断することを嫌っていた。感動的に思えた発言では、「政省令や運営基準や法をそのまま解釈することではない」ということ。そこから判断して、画一的・形式的・事務的に判断して返還させる指導を望んでいないというところであった。事案も例示して、デイサービスのミニハイクなど、利用者にとっていいことがあるじゃないかと。いまだに、これを認めない保険者もあると嘆いていた。あえて理解として、極端であるが文章1枚で判断して欲しくないということ。制度の大極的見地というかマクロのソーシャルケースワークなんだろう。当然、最低限のというか普通の基準を満たしていることが前提であって、介護支援専門員には、これを進める上で本当に多大な責任を負うことになる。これを忘れてはならない。
また、その他であるが、今後の生活援助の在り方(時間概念無し・内容制限・身体介護のプラスアルファ)や特殊寝台の付属品の購入への移行、居宅介護支援業務の(線引きガイドライン・混合報酬・加算減算の見直し・精神的独立中立性)、自己負担割合(2割3割)や消費税問題の話も聞くことが出来ました。
とにかく有意義な話を聞くことが出来たと思っているし、地域の活動方法を教えていただいた気がする。手前味噌ではあるが、私に出来ることもたくさんあるかも知れないので、連携を密にして、特区じゃないけれど、なんちゃって特区みたいな高福祉活動を展開できるかもしれない。
ちなみに講演の演題が、平成20年2月23日に北海道介護支援専門員協会主催の北海道ケアマネージャー研究交流会と一字一句一緒でしたので、この時期はこの内容でどこでも話されていると思われる。全国で蔓延している不適切な指導が改善されることを切に願うところである。皆さんも是非とも地域のケアマネ連絡会などで改善に向けての活躍をしていただければ、私にとっても書き込み甲斐があるところです。
課長補佐と年齢的にもさほど変わりない。介護支援専門官と介護支援専門員とでは一文字しか変わらないのに、講演を聞いていて仕事のスケールの違い、国民に対しての責任の大きさ、日本の高齢者を思う気持ちが、やはり、とっても優れていると思いました。私の方が。・・・・・・・・・・笑笑笑

















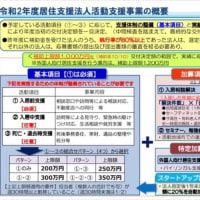


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます