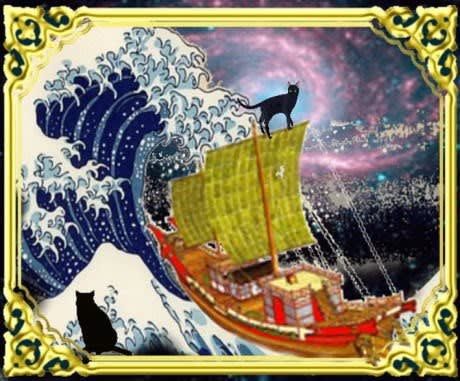蝦夷(カイ・えぞ・えみし)・・・ヱミシ・・・
・・・turned a whiter shade of pale・・・?
↓↑
黄昏=たそがれ=誰彼=だれかれ・・・?
↓↑ ↓↑
2016年6月(63歳)辛亥偏財~
2026年6月(73歳)庚戌正財~
↓↑ ↓↑
┏癸巳(戊庚丙)偏官・正財帝旺⇔庚子正財 2020
┗戊午(丙 丁)傷官・劫財建禄⇔丙戌劫財 10
丁酉(庚 辛) ・正財長生⇔辛卯偏財 15
丙午(丙 丁)劫財・劫財建禄⇔甲午印綬 12
辰巳空亡
星宿
↓↑
名=夕+口・・・「夕暮れ・黄昏=たそがれ=誰彼」には、視覚が鈍り
呼び名で「誰彼(だれかれ)」を確認する必要がある
↓↑
苗字=みょうじ=名字・・・命名・令名・指名・称名・唱名
↓↑ 姓名・氏名・家名・大名・戒名・人名
実名・虚名・有名・無名・代名
襲名・芳名・悪名・売名・高名
渾名・綽名・仇名・俗名・属名
別名・異名・題名・著名・汚名
改名・仮名・偽名・匿名・浮名
御名・法名・声名・古名・月名・星名
醜名(しこな)・四股名・雑名
忌名(諱・いみな)
↓↑ 贈名(諡・おくりな)

妙字・・・・・・奇妙・妙案
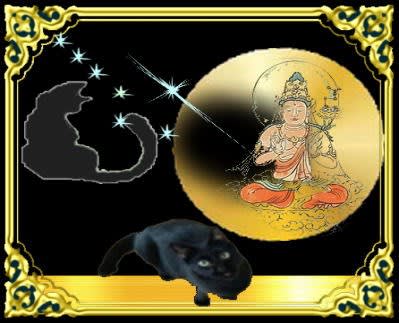
妙見・・・・・・「妙見菩薩」の略・国土を守り貧窮を救う神
こぐま座α星の仏教語
北辰妙見とも呼ばれる
世阿彌の能楽論で
絶妙の芸・この上なくすぐれた芸

妙見信仰・・・・インドに発祥した菩薩信仰が
中国で道教の北極星・北斗七星信仰 と習合し
北斗は天帝を守る剣
仏教の天部の一つとして日本に伝来
習合した
天台宗園城寺(三井寺)では
「吉祥天」と同体と説く・・・?
吉祥院天満宮
吉祥院
菅原清公卿、菅原是善公、伝教大師、孔子
と共に祀られる
「菅原道真」の幼名 吉祥丸
道真の祖父
清公の
遣唐使
霊験譚以降
菅原家は代々
吉祥天信仰になった

道真の正室
「島田宣来子(しまだ の のぶきこ
嘉祥三年(850年)~?」・・・?
嫡男・菅原高視や
「宇多天皇」の女御
「衍子(エンシ)」らを生んだ・・・?
阿衡事件
887年(仁和三年)十一月二十一日
の詔書~888年(仁和4年)十一月
藤原基経
と
宇多天皇
政治紛争
「衍子(エンシ?)or・・・?」
↓↑ ↓↑
衍=行+氵
彳+氵+亍
彳+氵+一+丁
エン
あまる
余分にあまる・余計な
衍字・衍文
延び広がる・押し広げる
衍義・敷衍
↓↑
名のり
「のぶ・ひろ・ひろし・みつ=衍」+子
↓↑
はびこる・あふれる
蔓衍(マンエン)
しく・ひろげる・ひろがる
衍義・敷衍
あまり・余分な
衍字・衍文
類字「羨(セン)」
ひろい・おおきい
平らな土地・平地
洲・なかす
侃=亻+口+川+言
カン
つよい
正しくひたむきで怯(ひる)まないさま
のびのびとやわらぎ楽しむさま
異体字「偘」
侃い(つよい)
侃諤(かんがく)
侃侃諤諤(かんかんがくがく)
相手に遠慮することなく
激しく議論を戦わせる様子
遠慮することなく
自分が思っていることをはっきりと言うこと
↓↑
衍曼流爛(エンマンリュウラン)
衍漫流爛
悪人が多く世の中全体に蔓延ること
衍曼=どこまでも広がる様子
流爛=離れ離れになること
↓↑
鄒衍降霜(スウエンコウソウ)
天に無実を訴え
真夏に霜を降らせたという鄒衍の故事
↓↑
愆=衍+心
=諐=侃+言
侃=亻+口+川+言
ケン
あやま(ち)
あやま(つ)
あやま(る)
あやまちをおかす
度をこす
あやまち・つみ・とが・しくじり
異体字「諐」
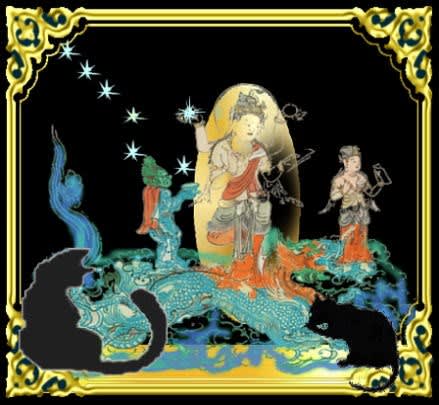
↓↑ ↓↑
妙音・・・・・・美しい声・音楽
・・・妙音菩薩=東方の一切浄光荘厳国に住み
霊鷲山 (りょうじゅせん) に来て
法華経を聴聞した菩薩
美しい声で十方世界に教えを広める
・・・ 弁才天=弁財天=辯才天=辨財天
(梵)Sarasvati=インド神話の河川の
女神
音楽・弁舌・財福・智慧の徳があり
吉祥天とともに信仰され
仏教・ヒンズー教の女神
琵琶 (びわ) を弾く天女の姿
日本で財福の神として
「弁財天」
七福神の一
↓↑
妙音院
藤原師長の院号
足利義視の正室
妙音院一鴎軒=外交僧
小田原征伐の前に
豊臣秀吉の
使節(富田信広・津田信勝)の
1人として派遣
後北条氏に内通し
逮捕・処刑
↓↑
妙音比丘尼
?~?
室町時代の尼僧
信濃(長野県)の人
文明年間(1469~1487)
紀伊(きい)
伊都郡(和歌山県)
慈尊院をおとずれ
洪水の害を予言
弥勒菩薩と堂を
山側の地に移転させた
天文(てんぶん)九年(1540)
紀ノ川の洪水で
旧寺地は川床となった
↓↑
妙音寺
岡山県
吉備中央町
↓↑
妙音寺
広島県
尾道市
↓↑
七宝山
妙音寺
香川県
三豊市
↓↑
妙音寺遺跡
埼玉県
秩父郡
皆野町
大字
下田野
↓↑
妙音寺洞穴遺跡
埼玉県
秩父郡
皆野町
大字
下田野
↓↑
出町
妙音堂
京都市
上京区
青竜町
↓↑
妙音寺
静岡県
静岡市
清水区
村松
↓↑
妙音十二楽
導師の読経する中
松風、村雨、杉登などの曲を
琵琶、太鼓、笛、手拍子、ホラ貝
など8種類の楽器で
演奏する古典音楽
日置市立吹上
鹿児島県
日置市
吹上町
中原
↓↑
妙音寺(妙経殿)
神奈川県
横浜市
南区
三春台
↓↑
妙音寺
東京都
台東区
松が谷
↓↑
医王山
不動院
妙音寺
東京都
江戸川区
一之江
↓↑
安房 高野山
妙音院
千葉県
館山市
上真倉
↓↑
平等山 慈光院
妙音寺
桐生市西久方町
↓↑
妙音沢
埼玉県
新座市
東部
黒目川沿いの雑木林の中
黒目川へと流れる湧き水の支流
大小2つが合わさった沢
↓↑
大須観音
愛知県名古屋市中区大須
・・・名護屋・名古屋・名児耶・那古屋・・・観音・漢字
観音菩薩(Avalokiteśvara)
アヴァローキテーシュヴァラ
=観世音菩薩=観自在菩薩=救世菩薩
チベットで
観音菩薩は「spyan ras gzigs(チェンレジー)」
「観自在」を意味する
「spyan ras gzigs dbang phyug」の省略
『妙法蓮華経』観世音菩薩 普門品 第二十五
(『観音経』)
↓↑
『妙法蓮華経』観世音 菩薩 普門品 第二十五
(『観音経』)
ゾロアスター教で
アフラ・マズダーの娘
「アナーヒター」
「スプンタ・アールマティ」
との関連づけられた女神・・・
ーー↓↑ーー
サラスヴァティー=弁財天
『大日経』で
「妙音天・美音天」
と呼ばれる
ブラフマーの妻
↓↑
肌は白
額には三日月の印
4本の腕
2本の腕には数珠とヴェーダ
もう1組の腕に
ヴィーナ(琵琶に似た弦楽器)
白鳥
孔雀
白い蓮華
の上に座る
白鳥・孔雀はサラスヴァティーの乗り物
↓↑
サラスヴァティー
水辺に描かれ
サンスクリットで
サラスヴァティー=「水(湖)を持つもの」
水と豊穣の女神
聖典『リグ・ヴェーダ』で
初めは
聖なる川、サラスヴァティー川
の化身
流れる川が転じ
流れるもの全て
言葉・弁舌や知識、音楽
などの女神となった
言葉の神=ヴァーチ
と同一視され
サンスクリット
とそれを書き記すための
デーヴァナーガリー文字
を創造した
後に
韻律・讃歌の女神
ガーヤトリー
と同一視された
↓↑
本地垂迹
宗像三女神の一柱
「市杵嶋姫命(いちきしまひめ)」
と同一視
「七福神」の一員
宝船に乗る縁起物
明治初頭の神仏分離以降
宗像三女神
または
市杵嶋姫命
を祭っている
「瀬織津姫」
が弁才天として祀られる例もある
↓↑
神名の「宇賀」
「宇迦之御魂神(うかのみたま)」
に由来
仏教語で「財施=宇迦耶(うがや)」
鸕鶿草葺不合尊
(うがやふきあえずのみこと)
地神五代の五代目
日向三代の三代目
天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(古事記)
彦 波瀲武鸕鶿草葺不合尊(日本書紀)
烏賀陽富貴和えず?
穿っても付記合えず?
↓↑
に由来・・・
人頭蛇身
蜷局(とぐろ)を巻く形
頭部も
老翁や
女性で一様ではない・・・女媧(Nuwa)
人類を創造した女神
姓は風
伏羲と
兄妹&夫婦
↓↑
「宇迦之御魂神」などと同様
穀霊神・福徳神・・・
「蛇神・龍神」の化身・・・
「蛇神」は
比叡山・延暦寺(天台宗)
の教学に取り入れられ
仏教の神(天)である
「弁才天」と習合、合体した
「宇賀弁才天」
↓↑
「竹生島・宝厳寺」
に坐する弁天像
「宇賀神」は
「弁才天」の頭頂部に小さく乗る
「鳥居」も添えられる
↓↑
鎌倉の宇賀福神社
宇賀神として祀っている
↓↑
石川県金沢市
永安寺
毎年9月23日に大祭
↓↑
「宇賀神」という
姓名が日本中に存在する
↓↑
妃 玉依姫(たまよりびめ=玉依毘売命)
海童の娘で
豊玉姫の妹
鸕鶿草葺不合尊の叔母
↓↑
彦五瀬命(ひこいつせ の みこと)
第一子
神武東征で矢にあたって薨じた
↓↑
稲飯命(いない の みこと)
第二子
『日本書紀』第二・第四の一書で
第三子
神武東征の際に
鋤持神となった
三毛入野命(みけいりぬ の みこと
別名
御毛沼命・稚三毛野命)
第三子
『日本書紀』第二の一書で
第二子
第三・第四の一書では第四子
神武東征の際に
常世郷へ行った
↓↑
彦火火出見尊(ひこほほでみ の みこと
別名
狭野命
若御毛沼命
豊御毛沼命)
第四子
『日本書紀』第三の一書では第三子
第四の一書では第二子
『日本書紀』第一書での幼名は
「狭野命」
初代天皇
「神日本磐余彦天皇」
漢風諡号「神武天皇」
↓↑
サンスクリットの
アヴァローキテーシュヴァラ
(Avalokiteśvara)
を
「玄奘」は
「観察された(avalokita )」
と
「自在者(īśvara)」
の合成語と解釈し
「観自在」と訳した
「鳩摩羅什」は
「観世音」とし、
「玄奘」の
「光世音・観世音・観世音自在」
などの漢訳は語訳とした・・・
古いサンスクリットの『法華経』
アヴァローキタスヴァラ
(avalokitasvara)
となっており
「観察された(avalokita)」
+
「音・声(svara)」
と解され
古訳に
『光世音菩薩』の訳語もある・・・
現在発見されている
「写本」に記された名前は
「avalokitasvara」
がもっとも古形・・・
「観音菩薩」は・・・「般若=智慧の象徴」
「大慈大悲」を本誓・・・
代字対比(替比・他意比)を
本章(翻性)・・・?
すべての物事の特性
三相=無常・苦・無我
務定・句・武画(雅・兼・臥)?
を理解する力
大乗仏教では
「空(シューニヤ)=宀(宇宙)
+
八(捌)
+
工(巧)」の理解・・・
空蒼・繰う・倥・・・脳ミソ=認識思惟空間?
・・・turned a whiter shade of pale・・・?
↓↑
黄昏=たそがれ=誰彼=だれかれ・・・?
↓↑ ↓↑
2016年6月(63歳)辛亥偏財~
2026年6月(73歳)庚戌正財~
↓↑ ↓↑
┏癸巳(戊庚丙)偏官・正財帝旺⇔庚子正財 2020
┗戊午(丙 丁)傷官・劫財建禄⇔丙戌劫財 10
丁酉(庚 辛) ・正財長生⇔辛卯偏財 15
丙午(丙 丁)劫財・劫財建禄⇔甲午印綬 12
辰巳空亡
星宿
↓↑
名=夕+口・・・「夕暮れ・黄昏=たそがれ=誰彼」には、視覚が鈍り
呼び名で「誰彼(だれかれ)」を確認する必要がある
↓↑
苗字=みょうじ=名字・・・命名・令名・指名・称名・唱名
↓↑ 姓名・氏名・家名・大名・戒名・人名
実名・虚名・有名・無名・代名
襲名・芳名・悪名・売名・高名
渾名・綽名・仇名・俗名・属名
別名・異名・題名・著名・汚名
改名・仮名・偽名・匿名・浮名
御名・法名・声名・古名・月名・星名
醜名(しこな)・四股名・雑名
忌名(諱・いみな)
↓↑ 贈名(諡・おくりな)

妙字・・・・・・奇妙・妙案
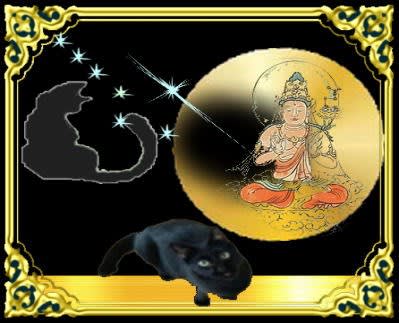
妙見・・・・・・「妙見菩薩」の略・国土を守り貧窮を救う神
こぐま座α星の仏教語
北辰妙見とも呼ばれる
世阿彌の能楽論で
絶妙の芸・この上なくすぐれた芸

妙見信仰・・・・インドに発祥した菩薩信仰が
中国で道教の北極星・北斗七星信仰 と習合し
北斗は天帝を守る剣
仏教の天部の一つとして日本に伝来
習合した
天台宗園城寺(三井寺)では
「吉祥天」と同体と説く・・・?
吉祥院天満宮
吉祥院
菅原清公卿、菅原是善公、伝教大師、孔子
と共に祀られる
「菅原道真」の幼名 吉祥丸
道真の祖父
清公の
遣唐使
霊験譚以降
菅原家は代々
吉祥天信仰になった

道真の正室
「島田宣来子(しまだ の のぶきこ
嘉祥三年(850年)~?」・・・?
嫡男・菅原高視や
「宇多天皇」の女御
「衍子(エンシ)」らを生んだ・・・?
阿衡事件
887年(仁和三年)十一月二十一日
の詔書~888年(仁和4年)十一月
藤原基経
と
宇多天皇
政治紛争
「衍子(エンシ?)or・・・?」
↓↑ ↓↑
衍=行+氵
彳+氵+亍
彳+氵+一+丁
エン
あまる
余分にあまる・余計な
衍字・衍文
延び広がる・押し広げる
衍義・敷衍
↓↑
名のり
「のぶ・ひろ・ひろし・みつ=衍」+子
↓↑
はびこる・あふれる
蔓衍(マンエン)
しく・ひろげる・ひろがる
衍義・敷衍
あまり・余分な
衍字・衍文
類字「羨(セン)」
ひろい・おおきい
平らな土地・平地
洲・なかす
侃=亻+口+川+言
カン
つよい
正しくひたむきで怯(ひる)まないさま
のびのびとやわらぎ楽しむさま
異体字「偘」
侃い(つよい)
侃諤(かんがく)
侃侃諤諤(かんかんがくがく)
相手に遠慮することなく
激しく議論を戦わせる様子
遠慮することなく
自分が思っていることをはっきりと言うこと
↓↑
衍曼流爛(エンマンリュウラン)
衍漫流爛
悪人が多く世の中全体に蔓延ること
衍曼=どこまでも広がる様子
流爛=離れ離れになること
↓↑
鄒衍降霜(スウエンコウソウ)
天に無実を訴え
真夏に霜を降らせたという鄒衍の故事
↓↑
愆=衍+心
=諐=侃+言
侃=亻+口+川+言
ケン
あやま(ち)
あやま(つ)
あやま(る)
あやまちをおかす
度をこす
あやまち・つみ・とが・しくじり
異体字「諐」
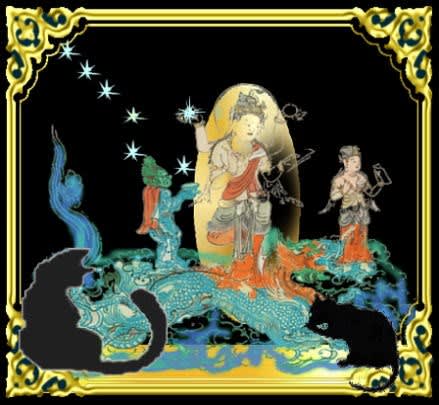
↓↑ ↓↑
妙音・・・・・・美しい声・音楽
・・・妙音菩薩=東方の一切浄光荘厳国に住み
霊鷲山 (りょうじゅせん) に来て
法華経を聴聞した菩薩
美しい声で十方世界に教えを広める
・・・ 弁才天=弁財天=辯才天=辨財天
(梵)Sarasvati=インド神話の河川の
女神
音楽・弁舌・財福・智慧の徳があり
吉祥天とともに信仰され
仏教・ヒンズー教の女神
琵琶 (びわ) を弾く天女の姿
日本で財福の神として
「弁財天」
七福神の一
↓↑
妙音院
藤原師長の院号
足利義視の正室
妙音院一鴎軒=外交僧
小田原征伐の前に
豊臣秀吉の
使節(富田信広・津田信勝)の
1人として派遣
後北条氏に内通し
逮捕・処刑
↓↑
妙音比丘尼
?~?
室町時代の尼僧
信濃(長野県)の人
文明年間(1469~1487)
紀伊(きい)
伊都郡(和歌山県)
慈尊院をおとずれ
洪水の害を予言
弥勒菩薩と堂を
山側の地に移転させた
天文(てんぶん)九年(1540)
紀ノ川の洪水で
旧寺地は川床となった
↓↑
妙音寺
岡山県
吉備中央町
↓↑
妙音寺
広島県
尾道市
↓↑
七宝山
妙音寺
香川県
三豊市
↓↑
妙音寺遺跡
埼玉県
秩父郡
皆野町
大字
下田野
↓↑
妙音寺洞穴遺跡
埼玉県
秩父郡
皆野町
大字
下田野
↓↑
出町
妙音堂
京都市
上京区
青竜町
↓↑
妙音寺
静岡県
静岡市
清水区
村松
↓↑
妙音十二楽
導師の読経する中
松風、村雨、杉登などの曲を
琵琶、太鼓、笛、手拍子、ホラ貝
など8種類の楽器で
演奏する古典音楽
日置市立吹上
鹿児島県
日置市
吹上町
中原
↓↑
妙音寺(妙経殿)
神奈川県
横浜市
南区
三春台
↓↑
妙音寺
東京都
台東区
松が谷
↓↑
医王山
不動院
妙音寺
東京都
江戸川区
一之江
↓↑
安房 高野山
妙音院
千葉県
館山市
上真倉
↓↑
平等山 慈光院
妙音寺
桐生市西久方町
↓↑
妙音沢
埼玉県
新座市
東部
黒目川沿いの雑木林の中
黒目川へと流れる湧き水の支流
大小2つが合わさった沢
↓↑
大須観音
愛知県名古屋市中区大須
・・・名護屋・名古屋・名児耶・那古屋・・・観音・漢字
観音菩薩(Avalokiteśvara)
アヴァローキテーシュヴァラ
=観世音菩薩=観自在菩薩=救世菩薩
チベットで
観音菩薩は「spyan ras gzigs(チェンレジー)」
「観自在」を意味する
「spyan ras gzigs dbang phyug」の省略
『妙法蓮華経』観世音菩薩 普門品 第二十五
(『観音経』)
↓↑
『妙法蓮華経』観世音 菩薩 普門品 第二十五
(『観音経』)
ゾロアスター教で
アフラ・マズダーの娘
「アナーヒター」
「スプンタ・アールマティ」
との関連づけられた女神・・・
ーー↓↑ーー
サラスヴァティー=弁財天
『大日経』で
「妙音天・美音天」
と呼ばれる
ブラフマーの妻
↓↑
肌は白
額には三日月の印
4本の腕
2本の腕には数珠とヴェーダ
もう1組の腕に
ヴィーナ(琵琶に似た弦楽器)
白鳥
孔雀
白い蓮華
の上に座る
白鳥・孔雀はサラスヴァティーの乗り物
↓↑
サラスヴァティー
水辺に描かれ
サンスクリットで
サラスヴァティー=「水(湖)を持つもの」
水と豊穣の女神
聖典『リグ・ヴェーダ』で
初めは
聖なる川、サラスヴァティー川
の化身
流れる川が転じ
流れるもの全て
言葉・弁舌や知識、音楽
などの女神となった
言葉の神=ヴァーチ
と同一視され
サンスクリット
とそれを書き記すための
デーヴァナーガリー文字
を創造した
後に
韻律・讃歌の女神
ガーヤトリー
と同一視された
↓↑
本地垂迹
宗像三女神の一柱
「市杵嶋姫命(いちきしまひめ)」
と同一視
「七福神」の一員
宝船に乗る縁起物
明治初頭の神仏分離以降
宗像三女神
または
市杵嶋姫命
を祭っている
「瀬織津姫」
が弁才天として祀られる例もある
↓↑
神名の「宇賀」
「宇迦之御魂神(うかのみたま)」
に由来
仏教語で「財施=宇迦耶(うがや)」
鸕鶿草葺不合尊
(うがやふきあえずのみこと)
地神五代の五代目
日向三代の三代目
天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(古事記)
彦 波瀲武鸕鶿草葺不合尊(日本書紀)
烏賀陽富貴和えず?
穿っても付記合えず?
↓↑
に由来・・・
人頭蛇身
蜷局(とぐろ)を巻く形
頭部も
老翁や
女性で一様ではない・・・女媧(Nuwa)
人類を創造した女神
姓は風
伏羲と
兄妹&夫婦
↓↑
「宇迦之御魂神」などと同様
穀霊神・福徳神・・・
「蛇神・龍神」の化身・・・
「蛇神」は
比叡山・延暦寺(天台宗)
の教学に取り入れられ
仏教の神(天)である
「弁才天」と習合、合体した
「宇賀弁才天」
↓↑
「竹生島・宝厳寺」
に坐する弁天像
「宇賀神」は
「弁才天」の頭頂部に小さく乗る
「鳥居」も添えられる
↓↑
鎌倉の宇賀福神社
宇賀神として祀っている
↓↑
石川県金沢市
永安寺
毎年9月23日に大祭
↓↑
「宇賀神」という
姓名が日本中に存在する
↓↑
妃 玉依姫(たまよりびめ=玉依毘売命)
海童の娘で
豊玉姫の妹
鸕鶿草葺不合尊の叔母
↓↑
彦五瀬命(ひこいつせ の みこと)
第一子
神武東征で矢にあたって薨じた
↓↑
稲飯命(いない の みこと)
第二子
『日本書紀』第二・第四の一書で
第三子
神武東征の際に
鋤持神となった
三毛入野命(みけいりぬ の みこと
別名
御毛沼命・稚三毛野命)
第三子
『日本書紀』第二の一書で
第二子
第三・第四の一書では第四子
神武東征の際に
常世郷へ行った
↓↑
彦火火出見尊(ひこほほでみ の みこと
別名
狭野命
若御毛沼命
豊御毛沼命)
第四子
『日本書紀』第三の一書では第三子
第四の一書では第二子
『日本書紀』第一書での幼名は
「狭野命」
初代天皇
「神日本磐余彦天皇」
漢風諡号「神武天皇」
↓↑
サンスクリットの
アヴァローキテーシュヴァラ
(Avalokiteśvara)
を
「玄奘」は
「観察された(avalokita )」
と
「自在者(īśvara)」
の合成語と解釈し
「観自在」と訳した
「鳩摩羅什」は
「観世音」とし、
「玄奘」の
「光世音・観世音・観世音自在」
などの漢訳は語訳とした・・・
古いサンスクリットの『法華経』
アヴァローキタスヴァラ
(avalokitasvara)
となっており
「観察された(avalokita)」
+
「音・声(svara)」
と解され
古訳に
『光世音菩薩』の訳語もある・・・
現在発見されている
「写本」に記された名前は
「avalokitasvara」
がもっとも古形・・・
「観音菩薩」は・・・「般若=智慧の象徴」
「大慈大悲」を本誓・・・
代字対比(替比・他意比)を
本章(翻性)・・・?
すべての物事の特性
三相=無常・苦・無我
務定・句・武画(雅・兼・臥)?
を理解する力
大乗仏教では
「空(シューニヤ)=宀(宇宙)
+
八(捌)
+
工(巧)」の理解・・・
空蒼・繰う・倥・・・脳ミソ=認識思惟空間?
「般若=prajnā」
であり借音漢字は
「波若・般羅若
斑若・鉢若・鉢羅枳嬢」
とも書く 枳(からたち・シ・キ)
漢訳は「慧・智慧・明」
枳=木+只
木+口+八
十+八+口+八
シ・・・史・詞?
キ・・・記・紀?
からたち
ミカン科の落葉低木・・・橘(たちばな)
わかれる・枝分かれする
只=口+八
シ
ただ
「ただ・・・のみ」
「ただ・・・だけ」
助字
句中や句末に置いて
語調を整え
訓読では読まない
ただ・無料
↓↑
『摩訶般若波羅蜜経』=『二万五千頌般若経』
「鳩摩羅什」による漢訳
90品
高麗大藏再雕本は27巻
思溪資福藏
普寧藏等は30巻
通常
『大品般若経(大品)』
と呼ばれている
↓↑
「鳩摩羅什」の訳した経の中に
『摩訶般若波羅蜜経』
『八千頌般若経』
の漢訳(408年)で
大品に対し29品(10巻)で
『小品般若経(小品)』
と呼ばれる
↓↑
「ナーガールジュナ(龍樹)」
が著した
『大智度論』は
『大品般若経』に対する注釈書
ーー↓↑ーー
笽(そうけ)
国字
そうけ
竹製の皿
竹を編んで作ったざる
↓↑
笽=竹+皿
笽(そうけ)
お米を研ぐ笊(ざる)
竹で編んだ半円形のかご
↓↑
富山市には昔
笽山(そうけやま)
の地名があった
笽島=そうけじま
富山県婦負郡八尾などにみられる
↓↑
㳑=水+皿
イツ・イチ
あふれる
溢=氵+皿=㳑
一杯になって
もうそれ以上は
収(おさ)まらなくなる
入り切らずに零(こぼ)れ出る
過大な・過ぎる
満ちる・一杯になる
齊国(周代~春秋・戦国代の国)
↓↑ ・・・齊・齋・斉・斎
・・・斎王=皇族の皇女=みこ=巫女
斎王(さいおう)=斎皇女(いつきのみこ)
伊勢神宮、賀茂神社に巫女として
奉仕した未婚の内親王(親王宣下を受けた天皇の皇女)
女王(親王宣下を受けていない天皇の皇女
親王の王女)
内親王=斎内親王
↓↑ 女 王=斎女 王
の量の単位
片手一杯分の量
「孔叢子:小爾雅:量」
「一手之盛 謂之溢两手 謂之掬掬一升也
掬四 謂之豆豆四 謂之區區四謂
之釜釜二有半 謂之藪藪二有半
謂之𦈢二𦈢 謂之鍾二鍾
謂之秉秉十六斛也」
(2溢=1掬=1升
4掬=1豆
4豆=1區
4區=1釜)
↓↑
㿽=兮+皿
ケイ・ゲ
八一𠃌丂兮皿=㿽
小さな盆・口が開き底が平らな容器
↓↑
諡=言+㿽
シ・ジ
おくりな
言八一𠃌丂兮皿㿽=諡
おくりな
生前の功績や徳行を称え死者に贈る名
同「謚」
↓↑
Whiter Shade
『A Whiter Shade of Pale』
↓↑
turned a whiter shade of pale
白く儚(はかな)い影へと変わっていた
はかない=墓内・葉和(懸・掛)名意・墓無い
↓↑
turned a whiter shade of pale
白く儚い影へと変わっていた
↓↑
「but・although・even though・however」
ーーーーー
・・・???・・・
であり借音漢字は
「波若・般羅若
斑若・鉢若・鉢羅枳嬢」
とも書く 枳(からたち・シ・キ)
漢訳は「慧・智慧・明」
枳=木+只
木+口+八
十+八+口+八
シ・・・史・詞?
キ・・・記・紀?
からたち
ミカン科の落葉低木・・・橘(たちばな)
わかれる・枝分かれする
只=口+八
シ
ただ
「ただ・・・のみ」
「ただ・・・だけ」
助字
句中や句末に置いて
語調を整え
訓読では読まない
ただ・無料
↓↑
『摩訶般若波羅蜜経』=『二万五千頌般若経』
「鳩摩羅什」による漢訳
90品
高麗大藏再雕本は27巻
思溪資福藏
普寧藏等は30巻
通常
『大品般若経(大品)』
と呼ばれている
↓↑
「鳩摩羅什」の訳した経の中に
『摩訶般若波羅蜜経』
『八千頌般若経』
の漢訳(408年)で
大品に対し29品(10巻)で
『小品般若経(小品)』
と呼ばれる
↓↑
「ナーガールジュナ(龍樹)」
が著した
『大智度論』は
『大品般若経』に対する注釈書
ーー↓↑ーー
笽(そうけ)
国字
そうけ
竹製の皿
竹を編んで作ったざる
↓↑
笽=竹+皿
笽(そうけ)
お米を研ぐ笊(ざる)
竹で編んだ半円形のかご
↓↑
富山市には昔
笽山(そうけやま)
の地名があった
笽島=そうけじま
富山県婦負郡八尾などにみられる
↓↑
㳑=水+皿
イツ・イチ
あふれる
溢=氵+皿=㳑
一杯になって
もうそれ以上は
収(おさ)まらなくなる
入り切らずに零(こぼ)れ出る
過大な・過ぎる
満ちる・一杯になる
齊国(周代~春秋・戦国代の国)
↓↑ ・・・齊・齋・斉・斎
・・・斎王=皇族の皇女=みこ=巫女
斎王(さいおう)=斎皇女(いつきのみこ)
伊勢神宮、賀茂神社に巫女として
奉仕した未婚の内親王(親王宣下を受けた天皇の皇女)
女王(親王宣下を受けていない天皇の皇女
親王の王女)
内親王=斎内親王
↓↑ 女 王=斎女 王
の量の単位
片手一杯分の量
「孔叢子:小爾雅:量」
「一手之盛 謂之溢两手 謂之掬掬一升也
掬四 謂之豆豆四 謂之區區四謂
之釜釜二有半 謂之藪藪二有半
謂之𦈢二𦈢 謂之鍾二鍾
謂之秉秉十六斛也」
(2溢=1掬=1升
4掬=1豆
4豆=1區
4區=1釜)
↓↑
㿽=兮+皿
ケイ・ゲ
八一𠃌丂兮皿=㿽
小さな盆・口が開き底が平らな容器
↓↑
諡=言+㿽
シ・ジ
おくりな
言八一𠃌丂兮皿㿽=諡
おくりな
生前の功績や徳行を称え死者に贈る名
同「謚」
↓↑
Whiter Shade
『A Whiter Shade of Pale』
↓↑
turned a whiter shade of pale
白く儚(はかな)い影へと変わっていた
はかない=墓内・葉和(懸・掛)名意・墓無い
↓↑
turned a whiter shade of pale
白く儚い影へと変わっていた
↓↑
「but・although・even though・however」
ーーーーー
・・・???・・・