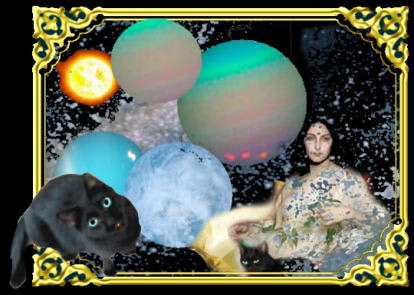ニワの椿(?)と八重桜と梨の花が満開・・・多分「ユキバタツバキ(雪端椿)」?・・・or・・・「ヤブツバキ(藪椿)」?・・・or、「山茶花(sasanqua)」・・・
ピンクの「八重咲き」なんだけれど
ピンクの「八重咲き」なんだけれど
検索で調べたが「正体」がワカラナイ・・・
「山茶花(さざんか)」に似ているが、咲く季節が違う・・・

庭の花は
「一本の幹の背丈が1m前後で、枝分かれが3本、花が3輪」
「獅子咲きのツバキ」
・・・「弁化が進み、不規則な大小、多くの花弁に
雄しべが混じって
花全体が盛りあがって見えるもの」
「千重咲き = 雄しべが総て花弁に変わり
整った多数の花弁が
鱗状に重なりあったもの」
ではなく
「八重咲き」・・・実は「獅子咲き=八重咲き」らしい
「花びらは五弁」
「花蘂(はなしべ)が一本」
・・・躑躅(つつじ)に似ているけれど・・・チガウ
「葉もギザギザ(鋸歯)」ではない
↓↑
「葉は楕円形で、互い違いに生える(互生)
葉の先は尖り・・・鋸歯は無い
・・・山茶花にはギザギザ(鋸歯)があるらしい・・・
葉の質は革質で艶があり
表面は濃い緑色をしている」・・・

↓↑
「椿三十郎」のツバキは・・・
赤、白で
木の背丈が塀の高さの三メートル前後・・・
白黒の映画だったが・・・
↓↑
椿(つばき・チン・チュン)・・・ツバキ(海柘榴)
センダン科の落葉樹・チャンチン
伝説中の長寿の大木
椿寿・椿葉・大椿
木の名
思いがけないこと
↓↑
珍しい霊木、「椿の木」があった
その椿の木に花が咲くことは
極めて珍しく
ある時に花が咲いた
思いがけない出来事だった(荘子)
↓↑
珍事中夭(チンジチュウヨウ)=「義経記」
闖事(チンジ)に同じ
馬が突然門から出てくること
闖入(チンニュウ)
↓↑
樁の字
樁=木+舂
木+𡗗+臼
木+三+人+臼
木+一+一+一+人+臼
=十+八+一+一+一+人+臼
ショウ・トウ
撞(つ)く・・・穀物を臼で撞く
大きなくい・木製のくい
杵(きね)
事柄を数える語
異体字「桩=木+庄」
𡗗=奉=ブ・ホウ・たてまつる・うける・ささげる
𡗗
異体字「俸・𠬻・捧・𢱵・捀・摓・𢩱・𢪋」
↓↑
荘子の「逍遥遊」
大木、大椿(ダイチン)が由来
この木は
八千年を春とし
八千年を秋とし
三万二千年が
人間の一年に当たる・・・
長寿で目出鯛木で
滅多に花を咲かすことがないので
花が咲くと
「椿事=非常に珍しいこと=珍事」
という・・・
↓↑
「秦」=中国の王朝・国名
はた。シン
応神天皇のとき
機織りを伝えて渡来した
帰化系民族の子孫にあたえられた名
先秦(センシン)・大秦(タイシン)
禾+舂(ショウ・うすづく
𡗗は秦の省略形)
𡗗=大+二
三+人
夫+一
↓↑
「椿事・椿説」
「椿説弓張月(ちんせつ ゆみはりづき)」
曲亭馬琴作・葛飾北斎画の読本
文化四年(1807年)~文化八年(1811年)刊行・全五篇

↓↑
「椿 椿山(つばき ちんざん)
享和元年六月四日(1801年7月14日)
~
嘉永七年七月十三日(1854年8月6日)
文人画家
江戸
小石川天神生まれ
花鳥画、人物画を得意とした
名は弼(たすく)・・・井伊直弼の「弼」・桜田門外で殺害
↓↑ 弼=㢶+弓
弓+百+弓・・・東西から百済を攻める
弓+一+白+弓
・・・弓=キュウ=九・球・宮・救
百(済)=一(初)新羅(白・曰)?
「志木⇔志楽木⇔新羅⇔白子(しらこ)」?
たすける・たすけ・ヒツ
補佐する
ゆだめ・弓の形を整える道具
弓を両側から締め付けて、ひずみを正す
↓↑ 四等官(シトウカン)・弾正台の第二位
字は篤甫(とくほ)
通称を忠太・亮太
号は椿山・琢華堂・休庵・四休庵・春松軒
碧蔭山房・羅渓・琢華道人
十七歳頃
同門の
渡辺崋山・・・ 三河国田原藩(愛知県田原市東部)
↓↑ 家老
著書
『慎機論』『初稿西洋事情書』
『再稿西洋事情書』『外国事情書』
『鴃舌或問』『鴃舌小記』など
天保十年(1839年)五月
蛮社の獄
鳥居耀蔵による幕府の
言論弾圧事件
高野長英、小関三英、渡辺崋山
ら「尚歯会」メンバーが
モリソン号事件、鎖国政策を批判し
↓↑ 弾圧された
を慕い・・・
崋山塾に入門
崋山を終生の師とした」
↓↑
𠁥・𠓛・𠓝・𠓞・・人が𠆢に入る・・「和同開珎」の発行?
𠁥=羊の角の象形
「讀みて𦮃の若くす(説文)」
「𠁥は部首・𦮃、芇を収める」
「𠁥を意符として持つ会意字に𥄕、雈」
などがある
異体字「𦫳(正字通)」
「方言で拐と同用・カイ・カ」
↓↑
鎮魂歌
↓↑
金+眞
↓↑
土+真
土+十+具
土+十+目+一+八
↓↑
精衛=伝説上の小鳥
填海=海を埋めること
皇帝炎帝の娘、女娃は東海で溺れ死んだ
女娃は小鳥(精衛)に化身
自身の死んだ東海を
小石や小枝などで埋めようとし
失敗に終わった
↓↑
月(肉)+关
月(肉)+丷+天
月(肉)+ᅭ+大・・・ᅭ
月(肉)+丷+一+大
↓↑
笑の初文
关=ショウ=丷+天=八+天
繁体字「關=門+幺+幺+丱」
異体字「笑・関」
↓↑
王+㐱
王+人+彡
↓↑
島津久光の四男
母は千百子・・・千百(千の桃)の子?
最後の薩摩藩主
島津茂久(忠義)の同母弟
名(諱)は紀寛→忠鑑→珍彦
通称は敬四郎→又次郎→周防→常陸→備後
珍彦(うずびこ・チンゲン⇔珍言・珍諺?)
は
記紀神話の神
椎根津彦の別名
父の
久光が薩摩藩主家へ復帰し
大隅重富
を領有、重富家を相続
忠鑑(ただあき)と名乗った後
珍彦と改名・・・珍諺・陳諺?
↓↑
「銅=金+同」の略字「同」
唐の
「開元通寳」にならって
「寳」の略字の
「珎」にして
「和同開珎」とした
寳=珎=ホウ
↓↑
和銅発掘献上
西暦708年
和銅元年(一月十一日改元)
一月
武蔵国より銅を献上
よって改元
二月
催鋳銭司設置
平城の地に新都造営の詔
五月
銀銭(和同開珎)発行
八月
和同開珎を発行
↓↑
和銅の採掘
武蔵国
秩父郡
に
「自然になれる和銅」
(おのずからになれるにぎあかがね)
都に献上
慶雲五年
改元されて
和銅元年
一月十一日
日下部-宿禰-老(くさかべ・の・すくね・の・おゆ)
津島-朝臣-堅石(つしま・の・あそん・かたしわ)
金-上-无(こんじょうむ)
二月十一日
催鋳銭司設置
多治比-真人-三宅麻呂(たじひ・まひと・みやけまろ)
を任命
鋳銭司は
地方国府に近いところに置き、国府に管理させた
採銅、鋳造などの知識・技術面
和銅献上時
無位の
金上无
が従5位以下に叙せられた
金上无と
津島朝臣堅石
との関係
和銅献上の2年前
慶雲三年十一月三日
文武天皇は
新羅国王に
「大使の従5位以下
美努-連-浄麻呂(みのむらじきよまろ)
の福使として
従六位以下の
津島-連-堅石
(むらじ・後、和銅元年までに朝臣)を遣わす」
という勅書を賜った記事から
遣新羅副使としての在任中に
新羅人の
金上无
と関係・・・
日下部宿禰老
和銅献上時に3人一緒の授位
霊亀三年(717年)四月二十五日
従5位上に叙せられ
養老五年(721年)正月二十三日
皇太子(首皇子・おひと・聖武天皇)
のお付きを命じられ
神亀元年(724年)二月二十二日
従四位以下に叙され
天平四年(732年)三月二十二日
死没
↓↑
多治比真人三宅麻呂
出世したが、最後は失脚し
その後
多治比真人県守
一族七人が
武蔵国司
9世紀後半に
多治比武信
が
武蔵国に配流され
秩父・児玉を押領
後、京より下った
峯時
が武蔵に居住
石田牧(長瀞町岩田)別当を兼ね
丹貫主と号し
丹治氏と称し
子
峯房
以下になって
秩父郡の領主として
武蔵七党の
丹党として活躍・・・
↓↑
金上无・・・金の上(かみ・うえ)の无(ない・ム・ブ)?
叙位を受け
和銅二年十一月二日
伯耆守(ほうきのかみ・鳥取県)
に任ぜられた・・・
↓↑
「多胡碑(たごのヒ)=羊さま」・・・多(おほの)
胡(えびす)
碑(石の卑)
群馬県
多野郡
吉井町
池
字
御門
国の特別史跡
和銅四年(711)建立
↓↑
弁官符上野国片岡郡緑野郡甘
良郡并三郡三百戸郡成給羊
成多胡郡
和銅四年三月九日甲寅
宣左中弁正五位下
多治比真人
太政官二品
穂積親王左太臣正二位
石上尊右太臣正二位
藤原尊
(弁官の符に
上野(かみつけぬ)の国の
片岡の郡(こおり)
緑野(みどの)の郡
甘良(から・甘楽)の郡
并(ならび)に
三郡の内三百戸を郡と成し
羊に給して
多胡郡と成す
↓↑
和銅四年三月九日甲寅の宣
左中弁は
正五位下
多治比の真人
太政官は
二品
穂積(ほずみ)親王
左大臣は
正二位
石上(いそのかみ)の尊(みこと)
右大臣は
正二位
藤原尊(藤原不比等)
↓↑
「羊に給して多胡郡と成す」
の
「羊」・・・日本円の「¥(通貨記号)」
↓↑ ・・・「咩(ビ)」=口+羊
発音(miē・み・ビ・ミーエ)
異体字「哶 ・哶・咪・𠴟・羋」
繁体字「哶・𠴟」
石川県白山市 比咩神社
白山-比咩(ひめ) 神社
阿蘇神社、熊本県阿蘇市にある神社
「阿蘓神社」とも
「健磐竜命神」、「阿蘇比咩神」を祀る
大分県宇佐市
和銅三年(710年)創建
乙-咩(め) 神社・・・乙咩(おとめ・乙女)
↓↑ 羊の鳴き声・the bleating of sheep
は
帰化人の多い地方に新たに郡を建て
その長になった
「羊」=伝説の「羊太夫」・・・
「羊太夫は、奈良まで(和銅を持って)
毎日
天皇の御機嫌伺いに100余里の道を往復
太夫の乗った馬に
小脛(こはぎ)という若者がついて行くと
馬は矢のように走った
ある日、都への途中、
木の下で昼寝をしている小脛の両脇の下に
羽が生えているのを
羊太夫
は見てしまった。
普段から
「私の寝姿は絶対に見ないで下さい」
と言われていたので、好奇心が湧いたのだ
そっと
羊太夫は
小脛の
羽を抜いてしまった
そこからは
今までの速さでは走れなくなり
天皇の怒りをかった
羊太夫は
討伐されてしまった」
↓↑
和銅元年・戊申(708年)
元明天皇
武蔵国秩父郡より
和銅献上
年号を
和銅と改元する(一月十一日)・・・十一日=拾壹似地
催鋳銭司を置く(二月十一日)・・・十一日=足位置丹治
↓↑ ↓ ↑
(四月十一日)・・・十一日=???
(四月十三~十一日)・・・・???
₩=「w+=」=「圓(1953年貨幣改革以前)Won・Wŏn」
↓↑ ↓ ↑
2019年~隣国の通貨(₩)危機だろう・・・
warai=wの省略=ワラに二
W=ダブリュー(double U=U+U)=V+V
w/=with(ウィズ)の省略
w/o=without=~がなくて
↓↑
和同銀銭発行 (五月十一日)・・・十一日=廿市仁智?
近江国に
銅銭鋳造させる(七月二十六日)
和同銅銭発行 (八月十日)
↓↑
和銅二年・己酉(709年)
元明天皇
銀銭私鋳罰則の詔(一月二十五日)
銅銭使用督励命令(三月二十八日)
銀銭廃止
銅銭だけを流通貨幣とする(八月二日)
↓↑
「富本銭が最古の貨幣」?
富の本の銭・・・富=宀+𠮛(𠫔)+田
一+口+口+十
(一+ム)+口+十
冨=冖+𠮛(𠫔)+田
一+口+口+十
(一+ム)+口+十
↓↑
富本銭
江戸時代
寛政十年(1798年)
の古銭カタログといった類の本に
「富本七星銭」の名前で銭の図柄と共に載っていて
それは普通使われるお金ではなく
「まじない銭」
専門的には厭勝銭(ようしょうせん)
↓↑
昭和44年(1969年)
平城京跡から発掘
平成3年(1991年)
更に古い地層の
藤原京跡から発掘
「和同開珎」より
古い貨幣
鋳造されたのは奈良時代
↓↑
平成9年(1997年)
大阪(難波宮)の
細工谷遺跡から
一枚発見
飛鳥池遺跡からの発見
発掘場所や
出土した
富本銭の状態等から
飛鳥で鋳造された
↓↑
富本銭が埋まっていた
地層から出た
木簡や古寺の瓦などの遺物が証拠で
造られた年代も七世紀後半と確認
↓↑
日本書紀に
「今(天武十二年~687年)よりは
銅銭を用いよ」
とある『銅銭』が「富本銭」である・・・
↓↑
唐の「芸文類聚」に
「民を富ませる本は
食(食べるもの)と貨(貨幣)だ」
とあることからとった
「富本と名付けたお金」・・・
ーーーーー
𠫔=一+ム・・・ム=「私」の源字
・・・訓読で「よこしま」・・・
𣅀=亠+日
シ・むね・うまい
「旨・㫖・𣅌・𠤔・𤮻・𠩊・𠮛」
畐=𠮛(一口)+田(囗十)
𠮛の異体字「𠫔・旨・𤮻」
豆=𠮛+ㅛ
一+口+ㅛ
一+口+丷+一
ㅛ=ヨ?
𠮛の異体字=𠫔=一+ム
𣅀=亠+日
シ・むね・うまい
旨㫖𣅌𠤔𤮻𠩊𠮛
亠(音・おと)+日(曰・いわく)=𣅀
むね=意図していること、意向
天子や上位者の指示や命令
その考えや意向
うまい・美味・食べ物がおいしい
「合」=𠆢+𠮛=「會」
𠆢+一+口
「会」=𠆢+𠫔=「會・會の略字」
𠆢+一+ム ・・・遭・遇・逢・・・ミチとの遭遇?
・・・「口」=「ム」・・・「△・▽」
口のモグモグの様子
↓↑
「仝」=同・・・「𠆢=冂」、「工=𠮛」
「𠓛+丄」=「冂+𠮛」
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+サ」、屋号・ヤマサ=味噌醤油
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+ナ」、屋号・ヤマナ=味噌醤油
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+二」、屋号・ヤマニ=回漕・廻船問屋
藍玉・藍色染料
藍の葉を発酵
熟成させた
蒅(すくも)を
固めて乾燥させたもの
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+吉」、屋号・ヤマキチ=材木・海産物
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+川」、屋号・ヤマカワ=
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+炭」、屋号・ヤマズミ=
↓↑
「𠓛・𠓝・𠓞・傘・☂」
𠓛=雧=隹隹隹木=集=隹+木
シュウ
あつまる・あつめる・つどう
異体字「亼・𠓛・𠍱・輯・雦・雧
辑・𨌖・𨍣・𨍾・𨎵」
↓↑
𠓞.=入+二
↓↑
兦・𠓛
內・𠓜・𠓝・𠓞・內
㒰・㒱・𠓟
全・氽・㒲・𠇒・𠓠・𠓡・𠓢・𠓣
↓↑
𠁥・𠇒・𠓛・𠓜・𠓝・𠓞
↓↑
乏(とぼ)しい・・・貧乏
異体字
「𣥄・𠂜・𠓟・疺・貶・贬・𡬯・𡬸・𦥘・𦥧・𧴷・𧸘」
ーーーーー
・・・???・・・「11・十一・拾壱・壱壹・足壹」・・・
「山茶花(さざんか)」に似ているが、咲く季節が違う・・・

庭の花は
「一本の幹の背丈が1m前後で、枝分かれが3本、花が3輪」
「獅子咲きのツバキ」
・・・「弁化が進み、不規則な大小、多くの花弁に
雄しべが混じって
花全体が盛りあがって見えるもの」
「千重咲き = 雄しべが総て花弁に変わり
整った多数の花弁が
鱗状に重なりあったもの」
ではなく
「八重咲き」・・・実は「獅子咲き=八重咲き」らしい
「花びらは五弁」
「花蘂(はなしべ)が一本」
・・・躑躅(つつじ)に似ているけれど・・・チガウ
「葉もギザギザ(鋸歯)」ではない
↓↑
「葉は楕円形で、互い違いに生える(互生)
葉の先は尖り・・・鋸歯は無い
・・・山茶花にはギザギザ(鋸歯)があるらしい・・・
葉の質は革質で艶があり
表面は濃い緑色をしている」・・・

↓↑
「椿三十郎」のツバキは・・・
赤、白で
木の背丈が塀の高さの三メートル前後・・・
白黒の映画だったが・・・
↓↑
椿(つばき・チン・チュン)・・・ツバキ(海柘榴)
センダン科の落葉樹・チャンチン
伝説中の長寿の大木
椿寿・椿葉・大椿
木の名
思いがけないこと
↓↑
珍しい霊木、「椿の木」があった
その椿の木に花が咲くことは
極めて珍しく
ある時に花が咲いた
思いがけない出来事だった(荘子)
↓↑
珍事中夭(チンジチュウヨウ)=「義経記」
闖事(チンジ)に同じ
馬が突然門から出てくること
闖入(チンニュウ)
↓↑
樁の字
樁=木+舂
木+𡗗+臼
木+三+人+臼
木+一+一+一+人+臼
=十+八+一+一+一+人+臼
ショウ・トウ
撞(つ)く・・・穀物を臼で撞く
大きなくい・木製のくい
杵(きね)
事柄を数える語
異体字「桩=木+庄」
𡗗=奉=ブ・ホウ・たてまつる・うける・ささげる
𡗗
異体字「俸・𠬻・捧・𢱵・捀・摓・𢩱・𢪋」
↓↑
荘子の「逍遥遊」
大木、大椿(ダイチン)が由来
この木は
八千年を春とし
八千年を秋とし
三万二千年が
人間の一年に当たる・・・
長寿で目出鯛木で
滅多に花を咲かすことがないので
花が咲くと
「椿事=非常に珍しいこと=珍事」
という・・・
↓↑
「秦」=中国の王朝・国名
はた。シン
応神天皇のとき
機織りを伝えて渡来した
帰化系民族の子孫にあたえられた名
先秦(センシン)・大秦(タイシン)
禾+舂(ショウ・うすづく
𡗗は秦の省略形)
𡗗=大+二
三+人
夫+一
↓↑
「椿事・椿説」
「椿説弓張月(ちんせつ ゆみはりづき)」
曲亭馬琴作・葛飾北斎画の読本
文化四年(1807年)~文化八年(1811年)刊行・全五篇

↓↑
「椿 椿山(つばき ちんざん)
享和元年六月四日(1801年7月14日)
~
嘉永七年七月十三日(1854年8月6日)
文人画家
江戸
小石川天神生まれ
花鳥画、人物画を得意とした
名は弼(たすく)・・・井伊直弼の「弼」・桜田門外で殺害
↓↑ 弼=㢶+弓
弓+百+弓・・・東西から百済を攻める
弓+一+白+弓
・・・弓=キュウ=九・球・宮・救
百(済)=一(初)新羅(白・曰)?
「志木⇔志楽木⇔新羅⇔白子(しらこ)」?
たすける・たすけ・ヒツ
補佐する
ゆだめ・弓の形を整える道具
弓を両側から締め付けて、ひずみを正す
↓↑ 四等官(シトウカン)・弾正台の第二位
字は篤甫(とくほ)
通称を忠太・亮太
号は椿山・琢華堂・休庵・四休庵・春松軒
碧蔭山房・羅渓・琢華道人
十七歳頃
同門の
渡辺崋山・・・ 三河国田原藩(愛知県田原市東部)
↓↑ 家老
著書
『慎機論』『初稿西洋事情書』
『再稿西洋事情書』『外国事情書』
『鴃舌或問』『鴃舌小記』など
天保十年(1839年)五月
蛮社の獄
鳥居耀蔵による幕府の
言論弾圧事件
高野長英、小関三英、渡辺崋山
ら「尚歯会」メンバーが
モリソン号事件、鎖国政策を批判し
↓↑ 弾圧された
を慕い・・・
崋山塾に入門
崋山を終生の師とした」
↓↑
𠁥・𠓛・𠓝・𠓞・・人が𠆢に入る・・「和同開珎」の発行?
𠁥=羊の角の象形
「讀みて𦮃の若くす(説文)」
「𠁥は部首・𦮃、芇を収める」
「𠁥を意符として持つ会意字に𥄕、雈」
などがある
異体字「𦫳(正字通)」
「方言で拐と同用・カイ・カ」
↓↑
鎮魂歌
↓↑
金+眞
↓↑
土+真
土+十+具
土+十+目+一+八
↓↑
精衛=伝説上の小鳥
填海=海を埋めること
皇帝炎帝の娘、女娃は東海で溺れ死んだ
女娃は小鳥(精衛)に化身
自身の死んだ東海を
小石や小枝などで埋めようとし
失敗に終わった
↓↑
月(肉)+关
月(肉)+丷+天
月(肉)+ᅭ+大・・・ᅭ
月(肉)+丷+一+大
↓↑
笑の初文
关=ショウ=丷+天=八+天
繁体字「關=門+幺+幺+丱」
異体字「笑・関」
↓↑
王+㐱
王+人+彡
↓↑
島津久光の四男
母は千百子・・・千百(千の桃)の子?
最後の薩摩藩主
島津茂久(忠義)の同母弟
名(諱)は紀寛→忠鑑→珍彦
通称は敬四郎→又次郎→周防→常陸→備後
珍彦(うずびこ・チンゲン⇔珍言・珍諺?)
は
記紀神話の神
椎根津彦の別名
父の
久光が薩摩藩主家へ復帰し
大隅重富
を領有、重富家を相続
忠鑑(ただあき)と名乗った後
珍彦と改名・・・珍諺・陳諺?
↓↑
「銅=金+同」の略字「同」
唐の
「開元通寳」にならって
「寳」の略字の
「珎」にして
「和同開珎」とした
寳=珎=ホウ
↓↑
和銅発掘献上
西暦708年
和銅元年(一月十一日改元)
一月
武蔵国より銅を献上
よって改元
二月
催鋳銭司設置
平城の地に新都造営の詔
五月
銀銭(和同開珎)発行
八月
和同開珎を発行
↓↑
和銅の採掘
武蔵国
秩父郡
に
「自然になれる和銅」
(おのずからになれるにぎあかがね)
都に献上
慶雲五年
改元されて
和銅元年
一月十一日
日下部-宿禰-老(くさかべ・の・すくね・の・おゆ)
津島-朝臣-堅石(つしま・の・あそん・かたしわ)
金-上-无(こんじょうむ)
二月十一日
催鋳銭司設置
多治比-真人-三宅麻呂(たじひ・まひと・みやけまろ)
を任命
鋳銭司は
地方国府に近いところに置き、国府に管理させた
採銅、鋳造などの知識・技術面
和銅献上時
無位の
金上无
が従5位以下に叙せられた
金上无と
津島朝臣堅石
との関係
和銅献上の2年前
慶雲三年十一月三日
文武天皇は
新羅国王に
「大使の従5位以下
美努-連-浄麻呂(みのむらじきよまろ)
の福使として
従六位以下の
津島-連-堅石
(むらじ・後、和銅元年までに朝臣)を遣わす」
という勅書を賜った記事から
遣新羅副使としての在任中に
新羅人の
金上无
と関係・・・
日下部宿禰老
和銅献上時に3人一緒の授位
霊亀三年(717年)四月二十五日
従5位上に叙せられ
養老五年(721年)正月二十三日
皇太子(首皇子・おひと・聖武天皇)
のお付きを命じられ
神亀元年(724年)二月二十二日
従四位以下に叙され
天平四年(732年)三月二十二日
死没
↓↑
多治比真人三宅麻呂
出世したが、最後は失脚し
その後
多治比真人県守
一族七人が
武蔵国司
9世紀後半に
多治比武信
が
武蔵国に配流され
秩父・児玉を押領
後、京より下った
峯時
が武蔵に居住
石田牧(長瀞町岩田)別当を兼ね
丹貫主と号し
丹治氏と称し
子
峯房
以下になって
秩父郡の領主として
武蔵七党の
丹党として活躍・・・
↓↑
金上无・・・金の上(かみ・うえ)の无(ない・ム・ブ)?
叙位を受け
和銅二年十一月二日
伯耆守(ほうきのかみ・鳥取県)
に任ぜられた・・・
↓↑
「多胡碑(たごのヒ)=羊さま」・・・多(おほの)
胡(えびす)
碑(石の卑)
群馬県
多野郡
吉井町
池
字
御門
国の特別史跡
和銅四年(711)建立
↓↑
弁官符上野国片岡郡緑野郡甘
良郡并三郡三百戸郡成給羊
成多胡郡
和銅四年三月九日甲寅
宣左中弁正五位下
多治比真人
太政官二品
穂積親王左太臣正二位
石上尊右太臣正二位
藤原尊
(弁官の符に
上野(かみつけぬ)の国の
片岡の郡(こおり)
緑野(みどの)の郡
甘良(から・甘楽)の郡
并(ならび)に
三郡の内三百戸を郡と成し
羊に給して
多胡郡と成す
↓↑
和銅四年三月九日甲寅の宣
左中弁は
正五位下
多治比の真人
太政官は
二品
穂積(ほずみ)親王
左大臣は
正二位
石上(いそのかみ)の尊(みこと)
右大臣は
正二位
藤原尊(藤原不比等)
↓↑
「羊に給して多胡郡と成す」
の
「羊」・・・日本円の「¥(通貨記号)」
↓↑ ・・・「咩(ビ)」=口+羊
発音(miē・み・ビ・ミーエ)
異体字「哶 ・哶・咪・𠴟・羋」
繁体字「哶・𠴟」
石川県白山市 比咩神社
白山-比咩(ひめ) 神社
阿蘇神社、熊本県阿蘇市にある神社
「阿蘓神社」とも
「健磐竜命神」、「阿蘇比咩神」を祀る
大分県宇佐市
和銅三年(710年)創建
乙-咩(め) 神社・・・乙咩(おとめ・乙女)
↓↑ 羊の鳴き声・the bleating of sheep
は
帰化人の多い地方に新たに郡を建て
その長になった
「羊」=伝説の「羊太夫」・・・
「羊太夫は、奈良まで(和銅を持って)
毎日
天皇の御機嫌伺いに100余里の道を往復
太夫の乗った馬に
小脛(こはぎ)という若者がついて行くと
馬は矢のように走った
ある日、都への途中、
木の下で昼寝をしている小脛の両脇の下に
羽が生えているのを
羊太夫
は見てしまった。
普段から
「私の寝姿は絶対に見ないで下さい」
と言われていたので、好奇心が湧いたのだ
そっと
羊太夫は
小脛の
羽を抜いてしまった
そこからは
今までの速さでは走れなくなり
天皇の怒りをかった
羊太夫は
討伐されてしまった」
↓↑
和銅元年・戊申(708年)
元明天皇
武蔵国秩父郡より
和銅献上
年号を
和銅と改元する(一月十一日)・・・十一日=拾壹似地
催鋳銭司を置く(二月十一日)・・・十一日=足位置丹治
↓↑ ↓ ↑
(四月十一日)・・・十一日=???
(四月十三~十一日)・・・・???
₩=「w+=」=「圓(1953年貨幣改革以前)Won・Wŏn」
↓↑ ↓ ↑
2019年~隣国の通貨(₩)危機だろう・・・
warai=wの省略=ワラに二
W=ダブリュー(double U=U+U)=V+V
w/=with(ウィズ)の省略
w/o=without=~がなくて
↓↑
和同銀銭発行 (五月十一日)・・・十一日=廿市仁智?
近江国に
銅銭鋳造させる(七月二十六日)
和同銅銭発行 (八月十日)
↓↑
和銅二年・己酉(709年)
元明天皇
銀銭私鋳罰則の詔(一月二十五日)
銅銭使用督励命令(三月二十八日)
銀銭廃止
銅銭だけを流通貨幣とする(八月二日)
↓↑
「富本銭が最古の貨幣」?
富の本の銭・・・富=宀+𠮛(𠫔)+田
一+口+口+十
(一+ム)+口+十
冨=冖+𠮛(𠫔)+田
一+口+口+十
(一+ム)+口+十
↓↑
富本銭
江戸時代
寛政十年(1798年)
の古銭カタログといった類の本に
「富本七星銭」の名前で銭の図柄と共に載っていて
それは普通使われるお金ではなく
「まじない銭」
専門的には厭勝銭(ようしょうせん)
↓↑
昭和44年(1969年)
平城京跡から発掘
平成3年(1991年)
更に古い地層の
藤原京跡から発掘
「和同開珎」より
古い貨幣
鋳造されたのは奈良時代
↓↑
平成9年(1997年)
大阪(難波宮)の
細工谷遺跡から
一枚発見
飛鳥池遺跡からの発見
発掘場所や
出土した
富本銭の状態等から
飛鳥で鋳造された
↓↑
富本銭が埋まっていた
地層から出た
木簡や古寺の瓦などの遺物が証拠で
造られた年代も七世紀後半と確認
↓↑
日本書紀に
「今(天武十二年~687年)よりは
銅銭を用いよ」
とある『銅銭』が「富本銭」である・・・
↓↑
唐の「芸文類聚」に
「民を富ませる本は
食(食べるもの)と貨(貨幣)だ」
とあることからとった
「富本と名付けたお金」・・・
ーーーーー
𠫔=一+ム・・・ム=「私」の源字
・・・訓読で「よこしま」・・・
𣅀=亠+日
シ・むね・うまい
「旨・㫖・𣅌・𠤔・𤮻・𠩊・𠮛」
畐=𠮛(一口)+田(囗十)
𠮛の異体字「𠫔・旨・𤮻」
豆=𠮛+ㅛ
一+口+ㅛ
一+口+丷+一
ㅛ=ヨ?
𠮛の異体字=𠫔=一+ム
𣅀=亠+日
シ・むね・うまい
旨㫖𣅌𠤔𤮻𠩊𠮛
亠(音・おと)+日(曰・いわく)=𣅀
むね=意図していること、意向
天子や上位者の指示や命令
その考えや意向
うまい・美味・食べ物がおいしい
「合」=𠆢+𠮛=「會」
𠆢+一+口
「会」=𠆢+𠫔=「會・會の略字」
𠆢+一+ム ・・・遭・遇・逢・・・ミチとの遭遇?
・・・「口」=「ム」・・・「△・▽」
口のモグモグの様子
↓↑
「仝」=同・・・「𠆢=冂」、「工=𠮛」
「𠓛+丄」=「冂+𠮛」
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+サ」、屋号・ヤマサ=味噌醤油
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+ナ」、屋号・ヤマナ=味噌醤油
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+二」、屋号・ヤマニ=回漕・廻船問屋
藍玉・藍色染料
藍の葉を発酵
熟成させた
蒅(すくも)を
固めて乾燥させたもの
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+吉」、屋号・ヤマキチ=材木・海産物
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+川」、屋号・ヤマカワ=
「工(巧・匠・技)」に代えて「𠆢+炭」、屋号・ヤマズミ=
↓↑
「𠓛・𠓝・𠓞・傘・☂」
𠓛=雧=隹隹隹木=集=隹+木
シュウ
あつまる・あつめる・つどう
異体字「亼・𠓛・𠍱・輯・雦・雧
辑・𨌖・𨍣・𨍾・𨎵」
↓↑
𠓞.=入+二
↓↑
兦・𠓛
內・𠓜・𠓝・𠓞・內
㒰・㒱・𠓟
全・氽・㒲・𠇒・𠓠・𠓡・𠓢・𠓣
↓↑
𠁥・𠇒・𠓛・𠓜・𠓝・𠓞
↓↑
乏(とぼ)しい・・・貧乏
異体字
「𣥄・𠂜・𠓟・疺・貶・贬・𡬯・𡬸・𦥘・𦥧・𧴷・𧸘」
ーーーーー
・・・???・・・「11・十一・拾壱・壱壹・足壹」・・・