― 妖元山 麓 ―
参謀従事タクエンの死を賭けた説得に忠義心を揺さぶられたスワト、それに追随するように進言したミケイによって、ジャデリンを大将とする官軍5千の軍団は、武具兵馬を整えると、妖元山の麓に後詰めとして待機していたキイの弓兵隊1千と合流した。
「…(流石は名のある将達を纏(まと)めるジャデリンの軍だ。ここまで早く兵を動かすとは)」
ジャデリンの官軍より先に後詰め部隊に合流していたタクエンは、ジャデリン以下将軍達が率いる兵達の顔を前にして、その士気の高さに驚いていた。頂天教軍が乱を起こして早数ヶ月、南部官軍が討伐に乗り出し、連戦を重ねるほど2ヶ月半。普通ならば、非日常の繰り返しである戦を数十と繰り返せば、いくら良く統率された兵士達でも精神身体は疲労し、厭戦(えんせん)(※戦いに飽き飽きとすること)気分が隠し切れないものである。
だが、ジャデリンが命を下してから準備と行軍を終えるまでの速さは、驚くべきものであった。
「真に恐るべしは、あのジャデリンという男の大将としての強さか…」
タクエンは、麓に座巻する将兵達を見ながら小さく呟いた。
軍という物は、兵が多ければ多いほど行軍が遅れるものである。だが、援軍に来たジャデリンは5千という兵数を持ちながら、行軍にかかった時間は半刻(1時間)ほど。これはタクエンの予想した時間を、遥かに超えるものであった。
「流石はジャデリン将軍。この早駆け、私も見習いたいものです」
「ミケイめ。今さら、わしを煽てても遅いわ。この戦に勝ったら、懲罰の覚悟をしておけい」
「おっ、こちらの軍の大将が挨拶に来ますぞ」
「ちい、話をそらしおって…ええい、もうよいわ」
立ち並ぶ将兵達の中、ミケイとジャデリンが馬を横に並べて喋る。
ジャデリンは面子を大事にするため感情的に怒りやすい人物だったが、ミケイのような自分より若輩で地位も低い一癖者を囲えるだけの度量があった。何か一つに秀でた単純な才能よりも、地位や名声、礼儀や素行が大事とされるこの時代にそれは、将兵一貫の姿勢を貫くジャデリンの懐の深さを覗わせた。
ドッドッドッ…トッ
その時、ジャデリン達の前に二人の男が現れた。
それは、緑色の甲冑を身に纏う、キレイの弟キイと騎乗した馬の横に付く、参謀従事のタクエンであった。
「キイ様。援軍に来てくださったジャデリン将軍の前ですぞ。そのように気落ちした顔で迎えては無礼にあたりますぞ。さあ下馬してお迎えなされ」
「う、うむ。すまんタクエン。そうだのう、兄上のための援軍に来てくださったのだ。粗相があっては、私の恥だ」
タクエンはキイを励ましながら緩々と下馬させると、ジャデリン達の前で膝を着いて跪いた。
援軍を待つ間、焦る兵士たちを場に留めていたキイの心は、兄の死という不安に苛まれ、決して優れるものではなかった。すでに敵の手にかかっているかもしれない兄の事を思うキイの表情は、血の気が引くほど青ざめていた。
「ジャデリン将軍!私は後詰め部隊を預かるキイと申す者。此度は兄上…いえ、我が身内の不始末にこれほどの援軍を助成していただき…言葉も無きしだいでございます」
「助けを求める味方あれば、助けるのが義である。何もおかしくはあるまいて」
「おお、抜け駆け同然の無礼を働いた兄に、なんと寛大な。ジャデリン将軍のこのキイ、二度と忘れませぬ」
「当たり前の事をしておるだけだ!」
ジャデリンは目の前で自分に遜(へりくだ)った態度で迎えるキイを見て、格好を付けた言葉で返した。よもや『部下からの挑発に負けて怒りに任せて出陣した』などとは、口が裂けても言えなかったからである。
「クスクス…」
「ミケイ!何がおかしい!」
「いえ…なにも。ジャデリン将軍は嘘が上手いと思いまして」
「このぉ…黙らぬか!」
ジャデリンは視線を数度横にやりながら、小声でミケイを牽制した。
隣で馬の手綱を握りながらクスりと聞こえるに笑う、ミケイの小さな嘲笑が耳に入るたびに、拳がギュッと音を立てて絞られ、兜に隠れた眉のつりあがり加減、甲冑の隙間から見える喉の震えは、大声でミケイに怒鳴り散らしたいという怒りの表情は、事情を知るものからすれば恐ろしくもあり、また滑稽でもあった。
だが、部下に口喧嘩で負けたとなると、これは大将としての面子に関わると、ひたすらに怒りを押し殺し、キイにそれを気取られてはならぬと、一方的に言葉を続けた。
「キイ殿!わしは、使者タクエンの厚い忠義心に胸打たれただけのこと!面子や私情で援軍を出すはずがなかろう!のう、そうであろう!のう!」
「は…?はあ」
「わしは将が気に食わなくて援軍を出さぬような矮小な器の者ではないし、抜け駆けされたからといって味方を見殺しにするような非情な将でもない!いいか、わしは当然のことをしているのだ!当然のことを!決して私憤の気持ちからではないぞ!キイ将軍もそう思われるだろう!」
「はっ…はあ。それはもう」
事情のわからないキイは、目の前のジャデリンの捲し立てるような言葉の数々に、訝しげな気持ちを抱いたまま、困惑せざるを得なかった。だが、ジャデリンの口から言葉が放たれれば放たれるほど、横で聞くミケイの口からは小さな笑いが漏れた。
そこへ…
「物見(斥候)の兵が帰ってきたぞ!」
兵達の波を割くように、一人の傷ついた兵士が肩を担がれながら、ジャデリン達の前に現れた。この兵士は、キイが兄キレイの部隊の様子を探るために山の道中に送った者であった。
「そ、その姿は!一体どうしたのだ!敵が居たのか!いや、それより兄上は無事であるのか!」
キイは形振り構わず、倒れる兵の側に駆け寄った。
だが兵士は、体中に矢傷や刀傷が残り、血は場を浸すほど流れ、もう虫の息。声にならない声を、口からつぶさに出すのがやっとであった。
「良く聞こえぬ。ええい!」
キイは兜を脱ぎ、血に濡れる男の口元に耳を近づけると、弱々しく放たれる最後の言葉を逃さず聞いた。物見の男は敵に襲われながらも、キレイが惨敗する一部始終を知る騎馬武者の最後に運良く出くわし、その騎馬武者から聞いた情報をキイに伝えると、物見の男もまた最後を迎えた。唇に接したキイの耳は血に染まって汚れていたが、心からは不安が消え、一際の抑揚が全身を駆け巡った。
「おおお…兄上は、まだ生きておられたか…!」
声を押し殺しながら出た、小さな雄たけび。
キイは物見の男から全てを知らされ、まだ自分の兄が信頼するオウセイと供に生き延びている事を知ると、不安に青ざめていた顔は血を通わせ、瞑った目には力が戻っていた。
「…」
その隣でキイの放つ言葉を拾うタクエンの顔が、一瞬緩む。
最悪、キレイの死も予想していただけに、キイの喜びはタクエンにも重々理解できるものだった。
「では、すぐに救出部隊を差し向けましょう。及ばずながら、このミケイに策がございます」
平静を取り戻したキイを見ていたミケイは、将兵が見守る中、静かに語り始めた。
知将ミケイの考案した救出作戦は、頂天教軍が篭る本陣への山攻めも兼ねていた。
「合流した官軍総勢6千が一方に出撃し戦っても、高地で備えが十分な頂天教軍の厚い守りを一気に突破するのは難しく。数に任せて力攻めをしても、キレイ将軍の二の舞を演じることになるでしょう。そこでまず、部隊を三分し、兵力を山の五路の内の三方に分けます」
ミケイは馬を降り、雲を帯びる妖元山の五つの道筋を指し、将兵達の目に見えやすいように、右に左に手振りをしながら説明を続けた。
「これは、三方面に渡る時間差の波状攻撃を仕掛けつつ、敵の力の分散と疲労を狙うのが目的の作戦です。まず一番近い東側面道からは、私ミケイ以下1千5百の分隊が一気に攻め敵の備えを揺さぶりつつ、遊撃を敢行して敵をいぶりだします。その間に中央道からキイ将軍以下2千の分隊が三色の旗指物を持ち、多勢を装って正面を構えながら、キレイ将軍の救出を最優先にして緩やかに進みます。そして一番遠い西道からは、ジャデリン将軍率いる2千5百の本隊を進め、兵力の分散した敵の本拠地を奪います」
「あいやまたれい。ミケイ将軍の策は確かですが、些かの不安が残りまする」
話を割って入ってきたのは、タクエンであった。
タクエンは、眉をひそめ訝しげな顔でミケイに言う。
「敵の備えがいち早く完了しており、伏兵や各個撃破が可能な位置に陣取られていたら、いかが致しましょう。地の利は確実に相手にあり、敵の本陣も強固となれば、時間をかければかけるほど、我らの敗北は必須と思われまするが…」
「ふふふ、ご心配は無用のこと。敵は早朝からのキレイ将軍の攻めによって被害、疲労ともに多々あり。悪路の山道を往復しているのなら、いかに強靭な兵を抱えたとしても、そう早くは動けません。だとすれば本拠地に篭って完全守備に徹するはず。そこに我が三方から来る総勢6千の波状攻撃がかかれば、いかに敵が備えをしても耐えられますまい。精神肉体ともに疲労は必ずあり。人間一日続けて戦うことは難しい」
「なるほど。我らが人間であるように、敵も人間であるということですな」
参謀従事タクエンの一抹の不安を、知将ミケイは論破した。
練りに練った作戦を見事に唱えたミケイの周りには、タクエン以外、意見を述べる将は居なかった。皆、その綿密な作戦に唖然とし、閉口せざるを得なかった。
「…(ミケイ、やはり只者ではない。おそらく未来には天下に名だたる知将となるな…)」
「…(このタクエンという者。私の策の穴を良く突く。恐るべき兵学者のようだな…)」
策士は、策士を知る。
瞬間的に訪れた沈黙の中、二人は視線を交わらせた。
この時、両人とも口に出さなかったとはいえ、二人は兵学者、知者としての才能を己の肌で感じとっていた。二人の胸に去来するものは、皮肉にも知恵の持ち主たる互いを認め、その未来を意識しあうという同じものであった。
ヒュゥゥゥ……
荒野をそよぐ風が大地に降り注いでいた雨が止んだ事を将兵達に教えたが、タクエンとミケイは、それに気付かなかった。
そして、ミケイはジャデリンに駆け寄り。
「ジャデリン将軍。意見が無い様であれば、私に兵の分配をお任せください」
「お主は指揮官ではないのだぞ!何を言っておるか」
「私にお任せください。必ずや勝ちをジャデリン将軍に与えるでしょう」
「ふむむ…わかった。お前の好きにやるがよい」
ミケイはジャデリンの返答を受け取るとすぐに、今現在総指揮官であるジャデリンを差し置き、次々に各部隊に命令を飛ばした。ジャデリンは、この光景をいつにも増して苦々しく思ったが、ミケイには返し難い実績と言い難い気迫があったので、指揮以外の全てを任せることにした。
「官軍隊、出発ーッ!」
ジャデリンの号令が麓に響く。
かくして官軍は部隊を三つに分け、それぞれ山道の三路へと出発した。
時間は昼を過ぎ、兵が進む頃にはすでに夕方近くなっていたが、朝方から吹き付けていた山風も、河川のように山から流れていた大雨も、確実に弱まっていた。山頂にかかる黒雲は、官軍の馬蹄の音が聞こえる度に千切れるようであった。
参謀従事タクエンの死を賭けた説得に忠義心を揺さぶられたスワト、それに追随するように進言したミケイによって、ジャデリンを大将とする官軍5千の軍団は、武具兵馬を整えると、妖元山の麓に後詰めとして待機していたキイの弓兵隊1千と合流した。
「…(流石は名のある将達を纏(まと)めるジャデリンの軍だ。ここまで早く兵を動かすとは)」
ジャデリンの官軍より先に後詰め部隊に合流していたタクエンは、ジャデリン以下将軍達が率いる兵達の顔を前にして、その士気の高さに驚いていた。頂天教軍が乱を起こして早数ヶ月、南部官軍が討伐に乗り出し、連戦を重ねるほど2ヶ月半。普通ならば、非日常の繰り返しである戦を数十と繰り返せば、いくら良く統率された兵士達でも精神身体は疲労し、厭戦(えんせん)(※戦いに飽き飽きとすること)気分が隠し切れないものである。
だが、ジャデリンが命を下してから準備と行軍を終えるまでの速さは、驚くべきものであった。
「真に恐るべしは、あのジャデリンという男の大将としての強さか…」
タクエンは、麓に座巻する将兵達を見ながら小さく呟いた。
軍という物は、兵が多ければ多いほど行軍が遅れるものである。だが、援軍に来たジャデリンは5千という兵数を持ちながら、行軍にかかった時間は半刻(1時間)ほど。これはタクエンの予想した時間を、遥かに超えるものであった。
「流石はジャデリン将軍。この早駆け、私も見習いたいものです」
「ミケイめ。今さら、わしを煽てても遅いわ。この戦に勝ったら、懲罰の覚悟をしておけい」
「おっ、こちらの軍の大将が挨拶に来ますぞ」
「ちい、話をそらしおって…ええい、もうよいわ」
立ち並ぶ将兵達の中、ミケイとジャデリンが馬を横に並べて喋る。
ジャデリンは面子を大事にするため感情的に怒りやすい人物だったが、ミケイのような自分より若輩で地位も低い一癖者を囲えるだけの度量があった。何か一つに秀でた単純な才能よりも、地位や名声、礼儀や素行が大事とされるこの時代にそれは、将兵一貫の姿勢を貫くジャデリンの懐の深さを覗わせた。
ドッドッドッ…トッ
その時、ジャデリン達の前に二人の男が現れた。
それは、緑色の甲冑を身に纏う、キレイの弟キイと騎乗した馬の横に付く、参謀従事のタクエンであった。
「キイ様。援軍に来てくださったジャデリン将軍の前ですぞ。そのように気落ちした顔で迎えては無礼にあたりますぞ。さあ下馬してお迎えなされ」
「う、うむ。すまんタクエン。そうだのう、兄上のための援軍に来てくださったのだ。粗相があっては、私の恥だ」
タクエンはキイを励ましながら緩々と下馬させると、ジャデリン達の前で膝を着いて跪いた。
援軍を待つ間、焦る兵士たちを場に留めていたキイの心は、兄の死という不安に苛まれ、決して優れるものではなかった。すでに敵の手にかかっているかもしれない兄の事を思うキイの表情は、血の気が引くほど青ざめていた。
「ジャデリン将軍!私は後詰め部隊を預かるキイと申す者。此度は兄上…いえ、我が身内の不始末にこれほどの援軍を助成していただき…言葉も無きしだいでございます」
「助けを求める味方あれば、助けるのが義である。何もおかしくはあるまいて」
「おお、抜け駆け同然の無礼を働いた兄に、なんと寛大な。ジャデリン将軍のこのキイ、二度と忘れませぬ」
「当たり前の事をしておるだけだ!」
ジャデリンは目の前で自分に遜(へりくだ)った態度で迎えるキイを見て、格好を付けた言葉で返した。よもや『部下からの挑発に負けて怒りに任せて出陣した』などとは、口が裂けても言えなかったからである。
「クスクス…」
「ミケイ!何がおかしい!」
「いえ…なにも。ジャデリン将軍は嘘が上手いと思いまして」
「このぉ…黙らぬか!」
ジャデリンは視線を数度横にやりながら、小声でミケイを牽制した。
隣で馬の手綱を握りながらクスりと聞こえるに笑う、ミケイの小さな嘲笑が耳に入るたびに、拳がギュッと音を立てて絞られ、兜に隠れた眉のつりあがり加減、甲冑の隙間から見える喉の震えは、大声でミケイに怒鳴り散らしたいという怒りの表情は、事情を知るものからすれば恐ろしくもあり、また滑稽でもあった。
だが、部下に口喧嘩で負けたとなると、これは大将としての面子に関わると、ひたすらに怒りを押し殺し、キイにそれを気取られてはならぬと、一方的に言葉を続けた。
「キイ殿!わしは、使者タクエンの厚い忠義心に胸打たれただけのこと!面子や私情で援軍を出すはずがなかろう!のう、そうであろう!のう!」
「は…?はあ」
「わしは将が気に食わなくて援軍を出さぬような矮小な器の者ではないし、抜け駆けされたからといって味方を見殺しにするような非情な将でもない!いいか、わしは当然のことをしているのだ!当然のことを!決して私憤の気持ちからではないぞ!キイ将軍もそう思われるだろう!」
「はっ…はあ。それはもう」
事情のわからないキイは、目の前のジャデリンの捲し立てるような言葉の数々に、訝しげな気持ちを抱いたまま、困惑せざるを得なかった。だが、ジャデリンの口から言葉が放たれれば放たれるほど、横で聞くミケイの口からは小さな笑いが漏れた。
そこへ…
「物見(斥候)の兵が帰ってきたぞ!」
兵達の波を割くように、一人の傷ついた兵士が肩を担がれながら、ジャデリン達の前に現れた。この兵士は、キイが兄キレイの部隊の様子を探るために山の道中に送った者であった。
「そ、その姿は!一体どうしたのだ!敵が居たのか!いや、それより兄上は無事であるのか!」
キイは形振り構わず、倒れる兵の側に駆け寄った。
だが兵士は、体中に矢傷や刀傷が残り、血は場を浸すほど流れ、もう虫の息。声にならない声を、口からつぶさに出すのがやっとであった。
「良く聞こえぬ。ええい!」
キイは兜を脱ぎ、血に濡れる男の口元に耳を近づけると、弱々しく放たれる最後の言葉を逃さず聞いた。物見の男は敵に襲われながらも、キレイが惨敗する一部始終を知る騎馬武者の最後に運良く出くわし、その騎馬武者から聞いた情報をキイに伝えると、物見の男もまた最後を迎えた。唇に接したキイの耳は血に染まって汚れていたが、心からは不安が消え、一際の抑揚が全身を駆け巡った。
「おおお…兄上は、まだ生きておられたか…!」
声を押し殺しながら出た、小さな雄たけび。
キイは物見の男から全てを知らされ、まだ自分の兄が信頼するオウセイと供に生き延びている事を知ると、不安に青ざめていた顔は血を通わせ、瞑った目には力が戻っていた。
「…」
その隣でキイの放つ言葉を拾うタクエンの顔が、一瞬緩む。
最悪、キレイの死も予想していただけに、キイの喜びはタクエンにも重々理解できるものだった。
「では、すぐに救出部隊を差し向けましょう。及ばずながら、このミケイに策がございます」
平静を取り戻したキイを見ていたミケイは、将兵が見守る中、静かに語り始めた。
知将ミケイの考案した救出作戦は、頂天教軍が篭る本陣への山攻めも兼ねていた。
「合流した官軍総勢6千が一方に出撃し戦っても、高地で備えが十分な頂天教軍の厚い守りを一気に突破するのは難しく。数に任せて力攻めをしても、キレイ将軍の二の舞を演じることになるでしょう。そこでまず、部隊を三分し、兵力を山の五路の内の三方に分けます」
ミケイは馬を降り、雲を帯びる妖元山の五つの道筋を指し、将兵達の目に見えやすいように、右に左に手振りをしながら説明を続けた。
「これは、三方面に渡る時間差の波状攻撃を仕掛けつつ、敵の力の分散と疲労を狙うのが目的の作戦です。まず一番近い東側面道からは、私ミケイ以下1千5百の分隊が一気に攻め敵の備えを揺さぶりつつ、遊撃を敢行して敵をいぶりだします。その間に中央道からキイ将軍以下2千の分隊が三色の旗指物を持ち、多勢を装って正面を構えながら、キレイ将軍の救出を最優先にして緩やかに進みます。そして一番遠い西道からは、ジャデリン将軍率いる2千5百の本隊を進め、兵力の分散した敵の本拠地を奪います」
「あいやまたれい。ミケイ将軍の策は確かですが、些かの不安が残りまする」
話を割って入ってきたのは、タクエンであった。
タクエンは、眉をひそめ訝しげな顔でミケイに言う。
「敵の備えがいち早く完了しており、伏兵や各個撃破が可能な位置に陣取られていたら、いかが致しましょう。地の利は確実に相手にあり、敵の本陣も強固となれば、時間をかければかけるほど、我らの敗北は必須と思われまするが…」
「ふふふ、ご心配は無用のこと。敵は早朝からのキレイ将軍の攻めによって被害、疲労ともに多々あり。悪路の山道を往復しているのなら、いかに強靭な兵を抱えたとしても、そう早くは動けません。だとすれば本拠地に篭って完全守備に徹するはず。そこに我が三方から来る総勢6千の波状攻撃がかかれば、いかに敵が備えをしても耐えられますまい。精神肉体ともに疲労は必ずあり。人間一日続けて戦うことは難しい」
「なるほど。我らが人間であるように、敵も人間であるということですな」
参謀従事タクエンの一抹の不安を、知将ミケイは論破した。
練りに練った作戦を見事に唱えたミケイの周りには、タクエン以外、意見を述べる将は居なかった。皆、その綿密な作戦に唖然とし、閉口せざるを得なかった。
「…(ミケイ、やはり只者ではない。おそらく未来には天下に名だたる知将となるな…)」
「…(このタクエンという者。私の策の穴を良く突く。恐るべき兵学者のようだな…)」
策士は、策士を知る。
瞬間的に訪れた沈黙の中、二人は視線を交わらせた。
この時、両人とも口に出さなかったとはいえ、二人は兵学者、知者としての才能を己の肌で感じとっていた。二人の胸に去来するものは、皮肉にも知恵の持ち主たる互いを認め、その未来を意識しあうという同じものであった。
ヒュゥゥゥ……
荒野をそよぐ風が大地に降り注いでいた雨が止んだ事を将兵達に教えたが、タクエンとミケイは、それに気付かなかった。
そして、ミケイはジャデリンに駆け寄り。
「ジャデリン将軍。意見が無い様であれば、私に兵の分配をお任せください」
「お主は指揮官ではないのだぞ!何を言っておるか」
「私にお任せください。必ずや勝ちをジャデリン将軍に与えるでしょう」
「ふむむ…わかった。お前の好きにやるがよい」
ミケイはジャデリンの返答を受け取るとすぐに、今現在総指揮官であるジャデリンを差し置き、次々に各部隊に命令を飛ばした。ジャデリンは、この光景をいつにも増して苦々しく思ったが、ミケイには返し難い実績と言い難い気迫があったので、指揮以外の全てを任せることにした。
「官軍隊、出発ーッ!」
ジャデリンの号令が麓に響く。
かくして官軍は部隊を三つに分け、それぞれ山道の三路へと出発した。
時間は昼を過ぎ、兵が進む頃にはすでに夕方近くなっていたが、朝方から吹き付けていた山風も、河川のように山から流れていた大雨も、確実に弱まっていた。山頂にかかる黒雲は、官軍の馬蹄の音が聞こえる度に千切れるようであった。











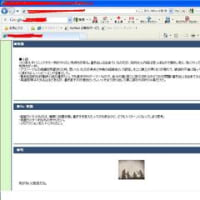







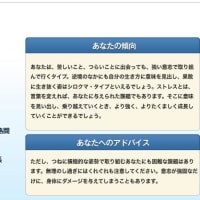






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます