― 妖元山 中央山道 ―
山中の天候は、吹いては飛ぶ女心のように変わりやすいものである。
さっきまで身を濡らしていた小雨が嘘のように、天候は不順に不順を重ね、山の下へ下へと吹き始めた逆風は山肌を削るように荒れ、当たる雨粒は身を弾くほどの豪雨に早変わりしていた。
「くっ…恐将歩めば山が泣くか。天め、この私が勝つのがそれほど疎ましいか」
悪天候の中、キレイは馬の手綱を強く握りながら呟いた。
キレイの特徴である赤で染められた甲冑と戦包(せんぽう)(合戦の時に身を包む厚手の戦闘服、または肩掛けの総称)は、雨粒を吸い込んで重みを増し、冷たくべったりと肌に付く布は疲労感を増幅させた。
「だがな。このような風雨に負けるほど、私は虚弱ではない。天よ見ていろ、見事敵の本拠を落として、悔し顔の貴様を笑ってやる」
だが、キレイの意思と騎馬の歩みは、逆境を跳ね除けるように少しも緩む事が無かった。
ぬかるみに歪む山道で、強風と雨粒が山へ人へ打たれる中、強く手綱を握られた騎馬は、ただ前へ前へと強く土を踏み、馬蹄は窪みに出来た池を弾いて行く。
そこへ、副将の一人が報せを告げようとキレイに近づく。
「御大将!そう足を急かされても、後ろの兵が付いて来れませぬ!」
「なんだと?」
キレイは、風雨に晒される顔面を右腕で防ぐと自分の後方を覗いた。
そしてキレイは見た。先ほどまで近くで雄々しく歩を進めていた率いる歩兵隊2千5百が、キレイから大分離れた岩肌の突き出した傾斜の悪路で立ち往生していたのを。
「あの程度の傾斜、何故登れん」
「岩肌が滑り、土は泥となって流れるような悪路。それにこの悪天候では仕方ありますまい」
「ええい、この程度の風雨で足を止まらせるな。甲冑を捨ててでも登らせよ。絶対に足を止めてはならんぞ」
「はっ…」
急ぎ攻め。こうまでしてキレイが進軍を速めさせる理由は、ただ一つだった。
奇襲、いわゆる備え無き敵の不意を突く作戦のためである。
敵に発見されないための進軍速度が重要である奇襲戦において、この進軍の遅さは致命的であった。参軍従事のタクエンが危惧したように、絶対的な守りに適した敵が、奇襲を知り、備えを本腰にして構えれば、数で勝っていても勝てる見込みなどない。
「急がせよ…見つかっては奇襲の意味がない」
しかしその時、山道の先に存在する妖元山の高台から、数人の影が散るのが見えた。
― 妖元山採石所 頂天教軍 本陣 ―
「アカシラ様!教祖様!大変です!敵がやってきます!」
妖元山上部。
鉱石を産出するために切り開かれた採石所は、篭る頂天教軍によって山塞(さんさい)と化していた。強い雨音が聞こえる石室に、怪しげな衣服を纏った一人の男が座っている。
「ヒャッヒャッ…こんな悪天候に、どこの馬鹿じゃあ」
「遠目ですが、中央道より官軍の歩兵が数千ほど」
「ヒャッヒャッ…悪天候に紛れて奇襲のつもりかのう。それで、他の物見の兵はどうしたんじゃあ?」
「はっ、各所に報せをと、走り回っております」
「ヒャッヒャッ…それは、いかんのお。全員戻らせるんじゃ」
「はっ…しかしそれでは敵軍が本陣を」
「ヒャッヒャッ…いいんじゃ。いいんじゃ。敵が取りたきゃ取らせれば良いんじゃ。愚かな奴らの願いが叶えられて、絶頂を迎えたところを…虫けらのようにクイッ!っと叩き潰す…のぉ?」
「では、アカシラ様には何かお考えがおありで…?」
「ヒャッヒャッ…ほれ、これを配ってこい。お前は諸将にこれを読ませて、その通りに遂行させるんじゃ。少し経てば、わしの奇跡を間近で見れる。良いものじゃぞぉー」
「ははっ、それでは伝えてまいります」
石室の中央に、燃え盛る蝋燭を何本も周りに立てて書き物に熱中していた男は、歯茎がむき出しになるほど声高に笑うと、やってきた頂天教軍の兵士達に一巻の巻物を渡し、そう告げた。
「ヒャッヒャッ、まずいのう。実にまずい。小さく弱い虫を殺す時に限って、どう捻り潰そうかと思考が冴えてしまうのう。このように老いを感じる歳になっても、益々冴える。ヒャッヒャッ…いやー、まずいのう!」
初老を迎えた男は、誰も居なくなった石室で、ただケタケタと笑い続けた。
妖しげな衣服を身に纏った男の名前は、アカシラ。
帝国に対し乱を起こした首謀者、頂天教軍の最高司令官にして、長らく官軍が適うことが出来なかった頂天教軍随一の知恵の持ち主である。
― 妖元山 中央山道 ―
その頃、敵に見つかったことなど露知らない官軍歩兵隊たちは、立ち往生と緩やかな進軍を繰り返していた。キレイの思い描く、神速をもっての奇襲戦法の意図とは反対に、進軍は難航を極めた。
ザァー!ザァー!
ビューッ!ビューゥ!
「うわーぁ!吹き飛ばされる!」
「なんて逆風だ!一歩前へ出るだけでも辛い」
「か、風も強い!わわわ、吹き飛ばされそうじゃ」
容赦なく吹き付ける逆風が兵の体を止め
ズザザーッ!
ガラガラガラッ!
「あっ、また一人転んだぞ!」
「こう道が悪くちゃ仕方ないさ…うわっ!」
「く、くそ。このままじゃ敵と戦う前に疲れちまうぞ」
豪雨と兵の足によって山道の柔らかな土が捌けられ、剥き出しの岩肌が足を滑らせ
ゴロゴロ…カッ!
バリバリバリ!
「ひええ、また光ったぁ!
「ブルブル…雷怖いよぉ」
「い、戦で死ぬのはいいが、雷に当たって死ぬのは嫌だなぁ」
山上に差し掛かる黒雲は雷雲となって、そこから落ちる雷光と響く雷鳴は、おびただしい光とけたたましい音を兵士の目と耳に轟かせる。
「ええい!進め!進まぬか!」
キレイの怒号に似た号令が雷光を背景に飛ぶ。
だが将兵達は足を早めるどころか、不安定な足場に一歩ずつ足場を確かめながら進軍しなければならなかった。また、転んで打ち所悪く死者も出始めたことから、士気も上がらなかった。行く時は天を突くほどの勢いだった兵士達の意気は下がりに下がり、度重なる疲労感を含めて、その士気は今や崩壊寸前であった。
「ぬうう…このような鈍足では、奇襲の意味がない…」
「キレイ様!駄目です、兵達は皆風雨に晒されて士気は落ちる一方。ここは、いったん出直しましょう。天候が回復した後、攻め入るのが良いかと思われまするが」
「そのような事が出来れば、とうにやっておるわ馬鹿者め」
「しかし…」
「ここで後退すれば山中の敵が察して出陣し、追撃の格好の餌食になってしまう。大打撃の負け戦を演じるつもりか?」
「そ、それはたしかにそうですが」
「それに引いて惨敗するなど、このキレイの心が許せん!どの道、勝利するためには行かねばならんのだ!進め!進むのだ!何を犠牲にしても進めぇ!」
冷静さを欠き、雷鳴と同じほど憤るキレイは、恐怖の視線と狂気の口調に満ち溢れ、いわば逃げ腰気味だった副将の下唇を思わず強く噛ませた。
そして副将は風雨の中、手を高らかに振り上げ、今まであげたことの無いような大声を放ち、難航する兵達を急がせようと捲し立てる。
「す、進め!進めーーー!」
副将は、この男の言う『犠牲』の意味を恐怖と焦燥の中うすらと感じていた。
逆らえば明日の命もわからないという、その恐怖の鞭が副将にも染み付いていたのだ。
「疲労も多いが勝てるはずだ。幸い、黒雲と雷鳴で我らの姿と音は消えておるのだ。その証拠に敵の陣の灯火が見えんではないか。ははは、まだ勝てるぞ!」
キレイは、眼をクワッと大きく開くと、再び手綱を握り、ただ前へと進んだ。
無意識の焦りが、キレイにはあった。脳裏にタクエンの言葉が焼きついていたからだ。
(…ふざけるな!…私が負けて奴に笑われるわけにはいかんのだ!)
矮小な意地が、キレイの心を塗りつぶす。
自分自身、悪天候に苛まれれば危険を伴うと思っていただけに、タクエンの言葉が痛烈に勝利への意地を増徴させる。他人に自身の才能を鼻にかけ傲慢になりながら、他人に優越たる才能を否定されて笑われる事を嫌う。
…負けるわけには。
…負けるわけには、いかなかったのだ。
そのキレイの気持ちとは裏腹に、傲慢にも参謀タクエンの進言も聞き入れず、頑なに山攻めを敢行したキレイの軍に、天地は罰を与えるように味方しなかった。雨と雷は止まず兵の体を脅かし、風と水は進軍を妨げ、行くも戻るも難しく、立ち往生した将兵達は、いつ敵に襲われるのではないかと、差し迫るその絶望感を味わった。
天地に嫌われた、キレイの歩兵隊は孤立した。
「皆の者、良く聞けい!!」
だがキレイは、ただその場で立ち止まり、ただその場でうずくまる様な男ではない。
龍は雷鳴の波を泳いでこそ龍であり、天を逆らって昇るからこそ龍なのである。
キレイは知っていた。こういう時に、どうすれば良いかを。
足を止めて進まない兵士達に、何が『足りない』のかを。
キレイは叫んだ。
「誉れ高き官軍の強兵達よ聞け!そして見よ!あの雷鳴の先に見えるのが敵の陣だ!あと少し!この苦難もあと少しだ!タダでとは言わん。将も兵卒も身分に関わらず、敵の陣に一番に攻め込んだ者には、褒美として1千の黄金!大将首をとった者には、褒美として1千の部下を率いる大将の地位を約束するぞ!このキレイが声高に言うのだ、間違いは無いぞ!」
風雨と稲妻を遮るように、兵士達の耳に通ってゆくキレイの声。
ザワザワ…
ザワザワ…
「えっ!?1千の大将だって!?」
「1千の黄金!?おいおい本当か!?」
「こ、この俺が1千人の部下を持つ大将…うはは」
「へ、へっへっ、身分に関わらずとは、こりゃ恐れ入る御褒美だ!」
「なんだなんだ、こんな雨や風!俺のような雑兵が大将になれるなら屁でもないじゃねえか!」
「そうと決まれば膳は急げ!俺が一番だ!!」
「どけどけおまえら!オイラが一番乗りだ!」
ワーワーッ!
ワーワーッ!
キレイの放った破格の褒美は、ざわめく兵士たちの声を一瞬にして怒涛の喚声へと変えた!
それまで鈍重だった動きがまるで嘘のように、将兵たちは我も先へと進軍してゆく!
「おおお!き、キレイ様!兵がこぞって進んでいきますぞ!」
「お前は行かなくて良いのか?褒美は聞いての通りだぞ」
「は、ははは…ご、御免!先手を仕る!」
キレイの顔色を窺っていた副将ですら、馬の手綱を強めて、雄々しく腹を蹴り上げ、無謀とも呼べる速度で山を駆け上がってゆく。
「「「 オ オ オ ー ッ ! 」」」
それまで立ち往生するほど苦しかったはずの行く行く悪路は、すでに悪路では無かった。
ゆくゆく山道を物ともせずに進む将兵たちの姿を見て、キレイは俄かに鼻を鳴らした。
「ふん。過度の恐怖の鞭に慣れると、与える飴が事のほか美味く思えるものよ」
今考えて実行した、急ごしらえとは思えないほど的確な鼓舞。
実行する時を選ばぬ度胸と人間心理を良く心得るほどの観察眼。
天地天候に嫌われ、絶望と焦燥と隣り合わせになりながらも、これを実行できるキレイという人物は、己が自負する以上に天才であった。
官軍の将兵達は、妖元山の敵本陣へとあっという間に進軍した。
山中の天候は、吹いては飛ぶ女心のように変わりやすいものである。
さっきまで身を濡らしていた小雨が嘘のように、天候は不順に不順を重ね、山の下へ下へと吹き始めた逆風は山肌を削るように荒れ、当たる雨粒は身を弾くほどの豪雨に早変わりしていた。
「くっ…恐将歩めば山が泣くか。天め、この私が勝つのがそれほど疎ましいか」
悪天候の中、キレイは馬の手綱を強く握りながら呟いた。
キレイの特徴である赤で染められた甲冑と戦包(せんぽう)(合戦の時に身を包む厚手の戦闘服、または肩掛けの総称)は、雨粒を吸い込んで重みを増し、冷たくべったりと肌に付く布は疲労感を増幅させた。
「だがな。このような風雨に負けるほど、私は虚弱ではない。天よ見ていろ、見事敵の本拠を落として、悔し顔の貴様を笑ってやる」
だが、キレイの意思と騎馬の歩みは、逆境を跳ね除けるように少しも緩む事が無かった。
ぬかるみに歪む山道で、強風と雨粒が山へ人へ打たれる中、強く手綱を握られた騎馬は、ただ前へ前へと強く土を踏み、馬蹄は窪みに出来た池を弾いて行く。
そこへ、副将の一人が報せを告げようとキレイに近づく。
「御大将!そう足を急かされても、後ろの兵が付いて来れませぬ!」
「なんだと?」
キレイは、風雨に晒される顔面を右腕で防ぐと自分の後方を覗いた。
そしてキレイは見た。先ほどまで近くで雄々しく歩を進めていた率いる歩兵隊2千5百が、キレイから大分離れた岩肌の突き出した傾斜の悪路で立ち往生していたのを。
「あの程度の傾斜、何故登れん」
「岩肌が滑り、土は泥となって流れるような悪路。それにこの悪天候では仕方ありますまい」
「ええい、この程度の風雨で足を止まらせるな。甲冑を捨ててでも登らせよ。絶対に足を止めてはならんぞ」
「はっ…」
急ぎ攻め。こうまでしてキレイが進軍を速めさせる理由は、ただ一つだった。
奇襲、いわゆる備え無き敵の不意を突く作戦のためである。
敵に発見されないための進軍速度が重要である奇襲戦において、この進軍の遅さは致命的であった。参軍従事のタクエンが危惧したように、絶対的な守りに適した敵が、奇襲を知り、備えを本腰にして構えれば、数で勝っていても勝てる見込みなどない。
「急がせよ…見つかっては奇襲の意味がない」
しかしその時、山道の先に存在する妖元山の高台から、数人の影が散るのが見えた。
― 妖元山採石所 頂天教軍 本陣 ―
「アカシラ様!教祖様!大変です!敵がやってきます!」
妖元山上部。
鉱石を産出するために切り開かれた採石所は、篭る頂天教軍によって山塞(さんさい)と化していた。強い雨音が聞こえる石室に、怪しげな衣服を纏った一人の男が座っている。
「ヒャッヒャッ…こんな悪天候に、どこの馬鹿じゃあ」
「遠目ですが、中央道より官軍の歩兵が数千ほど」
「ヒャッヒャッ…悪天候に紛れて奇襲のつもりかのう。それで、他の物見の兵はどうしたんじゃあ?」
「はっ、各所に報せをと、走り回っております」
「ヒャッヒャッ…それは、いかんのお。全員戻らせるんじゃ」
「はっ…しかしそれでは敵軍が本陣を」
「ヒャッヒャッ…いいんじゃ。いいんじゃ。敵が取りたきゃ取らせれば良いんじゃ。愚かな奴らの願いが叶えられて、絶頂を迎えたところを…虫けらのようにクイッ!っと叩き潰す…のぉ?」
「では、アカシラ様には何かお考えがおありで…?」
「ヒャッヒャッ…ほれ、これを配ってこい。お前は諸将にこれを読ませて、その通りに遂行させるんじゃ。少し経てば、わしの奇跡を間近で見れる。良いものじゃぞぉー」
「ははっ、それでは伝えてまいります」
石室の中央に、燃え盛る蝋燭を何本も周りに立てて書き物に熱中していた男は、歯茎がむき出しになるほど声高に笑うと、やってきた頂天教軍の兵士達に一巻の巻物を渡し、そう告げた。
「ヒャッヒャッ、まずいのう。実にまずい。小さく弱い虫を殺す時に限って、どう捻り潰そうかと思考が冴えてしまうのう。このように老いを感じる歳になっても、益々冴える。ヒャッヒャッ…いやー、まずいのう!」
初老を迎えた男は、誰も居なくなった石室で、ただケタケタと笑い続けた。
妖しげな衣服を身に纏った男の名前は、アカシラ。
帝国に対し乱を起こした首謀者、頂天教軍の最高司令官にして、長らく官軍が適うことが出来なかった頂天教軍随一の知恵の持ち主である。
― 妖元山 中央山道 ―
その頃、敵に見つかったことなど露知らない官軍歩兵隊たちは、立ち往生と緩やかな進軍を繰り返していた。キレイの思い描く、神速をもっての奇襲戦法の意図とは反対に、進軍は難航を極めた。
ザァー!ザァー!
ビューッ!ビューゥ!
「うわーぁ!吹き飛ばされる!」
「なんて逆風だ!一歩前へ出るだけでも辛い」
「か、風も強い!わわわ、吹き飛ばされそうじゃ」
容赦なく吹き付ける逆風が兵の体を止め
ズザザーッ!
ガラガラガラッ!
「あっ、また一人転んだぞ!」
「こう道が悪くちゃ仕方ないさ…うわっ!」
「く、くそ。このままじゃ敵と戦う前に疲れちまうぞ」
豪雨と兵の足によって山道の柔らかな土が捌けられ、剥き出しの岩肌が足を滑らせ
ゴロゴロ…カッ!
バリバリバリ!
「ひええ、また光ったぁ!
「ブルブル…雷怖いよぉ」
「い、戦で死ぬのはいいが、雷に当たって死ぬのは嫌だなぁ」
山上に差し掛かる黒雲は雷雲となって、そこから落ちる雷光と響く雷鳴は、おびただしい光とけたたましい音を兵士の目と耳に轟かせる。
「ええい!進め!進まぬか!」
キレイの怒号に似た号令が雷光を背景に飛ぶ。
だが将兵達は足を早めるどころか、不安定な足場に一歩ずつ足場を確かめながら進軍しなければならなかった。また、転んで打ち所悪く死者も出始めたことから、士気も上がらなかった。行く時は天を突くほどの勢いだった兵士達の意気は下がりに下がり、度重なる疲労感を含めて、その士気は今や崩壊寸前であった。
「ぬうう…このような鈍足では、奇襲の意味がない…」
「キレイ様!駄目です、兵達は皆風雨に晒されて士気は落ちる一方。ここは、いったん出直しましょう。天候が回復した後、攻め入るのが良いかと思われまするが」
「そのような事が出来れば、とうにやっておるわ馬鹿者め」
「しかし…」
「ここで後退すれば山中の敵が察して出陣し、追撃の格好の餌食になってしまう。大打撃の負け戦を演じるつもりか?」
「そ、それはたしかにそうですが」
「それに引いて惨敗するなど、このキレイの心が許せん!どの道、勝利するためには行かねばならんのだ!進め!進むのだ!何を犠牲にしても進めぇ!」
冷静さを欠き、雷鳴と同じほど憤るキレイは、恐怖の視線と狂気の口調に満ち溢れ、いわば逃げ腰気味だった副将の下唇を思わず強く噛ませた。
そして副将は風雨の中、手を高らかに振り上げ、今まであげたことの無いような大声を放ち、難航する兵達を急がせようと捲し立てる。
「す、進め!進めーーー!」
副将は、この男の言う『犠牲』の意味を恐怖と焦燥の中うすらと感じていた。
逆らえば明日の命もわからないという、その恐怖の鞭が副将にも染み付いていたのだ。
「疲労も多いが勝てるはずだ。幸い、黒雲と雷鳴で我らの姿と音は消えておるのだ。その証拠に敵の陣の灯火が見えんではないか。ははは、まだ勝てるぞ!」
キレイは、眼をクワッと大きく開くと、再び手綱を握り、ただ前へと進んだ。
無意識の焦りが、キレイにはあった。脳裏にタクエンの言葉が焼きついていたからだ。
(…ふざけるな!…私が負けて奴に笑われるわけにはいかんのだ!)
矮小な意地が、キレイの心を塗りつぶす。
自分自身、悪天候に苛まれれば危険を伴うと思っていただけに、タクエンの言葉が痛烈に勝利への意地を増徴させる。他人に自身の才能を鼻にかけ傲慢になりながら、他人に優越たる才能を否定されて笑われる事を嫌う。
…負けるわけには。
…負けるわけには、いかなかったのだ。
そのキレイの気持ちとは裏腹に、傲慢にも参謀タクエンの進言も聞き入れず、頑なに山攻めを敢行したキレイの軍に、天地は罰を与えるように味方しなかった。雨と雷は止まず兵の体を脅かし、風と水は進軍を妨げ、行くも戻るも難しく、立ち往生した将兵達は、いつ敵に襲われるのではないかと、差し迫るその絶望感を味わった。
天地に嫌われた、キレイの歩兵隊は孤立した。
「皆の者、良く聞けい!!」
だがキレイは、ただその場で立ち止まり、ただその場でうずくまる様な男ではない。
龍は雷鳴の波を泳いでこそ龍であり、天を逆らって昇るからこそ龍なのである。
キレイは知っていた。こういう時に、どうすれば良いかを。
足を止めて進まない兵士達に、何が『足りない』のかを。
キレイは叫んだ。
「誉れ高き官軍の強兵達よ聞け!そして見よ!あの雷鳴の先に見えるのが敵の陣だ!あと少し!この苦難もあと少しだ!タダでとは言わん。将も兵卒も身分に関わらず、敵の陣に一番に攻め込んだ者には、褒美として1千の黄金!大将首をとった者には、褒美として1千の部下を率いる大将の地位を約束するぞ!このキレイが声高に言うのだ、間違いは無いぞ!」
風雨と稲妻を遮るように、兵士達の耳に通ってゆくキレイの声。
ザワザワ…
ザワザワ…
「えっ!?1千の大将だって!?」
「1千の黄金!?おいおい本当か!?」
「こ、この俺が1千人の部下を持つ大将…うはは」
「へ、へっへっ、身分に関わらずとは、こりゃ恐れ入る御褒美だ!」
「なんだなんだ、こんな雨や風!俺のような雑兵が大将になれるなら屁でもないじゃねえか!」
「そうと決まれば膳は急げ!俺が一番だ!!」
「どけどけおまえら!オイラが一番乗りだ!」
ワーワーッ!
ワーワーッ!
キレイの放った破格の褒美は、ざわめく兵士たちの声を一瞬にして怒涛の喚声へと変えた!
それまで鈍重だった動きがまるで嘘のように、将兵たちは我も先へと進軍してゆく!
「おおお!き、キレイ様!兵がこぞって進んでいきますぞ!」
「お前は行かなくて良いのか?褒美は聞いての通りだぞ」
「は、ははは…ご、御免!先手を仕る!」
キレイの顔色を窺っていた副将ですら、馬の手綱を強めて、雄々しく腹を蹴り上げ、無謀とも呼べる速度で山を駆け上がってゆく。
「「「 オ オ オ ー ッ ! 」」」
それまで立ち往生するほど苦しかったはずの行く行く悪路は、すでに悪路では無かった。
ゆくゆく山道を物ともせずに進む将兵たちの姿を見て、キレイは俄かに鼻を鳴らした。
「ふん。過度の恐怖の鞭に慣れると、与える飴が事のほか美味く思えるものよ」
今考えて実行した、急ごしらえとは思えないほど的確な鼓舞。
実行する時を選ばぬ度胸と人間心理を良く心得るほどの観察眼。
天地天候に嫌われ、絶望と焦燥と隣り合わせになりながらも、これを実行できるキレイという人物は、己が自負する以上に天才であった。
官軍の将兵達は、妖元山の敵本陣へとあっという間に進軍した。











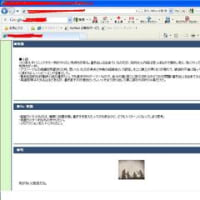







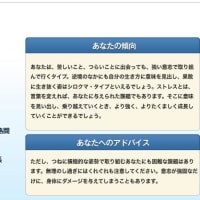

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます