ピロピロピーピロピー♪
「な、なんだこいつ…!」
理屈で攻略できないボスの存在。
最終面。ステージボスとの対決を意味する電子音は同じなのだが、そのボスキャラクターの質が、今までとまるで違う。悪質というか、悪辣というか、とにかく常軌を逸して強い!おそらく、これを作った製作者の性格がひん曲がっているとしか思えない仕様だ。
「そいつが、ラスボスの『三月鼠』。こいつがまた偉く強いんだわ」
そう男が言った時、すでに私のキャラクターは地を転がって天使の輪を浮かべていた。
ステージボスと出会ってから、すでに1時間ほどが過ぎていた。通算対戦回数51回にして気付いた法則。『三月鼠』の技と行動パターンは、おそらく一つしかない。それは、以下の通りだった。
①開始直後に画面中央へ大ジャンプ。
②素早く2×2ドットの七つの誘導弾攻撃。
③着地と同時に左右に5×5ドットの火柱攻撃。
④その場に数秒間停止し、自分の操作するキャラに向かって走って体当たり。
⑤両端一方の壁に張り付き、滑り降りながら①の行動に戻る。
おそらく行動パターンさえ読めば、攻略が可能だと思っていた私が、死亡すること51回目にして気付いた、このボスキャラクターの真の恐ろしさ。それは…
「こいつ、攻撃がまったく通用しないじゃないか!」
驚くべき事に、この『三月鼠』には、自分の操作するキャラクターの一切の攻撃手段が効かない。隙を見て何度か武器を放つのだが、キンキン!と弾くような電子音が聞こえるだけで、まるで効いていない様子だった。効く武器があるのか?と仮定して、あらゆる武器を試したが、その都度実験は失敗に終わる。あれだけあった残機が、見る見るうちに消えてゆく。無常に流れる、ラストステージの電子音。気付けば、自分の操作する残り機数は、3機。
しかし、前向きになれるような打開策も未だ発見できず。絶えず迫り来る鬼畜とも思えるステージ構成、そして何よりラスボスの存在が、状況を絶望的に塗り替えた。私は、心が折れて、泣きそうになった。理論で突破できないほど、敵が強かったからじゃない。ここでゲームオーバーを迎えることが即ち、男から見た私の敗北を認めるようで、ただ悔しかったのだ。一度でも私が、敗北をその身に感じてしまえば、今まで他者を突き放し、高まる自負心、プライドという己の作った防壁に逃げ込むことが途端に出来なくなる。他人を虐げることで悦楽を感じている、サディストとは名ばかりの寂しがり屋。実はそれこそが、私なのだと気付いた時には、また一つ残機が減っていた。
「…」
いつの間にか、ゲームに怯えていたのは、私の方だった。
コントローラーを持つ手には力が無くなり、目には真剣味が薄れていた。ただ自嘲するように緩慢なプレイをしてしまう。隣の男は、それをどのような目で見ていたのだろうか。私は、残り一機となったところで、ゲーム画面にポーズもかけず、ただゲームを投げ出すように、操作を放棄した自分のキャラクターに死をくれる敵の出現を待った。
だが、その時だった。
「おい!ふざけんなよ!諦めて死ぬとかお前らしくねえよ!」
「え…どういう…」
「いいから、コントローラー貸せ!」
男の語気から見える、明らかな苛立ち。
何故?あと数秒もすれば、残機が無くなってゲームオーバーになって、同時に私の敗北と、男の勝利が確定するというのに。いったい何故なの?
勝手気まま、野放図に、無造作に、私の手に置かれていたコントローラーを奪った男は、画面にポーズをかけ、暗転となった画面を見ながら、十字キーを数回動かし、設置された二つのボタンを一定のリズムで打ち出し、何かのコマンド入力処理を行った。すると…
ピロリロリーン!
「えっ…」
ゲームを開始してから数時間は経っているのに、聞いた事も無い奇妙な電子音。
事の次第にわからない私は、画面を見回した。すると、今まで表示されていた自分のキャラクターの体力ゲージの横に、もう一本。同じ色の体力ゲージが用意される。そして画面上には、別色で塗られた操作キャラクターが居た。
「…な、なんだこれ?」
「協力プレイ!見りゃわかんだろ!頭でっかちに、ラスボスの攻略法も教えてやる!」
「わ、私は別に、このままゲームオーバーで構わんぞ!」
「ったく、素直じゃねえなあ、お前も…俺がお前の勝ちを手伝ってやるっていってるんだよ!」
「い、良いのか?きょ、協力プレイで倒しても、お前に土下座はさせるが」
「ああ、いいよ!このまま煮え切らないプレイで終わっても、ゲーマーとして面白くねえからな!」
いつにも増して熱く、優しくも感じられる、男の言葉。
だが良く考えてみれば、土下座するのを覚悟でゲームクリアをするというのも、どうなんだ。…こいつ、そんなにサディストな私に攻めて欲しいのか?世間一般で言う、いわゆるマゾなのか?と、無粋な思考に陥りながらも、私は男から手渡されたコントローラーを握る手に力を入れた。不思議とさっきまで感じていた絶望感は無い。付かず離れず、男が隣に居るという感覚からだからだろうか。そして、その時、男が放った言葉を、私の耳は捉えて離さなかった。
「それに、諦めてゲームオーバーされて逃げられたんじゃ、俺がお前を誘った意味ねえだろ!」
「…え?」
「いいから、さっさとやるぞ!まずはラスボス前の敵の駆除からだ!」
「あ、ああ…」
言葉の意味は良く判らなかったが、隣の男は確かに本気だった。
このゲームに対してそれほど愛着があるのだろうか、それとも捨て鉢になった私を許せない理由があるのだろうか。だが、今まで一人で進めてきたゲームを二人でやるのは心強い。とにかく今は何も考えず、二人でボスを攻略して、二人でゲームクリアを目指そう。
「そこっ、右から敵沸くぞ」
「そんな事ぐらい、わかってる!」
「大ジャンプ、私の動きにあわせろ」
「冗談きついぜ、お前こそ落ちないように気をつけろよ」
「上から来るぞ!おいおい、お前体力やばくねーか?」
「わかってる。次のポイントで回復できる。下は私に任せろ!」
「しまった!ダメージを喰らいすぎた…」
「俺のキャラの後ろを歩け、大丈夫。もうすぐ回復アイテムだ」
おそらく通常時と比べて三倍以上の効率。一人が傷つけば一人が回復アイテムを譲り、一人が壁を壊せば、一人が敵を駆逐する。一人プレイでは味わえない、まさに二人プレイの協調という名の美徳。体力もアイテムも減らさずに、ボスステージ手前までガンガン進めることは、私の不安を払拭するのには十分だった。それよりも驚いたのは、私と男が、意外にも息が合うのだ。いつもは二人とも馴れ合いを嫌うような人間なのだが、コンビプレイという観点から言えば、その実、性に合っていたのかも知れない。今、この空間に居る二人の心は、ゲームという存在を媒介にして、俄かに交わりかけているのかもしれない。
「ラスボス、来るぞ!」
「攻略法を早く教えろ。でないと足手まといになる」
「あいつは、前からの攻撃に無敵なんだ。だから挟むようにして、隙を見て背中から攻撃を連打すれば、必ず勝てる!」
「そうだったのか!よし、いくぞ!」
二人プレイ必須とも思えるラスボスの構成。
このゲームソフトを作った人は、そう考えているのではないかと思うほど、ラスボスに対して二人プレイは必勝法だった。あの最高の難易度を誇っていたラスボスに、ダメージ効果である画面の点滅が出るほど、私は声高に「よし!」「やった!」と子どものように声を張る。優等生としての仮面、女の子として体裁、そんな煩わしいものを全て忘れた、ただ純粋な無邪気さが、今の私には、あった。
「これで最後ォォォ!」
ポン!バーン!
「や、やった勝った!やったぞ!私達やったんだ!」
そして、ついに画面のまがまがしい点滅と供に、ラスボスを撃破した私達。
私はコントローラーを置いて、思わず男の手を握って声をあげて喜んだ。その時の私は、すでにプライドも何もなかった。ステージをクリアした。その、達成したという純粋な喜びが、アドレナリンを放出させ、あらゆる脳内快楽物質が、全身を駆け巡っていたのだ。手を握られた男が、少し照れていたのがニヤケ顔の隙間に見えたが、その後すぐに、勝利の余韻に浸るために甲斐甲斐しく画面を見守りだした男の顔は、少しカッコよく見えた。
音の少ない三音の電子音と供に、浮かび上がるエンディング画面。
最終目的であった囚われの姫を持ち上げ、今まで操作されていたキャラクターが、操作の糸を離れて、自由に動き出す。ドット絵でもわかる可愛らしく踊る姫と主人公。おそらく数十年前には、感動と呼ばれていたであろうその画面を、私達は一緒に見ていた。男のほうは、なぜだかソワソワしていた。なぜだ?何かEDに内包された意味が、あるのだろうか。
そして私は、次のED場面で驚くべきローマ字の表記を目にした。
『GOOD LUCK!! ORE NI TOTTE DAIJI NA HITO YO!』
スタッフロールに書かれた一文の最後、名前の表記があり、その名前を私は知っていた。
隣に座っている、男の名前だった。
「え、これ…」
「悪いな騙して。俺って、こういう告白とか苦手だから」
「どういう意味?だって十年くらい前のゲームって…」
「得意分野でも無いのに、これでも調べ物しながら作って、結構大変だったんだぜ?」
「そんな…私、そんなの聞いてない」
「不意打ちだけど、俺みたいな文系の男が、お前みたいな理系の女の子を口説くには、これしかないと思ったんだ。そこんところ、よろしく加点お願いしますよ」
「…はい」
私は、いつの間にか、恋愛というゲームの始まりを予感していた。
しかし、二人の恋愛というゲームのスタート画面は、『土下座』からだった。











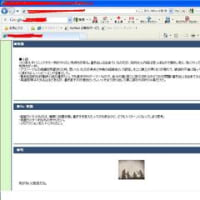







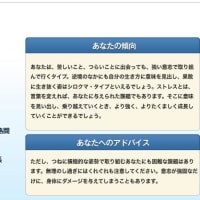

たかがゲーム、されどゲーム。ゲーム描写が論理的でかつ小難しいものになっているので、読んでるこっちが神経集中して一緒にゲームやってる気になってくるのが面白かった。
オチのどんでん返しで、いきなり恋愛にもってかれちゃうのはびっくりしたが、そうなるんなら序盤で少しばかりそのエッセンス。たとえば彼がほれてるんだったらそういう描写を一言でも、いっこの動作でもを(いつものドSな感じでいいからさ!)入れてくれると最後のカタルシスが大きかったのではと思うとおしいあともうちょっと見たいな感じでした。
個人的には萌えることができたので満足しました。