1、笑わない男
ゆるく吹き付ける海風が、潮の香りを運んでは消えていく。
まだ朝方は肌寒く感じられる4月の空の下、一直線に続く長い海岸線を行きかう様々な車両たち。
軽自動車。ワゴン車。路線バス。クレーン車。
路上清掃車。長距離トラック。コンテナ運搬用トレーラー。
バイク。
そこには、今日も普通の世界が広がっていた。
「……」
自動販売機の前で、カポッという缶コーヒーのプルタブを開ける音が聞こえた。
その音の先には、黒のジャンパーに身を包み、黒いヘルメットを左手に抱えた男が、物思いにふけるように缶コーヒーを飲んでいた。
「……にが……っ!」
目が覚めるような苦い味。というか、香り以外は苦味しかない。
男は、口いっぱいに広がる苦味に堪えられないのか、この世の破滅と言わんばかり目を瞑り、眉間に皺を浮かべた渋い顔をして、ゆっくりと手にとった温かい缶コーヒーを顔のところまで持ち上げる。
まだ湯気の立つ缶コーヒーのパッケージを見る男が、うっすらと開けた目には、ブラック無糖の文字が見えた。
「また間違えて無糖買っちまった……」
男はそういうと、路上にヘルメットを置き、どこからか片手で手掴みできる程度の空の水筒を取り出した。
「苦いのは、いつまでたっても慣れないもんだなあ」
男は水筒の蓋をあけると、ジョボジョボと音を立てながら缶コーヒーの中身を水筒の中に入れ始めた。
黒い液体の合間に見える白い湯気が、香りを男の鼻に運ぶが、男はその香りがするたびに苦い味を思い出し、渋い顔を遠ざける。
やっと缶コーヒーの中身全てを注ぎ、水筒の蓋を閉めると、男は路上に置いたヘルメットをかぶり、スッと立ち上がり、やや急ぎ目に歩き出した。
男の向かうその先には、海岸線の内側車道に止めてあったオフロードバイクがあった。
男は駆け足気味にバイクに飛び乗ると、鍵をひねり、エンジンをかける。
「しゃあねえ、口直しに行くか」
エンジンのかかる音が聞こえ、アクセルレバーに手を沿えながら男が呟く。
そしてバイクは、けたたましい音をたてて、一直線に続く長い海岸線を駆け抜けていった。
――――――――――
「うぅ~ん。いい朝だ。今日も何事もない、平和な朝を迎えられて神様に感謝します……っと」
やや潮の香りが薄まった海風を受けながら、補整されたアスファルトの道の上で、腰に黒い前掛けをつけたヒゲ面の中年の男が大きく伸びをして、太陽の方向に向かって礼をする。
「さあてと。今日も日課、始めますか」
ゆったりした白黒のチェックシャツはヨレヨレで、襟から覗ける濃紺のインナーシャツ、使い込まれたシックな茶色のジーンズで身を固めた中年の男。
彼は今日も日課である自慢のレンガ囲いの小さな家庭菜園の様子を見に行った。
「もうちっとばかし暖かくなればなァ。お前たちも大きくなって、あいつに食わせてやることも出来るんだがなァ」
弱い陽射しとヒンヤリとした空気の様子を肌で感じながら、嬉しそうにじょうろで水をやり、菜園の生き物たちに声をかけると、彼は次の日課にとりかかった。
「朝のお仕事……っと」
菜園を去る彼の目には、伐った丸太をそのまま使ったような、古びたロッジ風の建物が立っていた。
海風を受けるこの街に似つかわしくない建物の入り口の中に入る男。その男の頭上には楕円形の木製看板があり
その看板には『喫茶Sunrise/Sunset』という名前が刻まれていた。
入り口のドアを開けると、カランカランという綺麗な鈴の音をたててウェルカムベルが鳴り、男が仕掛けておいた水出しコーヒーのいい香りが店内に充満していた。
「さてと、何からやりますかね……っと。そうだまずは」
男はサッとジーンズのポケットから安全ピンのついたプラスチックケースの中に収められたネームプレートを取り出した。
そこには『伊崎洋一郎』という彼の名前と、この喫茶店のオーナー兼マスターであるという情報が書いてあった。
「これをつけないとサマにならないよねえ……っと」
うっすらと窓から差し込む陽光をバックに鏡を見てニンマリと笑う伊崎は、今日も自身の喫茶店の開店準備を始めた。
ブルルルル……!
伊崎が作業を始めようとした時、道路から一台のオフロードバイクが喫茶店の敷地の中に飛び込んできた。
ゆっくりと敷地内に停車したバイクから降りる黒のジャンパーを着た長身の男を見て、伊崎は表情をゆるめながら、つぶやいた。
「お、ありゃまさか……」
バイクからキーをぬき、ヘルメットを脱いで座席にしまい、首まであがっていたジャンパーのチャックを一気に開ける男は、窓際から見つめる伊崎の存在に気付いたのか、軽く手をあげながら、喫茶店のドアを開く。
「おっす。マスター」
伊崎を良く知っている割には、笑うでもなく、ただ手をあげたまま愛想のない真顔で店内に入る男。
「相変わらずだなぁゲラオちゃん。まだ開店前だってのに」
ウェルカムベルの音とともに、伊崎はゲラオと呼んだ男の無愛想な顔を見て、笑顔で迎えた。
その名前を聞いて、ゲラオは不愉快そうな口調でいう。
「マスター、いい加減その名前やめてくれないか。俺には御山サクヤって名前があるんだから」
「いいじゃないの。今も昔もゲラオちゃんは、ゲラオちゃんだよ」
「くっ……」
にこやかな伊崎に比べ、愛称であるゲラオという名前があまり気に入らない御山。
伊崎は、御山の姿を見ながら、カウンター席の内側で開店準備を続ける。
「で、ゲラオちゃん」
「なんだよ」
御山は、不愉快な表情のまま、ドカッと悪態をつくように勝手にカウンター席に座ると、ジャンパーのポケットから水筒を出し、テーブルに置く。
「今日は何しにきたの……って。まさかまた」
「ああ、口直し。勝手知ったるなんとやら。マスター、カップと砂糖借りるぜ」
御山は、カウンター席においてある厚手のコーヒーカップをまるで自分の物のように手に取ると、コポコポと水筒の無糖コーヒーを注いでいく。
「あーあ。やだやだ。見たくない見たくない」
御山が気に入りの水筒を出した時点で、何かを察した伊崎が、今までにこやかさが嘘のように、一気にしかめっ面になる。
ザッ、バサッ。
ザッ、バサッ。
そして、喫茶店には、砂を掻きこんでは放るような音が聞こえた。
御山の前には、喫茶店自慢の、内蔵量300グラムは入る陶器で出来た大きめの砂糖入れ。
御山の手には、カレーなどを食べる時に使う、やや大きめの平たい銀製のスプーン。
そして、そのスプーンには、明らかに尋常ではない量の砂糖の山が盛られていた。
「甘くなーれ、甘くなーれ。もっともっと甘くなーれ」
呪文のように口ずさむ御山の手は、素早く、そして手際が良かった。
そう。
先ほどの砂を放るような音とは。
御山の手によって、コーヒーカップの中に、大量の砂糖が放り込まれる音だった。
一杯。
二杯。
三杯。
四杯。
五杯。
「あ。ああ。あーーあー。あ~あ~あ~あ~。やめてくれ、コーヒーがだめになる。ゲラオちゃん。もうそのへんでやめてくれないか!」
眉をひそめた伊崎の、苦虫を噛み潰したような顔がさらに歪む。
それを尻目に、御山は無言で砂糖を放り込み続ける。
六杯。
七杯。
八杯。
九杯。
十杯。
「よし、この辺でいいだろう。いい塩梅だ」
カップをスプーンで素早くかき混ぜ始める御山。
すでにコーヒーであったカップの中の液体は少なく、かき混ぜることによって、液体というより、ややゲル状に近い存在となっていた。
「ふう。さて飲もう飲もう」
コーヒーカップの縁には、まだ固形のまま残る砂糖。
コーヒーカップの中には、コーヒーであったはずの悪魔の飲み物。
自分の唇まで持っていって、グイッと傾け一気に飲み干す御山。
「……甘い。これだよねコーヒーは。甘いっていいよねマスター」
常人には黒い毒物にしか見えないそのコーヒーを、喜ぶでも苦しむでもなく、あくまでも真顔でグイグイ飲んでいく御山。
「ゲラオちゃん。そんな、あきらかに体によくない飲み物を、よく真顔で飲めるね……うぷ。いやだ、いやだ」
それを見ていた伊崎の心には、すでにさわやかな朝の気分など消え、胸焼けと胃の痛みで気持ち悪さを覚えた。
数十分後。
カウンター席にいる御山を見ないように、さっさと開店準備を終えた伊崎が、ふとテレビをつける。
「この奇怪な連続殺人事件についての警察の見解は……」
映像には、伊崎と御山が良く知る街が映っていた。
「被害者の体液は全て抜き取られているところから、その残忍な犯行から犯人は猟奇的な……」
テレビの中継から流れる女性アナウンサーの声が、伊崎と御山の耳に入ってくる。
「ふんふんふーん」
事件が起きているのがこの喫茶店からそう遠くない場所だというのに、鼻歌交じりに割と気にしていない伊崎。
それに比べ、カウンター席から報道が伝える事件の概要を、マジマジと食い入るような眼差しでじっくり聞いている御山。
「マスター……この事件いつからだ?」
御山は、椅子にかけていた自分のジャンパーをそっと取ると、伊崎のほうを見て言った。
「あー、これね。今月からこの近くで起きてる連続殺人事件」
「たった十日で、十一件もの連続殺人か……」
「なんかね。街中で襲われるらしいんだけど、短時間で犯行が行われてるらしくて、犯人が使う凶器も証拠も、目撃者もいないから警察も犯人を特定できないんだって話」
「……街中で襲われているのに証拠もない。まさか、な」
眉間を険しくさせる御山が、ジャンパーの袖を通す。
「被害者を死なない程度の毒物で弱らせて、死体から血を抜き取って衰弱させて殺すんだって。怖い人間もいたもんだね」
「……」
「『現代に蘇った吸血鬼』なんてゴシップ記事もあるぐらい、事件が起こる前はこの世も平和だったってことかね……っと。まあ、ゲラオちゃんも気をつけないとなァ」
視線をテレビ映像から御山にやった伊崎。
その声が御山のところに届く前に、御山はジャンパーを着込み、チャックを首のところまでしっかり絞め、いつの間にか席を立っていた。
「マスター。意外と人間の仕業じゃないかもしれないぜ」
さっきまで普通に喋っていた御山の声が、やや低くなって伊崎の耳に聞こえた。
「ん、ゲラオちゃん。そりゃ、どういうことだい」
「ごちそうさん。なんかあったらまた寄るよ」
意味深な台詞に浮かんだ伊崎の疑問に答えることなく、御山はそそくさとドアを開け、店を出て行った。
笑いもせず、来た時と同じ愛想のない真顔のまま。
ヘルメットをかぶり、自前のオフロードバイクに飛び乗り、けたたましいエンジン音とともに海岸線道路に飛び出て、そのまま街に向けて走っていった。
まるで何かに急かされているようなスピードで。
「あーあ、いっちゃったよ」
伊崎がカウンター席に置かれた飲み干されたコーヒーカップを手に取りながら、すでに消えてしまった御山の姿を追うように、陽光の射す窓を見つめる。
「それにしても……いつからだろうね。ゲラオちゃんが、あんなに笑わなくなったのは……」
カップを片付け始めた伊崎の視線の先には、一枚の写真が飾ってあった。
そこには、まだヒゲをはやしていない伊崎と。
幸せそうに満面の笑顔を浮かべ、腹を抱えて笑う、御山の姿があった。
――――――――――
高層ビルが立ち並ぶオフィス街には、日の昇る朝を境目に色々な人たちがまばらに集まり始めていた。この場所に街が出来て、人が住んでから、何度も繰り返し行われてきた時間と人間の営み。その始まりが、うっすらと見えてきた頃。
「……」
とある高層ビルの屋上へリポートに、黒の帽子、黒のサングラス、黒の皮ベルト、全身カラスのような黒の衣装に身を纏い、無言でたたずむ謎の女の姿があった。高層ビル特有の上空に流れる強い風で煽られてはいるが、女はまるで微動だにしない。
「来たか……」
黒いルージュに浸された唇がゆっくりと開き、白い手袋をスッと自分の顔の前に出す女。その言葉の後に、女の後方でドサッと大きなものが着地する音が聞こえた。
「大いなる闇の洗礼を受けしモノ。屍食蜘蛛、プロリフェレ・スパイダー」
女の後ろには、いつの間にか異形のモノ達があふれかえっていた。
「グェッ……グェッ……」
異形のモノ達の口や手には、すでに人間のものであろう血のりがべったりとくっ付き、地面へと垂れ始めていた。
「そうだ、それでいい。お前たちは人間の生を奪い、殺ぎ、喰らい、増え。初めて、その生を実感できる存在。秘密結社Dに忠実なケダモノだ」
白手袋を横に流し、女がゆっくりと振り返る。
強く吹く風になびく黒い衣装が、照らされた日の光の後ろに黒い影をつくる。
その黒い影を縫って、かすかに反射する無数の赤い複眼。
「グエッ……グエッ……」
見た目は蜘蛛そのものだが、ヒト一人分はゆうに超える巨大な体を持ち。
口にはメタリックな銀色を放つ強固な鎌状の牙、細い体毛のついた赤黒い八本の足先には、獰猛で鋭い爪が生えている。
その怪物たちの姿を見て、ニンマリと不気味な笑みを浮かべる女は、再び振り返った。
今まで横に出していた手を下ろし、今度は白手袋からスッと伸びた人差し指で、人間たちが集まり始めた高層ビルの下界を指した。
「目の前に広がる全てがお前たちの餌場だ。生きるもの全てを奪い! 殺ぎ! 喰らい! 増えろ! ……行け!」
「グエッ!」
女がそう言うと、蜘蛛の怪物たちは声をあげ、腹部にある突起から強固で滑らかな糸を吐き出し、それを縁にかけ、次々と高層ビルの谷間へと降下していった。
女はそれを見ながらニヤッと笑い、ヘリポートをゆっくり歩き始めた。
「世界の歪みよ……広まれ。すべては秘密結社Dのために……」
風に吸い込まれる霧のように姿を消す女の微笑みは、邪悪に満ちていた。











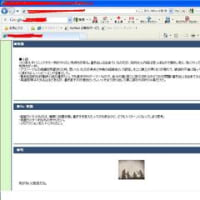







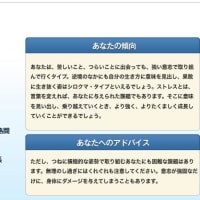






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます