2、変身
「仕事。だるいなあ……」
ブツブツとつぶやく男。
外資系の貿易会社に勤めるサラリーマンの男は、ややくたびれた黒のビジネススーツに身を固めながら、関係書類が入った薄いカバンを持って階段をのぼっていた。
「なんでこんな日に限ってエスカレーターは故障中なんだよ」
イラつく男の視線の先、階段の横には、でかでかと故障中と書かれたエスカレーター。
都市部に行き交う、いくつもの路線のターミナル駅として活躍する駅の地下から地上に出ようと、100段以上あるやたらと長く広い階段をのぼり始めた男の顔には、うっすらと汗が浮かんでいた。
男のまわりには、これから仕事に向かおうとする大量の人、人、人。
急なエスカレーターの故障で階段をのぼるはめになってしまった、憂鬱な人たちばかりが、ただ導かれるように地上の光を目指していく。
いつもの朝なら味わうはずもない階段をのぼるという徒労感。
循環されていない地下の空気が鼻腔と肌を撫でていく不快感。
これから仕事に向かわなければならないという憂鬱からの虚脱感。
「朝からついてないことだらけだぜ」
ついてないとつぶやく男は、長袖のシャツににじむ汗を背中に感じながら、やっと階段の先にある出口にたどり着いた。
しかし、この後に起こることについて、彼が本当についてないと思うには、少々……時間が足らなかった。
「うわぁぁッ!」
悲鳴。
オフィス街に続く出入り口に響く、異色の音に振り返る人たち。
地下からのぼった階段の先、その朝日が覗きこむ出口の先。
たしかにそこには、今の今までサラリーマン風の男が立っていたはず。
だが今、そこには誰も、何もいない。
「きゃあぁッ!」
再び悲鳴。
ガコン、と地上との空気交換用に設置された地下鉄のダクトの蓋が外れる音がしたあと、せこせこと階段をのぼっていたヘッドフォンをかけた女がその場から消えていた。
「どうしたってんだ、いったい。ぐわッ!」
野太い声。
今度は、それまで額から噴出していた汗をぬぐい、悲鳴のしたあたりに振り返った汗かきの着流しの男が、グサッと何かが刺さる音を立て、またその場から消えていた。
「……なになに、なんだっていうの!?」
不安感を感じたOLが、階段の先の出口を急ぐ。
悲鳴のあと、人間がその場から消えるという、あきらかな異常。
自分にも訪れるかもしれない『見えない』という未知への災いは、ただただ彼女の心を恐怖へと追いやる。
「ギャアッ!」
再び男性の悲鳴。
それが彼女の耳に入り、またそこに立っていた人間が消える。
一刻でも、一秒でも速く、その場から立ち去りたい彼女の気持ちは、逃亡という行動となってあらわれる。
カツンカツカツッ!
ヒールが地面を叩くけたたましい音。それは足早な彼女の恐怖心を表すものだった。
苦労してのぼってきた階段を駆けくだり、ありとあらゆる人の中をかきわけ、かわるがわる変わる背景。そして後ろから聞こえる、人間の悲鳴。
いつしか。
彼女の顔には。
恐怖しかなかった。
シュルシュルシュル……
「……!?」
その時、彼女の首に違和感が走った。
長く束ねられた白い糸のようなものが、自分の首に強く巻きつく。
彼女の顔は徐々にその苦しさを増し、手は、苦しみを解くために巻きついた糸をガッとつかむ。
だが、振り解こうと思っても巻きつきは強く、ちぎろうと思っても、粘着質な糸は彼女の込める力に反発するように締め付けを強くする。
「……ンッ!!」
あたりの人に助けを呼ぼうにも、後ろから巻きついた頑丈な糸が首を絞める力を増し、彼女の声はカエルのような濁った悲鳴しかでなかった。
グイッ……
そして糸は、彼女の体を強く引っ張る。
引っ張る、というより、首ごと体を吊り上げるような、恐るべき力で。
彼女は最期の抵抗とばかりに足に力をいれてその場をするが、力に負けて、彼女の体が宙に浮くと、一瞬にして構内の天井に吊り上げられる。
「……!!」
首を絞められ、体全体が酸欠状態に陥った彼女が最期に見た光景。
それは。
「グエッ……グェッ……」
天井に張り付く巨大な蜘蛛のバケモノの群れと、首や手足を糸で包まれて、拘束された人間たち。
けだるい日常の崩壊を意味する、恐怖の顔を浮かべ。
体に突き刺された管から、バケモノに生きたまま吸われる体液。
そして、だんだんとしぼむ肉の塊。
「……」
目を疑う光景と極度の酸欠は、彼女の意識を遠くへやる。
だが、たった一瞬の出来事だというのに、彼女にこれほど確定的で具体的な『死』そのものを予兆できたことはない。
目の前のバケモノたちの手にかかって、死を迎えようとしている日常。
そんな、死に向かう日常の一部に自分自身もなってしまうのだということが認識できたところで、彼女の意識は途切れる。
だが、その時だった。
彼女の首を締め付けていた糸が、突如として断ち切られる。
乱れた麻のように、繊維質をまばらにあたりに撒き散らしながら、ゆるやかに解かれる粘着質の糸。
今までかかっていた吊り上げるような強い力が抜け、ふわっと宙に浮かぶ彼女の体を、今度は何かが抱きかかえるように強く支える。
落下とともに加速した体は、いつの間にかゆるやかに着地していた。
意識の途切れた彼女に、それが知覚できたかどうかはわからない。
ただ、結果として残っていたのは、死ではなく、生だった。
「グエーッ、グエッ!」
天井に張り付いていた蜘蛛のバケモノたちの声が荒々しくなる。
バケモノたちの視線の先には、黒いジャンパーに黒いヘルメットの男が立っていた。
「……悪い予感が当たった。やはりお前たちの仕業か」
救出した彼女を物陰に隠し、バケモノたちを背にして、苦虫を噛み潰すように言葉を吐く男。
その足で、一瞬にしてバケモノの糸を断ち切り、その腕で、落下する人間一人を抱えながら固い地面へと着地した。
およそ人間離れした技。
男はバケモノたちを見るべく悠然と振り返り、黒いヘルメットを脱ぐ。
差し込むライトの光に当てられた顔は、憎しみの色を浮き上がらせていた。
その男は、御山だった。
「グエッ!」
振り返ったのを挑発と受け取ったか、天井に張り付いていた蜘蛛のバケモノが、さっきまで捕食していた獲物を捨て、御山に襲い掛かった。
糸を切り離し、ドサドサと重力に負けて落ちていく人間の体などお構いなしに、その跳躍力で強く天井から鋭い爪を御山に向かって突きたてるバケモノ。
御山は、そんなバケモノたちの動きを見て、構えるでも、逃げるでもなく、その場に立ち尽くした。
「グエーッ!!」
気色の悪い声をあげながら、御山の心臓めがけてバケモノの爪が届く。
コンクリートに穴を開ける爪の硬度と鋭利さからいって、普通の人間ならば、かすっただけで致命傷になるであろうスピードと破壊力。
だが御山は、それに対して腰を落とし、ただ拳を引いた。
「ゲェビャッ!」
グンッと空気が震えるような音とともに、蜘蛛のバケモノの声が聞こえた。
気付けばバケモノは、遠くエスカレーターの壁まで吹っ飛ばされ、固い灰色のコンクリートでコーティングされたその壁に、深くめり込むように倒れていた。
命を奪われる瀬戸際だったはずの御山は、硬く握った拳を前に突き出すだけで無傷だった。
「餌は……よく選べ」
御山は、体液を撒き散らしながら崩れ去るバケモノの体を見て、あくまでも表情に浮かんだ憎しみの色を解かなかった。
バケモノを突き飛ばした衝撃によって生じた摩擦熱は、御山の拳に湯気が沸くほど赤く熱いものだった。
人間では反応できないであろうバケモノの攻撃をかわしもせず、さらに人間大まで巨大化した蜘蛛のバケモノを一撃で吹っ飛ばす恐るべき力。
その力は、バケモノたちの目に脅威と感じられたに違いない。
気付いた時には、無数の蜘蛛のバケモノたちが一斉に御山に飛び掛っていた。
さっきまで餌となる人間に与えていたはずの恐怖心が、いつの間にか彼らをひとつの思考に……いや、生物そのものに備わった生存本能に突き動かさせていたのだ。
『殺らねば、殺られる』
御山に襲い掛かる無数の蜘蛛たちから放たれる無数の糸、ギラリと光る爪と牙、それらを前にして御山は、すでに常人を超える脚力で駆け出していた。
「餌だ……俺にとってはお前らが……」
階段の手すり近くにある厚い壁を蹴り、御山の体は大きく宙に飛び上がった。
バケモノによって放たれた無数の糸は、御山の残像を追うように壁に粘着していく。
「Dへの憎しみを癒す、唯一の餌だ!!!」
牙を突き立てて、御山のほうへ飛び掛ってくる蜘蛛のバケモノの腹を横なぎに蹴り、
その大きな力で出来た反動を利用して、もう一方から爪を伸ばしてきたバケモノを硬く握った拳で、
思いっきり、ぶん殴る。
御山が空中で姿勢を動かすその度に、あたりの壁や天井に緑色の体液を撒き散らしながら、蜘蛛のバケモノが四方八方へと吹き飛び、叩きつけられていく。
「グェッ!グェエエッ!!」
一瞬にしてはあまりにも多くの出来事が消化された、数秒間。
御山が一度飛び上がってから着地するまでに、すでに九匹以上の蜘蛛のバケモノが死骸となって存在し、あたりに血なまぐさい死臭を撒き散らしていた。
「グエッ……グエッ……!」
蜘蛛のバケモノたちが、ドサッと音をたてながら地上に降りた。
御山を囲むようにとられた距離は、半径約3m。
だがどのバケモノも、御山の人間を超えた実力に手が出せず、うろたえるようにあたりを右往左往するだけだった。
「どうした。Dの改造実験の成果は、その程度か?」
バケモノたちを前に、誘うように体液で塗れた足と手を悠々と広げ構える御山。
「来ないのなら」
御山は、再びバケモノの一端に駆け出した。
「俺が」
糸を出してきたバケモノの攻撃を避け、素早く強烈な蹴りで吹っ飛ばしながら、近くにいた次のバケモノに拳を突き立てる御山。
「行くまでだ」
身を守ろうと防御したバケモノの足ごと、御山の拳はバケモノの腹に突き刺さった。
再び撒き散らかされる、強烈な死のスコール。
「グェッ……!!」
それを見て蜘蛛のバケモノたちは、糸と脚力を使って、全力で階段の先の出口へと逃げていった。
「……逃がすか」
無数のバケモノと人間の消えた階段に残された、バケモノと人間の無残な死体の山を見て、御山の心と体は再び湧き出た憎しみに染まる。
「罪のない人々の笑顔を奪うお前たちを、俺は絶対に許さんッ!」
拳を震わせ、怒号を咆え終わると、御山は出口に向かって駆け出していた。
――――――――――
「何なんだこのバケモノは、うわあっ!」
地下鉄の出入り口から、オフィス街に飛び出した無数の蜘蛛のバケモノは、行く先々で人間を襲い、その血液を奪っていた。
「ギャアアアアアッ!!」
車道に飛び出したバケモノが、乗用車やトラックの屋根や窓ガラスに飛び乗った。
バケモノは、車の屋根やガラスに爪を突き刺し、人間一人が入れそうな入り口を開けると、その場で糸を吐き、運転手や同乗者の顔を包んで窒息させ、長く伸びた管を刺し、悲鳴をあげながら何もすることが出来ない人間をただただ吸血する。
そして、行為を終えた人間の体であったものは、力をなくし、糸を引っ張るバケモノによって引きずるように道路に無残に叩きつけられる。
歩道、車道、老若男女を問わず、オフィス街にいる様々な人間たちが、無抵抗に、無差別にバケモノに殺されては命を吸われ、抜け殻となった体を道々に晒していく。
「グェッグェッ!」
バケモノは、一人の人間を吸い終わると、驚くべきことに、その固体数を増やしていく。
吸血を終えると、大きく体をくねらせ、腹のあたりから丸い卵のような物体を噴出させる。その物体は空気にふれるとすぐさま割れ、流れ出す液体とともに4、5匹の小さな蜘蛛のバケモノがあふれる。
小さなバケモノは親を探すようにすぐさま歩き出し、その後みるみるうちに巨大化し、一分ほどで生み出した蜘蛛のバケモノと同じ人間大のサイズになっていた。
「グェッ……グェッ……」
未知への恐怖へ悲鳴をあげ逃げ惑う人間、運転手を失ったことで追突事故を起こし爆発し、燃える車体。
死んでいく日常を尻目に、非日常の歪みが広がっていく。
増え続ける蜘蛛のバケモノの数は、いつの間にか千匹をゆうに超えていた。
ドンッ!!
「グェッ!」
死臭が火災によって空中へと巻き上がり、大量の非日常の群れが町中に放たれた中、駆けつけるまでにあたりのバケモノをぶっとばし、立ちすくむ御山の姿があった。
その瞳にうつるのは、ただ、無残に殺された人々と、バケモノに対する憎しみの色。
それ、だけ。
「グェッグェッ……」
大幅に数を増したことによって、御山に対する恐怖心をぬぐった蜘蛛のバケモノが、今度は御山を煽るように、糸で包まれた人間の死体をバタバタと積み上げていく。
御山は、その光景を淡々と見ながら、胸の奥からくる衝動を体に宿らせていた。
「……どんなに」
そして彼は、バケモノたちの前でつぶやき始めた。
「……どんなに数を増やしても」
スッと手を前にだすと、御山の手には金属製の長方形プレートが握られていた。
「……俺は、お前たちを倒すまでだ!」
プレートを正面にかざした時、御山の体から機械的なベルトが浮き上がった。
左手で握った拳をグイッと前に出すと、プレートを握った右手で、すぐさまベルトの中央に差し込み。
「変身!」
御山は、そう、大きく言い放った。
すると白い光と黒い影があたりを交差し、二つは大きなラインとなって御山の全身を包んだ。











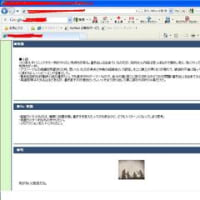







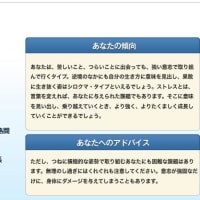

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます