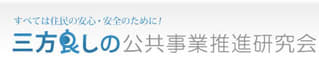「どうして紙が減らないんでしょう?」
というコーディネイターの問いに、
「簡単ですよ。わたしは、デュアルディスプレイにしたらぐっと減りました」
と答えたわたしの言葉にドット笑いがあがったのは何年前だったか。
わたし自身は場所も時間もはっきりと覚えているが、ここではその時も場所もシチュエーションもさして重要ではないので触れないでおく。
どうやらその言葉は、わたし自身の意に反しジョークだと受け止められたようだった。「あのくだり、サイコーでしたね。ナイスジョーク」と、そのパネルディスカッションが終わったあとで声をかけてくれた同業者がいたという事実でもそれはわかる。
ところが当人、言っちゃ悪いが(言わなきゃわからん)大まじめだった。
じじつ、わたしはディスプレイを複数にしてからというもの、提出物以外、つまり自分が仕事で使うものをプリントアウトすることがほとんどなくなった。画面に映し出したものを見ながら、別の画面で作業をすればいいだけのことだからだ。その場かぎりの一過性のものならもちろん、保存しておきたいものですら、自分発の資料ならなおさら、よほどのことでなければプリントアウトはしない。「極力しないように」と自分で自分に言い聞かせてもいる。
そうすると減る。増えない。「むしろ増える(た)」とお嘆きの諸兄は、パソコンを文房具の延長、つまりスーパー文房具として認識し使ってきた延長線上に、自らのアタマも行動様式も置いたままなのではないか。手描きの図面→ CAD → 3次元モデルを同じ延長線上のものとしてしか捉えられないのもまた根っこは同じだ。
そんなわたしだが、けっして「紙」全否定派というわけではない。ここはやっぱり「紙」でしょうというときは「紙」を使う。
今日も今日とて、たったひとりの事務所で、こんなものをグルグル回しながら、

となりのメインディスプレイでは、きのう、関係者数名で各タスクのつながりまでをつくった(まだ日数は入れてない)ネットワーク工程をいじくり回していたが、コイツはどうにも間尺に合わぬわいと、こんなものをつくった。

困ったときの「紙」頼みである。
そうだ!
アイツはどこにあるんだ?
記憶をたよりに探しあてたソイツとは・・


はい、かつては土木技術者たるもの皆の必需品だった色鉛筆。

オジさんだから「今という時代」に適応できないのではない。
「あたらしい技術を覚えない」オジさんだから「今という時代」に適応できないのだ。
その積み重ねてきた「経験と勘」と、それによって得た「引き出し」というアドバンテージがあるオジさんは、「あたらしい技術を覚える」ことでさらにパワーアップする。
「デジタルとアナログをハイブリッドして適時適所で使えるオジさんは最強なんだぞ」
誰もいない事務所で、そう独りごちる辺境の土木屋61歳。
誰も言ってくれないのなら自分で言う。
そんな厚かましさもまた、オジさんのストロングポイントなのである。
↑↑ 土木のしごと~(有)礒部組現場情報
↑↑ インスタグラム ーisobegumiー