ヒポクラテスと柳の樹皮――古代ギリシャの知恵が生んだ鎮痛剤の物語
時代背景: 紀元前5世紀の古代ギリシャ、医学の父と称されるヒポクラテスは、病を神の罰ではなく自然現象と捉え、経験に基づく治療を追求しました。彼の残したとされる記録の中には、柳の葉や樹皮を用いて痛みや熱を和らげる方法の記述があります。例えば、ヒポクラテスは出産時の痛みを軽減するため産婦に柳の葉を煎じた茶を飲ませたとも伝えられます
。当時から柳は炎症や熱を下げる薬草として知られており、古代エジプトの『エーベルス・パピルス』(紀元前16世紀頃)にも柳の効用が記録されています。
柳の薬効の発見: 柳(ヤナギ)の樹皮にはサリシンという成分が含まれ、これが体内で鎮痛・解熱作用を持つ物質に変化します。ヒポクラテスら古代の医師は、そのような成分の存在こそ知らずとも、柳を用いる経験則によって痛みや熱を和らげてきました
。この知識は長らく民間療法として伝わり、中世ヨーロッパでも「熱病には柳の樹皮」と言われるほど一般的でした。
近代への継承: 18世紀になると、西洋で古代からの知恵を科学的に解明しようという動きが起こります。1763年、英国のエドワード・ストーンは柳の樹皮が熱病に効くことを5年間の実験で確認し、王立協会に報告しました
19世紀にはドイツやフランスの化学者たちが柳の有効成分サリシンを抽出・分析することに成功します。1828年にミュンヘン大学のブッフナーが樹皮から苦味のある結晶を得て「サリシン」と命名し1838年にはフランスの化学者がその成分からサリチル酸を合成しました。さらに1897年、ドイツの製薬会社バイエル社で働いていたフェリックス・ホフマンがサリチル酸を改良して胃腸への負担を減らし、アセチルサリチル酸という薬品を作り出します
現在への影響: アスピリンは20世紀を通じて最も広く使われた鎮痛解熱剤となり、現在でも頭痛や発熱の緩和に用いられるだけでなく、血液をさらさらにする作用を活かして心筋梗塞や脳卒中の予防にも使われています。なお、「アスピリン」という名称は、サリチル酸の旧名(シュピーア酸)がその原料植物の一つシモツケソウ属(学名:Spiraea)にちなみ「スピリン酸」と呼ばれていたことに由来し、頭にアセチルのAを付けたものです。柳の樹皮から生まれたアスピリンの物語は、伝統的な生薬の知識が科学の発展によって新たな価値を得た好例と言えるでしょう。
LINE相談受付中
漢方専門寶元堂薬局楽天市場店が
漢方専門寶元堂薬局楽天市場店 開局致しました。 漢方薬1日分〜販売しております。お気軽にお買い求めいただけるようになっています。 まだまだ商品登録中ですが、 宜しかったら是非、覗いてみてください。
風邪の症状のお薬も気軽にお買い上げいただきます。
https://rakuten.co.jp/hougendou/
発行元;寶元堂薬品薬局
住所:〒神戸市中央区籠池通4-1-6
☎:078-262-7708📠:078-262-7709

















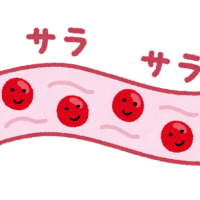

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます