Ⅷ
レムローズ王国の秋は短く、すぐそこには冬の足音が聞こえる。
まもなく、エリクは十六歳の誕生日を迎える。
北の大地が薄く雪化粧される頃には、王都エーザヴェスは交易や行き交う人々で、一年で最も賑々しくなる。
約半年もの間、深い雪に覆われる北の大地にあって、それはその半年間を生きる為の物資や食糧の取り引きが盛んに行われる期間であり、その賑やかさが失われるのと同じ頃に、王都エーザヴェスは雪の中に孤立する。
二人の兄たちは、今日もエリクにべったりで、その手は毛糸の手袋で暖かかった。
相変わらずハイゼンは、二人の兄たちがエリクの部屋を訪れるのを目こぼししてくれた。
昨年の冬に比べると、エリクはまた一段と美しく成長しており、これほどの絶世の美女をローヴェントもカルサスも、他に見たこともない。
レムローズの薔薇姫、まさにそれはエリクに相応しい呼び名と言えた。
エリクは前の冬の間に、二人の兄から贈られたレトレア織で、非常に素晴らしい白い絹のドレスを仕上げており、それを大事に部屋の隅に飾っていた。
着てみないのか? と、二人の兄は言うが、エリクは恥ずかしいと言っては、そのドレスを着るのを色んな口実を付けては避けてきた。
エリクとしては、それは自分の一番の宝物であったし、むやみに着ることで汚したくないとか、引っ掛けて大切な絹地を破いてしまうのが恐ろしかったのだ。
あと、その豪華すぎるドレスが自分に似合うのかという自信もなかったし、兄たちに笑われるのではと余計な心配もしていた。
世間を知らないエリクは、自分の容姿に自信がなかったし、自身に対する褒め言葉も、お世辞としか思っていなかった。その気取ったところの無さも、エリクの可愛らしさの一つといえたのだが。
実際、こんな生活を長くしていたので、エリクは異性に口説かれた経験など皆無で、目の前にいるこの二人は、あくまで『お兄ちゃん』の域を出てはいなかった。
その兄たちは、この絶世の美姫をその手にしたくて仕方なかったのだが、この三人でいる雰囲気を壊したくないという理由で、どちらもまだ抜け駆けしたことがない。
こういう場合も、甲斐性なしというのだろうか。
あまりにもその関係が大切なとき、それが壊れてしまうと思うのは恐怖である。
自分の全てを捧げても構わない相手ともなると、逆にあれこれ考えさせられてしまい、その『告白』が、勇気なのか無謀なのかさえ、区別がつかないようになる。
しかし、時間はもう限りなく少ない。
そして、先に行動を起こしたのは長兄のローヴェントだった。
その日の夜、ローヴェントは単身、エリクの部屋を訪れる。
「こんな夜更けに珍しいですね、ローヴェント兄様」
エリクはいつもの調子で扉を開けると、ローヴェントを部屋へと招き入れた。
ローヴェントは言葉少なに、テーブルへと着き、思い詰めた表情をしていた。
そんなローヴェントの姿を見て、エリクはホットミルクを差し出した。
ローヴェントがそのカップを手にすると、両手を伝って温かいぬくもりが伝わってくる。
「まずは、冷えた身体をあっためて下さいね」
エリクがそう言って微笑むと、ローヴェントは一口、ホットミルクを口にした。
エリクは少し安心したようにして、ちょっとした料理でも作ろうかとキッチンへ向かおうとした。
その時、ローヴェントがカップをテーブルに置いて、エリクの手を掴んだ。
「どうかなさいましたか? ローヴェント兄様」
エリクはいたって普通に振り返り、ローヴェントにそう言うと、ローヴェントはスッと席を立ち上がり、エリクの身体をそっと抱きしめた。
「に、兄さま!?」
これには、さすがのエリクも少し驚いたようで、ちょっとだけ声が上擦ってしまう。
ローヴェントは細身だが長身な為、エリクは少しローヴェントを見上げるような格好になる。われものを扱うような優しい抱き方だが、ローヴェントの腕から伝わってくる微かな震えは、ローヴェントの真剣さをエリクに悟らせた。
「エリク、頼みがある・・・」
ローヴェントの瞳は何処か不安げで、エリクは次の言葉を、息を呑んで待つ。
少しの沈黙の後に、ローヴェントはその瞳を閉じて、エリクにこう言った。エリクを抱きしめる腕に、少しだけ力が入る。
「エリクが十六歳の誕生日を迎えたら、・・・私と、結婚して欲しいんだ」
「!?」
エリクはその言葉に、ルビーのように赤く澄んだ瞳を大きく見開いた。
兄からのその告白が、とても冗談で言っているとは思えなかったし、この賢明な兄が何故、妹の自分に求婚するのかも疑問だった。
ローヴェントの次の言葉が、その疑問だけは解き明かしてくれる。
「私とカルサスは実の兄弟だが、エリク、お前とは血が繋がっていない。つまり、実の妹ではないんだ」
エリクは、正直、その事を驚いたが表情には出さなかった。
エリクがひたすらに考えたのは、この愛する兄の為に、一体、何をしてやれるかという事で、ローヴェントのその不安を、エリクは一刻も早く解きほぐしてあげたかった。
エリクは、話をどう繋げてよいやら混乱しているローヴェントの方を見て、にこやかな笑みを見せると、彼の唇にそっと人差し指を当てて、優しい口調でこう言う。
「わかりました。ローヴェント兄様が望むのであれば、エリクは喜んで兄様の妻になります。あ、えっと、その場合、兄様と言う呼び方はおかしいですよね。ローヴェント様? 旦那様? それとも、えっとご主人様??」
ローヴェントは、エリクのその言葉に、全ての不安を優しく溶かされる思いだった。
いつもの表情を取り戻したローヴェントに、クスクスと明るく笑みを浮かべるエリク。
「とりあえず、いつも通りで頼むよ。ハイゼン候や、カルサスの手前もあることだし」
「はい! 兄様っ」
ローヴェントはそう言うと、再び席へと着いた。テーブルに置かれたホットミルクは、まだ十分にあったかい。
エリクは普段通りの様子でキッチンへと向かい、ホットケーキを焼き始めた。
ローヴェントは、安心したようにホットミルクを口にする。
ローヴェントはこの時、エリクに救われた思いだった。
どこまでも優しい彼女。
エリクの性格を考えれば、彼女がそれを断るハズもない事ぐらい、今なら簡単に理解できた。それは例えば、先にカルサスがこの話をエリクにしていたなら、エリクはカルサスに良い返事をしただろうし、少し悔しいが、きっとそれを祝福できる自分がいただろうと、ローヴェントには思えた。
彼女が望むのは、カルサスやハイゼン候を含めたたった四人の、小さいがとても大切で、とても大事な、楽園とも呼べるこの場所で、私たち三人が彼女の前に、心安らかに笑っていることなのだと。
ローヴェントはテーブルに差し出された、大きめのバターとハチミツの乗ったホットケーキを口にしながら、こう考えていた。
エリクへの告白は、焦る自分がさせた事とはいえ、カルサスに相談なしなのは、さすがに気の引ける思いがした。
まずは、彼女を来たるべき最悪から守り抜いた上で、もう一度、カルサスと相談し、どちらが彼女の人生を幸せなものにするのか、語り合う必要があると。
幸い、エリクは口が堅いほうなので、軽々しくこの話をカルサスやハイゼンに漏らすことはないとローヴェントには言い切れた。
テーブルの向かい側に座ったエリクは、大好きなドーラベルンコーヒーを入れて、その香りを味わいながら、ローヴェントと談笑していた。二人の兄はコーヒーが苦手だったが、その豆から挽いたコーヒーの香りは、とても香ばしく、リラックスした気分にさせてくれる。
ローヴェントが何気にホットケーキをパクパクと口にしていると、二枚重ねのそのホットケーキも、残すところあと一口となっていた。
「ローヴェント兄様が、そんなに食べるのって珍しいですね。カルサス兄様なら、五、六皿はペロっといっちゃいますけど」
「ああ、すごく美味いよ。出来れば、もう少し食べたい気分だよ」
「煽てられては、張り切らないわけにはいきませんね!! 待っててくださいね、すぐに焼いてきますからっ」
エリクはそう残して、キッチンの方へと向かう。
ローヴェントは、カルサスには悪いが、少しだけエリクを独占させてもらうことにした。
静かに更け行く夜に、暖炉からは耳慣れたパチパチッという音が聞こえ、それを意識して聞いていると、室内はより温かな暖色の光に満たされていく感じがした。
暖炉の横に置かれた揺り椅子で、編み物をするエリクの姿を想像すると、大事に懐にしまっている毛糸の手袋からも、彼女の温度が伝わってくる気がした。
ローヴェントは、エリクの新しく焼いたホットケーキを子供のようにパクパクと頬張り、あまり遅くならないように気を付けて、「美味しかったよ」と言葉を残し、彼女の部屋を後にした。
それから、数日後。
間もなく、エリクは十六歳の誕生日を迎えようとしていた。
この日の夜、十二時の鐘が鳴ると同時にエリクは晴れて十六歳となる。
王都エーザヴェスも、降り積もる雪に閉ざされ、人々の姿を見ることもない。
この日、初めてレトレア織の絹地のドレスを身に付けたエリクは、特別に二人の王子から、豪華絢爛な造りの謁見の間へと招かれた。
この謁見の間は、レムローズ王国の宮廷中でも最も上等な造りの空間になっており、二人の王子たちはこの広間へと繋がる全ての場所を一気に借り切ることで、エリクをその白いドレス姿のまま、誰の目にも触れることなく、この場所へ招き入れることが出来た。
警備はハイゼン候、自らが進んで指揮を奮い、辺りはこの上なく万全な状況にある。
たった三人の姿しかいない謁見の間は、あまりに広すぎるともいえたが、レムローズ王国の贅の限りを尽くしたこの最高の舞台で、二人の王子たちはエリクの晴れの姿を見届けてやりたかった。
エリクは、金銀の敷き詰められた壁や床、宝石を星のように数多散りばめた天井と、この眩いばかりに華美な空間に、目のやり場に困るほどだったが、何よりその場所で一番の輝きを放っていたのは、当のエリク自身である。
レトレア織の絹のドレスは、まるで花嫁衣裳のように上品な仕上がりで、エリクはそれを完璧といえるほどに着こなしていた。
最高級のドレスの白い絹地は、辺りの煌びやかな光を吸い込むように様々な艶色を放っている。
広間の中央には、二人の王子たちが用意した長方形の晩餐用のテーブルが置かれており、プラチナやゴールドの装飾がなされたそのテーブルを、色とりどりの素晴らしい料理や最高級のシャンパンが彩っている。
給仕を必要としないよう、事前に全ての料理が盛り付けられているようで、それでも温かいものは温かいまま、冷やしたものは冷たいままで頂けるよう、様々な工夫がなされている。
エリクは、こんな豪華な食卓など見たのも初めてで、その席は四つ設けてある。
うち、一つはハイゼン候のものだろう。
様々な嗜好が全てエリクには嬉しかった。
喜びが溢れ出すエリクの表情を見て、二人の王子たちはご満悦な様子だ。
「お兄様方、わざわざこんな私の為に、こんなにも嬉しい宴の席を用意してくれたことを、心より感謝します」
エリクはそう言って深々と一礼する。
すると、王国で一番の晩餐会場となったこの広間で、カルサスはエリクに言った。
「さあ、堅苦しい挨拶は抜きだ。ハイゼン候がいらっしゃるまでは、まだ時間がある。まずは一曲、踊ってくれるかな、エリク姫」
「はい! カルサス兄様」
「兄貴、なるだけリズムのいいヤツを頼むぜ」
カルサスの注文に応えるように、ローヴェントはその肩にバイオリンを乗せると、右手に弓を持ち、軽やかにダンス曲を奏で始める。テンポは良いが、上品な音色が室内を満たす。
カルサスは、ダンスがあまり得意な方ではないが、ハイゼンに仕込まれたエリクのダンスはまさに完璧で、エリクは上手にカルサスをリードした。
ローヴェントは次々と美しい音色を自慢のバイオリンで奏でるが、自分が踊る時は誰が楽曲を奏でてくれるのかと、ふと思う。
カルサスは、リコーダーですら戦闘用の角笛に変えてしまうほどの音痴だ。
結局、ピアノの名手であるハイゼンが来るまで、自分の番は回ってこないことに気付くと、ちょっとだけ萎えた。
しかし、これほどまでの笑顔を振りまいてくれるエリクの、その清楚で可憐なステップを見ていると、ローヴェントはそんな些細なことなど、どうでもよくなった。
まずは、集中して丁寧に、曲を奏でようとするローヴェント。
そうしている内に、ローヴェントが待ち望んだハイゼン候がやって来たので、ようやく、手が痺れるほど弾いたバイオリンをケースにしまうことが出来た。
すると、カルサスはさっさと宴席に着いてしまい、次いでエリクも席に着いた。
するとハイゼンも、三人に軽く挨拶を済ませ、すぐさま席に着いてしまった為、結局、ローヴェントもハァ、と肩を落として、流されるように席に着いた。
ハイゼンは、エリクに言う。
「今宵のエリク様は、また一段とお美しい。まだ、十二時の鐘を迎えるには、あと二時間ほど時間がありはしますが、まずはこのめでたき日に祝杯を挙げましょうぞ!」
そう言ってハイゼンは、手にしたサーベルでシュポン!! と、シャンパンの口を落とすと、二人の王子の杯にシュワっと発泡する淡い琥珀の液体を注いだ。
それとほぼ同時にカルサスがシャンパンの口を落とすと、それをハイゼンの杯に注ぐ。
そして、最後にローヴェントが手にする緑色の瓶のシャンパンの口を彼が落とすと、男たちは一度、席を立ち、エリクを囲むようにして、三人一緒に手にしたそのシャンパンをエリクの杯に注いだ。
緑色の瓶のシャンパンは、風味を損なわずにアルコール分を0%に抑えた特注品で、未成年のエリクに酒を飲ませる事を許さない、頑固オヤジのハイゼンの用意したものだった。
やはりハイゼンにとっても、エリクは我が娘同然に可愛かった。
乾杯の音頭を取ったのは、お調子者のカルサスであったが、宴は大いに盛り上がり、割とかたい方のローヴェントもハイゼンも、今夜ばかりはと幾つものシャンパンを空にした。
男たち揃ってがほろ酔い気分になると、ハイゼンは「娘は誰にもやらん!」と言い張り、カルサスは、ハイゼンに「お父さんと呼ばせて下さい!!」などと、冗談なんだか本気なんだか分からないことを口々にした。
ローヴェントは酔ったせいで、エリクをみるたび顔を赤面させていたが、エリク自身はこんなにも楽しい宴を用意してくれた二人の兄と、師であるハイゼンに心よりの感謝をしていた。
楽しい時間の過ぎ去る早さをエリクが感じていると、次第に宴もたけなわとなり、間もなく、誕生日である十二時の鐘の音の鳴るその時を迎えようとしていた。
二人の兄とハイゼンはゆっくりと席を立つ。
その様子は今までと違い、酔った様子など微塵もない。
ゴォーーン! ゴォーーーン!!
と王宮の時計台にある鐘が、エリクの十六歳の誕生日を告げる。
三人は声を揃えて、とても大切な想いを込めてこう言った。
「ハッピーバースデイ、親愛なるエリク姫」、と。
刹那、三人は一斉に同じ方向へと振り返り、各々の腰に帯びた剣を抜刀する。
その時、エリクも敏感に感じ取った。
三人の視線のその先に迫る、その恐怖を。
レムローズ王国の秋は短く、すぐそこには冬の足音が聞こえる。
まもなく、エリクは十六歳の誕生日を迎える。
北の大地が薄く雪化粧される頃には、王都エーザヴェスは交易や行き交う人々で、一年で最も賑々しくなる。
約半年もの間、深い雪に覆われる北の大地にあって、それはその半年間を生きる為の物資や食糧の取り引きが盛んに行われる期間であり、その賑やかさが失われるのと同じ頃に、王都エーザヴェスは雪の中に孤立する。
二人の兄たちは、今日もエリクにべったりで、その手は毛糸の手袋で暖かかった。
相変わらずハイゼンは、二人の兄たちがエリクの部屋を訪れるのを目こぼししてくれた。
昨年の冬に比べると、エリクはまた一段と美しく成長しており、これほどの絶世の美女をローヴェントもカルサスも、他に見たこともない。
レムローズの薔薇姫、まさにそれはエリクに相応しい呼び名と言えた。
エリクは前の冬の間に、二人の兄から贈られたレトレア織で、非常に素晴らしい白い絹のドレスを仕上げており、それを大事に部屋の隅に飾っていた。
着てみないのか? と、二人の兄は言うが、エリクは恥ずかしいと言っては、そのドレスを着るのを色んな口実を付けては避けてきた。
エリクとしては、それは自分の一番の宝物であったし、むやみに着ることで汚したくないとか、引っ掛けて大切な絹地を破いてしまうのが恐ろしかったのだ。
あと、その豪華すぎるドレスが自分に似合うのかという自信もなかったし、兄たちに笑われるのではと余計な心配もしていた。
世間を知らないエリクは、自分の容姿に自信がなかったし、自身に対する褒め言葉も、お世辞としか思っていなかった。その気取ったところの無さも、エリクの可愛らしさの一つといえたのだが。
実際、こんな生活を長くしていたので、エリクは異性に口説かれた経験など皆無で、目の前にいるこの二人は、あくまで『お兄ちゃん』の域を出てはいなかった。
その兄たちは、この絶世の美姫をその手にしたくて仕方なかったのだが、この三人でいる雰囲気を壊したくないという理由で、どちらもまだ抜け駆けしたことがない。
こういう場合も、甲斐性なしというのだろうか。
あまりにもその関係が大切なとき、それが壊れてしまうと思うのは恐怖である。
自分の全てを捧げても構わない相手ともなると、逆にあれこれ考えさせられてしまい、その『告白』が、勇気なのか無謀なのかさえ、区別がつかないようになる。
しかし、時間はもう限りなく少ない。
そして、先に行動を起こしたのは長兄のローヴェントだった。
その日の夜、ローヴェントは単身、エリクの部屋を訪れる。
「こんな夜更けに珍しいですね、ローヴェント兄様」
エリクはいつもの調子で扉を開けると、ローヴェントを部屋へと招き入れた。
ローヴェントは言葉少なに、テーブルへと着き、思い詰めた表情をしていた。
そんなローヴェントの姿を見て、エリクはホットミルクを差し出した。
ローヴェントがそのカップを手にすると、両手を伝って温かいぬくもりが伝わってくる。
「まずは、冷えた身体をあっためて下さいね」
エリクがそう言って微笑むと、ローヴェントは一口、ホットミルクを口にした。
エリクは少し安心したようにして、ちょっとした料理でも作ろうかとキッチンへ向かおうとした。
その時、ローヴェントがカップをテーブルに置いて、エリクの手を掴んだ。
「どうかなさいましたか? ローヴェント兄様」
エリクはいたって普通に振り返り、ローヴェントにそう言うと、ローヴェントはスッと席を立ち上がり、エリクの身体をそっと抱きしめた。
「に、兄さま!?」
これには、さすがのエリクも少し驚いたようで、ちょっとだけ声が上擦ってしまう。
ローヴェントは細身だが長身な為、エリクは少しローヴェントを見上げるような格好になる。われものを扱うような優しい抱き方だが、ローヴェントの腕から伝わってくる微かな震えは、ローヴェントの真剣さをエリクに悟らせた。
「エリク、頼みがある・・・」
ローヴェントの瞳は何処か不安げで、エリクは次の言葉を、息を呑んで待つ。
少しの沈黙の後に、ローヴェントはその瞳を閉じて、エリクにこう言った。エリクを抱きしめる腕に、少しだけ力が入る。
「エリクが十六歳の誕生日を迎えたら、・・・私と、結婚して欲しいんだ」
「!?」
エリクはその言葉に、ルビーのように赤く澄んだ瞳を大きく見開いた。
兄からのその告白が、とても冗談で言っているとは思えなかったし、この賢明な兄が何故、妹の自分に求婚するのかも疑問だった。
ローヴェントの次の言葉が、その疑問だけは解き明かしてくれる。
「私とカルサスは実の兄弟だが、エリク、お前とは血が繋がっていない。つまり、実の妹ではないんだ」
エリクは、正直、その事を驚いたが表情には出さなかった。
エリクがひたすらに考えたのは、この愛する兄の為に、一体、何をしてやれるかという事で、ローヴェントのその不安を、エリクは一刻も早く解きほぐしてあげたかった。
エリクは、話をどう繋げてよいやら混乱しているローヴェントの方を見て、にこやかな笑みを見せると、彼の唇にそっと人差し指を当てて、優しい口調でこう言う。
「わかりました。ローヴェント兄様が望むのであれば、エリクは喜んで兄様の妻になります。あ、えっと、その場合、兄様と言う呼び方はおかしいですよね。ローヴェント様? 旦那様? それとも、えっとご主人様??」
ローヴェントは、エリクのその言葉に、全ての不安を優しく溶かされる思いだった。
いつもの表情を取り戻したローヴェントに、クスクスと明るく笑みを浮かべるエリク。
「とりあえず、いつも通りで頼むよ。ハイゼン候や、カルサスの手前もあることだし」
「はい! 兄様っ」
ローヴェントはそう言うと、再び席へと着いた。テーブルに置かれたホットミルクは、まだ十分にあったかい。
エリクは普段通りの様子でキッチンへと向かい、ホットケーキを焼き始めた。
ローヴェントは、安心したようにホットミルクを口にする。
ローヴェントはこの時、エリクに救われた思いだった。
どこまでも優しい彼女。
エリクの性格を考えれば、彼女がそれを断るハズもない事ぐらい、今なら簡単に理解できた。それは例えば、先にカルサスがこの話をエリクにしていたなら、エリクはカルサスに良い返事をしただろうし、少し悔しいが、きっとそれを祝福できる自分がいただろうと、ローヴェントには思えた。
彼女が望むのは、カルサスやハイゼン候を含めたたった四人の、小さいがとても大切で、とても大事な、楽園とも呼べるこの場所で、私たち三人が彼女の前に、心安らかに笑っていることなのだと。
ローヴェントはテーブルに差し出された、大きめのバターとハチミツの乗ったホットケーキを口にしながら、こう考えていた。
エリクへの告白は、焦る自分がさせた事とはいえ、カルサスに相談なしなのは、さすがに気の引ける思いがした。
まずは、彼女を来たるべき最悪から守り抜いた上で、もう一度、カルサスと相談し、どちらが彼女の人生を幸せなものにするのか、語り合う必要があると。
幸い、エリクは口が堅いほうなので、軽々しくこの話をカルサスやハイゼンに漏らすことはないとローヴェントには言い切れた。
テーブルの向かい側に座ったエリクは、大好きなドーラベルンコーヒーを入れて、その香りを味わいながら、ローヴェントと談笑していた。二人の兄はコーヒーが苦手だったが、その豆から挽いたコーヒーの香りは、とても香ばしく、リラックスした気分にさせてくれる。
ローヴェントが何気にホットケーキをパクパクと口にしていると、二枚重ねのそのホットケーキも、残すところあと一口となっていた。
「ローヴェント兄様が、そんなに食べるのって珍しいですね。カルサス兄様なら、五、六皿はペロっといっちゃいますけど」
「ああ、すごく美味いよ。出来れば、もう少し食べたい気分だよ」
「煽てられては、張り切らないわけにはいきませんね!! 待っててくださいね、すぐに焼いてきますからっ」
エリクはそう残して、キッチンの方へと向かう。
ローヴェントは、カルサスには悪いが、少しだけエリクを独占させてもらうことにした。
静かに更け行く夜に、暖炉からは耳慣れたパチパチッという音が聞こえ、それを意識して聞いていると、室内はより温かな暖色の光に満たされていく感じがした。
暖炉の横に置かれた揺り椅子で、編み物をするエリクの姿を想像すると、大事に懐にしまっている毛糸の手袋からも、彼女の温度が伝わってくる気がした。
ローヴェントは、エリクの新しく焼いたホットケーキを子供のようにパクパクと頬張り、あまり遅くならないように気を付けて、「美味しかったよ」と言葉を残し、彼女の部屋を後にした。
それから、数日後。
間もなく、エリクは十六歳の誕生日を迎えようとしていた。
この日の夜、十二時の鐘が鳴ると同時にエリクは晴れて十六歳となる。
王都エーザヴェスも、降り積もる雪に閉ざされ、人々の姿を見ることもない。
この日、初めてレトレア織の絹地のドレスを身に付けたエリクは、特別に二人の王子から、豪華絢爛な造りの謁見の間へと招かれた。
この謁見の間は、レムローズ王国の宮廷中でも最も上等な造りの空間になっており、二人の王子たちはこの広間へと繋がる全ての場所を一気に借り切ることで、エリクをその白いドレス姿のまま、誰の目にも触れることなく、この場所へ招き入れることが出来た。
警備はハイゼン候、自らが進んで指揮を奮い、辺りはこの上なく万全な状況にある。
たった三人の姿しかいない謁見の間は、あまりに広すぎるともいえたが、レムローズ王国の贅の限りを尽くしたこの最高の舞台で、二人の王子たちはエリクの晴れの姿を見届けてやりたかった。
エリクは、金銀の敷き詰められた壁や床、宝石を星のように数多散りばめた天井と、この眩いばかりに華美な空間に、目のやり場に困るほどだったが、何よりその場所で一番の輝きを放っていたのは、当のエリク自身である。
レトレア織の絹のドレスは、まるで花嫁衣裳のように上品な仕上がりで、エリクはそれを完璧といえるほどに着こなしていた。
最高級のドレスの白い絹地は、辺りの煌びやかな光を吸い込むように様々な艶色を放っている。
広間の中央には、二人の王子たちが用意した長方形の晩餐用のテーブルが置かれており、プラチナやゴールドの装飾がなされたそのテーブルを、色とりどりの素晴らしい料理や最高級のシャンパンが彩っている。
給仕を必要としないよう、事前に全ての料理が盛り付けられているようで、それでも温かいものは温かいまま、冷やしたものは冷たいままで頂けるよう、様々な工夫がなされている。
エリクは、こんな豪華な食卓など見たのも初めてで、その席は四つ設けてある。
うち、一つはハイゼン候のものだろう。
様々な嗜好が全てエリクには嬉しかった。
喜びが溢れ出すエリクの表情を見て、二人の王子たちはご満悦な様子だ。
「お兄様方、わざわざこんな私の為に、こんなにも嬉しい宴の席を用意してくれたことを、心より感謝します」
エリクはそう言って深々と一礼する。
すると、王国で一番の晩餐会場となったこの広間で、カルサスはエリクに言った。
「さあ、堅苦しい挨拶は抜きだ。ハイゼン候がいらっしゃるまでは、まだ時間がある。まずは一曲、踊ってくれるかな、エリク姫」
「はい! カルサス兄様」
「兄貴、なるだけリズムのいいヤツを頼むぜ」
カルサスの注文に応えるように、ローヴェントはその肩にバイオリンを乗せると、右手に弓を持ち、軽やかにダンス曲を奏で始める。テンポは良いが、上品な音色が室内を満たす。
カルサスは、ダンスがあまり得意な方ではないが、ハイゼンに仕込まれたエリクのダンスはまさに完璧で、エリクは上手にカルサスをリードした。
ローヴェントは次々と美しい音色を自慢のバイオリンで奏でるが、自分が踊る時は誰が楽曲を奏でてくれるのかと、ふと思う。
カルサスは、リコーダーですら戦闘用の角笛に変えてしまうほどの音痴だ。
結局、ピアノの名手であるハイゼンが来るまで、自分の番は回ってこないことに気付くと、ちょっとだけ萎えた。
しかし、これほどまでの笑顔を振りまいてくれるエリクの、その清楚で可憐なステップを見ていると、ローヴェントはそんな些細なことなど、どうでもよくなった。
まずは、集中して丁寧に、曲を奏でようとするローヴェント。
そうしている内に、ローヴェントが待ち望んだハイゼン候がやって来たので、ようやく、手が痺れるほど弾いたバイオリンをケースにしまうことが出来た。
すると、カルサスはさっさと宴席に着いてしまい、次いでエリクも席に着いた。
するとハイゼンも、三人に軽く挨拶を済ませ、すぐさま席に着いてしまった為、結局、ローヴェントもハァ、と肩を落として、流されるように席に着いた。
ハイゼンは、エリクに言う。
「今宵のエリク様は、また一段とお美しい。まだ、十二時の鐘を迎えるには、あと二時間ほど時間がありはしますが、まずはこのめでたき日に祝杯を挙げましょうぞ!」
そう言ってハイゼンは、手にしたサーベルでシュポン!! と、シャンパンの口を落とすと、二人の王子の杯にシュワっと発泡する淡い琥珀の液体を注いだ。
それとほぼ同時にカルサスがシャンパンの口を落とすと、それをハイゼンの杯に注ぐ。
そして、最後にローヴェントが手にする緑色の瓶のシャンパンの口を彼が落とすと、男たちは一度、席を立ち、エリクを囲むようにして、三人一緒に手にしたそのシャンパンをエリクの杯に注いだ。
緑色の瓶のシャンパンは、風味を損なわずにアルコール分を0%に抑えた特注品で、未成年のエリクに酒を飲ませる事を許さない、頑固オヤジのハイゼンの用意したものだった。
やはりハイゼンにとっても、エリクは我が娘同然に可愛かった。
乾杯の音頭を取ったのは、お調子者のカルサスであったが、宴は大いに盛り上がり、割とかたい方のローヴェントもハイゼンも、今夜ばかりはと幾つものシャンパンを空にした。
男たち揃ってがほろ酔い気分になると、ハイゼンは「娘は誰にもやらん!」と言い張り、カルサスは、ハイゼンに「お父さんと呼ばせて下さい!!」などと、冗談なんだか本気なんだか分からないことを口々にした。
ローヴェントは酔ったせいで、エリクをみるたび顔を赤面させていたが、エリク自身はこんなにも楽しい宴を用意してくれた二人の兄と、師であるハイゼンに心よりの感謝をしていた。
楽しい時間の過ぎ去る早さをエリクが感じていると、次第に宴もたけなわとなり、間もなく、誕生日である十二時の鐘の音の鳴るその時を迎えようとしていた。
二人の兄とハイゼンはゆっくりと席を立つ。
その様子は今までと違い、酔った様子など微塵もない。
ゴォーーン! ゴォーーーン!!
と王宮の時計台にある鐘が、エリクの十六歳の誕生日を告げる。
三人は声を揃えて、とても大切な想いを込めてこう言った。
「ハッピーバースデイ、親愛なるエリク姫」、と。
刹那、三人は一斉に同じ方向へと振り返り、各々の腰に帯びた剣を抜刀する。
その時、エリクも敏感に感じ取った。
三人の視線のその先に迫る、その恐怖を。














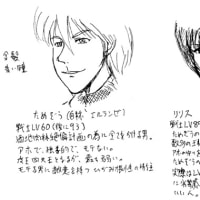

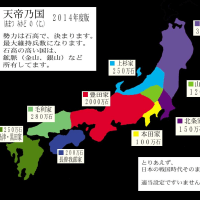



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます