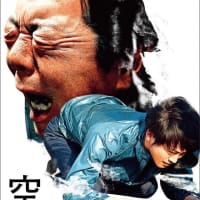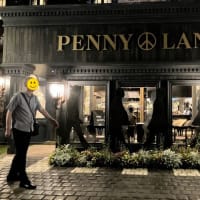現在、東京都美術館で「ゴッホとゴーギャン展」が開催されているのを機に、自分が以前、別のブログでゴッホや彼の出身国オランダについて書いた記事のことを思い出しました。
なかなかの力作なので(自画自賛を許してね・笑)、ここでご紹介したいと思います。
映画『ブラックブック』を見た後に、オランダと自分との縁について考えてみた。 私はオランダとは何かと縁がある(と、自分では思っている)。
私のオランダとの最初の接点は『アンネの日記』だった。子供時代地方に住んでいた私は、ある時地元紙の読者欄に投稿した謝礼に図書券を貰った。それと引き換えに入手したのが『アンネの日記』(文春文庫)だった。隠れ家での自分(彼女はまだローティーンだったのだ!)を押し殺した生活の中で、日記を親友にアンネは思索を深めて行く。同世代の私には彼女がかなり大人びて見えた。元々聡明な少女だったに違いない。アンネに触発されるように私も日記を書き出した。それは大学時代まで続いた。
『アンネの日記』への執着(関心)はそれに留まらない。後にその映画化作品も見た。映画公開に因んで地元のデパートで開催された『アンネ・フランク展』にも行った。屋根裏でペーターと腰掛けたトランク?も展示品の中にあったな。アンネに関する新聞記事をスクラップしたり、関連文献を読み漁ったりもした。
さらには大人になってオランダへ旅行し、子供時代からの念願であったアンネの隠れ家を訪ねた。夏の盛りで、世界中から多くの人々が訪れていた。日記を通して知っていた場所。初めて訪ねたような気がしなかった。隠れ家の人々が使ったであろうトイレの便座のかわいらしい花の図柄を見た時、「こうした図柄ひとつにも慰めを見出したのだろうか」と少女アンネの心中を想って切なさで胸が張り裂けそうになったのを覚えている。
アンネの一家もナチスのユダヤ人差別が始まる前までは、ドイツの富裕なユダヤ人商家のひとつだった。それでもユダヤ人であるというだけの理由で、父オットー・フランク氏を除く家族全員が悲惨な末路を辿ったのである。映画『ブラックブック』で描かれたユダヤ人の悲惨は、そのまま当時のユダヤ人達の姿に重なるものなのだろう。
ところで映画の中で、避難先の南部へ向う船に乗り込んだいかにも富裕そうなユダヤ人女性が、豪華な首飾りを外すように言われた時に「これは寝る時にも外したことはないのよ」と応えたくだりがある。こうした、豊かさを誇示してはばからないところが(たとえ一部の人々であったとしても)、戦争以前から他のヨーロッパ人の嫉妬と羨望を生み、心情的にナチスのユダヤ人差別を後押しする要因にもなったのではないかと思った。
2つ目の接点は後期印象派を代表する画家ゴッホである。学校の図画工作の課題で、たまたま彼の『アルルの跳ね橋』を題材に鑑賞文を書いたのが彼の存在を意識した最初だ。それから彼に興味を抱いた私は学校図書館で『炎の画家ゴッホ』という評伝を借りて読んだ。その評伝を原作に制作されたカーク・ダグラス主演の映画も見た。タイトルが示すように炎さながらにゴッホはすべてに熱情を注ぐあまり、その過剰さが周りとの軋轢を生み、努力も空回り。結果的にことごとくがうまく行かない彼が気の毒に思えた。こんなに不器用な生き様はそうそうないだろう。彼がもし身近にいたら、私も親しくはなれなかったかもしれない。
しかしそんな彼だからこそ、9年という短い画家生活で後世に残るような作品を描けたのではないかと思う。作品の一点一点が、彼にとっては妥協を許さない血を吐くような思いで描いた作品であっただろうから。世間の常識から乖離すればするほど、彼の芸術は純化していったような気がする。絵画は彼の熱情の受け皿としてはピッタリだったのかもしれない。
オランダ時代の初期ゴッホ作品の色彩は暗くくすんで色彩感に乏しい。それは彼の窮乏と心情の反映であると同時に、それが彼の身近にある色彩だったのかもしれない。フェルメールの絵画世界そのままの色彩に溢れる映画『真珠の首飾りの少女』では、窓を通して入る陽射しが生み出すトーンの低めな色彩が印象的である。いわゆるオランダ的絵画世界、色彩感を生み出す「オランダ独特の光」については、芸術家の視点も交えつつ科学的に検証したドキュメンタリー映画『オランダの光』に詳しい。
その後フランスのパリに渡ったゴッホは印象派に出会い徐々に明朗な色彩を獲得して行く。さらに南仏アルルの強い陽射しにその明度は強さを増して行くのだ。短期日のゴッホ作品の劇的な変化は、制作環境の変化が及ぼす作品への多大な影響を示して興味深い。
高校時代には、生活力のないゴッホが物心両面で依存しきっていた弟テオに宛てた書簡集『ゴッホの手紙』を読んだ。私が読んだのは文庫本だが、最近書店で翻訳も新たに刊行されたらしい単行本を見つけた。興味はあるが、いかんせん高価で手が出ない。図書館で収蔵されたら是非読んでみたい。
成人してからは海外駐在時代に、確か朝日新聞の日曜版で、彼の作品の初期作品を多く収蔵する「クレラー・ミュラー美術館」の存在を知った。この美術館は、誰にも先んじてゴッホ作品の価値を認め、その収集に努めたオランダ人実業家夫妻が設立した美術館だ。現在は寄贈され国立美術館になっている。広大な森の中に静かに佇む平屋建ての美術館で、周囲には彫刻を配置している。ここを訪ねたフジサンケイ・グループ総帥がその美しさにいたく感動して、日本にも同様の物をと設立したのが、今では箱根の観光ポイントとして欠かせない「箱根彫刻の森美術館」らしい。さらに美術関連で言えば、私が大学の卒論のテーマに選んだ画家も、ゴッホではないがオランダの画家だった。
昨年は知人に誘われ、日本在住のオランダ人女性の自宅を訪ねる機会があった。麻布の閑静な住宅街に建つ瀟洒なマンションのメゾネットタイプのお宅だ。要は帰国間近い駐在夫人のガレージセールに誘われたのだ。その女性は世界に名だたる石油会社ロイヤル・ダッチ・シェル石油のオーナー一族の一人だった。正確にはご主人がその直系に当たる方のようだが、彼女自身オランダの名家の出のようで、その一族の歴史はオランダが海運国として世界に名を馳せた17世紀の、東インド会社誕生にまで連なるらしい。
元々東インドの交易を行っていた貿易会社14社が、1602年に統合してできたのが東インド会社。元の14社がそれぞれ株主となったこの会社は、世界初の株式会社だった。東インド会社は、広大な海域の貿易独占権と共に条約の締結、海外領土の総督の指名、貨幣の鋳造などを行う権利を有し、ひとつの国家にも匹敵するような存在であったらしい。最盛期には数千人規模の軍隊を組織し参謀を置き、数十隻から成る艦隊をも擁していたと言われている。
彼女の先祖はその東インド会社の経営に関わっていたとのこと。さらに驚いたのは、デルフトを拠点に富を欲しいままにしていた先祖は、ナポレオン率いるフランス軍の侵攻により、そのすべての資産を奪われ、やむを得ずハーグへと移住するも、持ち前の商才を発揮して見事復活を遂げたと言うのだから、オランダを代表する実業家一族であることは間違いない(父君はオランダ商工会議所の会頭とも聞いた)。彼女は一族の歴史をデルフト時代にまで遡って一冊の本にまとめ上げ、先頃上梓したようだ。自費出版という形で100部限定らしいが、将来的にはこの本を下敷きに小説を書きたいのだとか。東インド会社、ナポレオン…学生時代に世界史で学んだ名前が一族の歴史に直接リンクしている。その凄さに思わず絶句。
ご主人の仕事の関係で、世界各地を転々として来た彼女は、それぞれの地で現地の言葉を学び、現地ならではの物を買い求め、人脈を広げて来たらしい。ちなみに「何カ国語を話すのですか?」と尋ねたところ、事も無げに「9カ国語」と答えた彼女。大学時代にラテン語とギリシャ語、それから英語、仏語、スペイン語、インドネシア語…と指折り数える彼女。日本語もマンツーマンの指導で学んだようだが、私達が訪ねた日の会話は殆ど英語だった。日本人の悪い癖かもしれないが、在留外国人に対してついつい英語で話しかけてしまうんだよね。相手は日本語を学びたがっているかもしれないのに。
彼女は4年間の日本での生活をどん欲に楽しんだようだ。テラスには先生について学んだという盆栽の鉢がいくつも陳列されていた。しかし植物検疫の関係で帰国時には一切本国に持ち帰れないとのこと。とても残念そうな表情で、大事にしてくれる人に譲りたいと話していた。
リビングにはさりげなく17世紀の中国の陶器や磁器が飾られ(特に直径10㎝ほどの小皿の来歴にはロマンを感じた。沈没船から引き揚げられた品で、茶箱の茶葉に埋もれていたおかげで奇跡的に割れなかった物をクリスティーズのオークションで入手したらしい)、フランスの農家で200年程前に使われていたという大きなダイニングテーブル、ジョージアンやヴィクトリアンの椅子が、現役で活躍しているようだ。テーブルなど素朴な作りでかなり年季の入ったものだが、「大好きだから、これは売らずに本国に持ち帰ります」と彼女。
世界をまたにかけて転勤を繰り返す中で身に付けた合理性と、古い物を愛おしむヨーロッパの伝統的な価値観とを併せ持った女性だった。世が世なら、場所が場所なら、私など到底お近づきできないような上流夫人だが、ホスピタリティ精神溢れる、気さくな人柄の持ち主だった。もちろん自身の立場をきちんと弁え、本国(では王族と親交のある方なのだ)での顔と、海外で私達のような異邦人に見せる顔は全然違うのだろう。ともかくも、外国人エグゼクティブの日本での暮らしの一端を垣間見た約3時間は、私にとっては貴重な経験となった。
(2007年4月4日初出)
なかなかの力作なので(自画自賛を許してね・笑)、ここでご紹介したいと思います。
映画『ブラックブック』を見た後に、オランダと自分との縁について考えてみた。 私はオランダとは何かと縁がある(と、自分では思っている)。
私のオランダとの最初の接点は『アンネの日記』だった。子供時代地方に住んでいた私は、ある時地元紙の読者欄に投稿した謝礼に図書券を貰った。それと引き換えに入手したのが『アンネの日記』(文春文庫)だった。隠れ家での自分(彼女はまだローティーンだったのだ!)を押し殺した生活の中で、日記を親友にアンネは思索を深めて行く。同世代の私には彼女がかなり大人びて見えた。元々聡明な少女だったに違いない。アンネに触発されるように私も日記を書き出した。それは大学時代まで続いた。
『アンネの日記』への執着(関心)はそれに留まらない。後にその映画化作品も見た。映画公開に因んで地元のデパートで開催された『アンネ・フランク展』にも行った。屋根裏でペーターと腰掛けたトランク?も展示品の中にあったな。アンネに関する新聞記事をスクラップしたり、関連文献を読み漁ったりもした。
さらには大人になってオランダへ旅行し、子供時代からの念願であったアンネの隠れ家を訪ねた。夏の盛りで、世界中から多くの人々が訪れていた。日記を通して知っていた場所。初めて訪ねたような気がしなかった。隠れ家の人々が使ったであろうトイレの便座のかわいらしい花の図柄を見た時、「こうした図柄ひとつにも慰めを見出したのだろうか」と少女アンネの心中を想って切なさで胸が張り裂けそうになったのを覚えている。
アンネの一家もナチスのユダヤ人差別が始まる前までは、ドイツの富裕なユダヤ人商家のひとつだった。それでもユダヤ人であるというだけの理由で、父オットー・フランク氏を除く家族全員が悲惨な末路を辿ったのである。映画『ブラックブック』で描かれたユダヤ人の悲惨は、そのまま当時のユダヤ人達の姿に重なるものなのだろう。
ところで映画の中で、避難先の南部へ向う船に乗り込んだいかにも富裕そうなユダヤ人女性が、豪華な首飾りを外すように言われた時に「これは寝る時にも外したことはないのよ」と応えたくだりがある。こうした、豊かさを誇示してはばからないところが(たとえ一部の人々であったとしても)、戦争以前から他のヨーロッパ人の嫉妬と羨望を生み、心情的にナチスのユダヤ人差別を後押しする要因にもなったのではないかと思った。
2つ目の接点は後期印象派を代表する画家ゴッホである。学校の図画工作の課題で、たまたま彼の『アルルの跳ね橋』を題材に鑑賞文を書いたのが彼の存在を意識した最初だ。それから彼に興味を抱いた私は学校図書館で『炎の画家ゴッホ』という評伝を借りて読んだ。その評伝を原作に制作されたカーク・ダグラス主演の映画も見た。タイトルが示すように炎さながらにゴッホはすべてに熱情を注ぐあまり、その過剰さが周りとの軋轢を生み、努力も空回り。結果的にことごとくがうまく行かない彼が気の毒に思えた。こんなに不器用な生き様はそうそうないだろう。彼がもし身近にいたら、私も親しくはなれなかったかもしれない。
しかしそんな彼だからこそ、9年という短い画家生活で後世に残るような作品を描けたのではないかと思う。作品の一点一点が、彼にとっては妥協を許さない血を吐くような思いで描いた作品であっただろうから。世間の常識から乖離すればするほど、彼の芸術は純化していったような気がする。絵画は彼の熱情の受け皿としてはピッタリだったのかもしれない。
オランダ時代の初期ゴッホ作品の色彩は暗くくすんで色彩感に乏しい。それは彼の窮乏と心情の反映であると同時に、それが彼の身近にある色彩だったのかもしれない。フェルメールの絵画世界そのままの色彩に溢れる映画『真珠の首飾りの少女』では、窓を通して入る陽射しが生み出すトーンの低めな色彩が印象的である。いわゆるオランダ的絵画世界、色彩感を生み出す「オランダ独特の光」については、芸術家の視点も交えつつ科学的に検証したドキュメンタリー映画『オランダの光』に詳しい。
その後フランスのパリに渡ったゴッホは印象派に出会い徐々に明朗な色彩を獲得して行く。さらに南仏アルルの強い陽射しにその明度は強さを増して行くのだ。短期日のゴッホ作品の劇的な変化は、制作環境の変化が及ぼす作品への多大な影響を示して興味深い。
高校時代には、生活力のないゴッホが物心両面で依存しきっていた弟テオに宛てた書簡集『ゴッホの手紙』を読んだ。私が読んだのは文庫本だが、最近書店で翻訳も新たに刊行されたらしい単行本を見つけた。興味はあるが、いかんせん高価で手が出ない。図書館で収蔵されたら是非読んでみたい。
成人してからは海外駐在時代に、確か朝日新聞の日曜版で、彼の作品の初期作品を多く収蔵する「クレラー・ミュラー美術館」の存在を知った。この美術館は、誰にも先んじてゴッホ作品の価値を認め、その収集に努めたオランダ人実業家夫妻が設立した美術館だ。現在は寄贈され国立美術館になっている。広大な森の中に静かに佇む平屋建ての美術館で、周囲には彫刻を配置している。ここを訪ねたフジサンケイ・グループ総帥がその美しさにいたく感動して、日本にも同様の物をと設立したのが、今では箱根の観光ポイントとして欠かせない「箱根彫刻の森美術館」らしい。さらに美術関連で言えば、私が大学の卒論のテーマに選んだ画家も、ゴッホではないがオランダの画家だった。
昨年は知人に誘われ、日本在住のオランダ人女性の自宅を訪ねる機会があった。麻布の閑静な住宅街に建つ瀟洒なマンションのメゾネットタイプのお宅だ。要は帰国間近い駐在夫人のガレージセールに誘われたのだ。その女性は世界に名だたる石油会社ロイヤル・ダッチ・シェル石油のオーナー一族の一人だった。正確にはご主人がその直系に当たる方のようだが、彼女自身オランダの名家の出のようで、その一族の歴史はオランダが海運国として世界に名を馳せた17世紀の、東インド会社誕生にまで連なるらしい。
元々東インドの交易を行っていた貿易会社14社が、1602年に統合してできたのが東インド会社。元の14社がそれぞれ株主となったこの会社は、世界初の株式会社だった。東インド会社は、広大な海域の貿易独占権と共に条約の締結、海外領土の総督の指名、貨幣の鋳造などを行う権利を有し、ひとつの国家にも匹敵するような存在であったらしい。最盛期には数千人規模の軍隊を組織し参謀を置き、数十隻から成る艦隊をも擁していたと言われている。
彼女の先祖はその東インド会社の経営に関わっていたとのこと。さらに驚いたのは、デルフトを拠点に富を欲しいままにしていた先祖は、ナポレオン率いるフランス軍の侵攻により、そのすべての資産を奪われ、やむを得ずハーグへと移住するも、持ち前の商才を発揮して見事復活を遂げたと言うのだから、オランダを代表する実業家一族であることは間違いない(父君はオランダ商工会議所の会頭とも聞いた)。彼女は一族の歴史をデルフト時代にまで遡って一冊の本にまとめ上げ、先頃上梓したようだ。自費出版という形で100部限定らしいが、将来的にはこの本を下敷きに小説を書きたいのだとか。東インド会社、ナポレオン…学生時代に世界史で学んだ名前が一族の歴史に直接リンクしている。その凄さに思わず絶句。
ご主人の仕事の関係で、世界各地を転々として来た彼女は、それぞれの地で現地の言葉を学び、現地ならではの物を買い求め、人脈を広げて来たらしい。ちなみに「何カ国語を話すのですか?」と尋ねたところ、事も無げに「9カ国語」と答えた彼女。大学時代にラテン語とギリシャ語、それから英語、仏語、スペイン語、インドネシア語…と指折り数える彼女。日本語もマンツーマンの指導で学んだようだが、私達が訪ねた日の会話は殆ど英語だった。日本人の悪い癖かもしれないが、在留外国人に対してついつい英語で話しかけてしまうんだよね。相手は日本語を学びたがっているかもしれないのに。
彼女は4年間の日本での生活をどん欲に楽しんだようだ。テラスには先生について学んだという盆栽の鉢がいくつも陳列されていた。しかし植物検疫の関係で帰国時には一切本国に持ち帰れないとのこと。とても残念そうな表情で、大事にしてくれる人に譲りたいと話していた。
リビングにはさりげなく17世紀の中国の陶器や磁器が飾られ(特に直径10㎝ほどの小皿の来歴にはロマンを感じた。沈没船から引き揚げられた品で、茶箱の茶葉に埋もれていたおかげで奇跡的に割れなかった物をクリスティーズのオークションで入手したらしい)、フランスの農家で200年程前に使われていたという大きなダイニングテーブル、ジョージアンやヴィクトリアンの椅子が、現役で活躍しているようだ。テーブルなど素朴な作りでかなり年季の入ったものだが、「大好きだから、これは売らずに本国に持ち帰ります」と彼女。
世界をまたにかけて転勤を繰り返す中で身に付けた合理性と、古い物を愛おしむヨーロッパの伝統的な価値観とを併せ持った女性だった。世が世なら、場所が場所なら、私など到底お近づきできないような上流夫人だが、ホスピタリティ精神溢れる、気さくな人柄の持ち主だった。もちろん自身の立場をきちんと弁え、本国(では王族と親交のある方なのだ)での顔と、海外で私達のような異邦人に見せる顔は全然違うのだろう。ともかくも、外国人エグゼクティブの日本での暮らしの一端を垣間見た約3時間は、私にとっては貴重な経験となった。
(2007年4月4日初出)