先週,所用で町に行った帰りに,ついつい寄ってしまい購入。
CD2枚組1,890円。
世間的には安いのかもしれないが,安物買いが得意な私にとって,CDソフトは1枚当たり500円を切らないと安いとはならない・・・。
ただ,迷いながら店のCD棚を漁る楽しさは,サイト上でのヴァーチャル体験とは全く別の次元のものである。
ブルックナーの交響曲第7番・同第8番。
演奏は故オイゲン・ヨッフム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(近年何故か王立或いはロイヤルコンセルトヘボウという表記が為されるのだが,個人的には否である。)
生涯に2度のセッション録音によるブルックナーの交響曲全集を録音した最初の指揮者である(その後は,ギュンター・ヴァントが続いた)。
第7番は1973年のアムステルダム・コンセルトヘボウでのステレオライブ録音で,冒頭に曲目紹介のクレジットが入る。
オランダ放送協会の音源か,それをエアチェックしたテープが音源なのか定かではないが,レンジが狭いものの聴きやすい音質となっている。
原盤は,歴史的音源の復刻に力を入れてきたTAHRAで,久しく廃盤になっていたそれをTower Recordが限定の企画ものとして再発売したようだ(詳細はこちら)。
以前,新星堂もかつての音源の復刻をしていたことがあったが,欧州各国の放送局のライブラリーに膨大に眠っている貴重な音源の復刻が今後も進んで欲しいものである。
ブルックナーの第7交響曲を初めて聴いたのは,10代の終わり頃だった。
多分,ザルツブルク音楽祭(ウィーン芸術週間か??)のライブであるヘルベルト・ブロムシュテット指揮ドレスデン国立管による演奏だったと思うが,以来填ってしまった。
当時は,何と言ってもマーラーの交響曲の一大ブームが起こり(アバド,メータ,レヴァインといった気鋭が競うように録音していた-後マゼールが続いた),私の周囲のクラシック通を気取った連中は皆マーラーの長大な交響曲を,男のロマンだとか言いながら聴いていた。
であるから,天の邪鬼を標榜する私がブルックナーの交響曲に走ったのも,今考えると当然だったような気がする。
大体,ブルックナーの交響曲の入門というと,「ロマンティック」なる珍妙な副題の付いた第4番変ホ長調が第一に挙げられるようだが,私の場合は何故か第1とこの第7だった・・・。
ブルックナーの全交響曲中で最も抒情的で宗教的色彩が濃いと言われるこの第7だが,冒頭の弦楽によるトレモロの弱奏にチェロとホルンのユニゾンが乗る神秘的な所謂「ブルックナー開始」からして,確かにアルプスの黎明のような静謐にして雄大な雰囲気を醸し出す。
さらに,深遠なAdagioである第2楽章終盤に,敬愛する大作曲家ワーグナーの訃報に接したブルックナーが,追悼の意味を込めてワーグナーチューバ五重奏によるコラールが演奏される。
それに比べて,後半の2つの楽章はややウェイトが軽い印象だが,跳躍音型のトランペットの活躍する第3楽章Scherzoや,霧が徐々に晴れ明るさを増すアルプスの秀峰のように晴れやかな終曲もそれぞれ魅力的な楽曲である。
ヨッフムのブルックナーの特徴は,一言で言え堅牢な構造物のような響きと緩抒部の対比,そして宗教臭さを感じさせないところだろうか。
かつて評論家たちに酷評された緩抒楽章でのテンポの動かしなど,インテンポ墨守が金科玉条のように言われた旧来のブルックナー演奏とは完全に一線を画すものであり,この演奏が為された60~70に於いては革新的なものだったと予想される。
第1楽章冒頭,神秘の「ブルックナー開始」は予想外に淡々と始まる。
あれっ,と少々肩すかしを食った気になったが,やがて金管の重奏に弦楽が絡む主部や,低弦の刻みにヴァイオリンと金管が乗って徐々に盛り上がる展開部直前など,完全に興に乗り,濃厚なブルックナーの世界にトリップすることができる・・・。
ソロを取るフルートの音程が一瞬怪しくなるのはご愛敬か・・・。
第2楽章は,ヨッフムの他の同曲演奏と同様に緩やかなテンポでたっぷりと歌われる味わいに満ちたAdagioとなった。
ブルックナーの交響曲を演奏する際に,問題となるのはエディションの違い-つまりハース版かノヴァーク版かということだが,ヨッフムは一貫してウィーンの音楽学者であったレオポルド・ノヴァーク(1904-1991)による版を使い続けた。
この曲の両版の決定的な相違は,簡単に言えば第1楽章コーダでのテンポの漸急と第2楽章後半のクライマックスでのシンバルとトライアングル(役70分の演奏中唯一の出番)の追加だろう。
いずれも金管の壮麗なコラールが輝く部分だが,ヨッフムの演奏はその辺のツボを見事に心得たもので,こちらの期待を全く裏切らない。
故に,第2楽章終盤で一度クライマックスの興奮が収まった直後に演奏されるチューバ五重奏の響きは痛切である・・・。
第3楽章は,ライブのせいかソロをとるトランペットが危うい場面もあったが,きびきびした進行で重苦しさがない。
本来ブルックナーの交響曲は,決して重苦しくも晦渋でもなく,すこぶる美感に溢れたものであることを再認識した次第である。
同様なことは,続く最終楽章にも言える。
軽やかな弦楽のトレモロによって導入される第一主題と,低弦の克明な刻みに乗って繰り返し奏される愁いに満ちた第二主題にホルン(手元にスコアが無いのではっきりしないが,ワーグナーチューバかも)が絡む瞬間などぞくぞくするし,ホルンのソリをトランペットが受け継ぎ,漸急の後全奏になだれこむコーダも,ブルックナーの交響曲聴く醍醐味を感じさせてくれる。
ヨッフムの第7というと,ステレオ録音以降だと前述のベルリンフィルとドレスデン国立管によるセッション録音による全集の他に,過去に2つのライブを聴いてきた。
ドレスデン国立管との録音の2年後である1980年のフランス国立管と,亡くなる半年前の1987年,今回と同様のコンセルトヘボウとの来日公演である。
今回のものはそれらよりも早い時期の,ヨッフムが60代終わりの演奏だけに,覇気が漲ったものとなっており,実に聴き映えがした。
私が音楽を聴き始めた若い頃,欧州ではこのヨッフムとギュンター・ヴァント(1912-2002)がブルックナー演奏の双璧でもあった。
その2人が,同時期にドレスデンとケルンという東西ドイツのオケを振って全集の録音を残したのは,今となっては偶然とは言え象徴的な出来事に思われてならない。
そしてその2人とも,晩年は欧州各地のオケを振って名演を残したものの,物故後は誰もブルックナーを振ることのできる大物が居なくなってしまったことは,まさに指揮者難と言われる現代を象徴しているように思われてならない。
・・・で,もう1枚の第8番については・・・。
第7番1曲だけでワープロ2ページ半以上も費やしてしまったので,今回は見送って機会を見てエントリしたいと思う・・・。










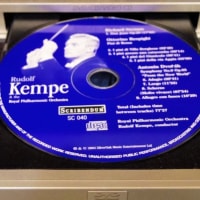
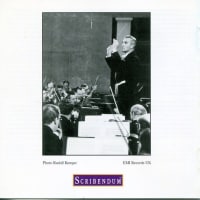
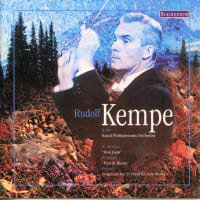







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます