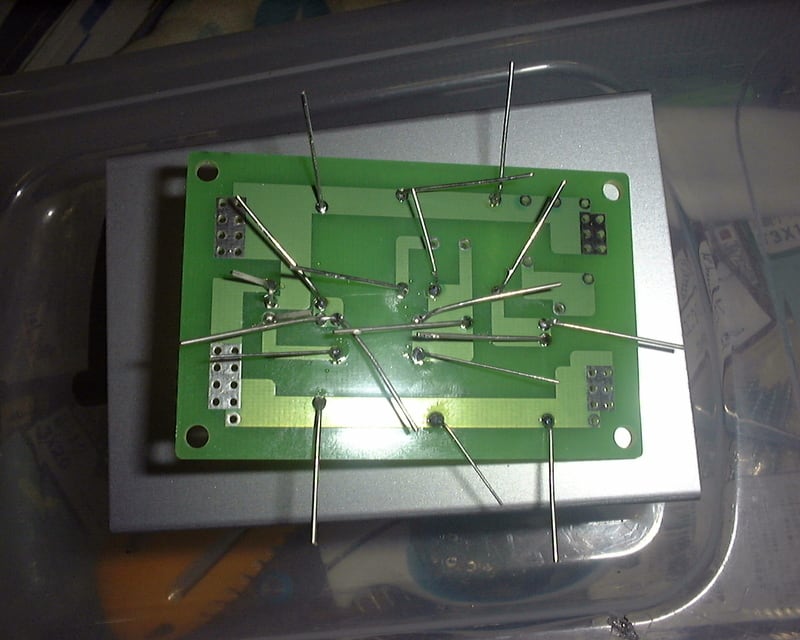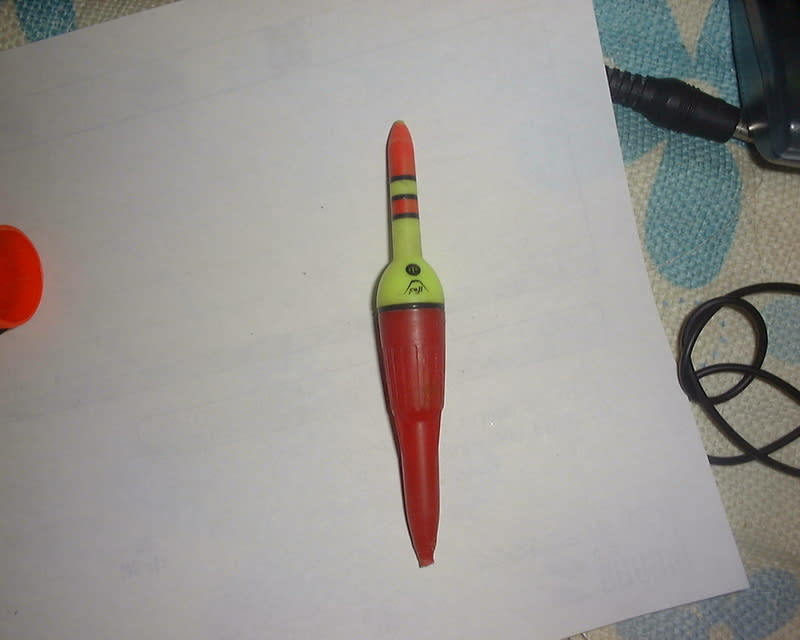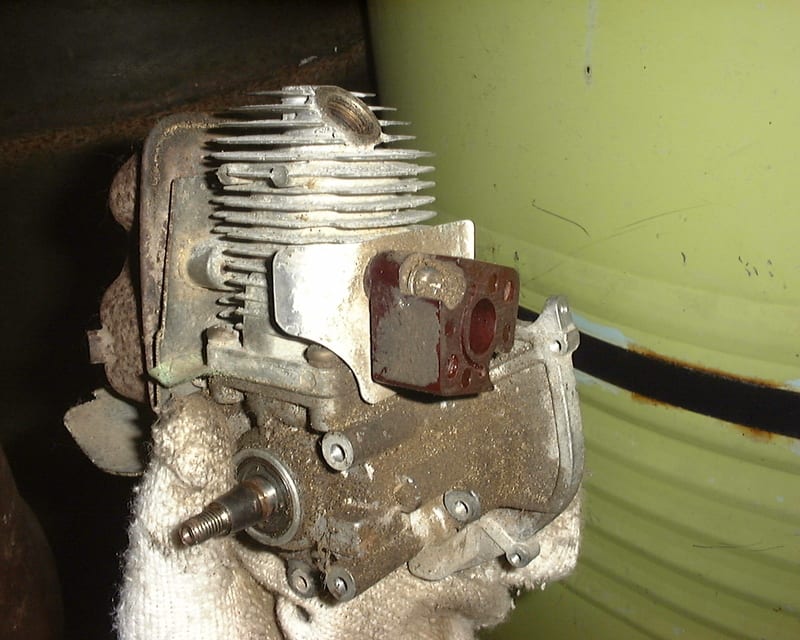たまに、ハンダごてを使うときがある。
一年前ぐらい前に作ったPC用ステレオスピーカ
電源は、12V駆動。
このほか、PCのマザーボードやビデオボードなどのコンデンサ交換をした。
まぁ、電子工作は回路図が読みやすいものだけ作れる程度であるが・・・・・・・
回路設計まで出来たらいんだけど・・・
それはさておき、ハンダずけがうまくいかないときがある、特にPC基盤は非常にやりにくかった。
で、あちこち調べたら、ハンダの成分によるハンダごての適正温度ってのがあるらしい。
往々にして、こて温度が高すぎるらしい。それを知ってから、23Wのこてでコンセントを抜き差ししながらやっていた。面倒だった。
市販のコントローラや温調ごてもあるけれど、値段が高い。
そうゆう時は、秋月電子。
トライアック万能調光器キット600円、送料別、コンセント、ソケット、フューズボックス、フューズ、ケース、取り付けねじ、などは付いていない、基盤と回路部品のみの値段です。
これに、電気コードが少々要る。
AC100V仕様だから、パターンが広いね。 だけどねぇ、20A流せるコード線が付かない。
まぁ、穴を通さず裏に直接付ければいいか・・・・・・・
これなら、作れそうだよね。
おれ、糸鋸で切ったけど。
PC電源のソケットが有ったので、それようの穴。
プラグコードでもぜんぜんOK。
やすりでギーギー入るまで削る。マル穴は、ドリルで開ける。
ソケット、コンセント、基盤スペーサーなどの固定ビスは、すべて3mm。
23Wをコントロールするだけなら、この太さは要らない・・・・
が、1KWをコントロールしたいがために太くした。
テスト行こう。
右にいっぱい回し。350℃。
ボリュウムがこの位置で、323℃。
次
つまみの印が真上の位置で、245℃。
コントロールできました。この鏝は23W。
部品が揃っていれば2時間もあれば出来るなぁ・・・・・・
一台5000円で売ったんじゃ詐欺だな。
秋田で作るとなると、送料が掛かるから、なるべくいっぺんに揃えないとコストが高くなる。
よーく計画した上で注文すると安く上がる。