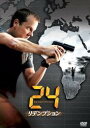『24』の最新シーズンのレンタルが開始になったので、3巻(6エピソード)を観た。大統領が女性になっていて、しかもなんとなくヒラリーさんを意識した女優なのはご愛嬌。黒人大統領は先取りして、早いシーズンでやっているのでバランス的にはしょうがないのではないかと思う。
それよりも気になったのは、心なしか、今のところ出てきている捜査関係者が概ね紳士的で遵法精神が高いこと。
確かにグアンタナモ米軍基地問題が告発、映画化までされ、オバマ大統領が閉鎖を支持・署名しているなど、米国の行き過ぎた軍事行動やテロ対策への風当たりが強い。その中でフィクションとはいえ、極端な拷問の描写がしにくくなっているのは、今のアメリカの世情の表れかもしれない(ジャック・バウアーは不満そうだが…)。
しかし一方でアメリカという国に良くも悪くも大いなる誤解を与えそうな、滑稽なまでの国への高いプライドは鳴りを潜め、普通のドラマに見える。拷問ありき、極端な国家への忠誠ありきのドラマでは最初からないとは思うが、ヤワで小粒な印象を全体から感じ、何がしたいのかわからない、登場人物が所在無く感じた(たった6エピソードの感想だけど)。単なるドラマ自体へのマンネリ感だけでない、何かを感じる。
日本では時代劇ブームという現象と同時に、ほんの少し前の歴史、つまり戦後から先の過去を描くドラマや映画が最近目に付く。この前始まった『官僚たちの夏』(TBS)、10月からは『不毛地帯』(CX)、『沈まぬ太陽』も映画化されるらしい。結構前だが、『黒部の太陽』もスペシャルドラマで放映されていた。一時期もてはやされた『ALWAYS-三丁目の夕日』的ノスタルジーではなく、硬派なものが多い。混迷の中、政治だけでなく経済にも国家観がより問われているということか。日本も米国も。どうしても日本の場合、過去に力強さを感じる。創らなければならないのは未来だけど。